東京・渋谷区出身で、2年前まで警視庁で警部補を務めていた男性が、突如として早期退職し、高知県の深い山奥へ“たった1人で移住”した理由に、視聴者は大きな関心を抱いたことでしょう。
彼には、最愛の娘と親友を立て続けに失い、さらに自身もがんと診断されるという過酷な人生ドラマがありました。
その悲劇を経て、「なぜ警部補という安定した職を捨て、この山奥を選んだのか」という疑問こそ、番組『ナゼそこ?+』が視聴者に問いかける核心です 。
都会の喧騒を離れ、野生のサワガニを捕り、電気やガスに頼らない生活を送る彼の姿は、都市生活に疲れた多くの人々にとって、心を揺さぶる映像となりました。
自然との共鳴を通じて心身を再生しようとする姿勢こそが、この移住の本質です 。
この記事では、なぜ彼が高知県の山奥という極限の場所を選び、どういった人生背景を背負ってそこに至ったのか、「元警部補」という社会的地位を捨ててまで追い求めた新たな生き方とは何かを、詳細かつ丁寧に紐解いていきます。
読者の方にとって、都市とは異なる暮らしの意味や、自分自身と向き合う勇気を考えるきっかけになれば幸いです。
高知県の山奥に移住した元警部補とは?

警視庁でのキャリアと警部補という職位
彼は渋谷区出身で、約2年間前まで東京の警視庁に勤務していました。
番組では「古畑任三郎と同じ“警部補”」と紹介され、警部補として中堅刑事の役割を担っていたことが明かされました。
警視庁における警部補は捜査や部署の指揮を任され、現場経験が豊富な職で、責任ある立場です。
そのキャリアを捨てるという決断の重さが視聴者の胸を打ちました。
移住前の暮らしと退職に至った事情
東京での生活はいわゆる典型的な都会派の公務員生活でしたが、数年前から身辺に次々と不幸が訪れます。
最愛の娘と親友を立て続けに失い、さらに自身もがんの告知を受けるなど、心身ともに深刻な状況に追い込まれました。
これらの悲劇が重なり、精神的にも限界を感じた彼は、警視庁を早期退職し、別の人生を選ぶ決断を下しました。
放送番組で語られた悲劇とドラマ
7月31日放送の「ナゼそこ?+」では、彼の人生ドラマが中心に描かれました。
最愛の人たちとの突然の別れと病との闘いを乗り越え、180度人生が変わっていった過程が詳細に紹介されました。
番組は、なぜ彼が東京の華やかな環境を去って、高知県の山奥で一人暮らしを選んだのか、その心の闇と再生を視聴者に向けて丁寧に紐解いています。
これらの内容は番組の構成そのものであり、視聴者に強い印象を残しました。
なぜ高知県の山奥を選んだのか?

自然回帰と孤独な環境による心の再生
彼が高知県の山奥に移住した背景には、これまでの喧騒ある都市生活から離れ、自然の中で自分を見つめ直したいという思いがあったと推察されます。
番組内では「たった1人で山暮らしを送る」という描写から、深い孤独と向き合いながら心の再生を図る姿勢が浮かび上がります。
自然と対峙する日々を通じて、以前の自分を癒し、新たな生き方を模索している様子が強く印象づけられました。
過去の喪失と疾病との向き合い
移住の決断には、最愛の家族や友人との別れ、さらに自身へのがん告知という数々の悲劇が深く関わっていました。
番組はこれらを「娘…親友…最愛の2人を失い…がん宣告」というキーワードで表現し、彼の抱えてきた心の痛みと向き合う過程を丁寧に描いています。
都会の環境では得られなかった静寂と距離感が、彼にとって回復のプロセスを進める場となったことが伺えます。
移住先の具体的な場所や生活環境の特徴
番組では具体的な地名こそ明かされていませんが、“高知県の山奥”というロケーションと「サワガニ獲り(秘)野生生活」といった描写から、自然豊かな渓流や野生に近い水辺を活動基盤にしている様子が伝わります。
また、「たった1人で山暮らし」というスタイルから、自給自足に近い、都市生活とはかけ離れた生活環境であることが強調されています。
こうした詳細は、彼の新たな生活がいかに自然に寄り添って構築されているかを示唆しています。
ナゼそこ?+で明かされた現在の暮らし

サワガニ獲りや野生的な食生活
番組では彼が自ら渓流でサワガニを捕獲し、それを主食の一部として調理する姿が紹介されました。
東京では到底経験できない自然との近さを感じさせるもので、川辺での採取からそのまま素朴な料理まで、ほぼ野生そのものの食生活を送っている様子です。
現代の都市文化から遠く離れた、徹底した自然重視の暮らしぶりが視覚的にも強く印象付けられました。
ひとり山暮らしの日常ルーティン
番組で描かれた日常は、完全に都市リズムから隔絶されています。
朝は渓流や山道の散策が日課となり、農作業や食材調達に多くの時間を割いています。
電気やガスに頼らず、火を起こし、自らの手で住環境を維持する生活は、ひとりで淡々と続けられています。
スタッフ取材を交えた映像からも、孤独ながら自分のペースで暮らす姿が浮かび上がりました。
番組スタッフが取材した秘境生活の裏側
取材スタッフによる密着映像では、彼が完全に都市と切り離された高知の“秘境”に暮らす実態が伝えられました。
「たった1人で山暮らし」というフレーズが強調され、萌芽から収穫まで自給自足に近い生活を送る日々が淡々と描かれています。
背景にある波瀾万丈の過去から回復期へと向かうプロセスとあわせて、視聴者に深い共感と驚きを呼び起こしました。
他の『ナゼそこ?+』高知エピソードとの共通点と差異

元看守や大家族の移住事例との比較
2025年4月3日放送回では、元刑務所看守として四国に勤務していた人物夫妻が、高知県の山奥に移住した事例が紹介されました。
3女2男の大家族が、山中で薪割りや畑仕事に取り組む姿が描かれ、子どもたちも共に自然と向き合う暮らしを実践。
元看守としての経験から「今頃死んじょった…」という過去を乗り越えた壮絶な背景が語られました。
一方、本件の元警部補は単身で自然と暮らす点が異なり、家族を伴わず「孤独」を選んだ点で明瞭な差違があります。
それぞれの背景にある人生ドラマの構造
看守だった一家の場合、過去の職務経験や家族との絆、子育てを通じた転機が中心に据えられており、「家族一丸で新生活へ踏み出す」過程が主軸でした。
対して、元警部補の物語では、娘や親友の死、がん告知という個人的な悲嘆を乗り越えるための「孤立と再生」がドラマ構造の核となっています。
この違いが番組内で語られた人生ドラマのトーンに大きな差異をもたらしています。
本件の独自性と視聴者に響く魅力
本件が特筆すべきは、「元警部補」という社会的にも尊敬される職の放棄、その重みと引き換えに選んだのが自然回帰と孤独の日々である点です。
しかも一家や複数人ではなく「たった1人」であることが特別感を演出し、視聴者は「なぜ彼1人がそこを選んだのか?」に強い共感と疑問を抱きます。
看守一家や大家族とは違い、身体的・精神的な再生を求めて自然に寄り添う姿に、視聴者が自身の人生を問い直すきっかけとなる点が、このエピソードの最大の魅力です。
まとめ

『ナゼそこ?+』2025年7月31日放送回では、東京・渋谷区出身で、2年前まで警視庁で警部補を務めていた男性が、なぜ高知県の山奥へ「たった1人で移住」したのか、その背景と現在の姿が丁寧に描かれました。
彼の移住決断の裏には、最愛の娘と親友との突然の別れ、さらには自身のがん告知という心身の極限状態がありました。
これらの現実が重なり、職を離れて自然の中で再生を図る道を選んだのです。
現在、彼は高知県の深い山中、渓流に近い環境で暮らしており、日々サワガニを捕って調理するなど、ほぼ野生に近い暮らしを送っています。
電気やガスには極力頼らず、自ら火を起こし、自然のリズムに沿った生活を築いている様子が番組で紹介されました。
同じく高知の山奥を舞台にした過去のエピソードと比較すると、元看守一家として複数人で移住した事例とは対照的です。
本件の元警部補の場合、「孤独」をあえて選び、個人の人生ドラマとして自己と向き合う姿勢が、視聴者に強い印象を与えています。
元警部補という社会的に尊敬される職を自ら捨て、自然と孤独の中で再出発を選んだ彼のストーリーは非常に感慨深いものでした。
特に、誰かと共にではなく、あえて「ひとり」であることを選ぶ強さと覚悟が心に残ります。
都市生活の快適さよりも、自分自身を静かに見つめ直す環境を選んだ決断には、読む人の胸を打つ力があります。
自然との接触が持つ癒しの力、孤独と引き換えに得られる再生の可能性。
こうしたポイントは、移住やセカンドライフ、新たな人生設計に関心を持つ人々にとって、とても示唆に富んだ内容です。
もし、自分を見つめ直したい、人生を根本から変えたいと思っている方には、彼の選択と生活スタイルから学ぶことが少なくありません。
この番組エピソードはまさに、「なぜその場所を選んだのか」を深掘りする良質な文学のようなドキュメンタリーでした。


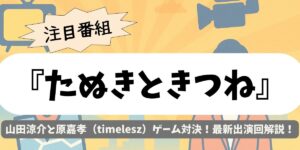


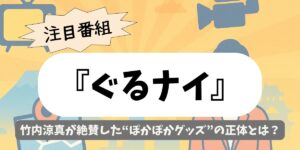
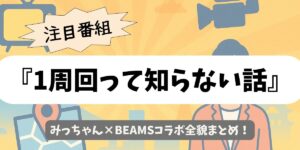
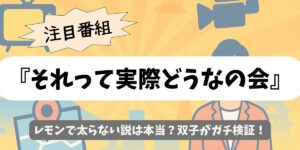
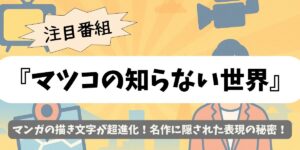
コメント