『世界の何だコレ!?ミステリー』の2025年10月8日(水)放送の2時間スペシャル回は、これまでとは一線を画す注目企画を携えて登場します。
今回の目玉は、神職資格を持つ女優・平祐奈が出雲大社を舞台に、「意外な参拝方法」や「㊙エリア」など、普段は知ることのできない深部に迫る案内役を務めることです。
さらには、島根の海底に眠る“謎の遺跡”を扱うサブ企画も併せて構成され、信仰とミステリーの融合が予告されています。
視聴者がこのキーワードで検索する背景には、単に「番組を観たい」「内容を先に知りたい」という動機だけでなく、「平祐奈が神職としてどこまで踏み込むか」「出雲大社で扱われる“秘蔵情報”とは何か」「海底遺跡は実在するのか」など、複数の興味関心が交錯していると考えられます。
「信仰的専門性 × ミステリー要素 × ロケ映像」という構成は、これまでのバラエティやドキュメントの枠を越える可能性を秘めており、ファン・歴史好き・ミステリーファン、さらには神社・文化に関心を持つ層にも広く響く企画です。
そこでこの記事では、放送前に視聴者がしっかり“準備”できるよう、番組公式情報をもとに、企画の枠組み、主要なキーワード(平祐奈の神職資格、出雲大社の参拝方法、㊙エリア、海底遺跡)への入り口、見るべき視点を整理します。
視聴後に「あ、これはこういう意味だったのか」と振り返りやすく、より深く楽しむための“ガイド”としての役割を果たすことを目的としています。
それではまず、企画の基本構成と見どころから見ていきましょう。
平祐奈×出雲大社企画の基本情報

放送日時・出演者・企画概要(出雲大社×平祐奈)
この企画は、2025年10月8日(水)19:00〜20:54に、『世界の何だコレ!?ミステリー』の2時間スペシャルとして放送予定です。
出演者として、MCに 蛍原徹/きゃりーぱみゅぱみゅ、ゲストに 伊集院光・足立梨花、VTR出演として平祐奈と 田中卓志(アンガールズ)が名を連ねています。
企画概要では、「神職の資格をもつ平祐奈と田中卓志が出雲大社を訪れ、意外な参拝方法や㊙(秘)エリアを紹介する」点がメインテーマとされています。
また、“島根の海底に謎の遺跡!?” というサブ企画も並行して扱われ、地元ダイバーの発見情報や伝承的な要素が調査対象になるようです。
公式予告で語られた見どころ(参拝方法・㊙エリア)
公式サイトの次回予告では、「出雲大社の意外な参拝方法から㊙エリアまで!出雲大社を深掘りします」と明記されており、通常の神社見学では味わえない裏側にも踏み込む意図が示されています。
“意外な参拝方法”という表現は、一般に知られている「二礼四拍手一礼」などとは異なる作法やルートを指す可能性があり、番組ではその違いを解説するシーンが想定されます。
“㊙エリア”についても、普段立ち入りが制限されている本殿裏側、内陣や奥殿近辺、あるいは神職関係者が使う通用路などを含む可能性が高いと予想されます。
公式予告文には「㊙エリアまで」と書かれており、視聴者の関心を引くサプライズ性を持たせた構成と見られます。
番組はこの見どころを前面に出すことで、通常の神社ツアーでは見ることのできない視点を提供する狙いがあると受け取れます。
同回で扱う“島根の海底に謎の遺跡!?”の連動企画
当該スペシャルには、出雲大社企画と並行して「島根の海底に謎の遺跡!?」というテーマが取り上げられる予定です。
公式告知文では「地元ダイバーが発見!島根の海底に謎の遺跡!? 地元で語り継がれる伝承と不思議な関連も!?」と記載されています。
この海底遺跡企画は、出雲大社の神道・参拝文化とは別次元で、地域伝承や考古学的視点も交える複合的な調査要素を含んでいます。
地元住民の伝説、潜水調査結果、遺跡の可能性検証などが番組構成の要素になりそうです。
番組側としては、この2本柱(出雲大社深掘り × 海底遺跡調査)を併行して進めることで、視聴者の興味を幅広く引きつける構成を狙っているようです。
予告文では「さらに…」という表現で海底遺跡がサプライズ要素として強調されています。
平祐奈の“神職資格”と学びの背景

國學院大學神道文化学部卒・神職資格の紹介
平祐奈さんは、國學院大學神道文化学部を卒業し、在学中に神職課程を専攻して「神職資格」を取得したことを、自らの卒業時に発表しています。
この神職資格は、神道教義、祭式の作法、神社の運営・祭祀実務といった科目を含むカリキュラムを修め、一定の要件を満たすことで取得されるものであり、學位とは別に神職としての認定が得られる制度です。
メディア報道によれば、平祐奈さんが保有する神職資格は、権禰宜(ごんねぎ)という階級である可能性が高いとされる情報もあります。
ただし、国家資格という形式のものではなく、神道に基づいた教育・研修を修了したうえで与えられる「神職」の一形態です。
番組公式サイトでも「神職の資格をもつ俳優・平祐奈」と明記されており、この企画が“神職である彼女の視点”を看板要素のひとつに据えていることが裏付けられています。
また、卒業・資格取得の時点で、彼女は和心(日本文化・精神性)を大切にした表現を今後の活動軸の一つに据える旨を述べています。
番組内で活きる知識と視点(神道の基礎理解)
平祐奈さんが神職資格を持つことは、この『世界の何だコレ!?ミステリー』出雲大社企画において、通常のロケ出演者とは異なる視点・知見を提供する立場を与えています。
番組公式告知にも「神職の資格をもつ平祐奈と…出雲大社へ」と明記されており、彼女の専門性が演出要素として前面に出る設計です。
具体的には、参拝作法や祭式の意味、古来からの祈りの在り方、神社構造(本殿・内陣・参道・摂社・末社など)等の知識が、視聴者に解説や案内の形で示される可能性が高いでしょう。
平さん自身が、その知識を活かして“意外な参拝方法”や“㊙エリア”を案内・解説する番組構成と推察されます。
さらに、神職資格を取得した者は、神社奉仕(祭典や巫女・祭具準備など)にも関わる能力を持つとされるため、制作側はロケ中に実務面での“奉仕”や祭祀体験を交えた場面も意図しているかもしれません。
こうした場面で彼女が参加・補助的役割を果たす可能性は十分にあります。
このように、平祐奈さんの持つ知見は、番組の“深掘り”要素を支える重要な柱になると考えられます。
視聴の注目ポイント(解説・案内役としての役割)
この企画で視聴者が注目すべき点のひとつは、“知識を持つ案内役”としての平祐奈さんの振る舞いでしょう。
他の出演者や視聴者向けに、神社・神道知識を“わかりやすく伝える”役回りを期待できます。
例えば、「本殿へ至る参道の意味」や「神域と俗域の境界」「摂社・末社・御神木の位置意義」など、一般参拝者には見過ごしやすいポイントを、彼女ならではの視点で語る場面が想定されます。
また、ロケ中に多くの聴衆が関心を持つであろう“㊙エリア”や“意外な参拝方法”において、ただ案内するだけでなく、背後にある宗教的・歴史的意味を交えて解説することで、視聴者の理解と興味を高める役割を担う可能性が高いです。
さらに、番組の進行においては、VTR出演者として解説を交えながら探索を進める構図になることが予測されます。
これにより、画面の中で「専門家」としての存在感が自然に際立つ演出がなされるでしょう。
視聴者としては、彼女の言葉と行動から、“神職として現場で働く人”の視点を垣間見ることができる場面にも期待したいところです。
出雲大社の基礎知識と“意外な参拝方法”

出雲大社の由緒・見どころの要点整理
出雲大社(いずもたいしゃ)は、島根県出雲市大社町に鎮座する神社で、御祭神は大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)。
日本神話における国造りや縁結びの神として信仰されており、縁結びの聖地として全国的に知られています。
境内全体の構成も特徴的で、拝殿、本殿、十九社、摂社・末社など複数の社殿が点在しています。
特に「十九社」は、旧暦10月(神在月)に全国の神々が集まるとされる期間、神々の滞在場所とされる小社群で、拝殿の東西に並んでいます。
また、出雲大社は社殿の構造的にも注目されます。
本殿は「大社造(たいしゃづくり)」様式と呼ばれる古来からの建築形式を踏襲しており、戦前から重要文化財/国宝に準じる価値が認められてきました。
さらに、拝殿は1963年に改築されたもので、木造神社建築として戦後最大級と評価されることもあります。
これらの見どころを訪問者は順に巡りながら、「神在月」や「国譲り神話」などを意識して、歴史と信仰を体感できる構成になっています。
“意外な参拝方法”とは(事前チェック)
「意外な参拝方法」として番組で扱われそうな内容は、一般的に知られる神社参拝とは異なる手順やルート、また伝統的信仰に即した作法などです。
出雲大社ならでは特徴を押さえると、次の要素が「意外な」注目点になりえます。
二礼四拍手一礼の作法
出雲大社の正式な参拝作法は二礼・四拍手・一礼とされています。
通常の神社参拝で一般的な「二礼・二拍手・一礼」とは異なり、拍手の動作が倍になる点が特徴です。
この四拍手には伝統的に、「例祭(勅祭)」の際には八拍手を行うとされ、数字「8」が無限性を示すという理解に基づくものと説明されることがあります。
平常時はその半分である四拍手を用いて神を称える作法が用いられると、出雲大社の FAQ に記されています。
参拝ルート・鳥居の順序
出雲大社には「一の鳥居 → 二の鳥居 → 三の鳥居 → 四の鳥居」という構成があり、参拝者は複数の鳥居をくぐって境内へ入ります。
特に「勢溜(せいだまり)の鳥居」付近から参拝を開始するルートが推奨されています。
門前町近くから歩く参拝ルートとして、まずこの鳥居を通るのが流れとして定着しています。
また、参道途中には祓社(はらえのやしろ)という社があり、心身を清らかにする祓の意味でここに立ち寄る作法を紹介する案内もあります。
参拝を初心者向けに案内する観光ガイドなどでは、このルート立ち寄りが推奨されています。
“砂をいただく”儀礼(稲佐の浜と素鵞社)
出雲大社参拝の伝統的な儀礼として、 稲佐の浜(いなさのはま)で砂を汲んでそれを社に奉納する工程を含むルートがあります。
具体的には、出雲大社から西へ徒歩約10分の距離にある稲佐の浜で少量の砂を頂き、その砂を素鵞社(そがのやしろ)に奉納するという流れが伝統的習慣として語られています。
こうした砂を介在させたルートを組み込む参拝方法は通常の神社参拝には見られない要素であり、番組が「意外な参拝方法」として扱う可能性が高いと言えます。
まとめると、「意外な参拝方法」とは、四拍手、特定の鳥居ルート、祓社立ち寄り、砂を使った奉納儀礼といった、出雲大社独自の作法・伝統を含めた参拝工程を指すものと見られます。
立入制限や“㊙エリア”の扱いとマナー
出雲大社や多くの神社では、一般参拝者が立ち入れない区域(本殿裏側、内陣、通用路、関係者控所など)が存在します。
こうした場所を “㊙エリア” と呼ぶ場合、番組で案内可能性がある区域と、訪問に際して注意すべきマナーを押さえておきましょう。
立入制限の基本原則
本殿内部や裏側、屋根裏、内陣(ご本尊に最も近い領域)などは概して関係者や神職のみが出入りできる場所です。
これらは信仰的にも神域性を保つ必要があるため、一般公開されていないことがほとんどです。
出雲大社の公式 FAQ にも、「本殿以外のご社殿をお参りの際も、二礼四拍手一礼の作法を用いて参拝してください」という記述があり、ご本殿・他社の区別は作法論ではあっても、アクセス可否については言及されていません。
従って、㊙エリアとは通常非公開領域を指し、番組側が特別な許可を得て案内する形になると考えられます。
マナーと注意点
一般参拝者が許される範囲であっても、神域には敬意を持った振る舞いが求められます。以下は参拝時の基本マナーです。
- 鳥居をくぐる前に一礼:神域へ入る際の礼儀として、鳥居前で軽く一礼をする習慣があります。
- 参道の中央を避けて歩く:参道中央は“神の通り道”という考えから、中央を避けて端を通る配慮が推奨されます。
- 鈴・お賽銭・拍手の作法の遵守:鈴を鳴らす際は振動音を立てすぎないよう心がけ、お賽銭は静かに差し入れるようにする、拍手のタイミングを守るなど、丁寧な動作が重視されます。
- 写真撮影の可否確認:社殿の特定部位や内部では写真撮影禁止の場合もあるため、案内板や係員の指示に従う必要があります。
番組における案内可能性
番組で「㊙エリア」を紹介できるのは、事前に出雲大社側から撮影許可を得た場所でしょう。
具体的には、普段施錠されている本殿裏手や渡殿、屋根上の装飾部など、通常見られない構造的要素を見せる演出が期待されます。
また、案内役として神職資格を持つ平祐奈さんが、普段非公開の通路や神職動線を指し示しながら解説する場面は、番組にとって大きな見どころとなるでしょう。
いずれにせよ、視聴者としては“許可された非公開部”という範囲を前提に、礼節を重んじた案内になることを心構えしておくとよいです。
島根の海底“謎の遺跡”トピックを予習

地元で語られる伝承と関連ポイント
番組の予告が示す「島根の海底に謎の遺跡!?」というテーマは、出雲周辺、とりわけ島根半島・日御碕沖に伝わる“海中に沈んだ祭祀跡”の伝承と重なります。
古くからこの海域には、祭壇や階段、参道のように見える岩の配列があると語られ、ダイバーの間で“海底参拝”の対象として知られてきました。
現地ルポでは、玉砂利が敷かれたトンネル状の地形や「亀石」と呼ばれる岩配列が紹介され、「人工的に加工された痕跡のように見えるが正体は不明」という“未解明”の魅力が強調されています。
伝承面では、日御碕の沖合にかつて祭祀の場があり、その一部が海に没したと語られてきた旨の記録があり、海中地形と神話・祭祀伝承が結び付けて論じられてきました。
こうした背景は、今回の“謎の遺跡”企画が「地形の特異性」と「出雲の信仰世界」を交差させて検証する土台になるはずです。
ダイバー発見情報と番組の検証視点
フジテレビの次回予告では、「地元ダイバーが発見!」という書きぶりで、遺跡風の海中地形を取り上げることが明示されています。
実際、出雲・日御碕沖には「海底遺跡ポイント」と呼ばれるダイビングサイトが複数の事業者・ガイドで紹介され、祠跡・参道・洞窟・亀石・滝跡といった“名称”でポイントが整理されています。
さらに、2025年9月末のダイビング投稿など、SNS上でも“海底遺跡を見た”という最新の現地発信が継続しており、話題の鮮度は高い状態です。
番組はこうしたローカルなダイバー情報と映像検証を組み合わせ、地形の成因や“人工物説/自然地形説”の見極め、伝承との符合を確認する流れが予想されます。
別番組ながら、2025年4月の特番でも「出雲の海に海底神社? 海底に沈んだ参道?」といった切り口で日御碕周辺の“海底神話”が取り上げられており、“見映えのする海中地形”+“神話・祭祀由来の語り”という二重構造が、今年に入って全国放送級で再評価されている文脈も押さえておくと理解が深まります。
放送で解明されそうな論点(仮説と検証の流れ)
今回の放送で特に注目したいのは、(1) 形態の実証(2) 伝承との照合、そして(3) 安全面・公開性の整理という三つの論点です。
(1) 形態の実証では、階段状・参道状に見える部分が浸食・断層・節理など自然作用で説明できるのか、あるいは人為的加工を示す規則性がどれほど確認できるかがポイント。
テレビ映像は“連続したスケール感”と“俯瞰”を補い、現地ダイビング情報で断片的に語られてきた地形群を一つの“面”として把握する助けになります。
(2) 伝承との照合では、「かつて祭祀の場が海に没した」という語りと現在の海底地形が、祭祀施設の“痕跡”として合理的に結びつくのか、神話・民俗学的モチーフとしての象徴性にとどまるのかを見極める作業が想定されます。
(3) 安全面・公開性の整理として、一般視聴者が関心を持つダイビング/見学の可否やロケでの撮影許可の取り扱い、保全配慮(立入や撮影のルール)等も、番組を通して“どこまで開かれた場所なのか”の目安が共有されるはずです。
これらは番組公式の次回予告がうたう「地元ダイバー発見」「伝承との関連」を踏まえれば、映像+取材で検証が進むと期待できる領域といえます。
まとめ:出雲大社 × 平祐奈 × 海底遺跡、期待と視点をもって観よう

今回の『世界の何だコレ!?ミステリー』スペシャルでは、神職資格を持つ女優・平祐奈が案内役として登場し、出雲大社の“意外な参拝方法”や㊙エリアの探訪、そして同時に展開される島根の海底に眠る“謎の遺跡”調査という二つのテーマを軸に放送されます。
公式サイトにもその趣旨は明示されており、番組はこの両柱を鮮やかに交錯させて視聴者の興味を引く構成を意図しています。
まず、平祐奈さんが神職資格保持者である点は、番組内で単なるタレント出演を超えた“専門性を伴う案内役”としての位置づけを確立しています。
彼女の知見を通じて、参拝作法の背景や神社構造の意味づけが視聴者に伝わる可能性が高く、ただ“見せるロケ”にとどまらない深みを与える要素となるでしょう。
次に、出雲大社における“意外な参拝方法”と“㊙エリア”という切り口は、一般参拝では触れにくい部分を照らす企画であり、四拍手作法や祓社ルート、社域非公開領域への案内など、普段目にできない神域の構造と礼儀を知る機会になりそうです。
この点は視聴者にとって、参拝の知識をアップデートする楽しみを提供するでしょう。
そして、島根の海底遺跡調査のテーマも只の“ミステリー”要素にとどまらず、地元ダイバーの発見情報や伝承との照合を番組的に検証する構成が予告で示されています。
これは、自然地形と人工構造の境界線をどこに引くか、あるいは伝承的構図と現実地形の整合性がどこまで取れるか、という論点に挑む意味を持つテーマです。
番組としては、観測映像・取材記録・神話・地形学的視点を織り交ぜながら、視聴者を仮説と検証のプロセスに引き込む意図が感じられます。
視聴する際の注意点としては、番組演出と実証性の区別を意識することです。
つまり、映像的に“見映えのする非公開部”を演出で強調する可能性はありますが、必ずしも全ての非公開区域が自由に案内されるわけではありません。
また、海底遺跡の部分も“人工構造説”と“自然地形説”の対立が予め想定されるテーマであり、最終判定が示されるかどうかは映像バランスと編集判断に依存する面があります。
とはいえ、本企画は“信仰の場”と“地形ミステリー”の融合という観点で、従来の歴史番組・探検番組とは一線を画す意欲的な編成と言えるでしょう。
番組を視聴した後には、以下のような切り口で振り返ると理解が深まります。
- 平祐奈さんの発言・案内をもとに、これまで知らなかった参拝作法や神社構成を整理
- 番組で公開された非公開部・㊙エリアと、公式資料・神社の立入許可範囲との整合性チェック
- 海底遺跡映像と地質・海洋地形学的な見地から“自然地形説 vs 人工構造説”を比較
- 番組後に発表される取材裏話・専門家コメント・追加情報を追って、理解を拡張
最後に、出雲大社や島根の歴史・文化・自然に興味を持つ方にとって、この番組は「知識を再構成するきっかけ」を与えてくれるでしょう。
視聴を楽しむにあたって、知的関心と先入観を交えずに耳を傾けることをおすすめします。
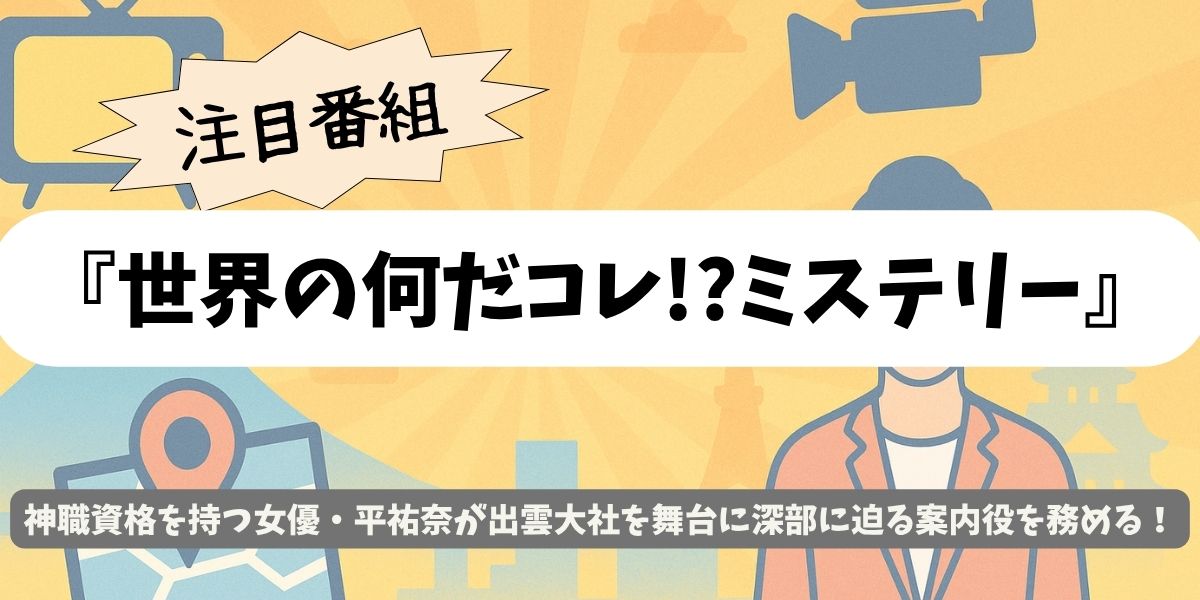
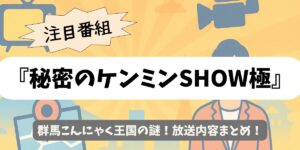
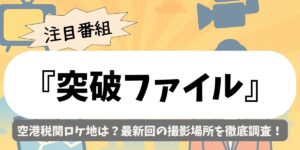
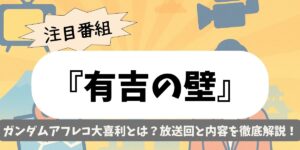
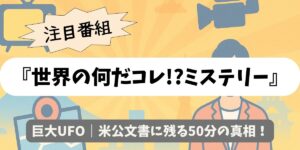
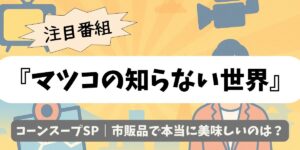
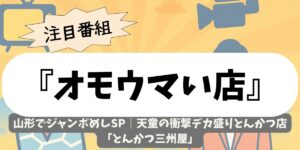
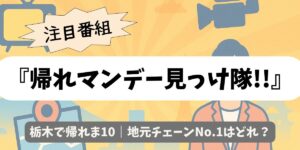

コメント