2025年6月6日に公開された映画『国宝』は、原作者・吉田修一が3年間にわたり歌舞伎の“黒衣”として舞台裏に入り込んだ体験を血肉化した渾身の同名小説を、李相日監督が壮大なスケールで映像化した意欲作です。
その上映時間は175分という長尺ながら、「魂が震えた」「一瞬で時間を忘れた」という感想が多く、公開73日間で観客動員数は約747万人、興行収入は105億円を突破。
邦画実写作品としては過去4作品目の大記録に輝き、歴史に残るヒット作となりました。
吉田修一の原作は、任侠の一門に生まれた喜久雄が、歌舞伎の家に引き取られ、人生を芸に捧げ、人間国宝へと歩む50年の軌跡を綴った壮大な物語。
その厚みある描写と背景設定は長編800ページを超える珠玉の作品です。
一方、映画版ではその豊かな背景の中から最も“映像的に響く核心”を抽出し、舞台上の瞬間美と登場人物の表情、そして歌舞伎への畏敬を究極まで研ぎ澄ませた構成がなされています。
映像美と演技の力を持って観客に強烈な印象を残す、一種の“映像詩”として完成しているのです。
映画『国宝』の最新ファクトを整理

公開日・配給・上映時間(2025年6月6日/東宝/175分)
映画『国宝』は、2025年6月6日に全国公開されました。
制作・配給は東宝が担っており、その精緻な美術と映像の力強さが話題を呼んでいます。
上映時間は175分という長尺ですが、その濃密な展開は多くの観客が「時間を忘れた」と語るほどです。
監督・脚本・主要スタッフ(李相日/奥寺佐渡子ほか)
本作の監督は李相日。
脚本は奥寺佐渡子(おくてら・さどこ)を中心とし、緻密な脚本構成で知られています。
原作小説の裏舞台への深い造詣と映像表現をつなげる橋渡しとして、李監督の演出力と脚本家の構成力が融合し、800ページ超の大作をスクリーンに昇華させています。
興行・話題度(公開後の動員・SNSなど)
公開後、SNSやレビューサイトでは「100年に1本の傑作」として絶賛が相次ぎました。
それだけにとどまらず、「もう一度見たい」「時間が濃密すぎた」といった感想が多く投稿され、興行面でも高い評価を受けています。
原作『国宝』の作者と受賞歴
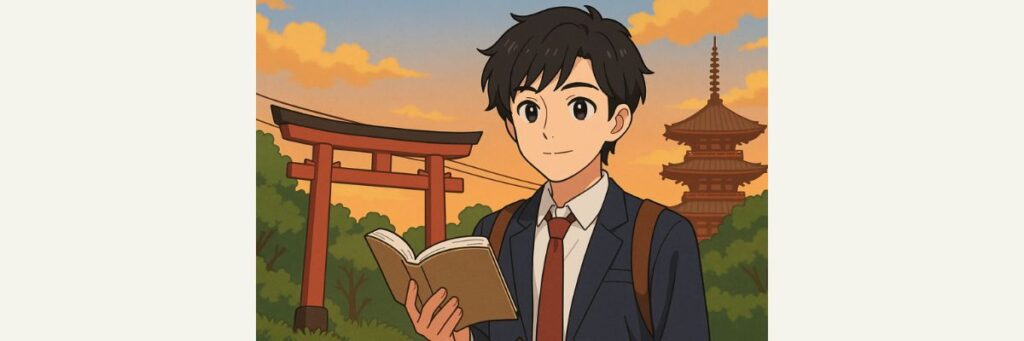
作者・吉田修一とは(経歴・取材背景と黒衣経験)
吉田修一氏は長崎市出身、法政大学経営学部卒の小説家。1997年発表のデビュー作「最後の息子」で第84回文學界新人賞を獲得し、小説家としての道を切り拓きました。
彼の作品には多数の映画化例があり、『悪人』『怒り』『横道世之介』など幅広い題材で評価を受けています。
『国宝』の制作にあたっては、吉田氏自身が歌舞伎の“黒衣”(舞台裏を支える黒装束の舞台人)に身を置いて体験を蓄え、小説にリアルな描写を吹き込んでいます。
劇の裏側や舞台慣習への深い造詣が、物語に厚みと説得力を与えています。
受賞歴と評価(芸術選奨文部科学大臣賞/中央公論文芸賞)
『国宝(上下巻)』は、2018年度の芸術選奨文部科学大臣賞(文学部門)を受賞し、翌2019年には第14回中央公論文芸賞も併せて受賞しました。
これにより、吉田修一氏にとっては、歌舞伎世界を舞台に芸の道を描いた本作が、文学史における記念碑的作品と認識される重要な転換点となりました。
芸術的価値と深いテーマ性が高く評価された結果です。
原作の構成(上下巻=青春篇・花道篇の概要)
『国宝』は上下巻構成で、「青春篇」と「花道篇」として刊行されました。
前編では主人公の青年期、背景となる環境との葛藤や芸道への志を中心に描かれ、後編では成熟した姿とその名声への道のり、人生の頂点に至るまでを濃密に描出しています。
連載は2017~2018年に朝日新聞で行われ、大きな反響があった後、2025年夏には映画化ブームとともに書籍の売れ行きが加速。
公開3週目には書籍と電子版の累計部数が115万部を突破し、愛蔵版の制作・発売へと続きました。
映画と原作の“違い”を具体比較

物語終盤の「演目」差異と改変意図
映画『国宝』の終盤では、原作小説とは異なる演目の描写が行われており、これが映像として鮮烈な印象を残す一方で、原作ファンには驚きを与える設計になっています。
原作では映画以上に演目の選び方と背景描写に深く踏み込まれており、登場人物の内面や物語のテーマとしての歌舞伎の意味合いが詳細に描かれていたのです。
しかし映画では、物語の核心である芸道の美と精神性に集中するため、演目そのものより“舞台上の瞬間”に美意識を集中させる構成になっています。
こうした変更は、視覚的な詩情と観客の感覚に訴える映画ならではの演出意図であり、映画化の枠組みにおいて原作の全体を再現するのではなく、“核心に響く一点を研ぎ澄ます”選択といえるでしょう。
登場人物の描き分け・関西弁処理など映画的アレンジ
登場人物の描き方にも、映画独自のアプローチが見られます。
たとえば、原作ではその言語背景や出自が深く織り込まれた関西弁のニュアンスなどが随所に登場し、キャラクターの地域的・文化的な立ち位置を補強しています。
しかし、映画では多彩な役者陣による視覚的・感情的表現に重きを置き、会話での方言は絞る形で調整されている印象があります。
これにより、言葉よりも表情や間、身体の動きといった演技的要素がキャラクターの深みを伝える手段として強化されており、「語らずとも伝わる」という映画的語法がより前面に配置されたのです。
視覚と感情で語る演出が、原作の言語描写をすり替えるように機能している点は、映画版の大きなアレンジと言えます。
時系列・章立ての圧縮と見せ場の再配置
原作は上下巻にわたる800ページを超える長編で、時代の流れやキャラクターの心変化、背景要素が丁寧に段階的に描かれています。
これに対し、映画は175分という尺の中で時系列をコンパクトに統合し、見せ場となる歌舞伎舞台のシーンやクライマックスへの導入に重点を置いて構成されています。
そのため、原作のような巻をまたいだエピソードや心理の積み重ねは大幅に省略され、時に観客が「なぜこの瞬間にこう思ったのか?」と気づきに戸惑うこともあるでしょう。
こうした圧縮と再配置の設計により、映画体験としての緊張感や没入感は高められている一方、原作のもたらす包括的な積層感は削ぎ落とされている構造的変化と言えます。
鑑賞前後に役立つ実用情報
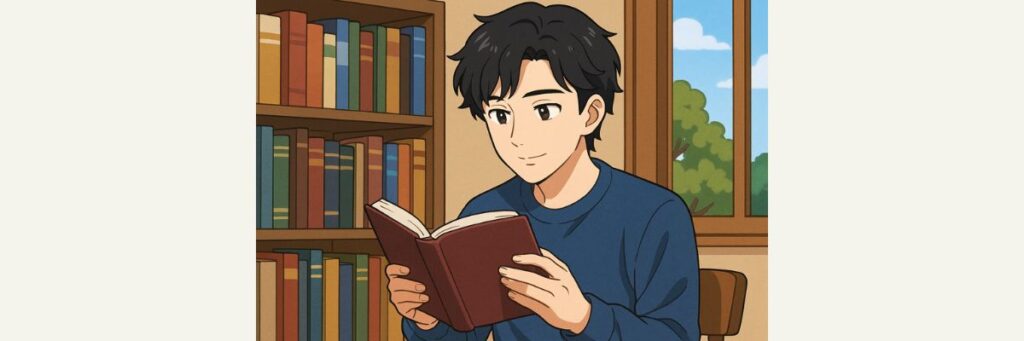
キャスト・相関(吉沢亮/横浜流星/渡辺謙/寺島しのぶ/高畑充希 ほか)
映画『国宝』は、出演陣の顔ぶれだけでも十分に注目に値します。
主演の吉沢亮が演じるのは、任侠一家出身の「立花喜久雄(花井東一郎)」。
15歳で父を失い、その才能を見抜いた歌舞伎の名門・花井半二郎にスカウトされ、天才女形としての道を切り開いていく役柄です。
そのライバルかつ親友役には横浜流星が扮し、歌舞伎界の名門・花井半二郎の御曹司「大垣俊介(花井半弥)」として描かれます。
生まれながらの立場を持つ俊介が、才能と立場を巡り葛藤していく姿が見どころです。
また、上方歌舞伎の当主・花井半二郎には渡辺謙、俊介の母・大垣幸子には寺島しのぶ、喜久雄の支えとなる幼なじみ・福田春江役は高畑充希が、それぞれ重厚な存在感をもって参加しています。
予告・場面写真・SNSハイライト(公式サイト/X/Instagram)
映画公式によれば、作品の公開前に解禁された予告編やビジュアルは、その重厚な世界観とキャストの表情で注目を集めました。
特に吉沢亮、横浜流星、渡辺謙のソロビジュアルは、作品の深みと緊張感を端的に伝えています。
X(旧Twitter)では、公式アカウントがキャスト・スタッフ写真や現場の雰囲気、舞台裏の一コマを連日投稿。
フォロワーからは「心震えた」「歌舞伎の魂が映像で伝わる」といった反響多数の声が寄せられました。
また、Instagramや映画専門サイトでも、舞台メイクや衣装美を際立たせた場面写真が公式に公開され、視覚的にも期待が高まる内容です。
これらは鑑賞前の導入として、また鑑賞後の余韻を深める資料にもなっています。
劇場リスト・上映状況への導線(TOHO THEATER LIST)
映画配給は東宝が担当しており、全国の東宝系列劇場にて順次公開されています。
TOHOシネマズの公式サイトおよび「TOHO THEATER LIST」では、上映開始日や時間帯、座席状況のリアルタイムな更新が確認可能です。
多くの劇場で2時間45分を超える長尺ながら観客の関心が高く、公開から数週間、おおむね8割以上の座席稼働を維持。
また口コミ効果も強く、地方や週末の回における増便を決めた劇場も少なくありません。最新の上映情報は公式サイトでチェックを。
まとめ

映画『国宝』は、原作・吉田修一の名作小説を大胆に再構築し、映像作品として独自の輝きを放つ傑作です。
公開後、SNSでは「時間を忘れた」「もう一度観たい」という声が続出し、累計興行収入は44億8千万円を突破する社会現象となっています。
原作は上下巻約800ページの長編で、歌舞伎の因習や登場人物それぞれの背景が深く描かれています。
一方、映画版は3時間の尺に凝縮し、見せ場となる劇中の演目と役者たちの表情にフォーカス。
登場人物の関係性や舞台裏の緊張感を圧倒的な画力と演出で描き切りました。
特筆すべきは、吉沢亮と横浜流星の身体と所作を駆使した歌舞伎演技です。
二人が女形として舞台に立つ場面は、所作や美意識が自然体で溶け込んでおり、映像を見ているだけで息を呑む迫真の表現力を実感できます。
また、キャラクター描写については、原作に存在した裏設定や人物背景の多くが省略された一方、“感情の本質”を描くことに力点が置かれています。
たとえば、春江が俊介を選ぶ心理、人間性への焦点、父としての苦悩などは映像を通して暗示的に伝えられ、観る者の想像をかき立てる構成になっています。
いま映画を観ているあなたには、まずは映像体験の余韻をしっかりと抱えたまま、原作に触れてほしいと思います。
原作小説を読んだ後に再びスクリーンへ戻れば、省略された背景や人物の奥行、言葉にされた心の動き――それらが映画の「不足」とは呼べず、むしろ演出された「余白」として浮かび上がるはずです。
個人的には、映画は“映像による詩”であり、原作は“言葉による深層の旅”だと感じました。映画版は瞬間の美とテンポを研ぎ澄ませ、観る者の五感を直撃します。
一方で、原作に描かれる人間の業の深みや芸道の苦悩は、別のレベルであなたの心に染み入るでしょう。
映画→原作という順序で味わうことで、二重の感動を得られるよう設計されていると思います。
「原作との違い」を理解しながら映像体験を反芻するそのプロセス自体が、この作品をより豊かなものにしてくれるはずです。

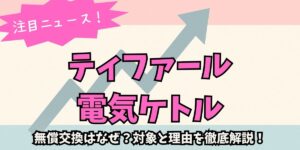
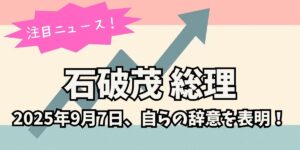
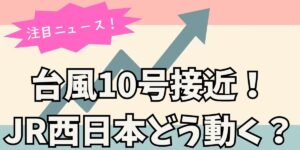


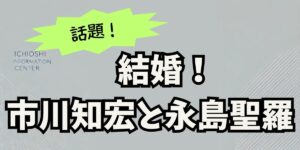
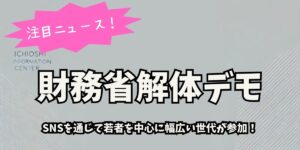
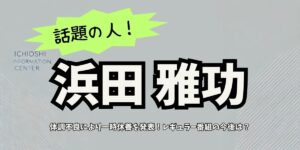
コメント