夜空を彩る花火と同じように、私たちの心に“わずかな光”を残す表現者がいる。
10月7日(火)放送の『マツコの知らない世界 憧れの職業1位【絵師】』では、まさにそのような“光”を描き出すアーティスト、藍にいなさんが登場します。
番組では、YOASOBI「夜に駆ける」のMVアニメーション制作裏側から、来場者数約100万人規模の絵師イベントへの潜入、そしてSNS時代における絵師の仕事像に至るまで、リアルな“絵師の世界”を掘り下げる内容が用意されています。
藍にいなさんは、東京藝術大学デザイン科を卒業後、アニメーション・イラスト・漫画といった表現を横断しながらキャリアを築いてきた新進気鋭のクリエイターです。
旧ペンネーム「べっこう飴」から「藍にいな」への改名後、彼女の作品は音楽映像との親和性を持ち、多くの注目を集めています。
ただ絵を描くだけで終わらない—。藍にいなさんは、絵を“メディア化”し、音楽や空間、観客体験と交差させながら表現を拡張する存在です。
番組を通して、視聴者は“絵師”という言葉の奥にある多層的な世界を垣間見ることができるでしょう。
この記事では、番組見どころ・藍にいなさんのプロフィール・代表作・絵師の現在地という四本柱で、あなたが知りたいすべての情報を丁寧に紐解いていきます。
10/7放送「絵師の世界」回の要点と見どころ

放送日時・テーマ・出演者(マツコ×藍にいな)
2025年10月7日(火)午後8時55分より、TBS系列で「マツコの知らない世界 ~憧れの職業1位【絵師】~」が放送されます。
番組では、絵師という職業を取り上げ、一般的には目立ちにくい“絵を描く人”の世界を掘り下げます。
ゲストとして、藍にいなさんが絵師の代表的存在として出演し、彼女自身のキャリアや制作現場の裏話を語ります。
マツコ・デラックスが司会を務め、藍にいなさんとの対話を軸に番組が進行。
加えて、秋の花火文化を扱うパートも併設され、絵師+花火という異色の組み合わせで構成されています。
藍にいなさん本人も、番組出演を告知する投稿で「マツコさんとイラストレーターについてたくさん話しました」と記しています。
番組が深掘りしたトピック(YOASOBI MVの制作裏・“絵師”の現在)
この回では、藍にいなさんが手がけたYOASOBI「夜に駆ける」のMVアニメーション制作過程が、番組のメインテーマとして取り上げられます。
番組予告によれば、「絵を動かす」スキルより先に“楽曲のもつ空気感を映像でどう伝えるか”という視点が語られるとのことです。
さらに、「絵師イベント」に実際に潜入して取材した様子や、その来場者数が約100万人に上るという規模感の報告も紹介される見込みです。
番組は「SNSで拡散すれば年齢や地域を問わず“プロ絵師”になれる時代になっている」というテーマも扱う予定で、絵師文化の変遷や拡張性も議論対象になるようです。
また、絵師文化の歴史的背景──初音ミクやVTuberといった存在の影響──を語るパートもあり、絵を描く現代表現がどのように受容され変化してきたかが番組を通じて整理される構成になっているようです。
関連コーナー(イベント潜入・SNSとプロ化の関係・秋花火パート)
番組構成には、藍にいなさんの核トーク以外にも複数のコーナーが設けられています。
まず、絵師イベントへの潜入取材があり、その現場の空気や来場者の反応、展示形式などを映像で伝える予定です。
イベントの規模は、報道ベースでは「来場者数約100万人」と表記されており、絵師の文化的インパクトを視覚的にも示す場面になると見込まれます。
また、SNS拡散→受注機会という流れについても番組で言及されるようです。
つまり、今は絵師が個人で発信し、フォロワーを通じて仕事を得る時代だ、という構造変化を映すパートがあります。
それによって、地域・年齢を問わず“絵師になりたい人”が参入可能になっている、ということが背景的トピックとして扱われそうです。
加えて、絵師の特集と並行して「秋花火」の世界も同じ回で取り上げられます。
番組説明には「最新音楽演出&世界に誇る日本の花火職人の裏側に迫る」ことが記されており、こちらも視覚・音響表現という切り口で、「花火×音楽×映像美」がテーマになるものと思われます。
このように、メインの“絵師”パートに加えて、視覚芸術と夜空を彩る花火との対比や親和性を見せる構成で、「知られざる美の領域」を番組テーマとして拡げる意図が感じられます。
藍にいなのプロフィールと歩み

東京藝大デザイン科卒/漫画・アニメ・イラストの横断キャリア
藍にいな(あい・にいな)さんは、東京藝術大学デザイン科卒業のアニメーション作家・イラストレーター・漫画家です。
芸大在学中から、音楽と映像を融合させた表現に強い関心を持ち、卒業制作の段階ですでにアニメーション監督としての感性を示していました。
大学ではデザイン理論とアニメーション実技の両面を学びつつ、音楽との共鳴をテーマにした作品制作を続けたことが、後のキャリア形成に直結しました。
学生時代のインタビューで彼女は「音を絵で“翻訳”することが自分の表現の出発点」と語っています(東京藝大広報誌2020年春号より)。
卒業後はフリーランスとして活動を開始。
アニメーション、グラフィックデザイン、漫画、ジャケットイラストなど、媒体を横断した制作スタイルを貫いており、本人のSNSプロフィールにも「アニメーション作家・イラストレーター・漫画家」と三職種を並列で表記しています。
アートワークの特徴は、透明感のある色彩と人物の“内面の温度”を感じさせる繊細な筆致。アニメーションでは動きよりも「時間の質感」を描く点に特徴があります。
東京藝術大学という美術系最高峰の教育環境で得た造形力と、SNS文化を吸収した新世代の視点が融合した存在と言えるでしょう。
改名経緯(元・べっこう飴→藍にいな)
藍にいなさんは、以前は「べっこう飴」というペンネームで活動していました。
改名は2019年12月頃に行われ、当時自身のTwitter(現・X)で「今後は藍にいなとして活動します」と公表。
以降、商業案件やメディア出演などすべてを新名義で統一しています。
旧名義「べっこう飴」は、個人制作時代に使用していたもの。
イラスト投稿サイトや自主アニメのクレジットにも残っており、ファンの間では長く親しまれていました。
改名の理由については本人のnote投稿(2019年12月付)で、「名前を“作品の器”として、より明確な自分の色を出したいと思った」と説明しています。
「藍にいな」という名前は、彼女が好む色“藍色”と、“新しい命”を意味する「にいな(新生)」の音を掛け合わせた造語とされています。
以降の活動では、映像監督やグラフィックディレクターとしてもこの名前でクレジットされており、実質的なブランド名として確立しています。
改名後は、YOASOBI「夜に駆ける」MVを皮切りに音楽業界での知名度が一気に上昇。
名前の持つ印象的な響きと作品のビジュアル世界が結びついたことで、“藍にいな”というアーティストネーム自体が表現の一部になっています。
書籍・作品集(『セキララマンガ 眠れぬ夜に届け』『羽化』ほか)
藍にいなさんは、アニメーションだけでなく、漫画家・イラストレーターとしての出版活動も精力的に行っています。
代表的な書籍に、KADOKAWA刊『セキララマンガ 眠れぬ夜に届け』(2021年)があり、これは深夜のSNS投稿をもとにした短編集です。
作品集『羽化』(2022年、自主出版)は、YOASOBI「夜に駆ける」以降に描かれたアートワークを中心に、音楽と感情を結びつける彼女の世界観を可視化した一冊。
ページ構成はストーリーマンガ、静止画、詩的なテキストを組み合わせたアートブック形式で、映像作品とは異なる“止まった時間”の表現を試みています。
また、女性誌『装苑』(文化出版局)や音楽誌『ROCKIN’ON JAPAN』でもイラスト連載やインタビューが掲載されており、単なる“イラストレーター”ではなく、ビジュアルストーリーテラーとしての地位を確立しています。
2024年には、初の個展「記憶の温度展」を渋谷PARCOで開催。展示では原画や映像インスタレーションに加え、観客が“音と絵で感情を再生する”体験型展示を展開しました。
個展公式サイトのコメントで、藍にいなさんは「見る人の感情の中で作品が完成する瞬間がある」と述べており、これは彼女の創作全体に通じる思想でもあります。
このように、藍にいなさんのキャリアは、出版・展示・アニメーションのすべてを通じて“絵で感情を描く表現者”として一貫しています。
メディアを越えて心の揺らぎを可視化することこそが、彼女の創作の核といえるでしょう。
代表作とビジュアルワークの特徴

YOASOBI「夜に駆ける」MV(監督・アニメーション/配信ジャケット)
藍にいなさんの代表作として、まず最も知られているのがYOASOBI「夜に駆ける」のアニメーションMVの制作です。
ウィキペディアにも、このMVが藍にいなさんの著名な実績のひとつとして記載されています。
このMVは2019年に公開され、YouTube上で累計再生数が2.7億回を突破したという報道もあります。
藍にいなさんは、この映像で“歌詞の語る情感を視覚化する”という難題に挑み、静かな時間推移や色彩の揺らぎを重視した演出を採用しました。
「夜に駆ける」はもともと短い物語をもとにした楽曲であり、藍にいなさんは楽曲の持つ感情(恋心、夜の闇、後悔と再生)を視覚的に拡張する役割を担いました。
彼女のタッチは、線や色で“呼吸”を感じさせるような、静と動の余白を大事にする作風です。
インタビューでも「音の余韻を絵で呼び出したい」と述べています。
また、MV公開後、藍にいなさんは「夜に駆ける」以外にも、昭和歌謡「木綿のハンカチーフ」のMV制作にも挑戦しており、音楽ジャンルを越えた“歌と絵の世界”を広げています。
この代表作は、藍にいなさんが“歌を視覚的に読む力”を持つクリエイターとして業界で頭角を現す契機となった作品です。
Ado「私は最強」MV、マカロニえんぴつほか音楽系コラボ
藍にいなさんは、Ado × Mrs. GREEN APPLE の劇中歌「私は最強」のMV制作でも強く注目を集めました。
このMVでは、主人公「ウタ(Ado)」を中心に、色彩の強さと躍動感のあるアニメーションで世界観を構築。ティザー版から公開後にはカラフルかつ力強い描写が特徴と評されました。
YouTube版MVのクレジットには、監督・アニメーション担当として “Ai Nina” の名前が記載されています。
この映像作品は、劇場用アニメ「ONE PIECE FILM RED」へのリンクも持ち、作品性と商業性の両立が評価されました。
また、藍にいなさんは他にも音楽分野のコラボ実績があります。
たとえば、マカロニえんぴつなどの音楽系アーティストとの映像・イラストタッチの重なりによって、楽曲の「空気感」を視覚に落とし込む手法を用いています。
これらのコラボでは、曲のテンションや歌詞の詩的要素を視覚語で拡張することが、彼女の得意領域とされています。
ライブ/イベント映像・テーマ企画(椎名林檎バックアニメ、マジカルミライ等)
藍にいなさんの表現は、MVにとどまらずライブ映像、アニメーション演出、テーマ展示など多岐に拡がっています。
たとえば、日本の音楽フェスやアーティストライブでバック映像や投影用アニメーションを担当した事例が複数あります(インタビュー記事で言及されており、“音楽と絵を同期させる演出”を手がけると語られています)
また、テーマ企画として、藍にいなさんは「絵と匂いや温度感をリンクさせる展示」も行っています。
彼女の個展「記憶の温度展」では、観客が作品を“感じる”インスタレーション演出が取り入れられ、音・光・空間を絡めて絵を体感させる形式が採られていました。
また、アーティスト椎名林檎のステージ映像で、バックアニメーションを手がけた事例もメディアインタビューで名前が挙がっています。
さらには、初音ミク・マジカルミライといった“音楽と映像の融合イベント”における参加意欲も公言されており、ライブ空間を“動く絵”の世界として演出する力を持つ作家として認知されています。
こうしたライブ・イベント系実績は、藍にいなさんが静止画/映像のみならず“現場空間そのものをデザインする”表現者であることを示しています。
“絵師”という仕事の現在地と拡張

SNS発信→受注へ:ポートフォリオとセルフディレクション
藍にいなさん自身が、SNSを活動基盤として育ててきた絵師の典型例といえます。
藝大在学中からTwitter(現在はX)へイラストを投稿し、反応を見ながら表現を変えていった経験があります。
藝大公式インタビューでは、最初期には「イラストでは反応を取れず、漫画投稿に移ったら反応が来るようになった」と語っており、SNSを実験場として用いてきた過程が窺えます。
公開された作品が多くの目に触れるにつれ、企業や音楽アーティストとのコラボ案件の話が舞い込むようになり、“発信力”そのものが営業ツールとなったかたちです。
藍にいなさんは、Xの自己紹介欄に「イラストレーター兼イメージディレクター」と名乗っており、単に絵を描くだけでなくコンセプト設計や表現統括を担う立場で受注を得ていることが窺えます。
また、インタビューで「個人のものづくりの第一歩は踏み出しやすくなっている」と述べ、作品をSNSに載せることで初期の成功機会を得やすい時代になっているという認識を示しています。
これは、発信→反応→改善→信頼構築→仕事依頼 というサイクルを、個人作家が自律的に回せる構造が現代の絵師像だということを示しています。
このように、従来は編集者や企業を仲介者とした受注構図が主流であったのに対し、現在の絵師はSNSを通じて直接クライアントやファンと関係を構築し、「自らのブランド価値」で仕事を得る流れが標準になりつつあります。
イベント・コミュニティの広がり(来場規模や層の変化)
「絵師イベント」の規模拡大が、絵師という職能の裾野を広げています。
番組『マツコの知らない世界』の予告情報によれば、今回の回で「来場者数約100万人の絵師イベントに潜入」というフレーズが使われており、絵師を主題とする催しが大規模化していることを示す目安となっています。
また、絵師100人展という恒例企画も、国内外を巡回する形で認知度を上げています。
「絵師100人展」は2011年開始以来、秋葉原を起点としつつ巡回展も併設し、これまで延べ来場者数が80万人以上に上ると公式サイトで告知されています。
この種の展示企画は、プロ絵師だけでなくアマチュア・新人も参加できる場を提供し、コミュニティの発展と次世代人材育成の役割も果たしています。
また、同人・ハンドメイド系のイベント(例:HandMade In Japan Fes など)にもイラストレーター/絵師出展枠が大きく設けられており、毎回数千〜数万人規模のクリエイターと来場者が集まる機会となっています。
こうした場では、直接のファンとの対話、作品頒布、サインや名刺交換が活発化しており、絵師にとって“現場力”を鍛える機会にもなっています。
これらの流れを背景に、絵師活動はネット中心だったものから、実際の物理空間を舞台に拡張しており、ファン層や交流機会の多様化が進んでいます。
表現と職能の交差点:アートディレクション/イメージディレクターという役割
藍にいなさんは、単なるイラスト/アニメーション作家を超えて、“イメージディレクター”“アートディレクター”的な役割を兼務するスタイルを見せています。
Xで「イラストレーター兼イメージディレクター」と自己紹介しているのがその表れです。
インタビュー記事では、「怖さも不気味さも作品の武器になる」という発言があり、絵としてのビジュアルを演出するだけでなく、観る側に呼びかける感情設計を重視していることが語られています。
これは、絵師が表情や線・色だけで物語を語る能力に加え、作品空間や観客体験をも設計する職能への拡張を意味します。
また、彼女が手がけるMVやライブ演出では、映像・音楽・演出を統括する役割が要求されることが多く、単に“絵を描くこと”以上の統合力が求められています。
藍にいなさんのキャリアを見ると、「曲の物語を膨らませて映像に落とし込む」「観る人の感情を誘導する画面構成を決める」など、ディレクター視点での概念設計力が作品の根幹になっていることが伝わってきます。
このように、現在の絵師は「描画スキル」だけではなく、演出・構成・体験設計を含んだ複合的な職能を担う存在へと変化しており、藍にいなさんはその最前線を走る一例となっています。
まとめ

今回の放送「マツコの知らない世界 憧れの職業1位【絵師】」では、藍にいなさんという“絵師”の最前線にいる人物を通して、「絵を描くこと」がどのように意味を持ちうるかが丁寧に浮かび上がりました。
放送内容、藍にいなさんの歩み、代表作、そして絵師という働き方の現在地を振り返ると、以下のような見通しが得られます。
まず、「絵師」という存在はかつて“趣味・副業”の延長に見られることもありましたが、今や音楽アーティストやライブ演出、企業広告作品など、表現の主要軸と直結する役割を担います。
藍にいなさんが手がけた YOASOBI「夜に駆ける」MV や Ado「私は最強」MV は、ただ“絵をつける”という役割を超えて、楽曲の世界観そのものを可視化する重要な表現装置になっています。
さらに彼女のキャリアを振り返ると、「SNS発信 → 受注」という流れを能動的に使い、自らの見せ方をデザインして仕事に結びつけてきた点が印象的です。
改名に際して名前をリ・ブランディングし、絵師としての自己を明快に示したことも、ひとつの戦略と見ることができます。
絵師イベントの来場者数増加、展示企画の全国巡回、コミュニティの拡張も、単なるファン層の拡大にとどまらず、絵を真剣に仕事にしたい人たちの“門戸”を押し広げています。
さらに、藍にいなさん自身も「イラストレーター兼イメージディレクター」として、作品の設計・演出を含めた責任を負う姿勢を明示しており、絵師の仕事が「描き手」から「表現統括者」に変化しつつあるトレンドを体現していると言えるでしょう。
個人的感想を添えれば、この一連の流れは、現代の表現者が「技術」だけでなく「文脈設計力」や「自己ブランディング力」を持たなければ生き残りにくい時代を示しています。
藍にいなさんのような型破りな表現者は、その挑戦と可能性を体現している存在だと感じます。
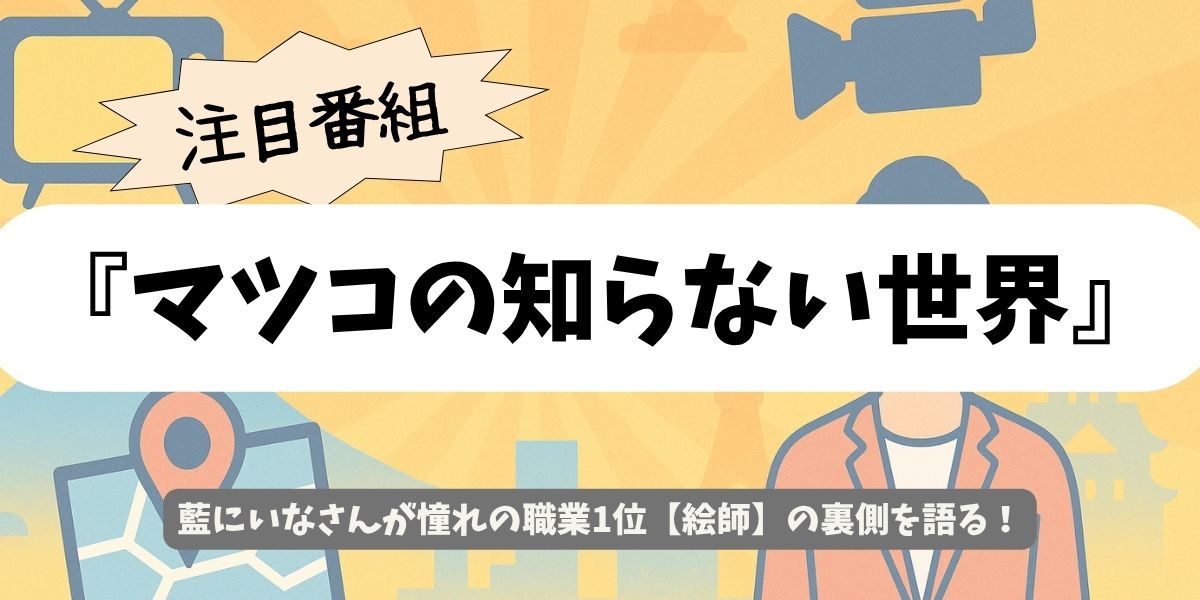
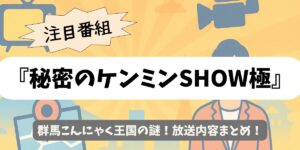
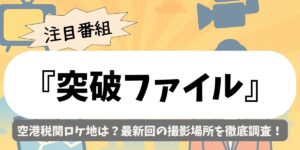
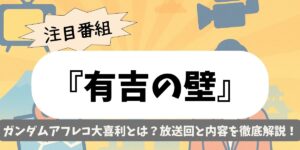
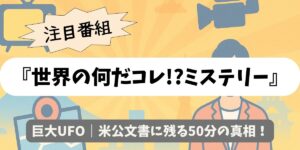
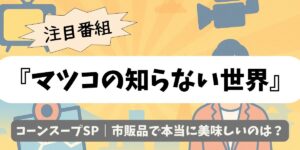
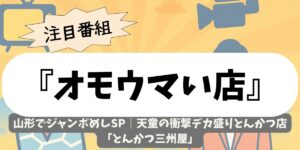
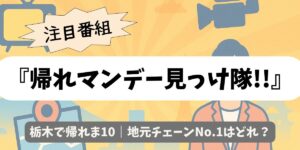

コメント