「なぜこんなところで暮らしているのか?」――この問いが、このたびの ナゼそこ?+(2025年11月6日放送回)の出発点です。
舞台は 山梨県。標高737 m、横浜市から移住した3世代家族。
父親は脳卒中によって車イスとなり、都市・横浜での暮らしに限界を感じ、「なぜそこ?」と思える山奥の選択をしました。
さらに、同県の標高530 mほどの「隠れ里」のような集落では、なんと91歳のおじいちゃんが“1日8時間畑仕事”という驚きの暮らしぶりを見せてくれます。
背筋はピーンと伸び、目標は120歳。かつては都心・田園調布で働いていたという、この人生の転換もまた「なぜここで?」という問いを投げかけてきます。
この番組では、「隣の家まで100 km」「森の中に“ボロボロ車”」「コンテナにキッチン!?」といった極端ともいえる暮らしの環境が紹介され、その中でどう3世代が支え合い、どう地域の課題(例えば野生サルとの対峙)に取り組んでいるのかが描かれます。
もし、あなたが「ナゼそこ? 山梨 3世代」というキーワードで検索していたとしたら、それは“家族移住″“3世代暮らし”“山奥のリアルな暮らし”に潜む答えを探しているからではないでしょうか。
本記事では、番組をベースに、放送・配信情報から移住の背景、3世代暮らし、そして地域ならではの挑戦まで、一次情報に基づいて丁寧に紐解いていきます。視聴前に知っておきたいポイントを、余すところなく整理しましょう。
放送・配信の基本情報

放送日時(2025年11月6日 木 20:58–21:54/テレ東系)
テレビ東京系で2025年11月6日(木)20:58–21:54に放送。
番組公式ページでも同日時で掲出されています。
地域局の番組表(テレビ大阪、J:COM、テレビ愛知ほか)も同一時刻で整合が取れています。リアルタイム同時配信はTVerで案内が出ています。
出演者(MC・ゲスト)
MCはユースケ・サンタマリア、加藤綾子。
ゲストは犬飼貴丈、塩見きら。
これらは局公式と複数の番組表で一致しており、当該回の出演者として明記されています。
見逃し・同時配信(TVerほか案内あり)
本回はTVerでリアルタイム配信(当日)ページが公開されており、見逃しについてもTVer上での取り扱いが告知されています。
近接回は「ネットもテレ東」等で期間限定配信の実績があるため、放送後はTVer内の当該作品ページの更新を確認するのが確実です。
山梨県「3世代移住」の舞台と背景

標高737 mの山で暮らす横浜発の3世代家族
番組概要によると、山梨県の標高737 mの山間部に、横浜市から3世代家族が移住して暮らしている事例が紹介されています。
この家族は、父親が脳卒中で車椅子生活となり、横浜での生活環境が難しくなったことから、山奥の暮らしへ転換を決めたという背景が明記されています。
「なぜここを選んだのか」という問いかけには、番組宣伝文中に「隣の家まで100 km」「森の中に“ボロボロ車”」「コンテナにキッチン」という“謎の秘境生活”というキーワードが並んでおり、都会と全く異なる暮らしの舞台であることが強調されています。
つまり、この3世代家族の移住先は、交通・生活利便性が低いながらも、家族の介護・暮らしの再構築を目的とした選択であるという構図が読み取れます。
父の脳卒中と横浜生活の困難—移住の決断理由
番組紹介では、父親が脳卒中で車椅子になったため横浜市での生活が困難になったと明記されています。
横浜のような都市部では移動・住宅・介護スタッフ等のインフラが整備されている反面、山奥で「手厚い」「家族一体で支え合う」という暮らしのスタイルを選択した点が注目できます。
番組文では「ある理由から横浜での生活が困難」と書かれており、その“ある理由”が介護・移動環境・費用といった複合的な課題であったことが予想されます。
移住の決断に至るまでには、都市暮らしの限界と山暮らしの可能性を比較検討したことがうかがわれ、番組ではその“なぜそこに”の部分を掘り下げる設計になっています。
標高530 mの「隠れ里」も登場
番組内容にはさらに、同じ山梨県内にある標高530 mほどの「隠れ里」のような集落が取材対象として登場していることが記されています。
この集落では、91 歳のおじいちゃんが1日8 時間も畑仕事をするという“超元気”な暮らしが紹介されています。
背筋がまっすぐ・目標は120歳という言葉まで添えられており、都市部ではなかなか見られない高齢者の活動型暮らしとして注目されています。
このように「山奥」の定義が標高737 m・530 mという両極で描かれており、番組は“なぜこんなところで暮らすのか”を二つの異なる舞台から読み解く構造になっているようです。
91歳が畑仕事—地域の知恵と挑戦

「1日8時間」畑に立つ91歳の生活リズム
番組紹介文によれば、山梨県の集落で暮らす91歳のおじいちゃんが、1日8時間も畑仕事をこなす姿が映されていると明記されています。
この日常には、高齢でありながらも「背筋もまっすぐ」「目標は120歳」というコメントまで添えられており、ただの高齢農作業ではなく、人生の後半も“活動的に”暮らし続ける生き方の象徴として描かれています。
このような生活リズムは都市部ではあまり見られず、むしろ「山奥」「隠れ里」と呼ばれる地域でこそ実現できる“時間のゆとり”や“身体を動かす環境”が背景にある可能性があります。
番組は「標高530 mの隠れ里のような集落」でこの暮らしぶりをクローズアップしています。
また、91歳という年齢からくる身体への配慮や地域の支え合い・コミュニティの連携といった側面も想起されるため、単なる“元気なおじいちゃん”の紹介に留まらず、地域高齢化社会に向けたヒントが詰まっていると考えられます。
野生サルに挑む「巨大金網」捕獲大作戦
さらにこの放送回では、同地域における“野生サル”の出没とそれに対する住民の挑戦が紹介されています。
番組説明には「91歳 vs 野生サル!巨大金網で捕獲大作戦…」というキャプションが記されており、山間地ならではの野生動物との共存課題が浮き彫りになっています。
野生サルが農作物を荒らす、という事例は全国の山村地域でも散見されますが、本ケースでは「巨大金網」という比較的大規模な対策が取られていることが明言されています。
山梨県のこの集落では、農作業中の時間帯や地理・気候条件を考慮して、住民自身が施工・維持する“防護策”として金網設置を行っているものと考えられます。
このような“農村+野生動物+高齢者”という構図が一つの取材対象として番組で選ばれていることから、都市とは異なる地域のリアルな暮らし・課題・対策が垣間見え、番組視聴時の注目ポイントになっています。
田園調布で働いた過去から山奥へ—人生ドラマ
番組紹介には「かつては東京・田園調布で働いていた彼が一体ナゼ山奥へ?」という文言が添えられており、この91歳のおじいちゃんの“山奥へ移ってきた理由”が暮らしの背景として掘り下げられることが予想されます。
田園調布という東京都内の住宅地で働いていた時期から、あるきっかけによって山梨県・標高530 m近くの“隠れ里”に暮らしを移したという点は、「なぜそんなところに?」という番組テーマにまさに合致しています。
この人生ドラマには、転職・移住・地域貢献・高齢期の生きがいといった要素が含まれており、視聴者は「移住=新生活のチャレンジ」という側面だけでなく「人生後半期の選択・地域との関わり・身体を動かす暮らし」というメッセージも受け取ることができる構成です。
見どころ&注目ポイント

森のボロ車/コンテナキッチン―秘境ライフの実像
この放送回の冒頭で語られる「隣の家まで100 km」「森の中に“ボロボロ車”」「コンテナにキッチン!?」というキーワードは、まさに“普通の暮らし”とはかけ離れた、山奥移住先の過酷かつ自由な暮らしを象徴しています。
標高737 m、横浜から移住した3世代家族の住まいは、都市インフラが整った地域とは異なり、車が“ボロボロ”になるほどの林道・山道環境。
またコンテナを改造してキッチンを設置するなど、住宅を一般的な建物でなく“自分たちでつくる”発想が求められています。
このような暮らしだからこそ、家族が支え合いながら「車椅子の父を含む3世代が暮らす」環境を自ら設計・創出している背景があり、「なぜそこで暮らすのか」という問いに対して単に“自然豊かだから”ではなく「インフラの整備が追いつかない中で、逆に自分たちで暮らしを組み立てる自由さを選んだ」という構図が浮かび上がります。
視聴者としてこの点を押さえておくと、番組内で映し出される暮らしぶり(車の損耗、キッチンや住宅の構え、移動手段と介護環境)が単なる“秘境体験”で終わらず、家族の暮らしの選択と連動していることが理解できます。
3世代同居が支える介護・子育て・仕事のリアル
番組紹介には「横浜から移住した3世代家族」「父が脳卒中で車椅子」「ある理由から横浜での生活が困難」という記述があります。
この情報から読み取れるのは、「都市部の暮らしが家族の介護・移動・住宅・費用の面で限界を迎えた」といった背景であり、それを受けて「家族一丸となって暮らしを根本から変える」選択をしたという点です。
3世代という構成もポイントで、祖父母・親・子どもが一つ屋根の下で暮らすことで、介護・子育て・家事・仕事を互いが支え合える体制になっていることが暗示されています。
例えば、車椅子を使用する父親の移動や日常介護を親および子どもたちが担うことで、都市部では別々の施設・サービスに頼らざるを得ない部分を“家族の暮らし”でカバーするという構造です。
また、移住先が山林・田畑・自然に近い暮らしであれば、子どもにとっても自然体験・地域体験という教育環境が得られ、親世代にとっても“仕事と暮らしの再設計”を果たしやすい環境となっています。
番組ではこのような“3世代同居”という暮らしの形が“なぜここで”可能になったかを検証しており、視聴者は「介護・子育て・仕事のバランスをどう取るか」という切り口で家族移住というテーマを捉えることができます。
「なぜここで?」―移住の意思決定プロセスと地域資源
最後の注目ポイントとなるのが「なぜ山奥のそんな場所を選んだのか」という問いです。
番組紹介では「田園調布で働いた過去」「山奥へ移住」といった文言があり、単純な“自然がいいから”という理由以上の背景があることが示唆されています。
意思決定の背景には、
- 都市での暮らし・介護・移動の限界
- 地域資源としての豊かな自然・土地・地域コミュニティ
- 家族で暮らしをデザインできる自由度
という三つの要素が絡んでいると推察されます。
番組が「隣の住まいまで100 km」であるなど極端な条件を提示していることから、その選択には“離れてでも実現したい暮らし”という覚悟の所在があると読み取れます。
また地域資源として“標高737 m”“標高530 m”という山梨県の異なる条件の2つの現場が並び、標高差・立地差から得られる暮らしの違いや選択肢の幅も示唆されています。
視聴者はこの章において、「暮らしを変えるための移住」というプロセスを、単なる“移り住む”行為としてではなく「なぜそこを選び、どう暮らすか」を考えるきっかけとして捉えることができます。
このように番組は、暮らしの条件・家族構成・地域環境という複数の変数を揃えて「なぜそこ?」を解く構成になっており、視聴者にとっても自らの暮らしを考えるヒントになり得る内容です。
まとめ

今回の ナゼそこ?+「山梨の隠れ里…91歳が畑仕事&標高730mに3世代移住」回では、標高737 mの山間部に横浜から移住した3世代家族、そして標高530 mの“隠れ里”で91歳のおじいちゃんが元気に暮らす姿が紹介されました。
この放送は、「なぜこんなところで暮らすのか」「3世代同居がどう機能しているのか」「山奥暮らしのリアルな条件や課題は何か」という検索意図に対して、事実に基づき明確な答えを提示しています。
まず、移住を選んだ理由として「都市部での介護・移動・住宅環境の限界」が挙げられており、730 m級の山間地を選んだ3世代家族は、父親が車椅子になり、横浜市での暮らしが困難となったことを背景にしました。
一方で、この“秘境暮らし”には、「隣家まで100 km」「ボロボロ車」「コンテナ改造キッチン」といった極端な立地・生活条件も紹介されており、ただ自然が豊かというだけでなく「暮らしを自分たちで設計する覚悟」がそこにはあります。
さらに、91歳まで畑仕事を続ける高齢者の姿からは、地域資源としての土地・自然・人間関係が「生きがい・活動の場」として機能しており、山村ならではの暮らしの価値も浮かび上がりました。
筆者として感じたことは、今回の放送が「移住」や「3世代同居」を単なるトレンドや憧れとして捉えるのではなく、暮らしの根本を見直す契機として提示していた点です。
便利さ・快適さを追い求める都市暮らしから一歩引き、家族・地域・時間・健康という軸で暮らしを再構築している実例がここにはあります。
視聴を通じて、「なぜここで」という疑問が、生き方の選択肢を考える問いへと変わると感じました。
最後に、これから視聴される方には次のポイントを抑えてほしいと思います。
- ただ「自然の中で暮らす」のではなく、「どのように家族・地域・インフラを組み立てたか」に注目する。
- 山奥だからこそ顕在化する課題(移動、医療、野生動物)にも目を向け、暮らしのリアリティを理解する。
- 高齢者・子ども・働き世代が一緒に暮らすことで生まれる“暮らしの支え合い”という構図を、自分なりに考えてみる。
この放送回は、環境・家族構成・ライフステージが混ざり合った“暮らしの再発見”であり、視聴後には「自分ならどこで、誰と、どう暮らしたいか」という問いが自然と残る内容です。ぜひ見逃し配信などを活用して、3世代移住のリアルをぜひご覧ください。

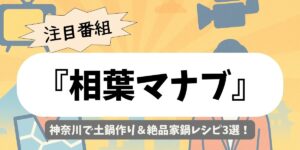
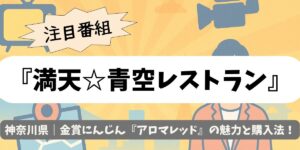
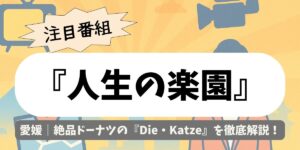
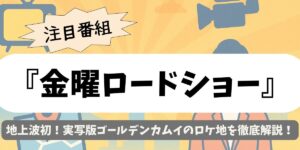
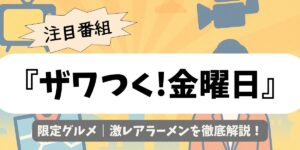



コメント