おにぎりを食べると「太るのでは?」と気になっているあなたへ――。
テレビ番組 巷のウワサ大検証!それって実際どうなの会 では、なんと「おにぎりはどれだけ食べても太らない?」という大胆なテーマを取り上げ、出演者が3日間にわたっておにぎり実践検証を行う予定です。
では「おにぎり=太る」というイメージは、本当に正しいのでしょうか?最新の栄養科学では、ご飯を含む米食品が「適切に摂れば太りにくい食材」であるという見方も出てきています。
例えば、白米には血糖値の上昇をゆるやかにする食物繊維様のレジスタントスターチが含まれており、炭水化物を抜く極端なダイエットよりも、バランスよく主食を取り入れた方が長期的に体重管理しやすいという論説も存在します。
しかし、一方で「おにぎり1個」のカロリー・糖質・脂質を無視すれば、複数個食べた際には“摂取過多”という形で太るリスクも否定できません。
管理栄養士が「太るおにぎり」と「太らないおにぎり」の違いを細かく分析している記事では、糖質量・具材・食べ方の違いが体重増加の鍵だと紹介されています。
つまり、本稿では「番組の意図」「おにぎりそのものの栄養的特徴」「実践的な食べ方の工夫」「短期検証の限界」――これらを総合的に整理しながら、あなた自身が“おにぎりをどう選び・どう食べれば太りにくくできるか”に迫ります。
番組放送前に、その背景を理解しておくことで「テレビ映え」だけでなく、日常の食事に活かす知識を手に入れましょう。
番組のポイント整理(テーマ・放送情報・出演者)

テーマ「おにぎりはどれだけ食べても太らない?」の狙いと検証方法
TBS公式の企画欄では、「おにぎりはどれだけ食べても太らない?」というギモンに対し、チャンカワイさんが3日間“おにぎりを食べまくり”というフォーマットで検証すると明記されています。
番組の定型どおり、“世の中のウマい話”を短期集中の実地検証で確かめ、放送内で結果を提示する構成です。
紹介文には「おにぎりは栄養バランスがよく、実はダイエットにも適していると言うが…実際どうなのか?」という問題提起が置かれ、視聴者が抱く“本当に太らないのか”への答えを実験ベースで探る狙いが読み取れます。
さらに、番組の公式Xでは“短期の体重変動”に関する話題(「人間のカラダは1日1キロ以上3日連続で太れない?」という専門家見解の紹介)にも触れています。
これは短期検証における体重の見え方を理解する補助線として提示されており、当日の結果解釈のヒントになります。
放送日・放送枠・出演者(MC/検証者)の確認
放送日時は2025年10月29日(水)よる7時からのSP枠(一部地域除く)で編成。
番組表でも「それって実際どうなの会【おにぎりは食べても太らない?】」として案内されています。
出演者は、MC:生瀬勝久さん。
パネラー・出演として満島真之介/大島美幸/藤田ニコル/野呂佳代/チャンカワイ/餅田コシヒカリ/大橋ミチ子/狩野英孝/大島てる/佐々木大光(KEY TO LIT)がクレジット(公式ページ記載)。
チャンカワイさんが“おにぎり検証”の当事者として登場します。
同放送回は「縄跳びVSトランポリン」や「激安ワケあり物件」「ロストボール」などの並行企画も同一枠で展開予定です。
公式予告(サイト・YouTube・SNS)で判明している事前情報
TBS公式サイトと当日ページ(番組表)では、検証テーマの文言(「おにぎりはどれだけ食べても太らない?」)と3日間検証が事前公開。
公式YouTubeの予告でも同テーマに沿った告知が出ており、当日の見どころとして“思わず『#チャンありがとう』と言いたくなる結果が!?”といったトーンの煽りも確認できます。
公式Xのポストは、体重変化のとらえ方や関連トピックを示す“導入のヒント”として機能しています。
これらの一次情報を突き合わせると、当日は「短期の食習慣操作×体重の動き」を中心に、“太らない”条件の有無をテレビ的な実験で検証する構図だと読み取れます。
おにぎりで太らないための基本原理(エネルギーバランス)

1日の総摂取カロリーと活動量の関係
食べたエネルギー(カロリー)を使い切れるかどうかが、体重変動の最も基本的な鍵です。
つまり「摂取カロリー > 消費カロリー」になれば、余った分が脂肪として蓄えられ、体重は増加します。
逆に「摂取カロリー ≤ 消費カロリー」であれば体重は維持、もしくは減少に向かいやすい。
おにぎりは主に炭水化物(糖質)を多く含むため、例えば1個 ≈ 170 〜 200 kcal程度(白米100 g前後)という目安情報があります。
したがって、おにぎりを食べる際には「今日自分が動いた量」「その他に摂取した食事・飲料」「夕食後の活動量・就寝時間」などを踏まえて、“おにぎり1〜2個がOKかどうか”を判断することが大切です。
特に座り仕事・運動習慣が少ない人が、夜遅くにおにぎりを多量に食べると、消費しきれず脂肪化しやすいリスクがあります。
このように、まず第一に「量と活動量のバランス」が太らないための基礎理論となります。
白米=高GIの弱点と“食べ合わせ”での改善策
日本人の主食である白米ご飯(=おにぎりのベースでもある)は、血糖値を上げやすい高GI(グリセミック・インデックス)食品に分類されることが研究で示されています。
例えば、米飯のGI値は84〜88と報告されており、食後高血糖のリスクに関連するという分析もあります。
血糖値が急上昇すると、インスリンが多量に分泌され、余った糖が脂肪として蓄積されやすいというメカニズムが働きます。
そこで“太らないおにぎり”を目指すなら、次のような改善策が有効です。
- 白米を玄米・雑穀米・もち麦ブレンドに変えることで、GI低下・食物繊維増加が期待。
例えば「もち麦110 gで作ったおにぎり」は白米より糖質・カロリーともに低いという実例があります。 - 食べる順番を工夫:野菜・具材たんぱく質を先に食べてからおにぎりを食べることで、糖の吸収をゆるやかにするという食事法も紹介されています。
これらを意識することで「白米ベース=太る」と即断せずに、“血糖値の上がりやすさ”という視点から量と質を制御できるようになります。
具材・海苔・油分(ツナマヨ等)による差
おにぎり1個あたりのカロリー・栄養構成は“ご飯”だけでなく「具材」「巻き海苔」「油分・調味料」「具材の種類」によって大きく異なります。
例えば、調査によると「梅干し」や「おかか」「高菜」の具を使ったおにぎりは概ね162〜170 kcal前後である一方、「ツナマヨネーズ」入りや「鶏五目」など脂質・具材量が多いものでは200 kcal以上、あるいは240 kcal近くになるというデータがあります。
したがって、“太らないため”には以下のポイントが有効です。
- 具材は「脂質・マヨネーズ・揚げ物系」など高カロリーになりやすいものを控える。
- 海苔・昆布・梅・鮭・シラス・枝豆など、比較的低脂質・高たんぱく・ミネラル豊富な具材を選ぶ。
例えば管理栄養士監修のレシピでは「桜えびと大豆の塩昆布おにぎり(203 kcal)」など、たんぱく質7.9 g・脂質2.3 gという構成例も紹介されています。 - 食べる量を1個に抑える、あるいはご飯量を減らして具材や海藻類を増やして“容量を満たすがカロリーは抑える”という考え方が効果的です。
これにより、“おにぎり=炭水化物の塊”というイメージを“炭水化物+具材+量を意識すればコントロール可能”という形に切り替えることができます。
太らないおにぎりの実践レシピと選び方

コンビニおにぎりの“避ける/選ぶ”基準
まず前提として、コンビニ各社はおにぎりの栄養成分を商品ラベルで表示しています。
購入前後にラベルで熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物(多くは糖質/食物繊維も)を確認するのが基本です。
セブン‐イレブンは商品ごとに栄養表示が異なる旨を明示し、ローソンも「おにぎり等はラベルでエネルギー等を表示」と案内、ファミリーマートはおむすびのアレルゲン・栄養成分ページを公開しています。
つまり“太らない”選びの第一歩は、ラベル確認を習慣化することです。
次に、具材と脂質量で差が出る点に注意します。
ローソンの例では、魚卵・鮭・たらこ等の“シンプル系”は1包装200kcal前後の表示が多い一方、カルビ焼肉など油を使う具材は240kcalと高め(掲載地域の例)です。
マヨネーズ系・肉系は脂質が伸びやすいため、減量中や活動量が少ない日は梅/鮭/昆布/おかか/塩など“低脂質寄り”を優先し、高脂質具材は頻度と個数を調整するのが現実的です。
さらに、同じ「おにぎり」でも規格差があります。
ファミマの“定番手巻の1.5倍”といった大きめ規格は満腹感は出ますが、総カロリーも比例して増加します。
発売日や規格・栄養は随時更新されるため、新商品ほどラベル確認が必須です。
迷ったら、
- 海苔つき(食物繊維/ミネラル)
- 具材は低脂質・高たんぱく寄り
- 標準サイズ
を基本に、組み合わせ全体の総カロリーで判断しましょう。
自作おにぎりの比率ルール(米:たんぱく質:食物繊維)
自作なら、主食(米)・主菜(たんぱく源)・副菜(野菜/海藻/きのこ等)をそろえる日本の「食事バランスガイド」を下敷きにできます。
ガイドは主食・副菜・主菜・牛乳/乳製品・果物の料理区分と“つ(SV)”という単位で、何をどれだけ食べるかの目安を示した公的指針。
料理(=実際の食べ方)ベースで考えるのが特徴で、主食を中心に副菜・主菜を組み合わせる考え方は、おにぎり設計にも応用しやすいです。
実践のコツは、米だけで完結させないこと。
例えば、
- 米:白米だけでなく雑穀・もち麦・玄米をブレンドして食物繊維を底上げ(血糖上昇の緩和に寄与)。
- たんぱく質:鮭・ツナ(水煮+少量マヨ)・鶏ささみ・卵・大豆製品などを具に選び、主菜要素を確保。
- 食物繊維・ミネラル:海苔・昆布・ひじき・わかめ・野菜系混ぜ込みで副菜要素を補完。
この“主食×主菜×副菜”の三位一体を守れば、エネルギー計上は主に米、満腹感と栄養密度は具と海藻で稼げます。
なお、エネルギー計算を行う場合は、日本食品標準成分表2020(八訂)のエネルギー算出法変更(平均約9kcal/100g低下)が導入されているため、旧表との比較に注意してください。
“比率”は厳密な固定値でなく、活動量と目的で調整します。
座位中心の日は米量を控え、肉体労働や長時間の歩行がある日は米量を増やす、といった状況適応が基本です。
公的ガイドは主食・副菜・主菜のバランスを軸に、活動量で総量を増減させる考え方を推奨しています。
タイミング別(朝/昼/運動前後)の取り入れ方
朝
一日のスタートは主食(米)でエネルギーを入れ、たんぱく質(主菜)と副菜を添えると安定します。
食事バランスガイドは主食を中心に副菜・主菜を組み合わせる考えを示しており、朝のおにぎりでも海苔・昆布+卵やツナ水煮/鮭などを組み合わせると、血糖の乱高下を抑えやすい構成になります(食べる順は野菜/具→米も有効)。
昼
活動の中心時間帯は、総量(個数)を午後の活動量と帰宅後の食事から逆算。
コンビニ利用時はラベルで脂質とカロリーを確認して高脂質具材は1個までなどのルール化が有効です(例:カルビ焼肉は240kcal表示例)。
糖質+たんぱく質+海苔/海藻の組み合わせは、満腹感と栄養密度の両立に役立ちます。
運動前後
日本のハイパフォーマンススポーツセンター(JISS)は、空腹で練習しない、運動前は炭水化物を補給、運動後はなるべく早く“炭水化物+たんぱく質”を摂ることを推奨しています。
おにぎりは運動前の炭水化物補給に適し、運動後はおにぎり+たんぱく源(ツナ水煮・卵・乳製品など)の組み合わせが理にかないます。
競技者向けの炭水化物目安(体重×g/日)はトレーニング量で変わるため、一般の人は運動量に応じておにぎりの個数を可変にするのが現実的です。
検証の前提と限界を理解する

3日間チャレンジの外挿限界と個人差
番組 それって実際どうなの会 にて “おにぎりはどれだけ食べても太らない?” というテーマで行われるのは、3日間というかなり短期間のチャレンジです。
公式番組の説明に「チャンカワイさんが3日間、おにぎりを食べまくり検証」だと明記されています。
このような短期検証は、視聴者にわかりやすく「結果」を提示するには有効ですが、次のような注意点(限界)があります。
- 3日間という期間では、体脂肪そのものが著しく増減する可能性は限定的。
体重の変化があったとしても、水分やグリコーゲン(筋肉・肝臓に蓄えられた糖)などの変動が多く、“脂肪そのものの増加・減少”を確定的に示すには不十分です。
- 参加者の体格(BMI・体脂肪率・筋肉量)、日常の活動量(仕事・運動習慣)、代謝の個人差などが大きく影響を及ぼします。
例えば、筋肉量が多い人は炭水化物を摂取しても消費しやすく、筋肉量が少ない人や運動が少ない人は余剰エネルギーになりやすいという個人差が存在します。
関連研究では体重制御には「運動・身体活動の変化」が重要であると指摘されています。
- 外的条件(食材・具材量・他の食事内容・飲料・睡眠・ストレスなど)が統一されていない場合、“おにぎりだけの影響”を厳密に特定することは難しいです。
番組としては“おにぎりをたくさん食べる”という条件を設定していますが、他の食事・運動・睡眠等がどのようにコントロールされているかは一般公開されていません。
以上のように、3日間チャレンジの結果を「長期的に太らない」と即断することは適切ではなく、「この条件下での短期的な変化を参考に、自分のライフスタイルに当てはめて考える」ことが重要です。
体重変動(むくみ・グリコーゲン)と短期検証の関係
短期間(数日~数週間)の食事変更や炭水化物量の増減が、体重計上において“見かけ上の増減”を引き起こすことは、複数の研究や解説で指摘されています。
たとえば、炭水化物を多く摂った際には筋肉・肝臓にグリコーゲンが蓄えられ、それに伴い水分も引き込まれるため、短期的に「体重が増加」することがあります。
逆に炭水化物を減らせば“グリコーゲン量減少+水分減少”で体重が落ちる場合もあります。
このため、番組検証で「おにぎりをたくさん食べたら体重がほとんど増えなかった」「むしろ増えたけど脂肪になったかどうかは不明」といった結果が出る可能性は、体脂肪ではなく水分・グリコーゲンの変動が中心だったという見方ができます。
また、むくみ(体内の水分保持)や腸内ガス量など、短期の体の内的状態も体重に影響します。
つまり「3日間で○kg増えた/増えなかった」という結果を、“太った/太ってない”の判断に直結させるには慎重を要します。
特に脂肪1kg増加=約7,000kcalの余剰であるという基準から考えると、3日間でそれほどの余剰を積み重ねない限り“本当の脂肪”としての体重増加には至りにくいという見方があります。
よって、番組の検証結果は「短期・別要因あり」であると理解すべきです。
長期的な体脂肪変化で見るべき指標
「太らない」という目的で食事を考えるなら、体脂肪率・ウエスト周囲径・筋肉量の維持・生活習慣の継続性など、中長期(数か月~1年)での変化を見据えることが非常に重要です。
最新のメタ解析では、食事法や摂取量制限を3週間程度から12週間以上行った試験でも、長期(1年以上)になるとその差が縮まり「継続可能な方法が最も有効」であると結論付けられています。
例えば、3日チャレンジで「おにぎりを沢山食べても体重があまり増えなかった」という結果が出たとしても、1か月後・半年後に体脂肪率が増えていれば“太らない”とは言えません。
逆に、量・具材・活動量を調整して継続できていれば、結果的に体脂肪を増やさず体重も維持しやすいという視点が大切です。
また、筋肉量が減ると基礎代謝が落ちるため、「太らないためのおにぎり習慣」を考えるなら、筋肉を落とさずに活動量を維持・増加させること、そして長期的に“無理なく続けられる範囲”で食事を管理することが鍵となります。
番組を見て、“3日間での変化”を興味深く追う一方で、自分の生活に落とし込む際には“1か月・3か月・6か月”スパンでの変化を見据えることを忘れないようにしましょう。
まとめ

検索意図の核心は「番組の“おにぎり太らない説”は実際どう解釈すべきか」「自分はどう選べば太りにくいのか」です。
一次情報では、10月29日(水)よる7時放送回で“おにぎりはどれだけ食べても太らない?”をチャンカワイさんが3日間検証することが明示されています。
短期チャレンジは“面白さ”と“気づき”を与えてくれますが、長期の体脂肪変化を断定できる設計ではありません。
放送は“短期の変動(体内の水分・グリコーゲンなど)も起こり得る”という前提で見て、自分の生活に落とす際は量・具材・活動量の三点管理に置き換えるのが現実的です。
実装面では、まず総量(総カロリー)の管理が土台です。
一般的なおにぎり1個は目安160〜200kcal、ツナマヨ等の高脂質系は220〜250kcalまで伸びやすい──この“差”が積み重なると結果に直結します。
外食・コンビニ利用時は栄養表示(エネルギー・脂質・炭水化物)を確認し、梅・鮭・昆布など低脂質の具材を基準に、高脂質具材は頻度や個数で調整を。
サイズが大きい商品は満腹感と引き換えに総カロリーも増えるため、標準サイズ×2種の組み合わせなどで調整するのが合理的です。
次に血糖応答(GI)と食べ合わせの観点。
白米ベースは血糖が上がりやすい側面があるため、海苔・食物繊維リッチな具材・たんぱく質を組み合わせる、ブレンド米(雑穀・もち麦等)を選ぶ、野菜やたんぱく質→主食の順で食べるといった工夫で“太りやすさ”のドライバーを弱められます。
運動習慣がある人は、運動前に炭水化物(おにぎり)を補給し、運動後は炭水化物+たんぱく質を意識すると回復と体重管理の両立に寄与します。
競技者向け原則ではありますが、一般の人にも有用なタイミング栄養の考え方です。
番組の“検証の爆発力”は日常を変えるきっかけになります。
ただし結論は「おにぎり=太らない」ではなく「設計次第で太りにくくできる」に尽きます。
- 総量管理(まずは1〜2個の範囲で)
- 具材の脂質コントロール(梅・鮭・昆布などを軸に)
- 食べるタイミングの最適化(朝・活動前優先、夜は控えめ)
この3点を今日から回し、体重だけでなく体脂肪率やウエスト**の推移で振り返る。
番組の一次情報(放送当日)で示される“短期の結果”は、あなたの長期の習慣設計へと橋渡ししてくれるはずです。
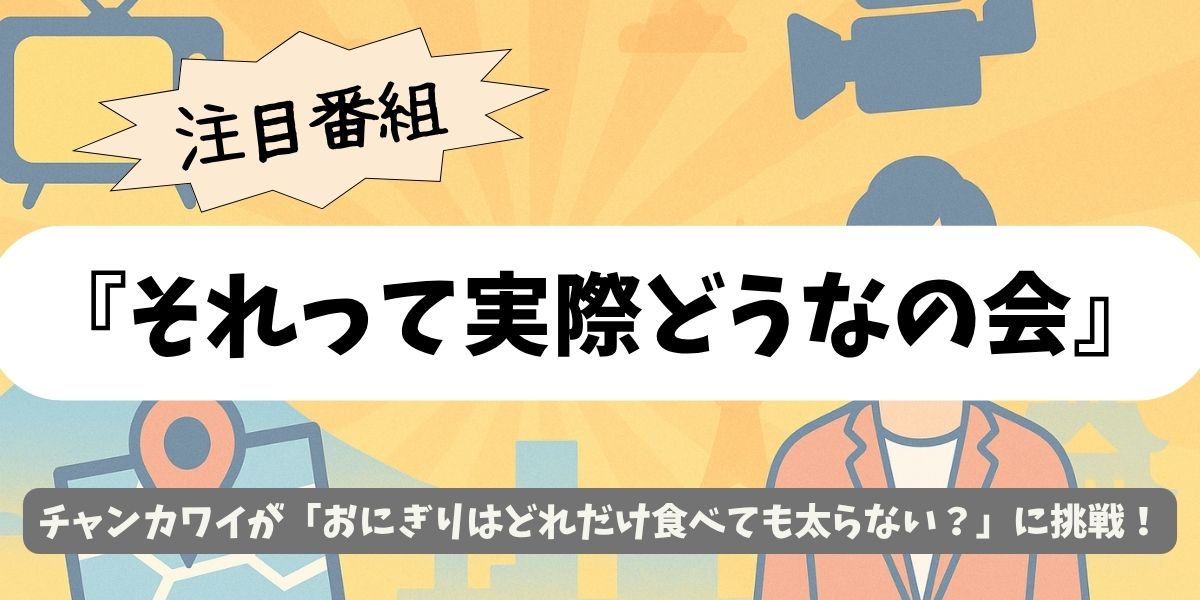

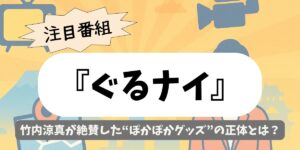
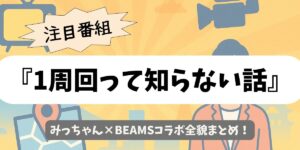
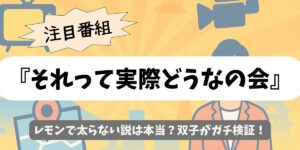
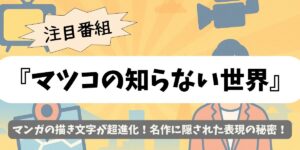
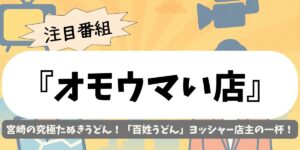

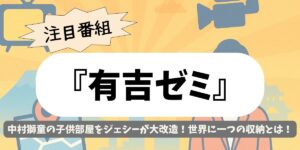
コメント