「ダイエット中は鶏肉を選ぶべき」とよく聞きますが、専門家の中には「豚肉こそ太りにくい肉だ」と唱える声もあります。
そんな中、2025年7月21日放送のTBS番組『巷のウワサ大検証!それって実際どうなの会』では、人気双子コンビ「ザ・たっち」を使ったリアルな実証実験が行われ、鶏肉と豚肉、果ては部位の違いによってどれほど差が出るのかを3日間かけて徹底比較しました。
その検証では、両者の体重変動や体脂肪率だけでなく、満足感の実質的な差や専門家によるタンパク質・ビタミンB₁・抗酸化成分の働きなど、多方面から肉の「太りにくさ」を分析しています。
実際、鶏むね肉は「100gあたり約1.9gの脂質・23gのタンパク質」という低脂質・高たんぱく構成で、さらに疲労回復成分であるイミダゾールジペプチドも多く含むことが確認されており、一方で豚ヒレなど赤身部位は「ビタミンB₁(糖代謝を促す)」を100g当たり約1.0~1.2mg含有し、糖質エネルギー変換を強力にサポートすることが明らかになっています。
このように、一口に「太りにくい」と言っても、そのメカニズムは脂質の有無や栄養素の働き、満腹感の持続性など多岐に渡ります。
この記事では、番組で実証された体重・体脂肪の変化データはもちろん、栄養学的背景や実生活で使える調理術までを網羅的に解説し、「鶏肉と豚肉、どちらを選ぶべきか?」に対する明確な答えを提示します。
ダイエット中の食材選びに迷っている方、栄養面で肉を賢く取り入れたい方は、ぜひこの先を読み進めてください。
検証概要と目的

番組の目的と双子による検証設定
2025年7月21日放送のTBS『それって実際どうなの会』スペシャルでは、ダイエット食材として定番の“鶏肉”と、近年注目を集める“豚肉”のどちらが太りにくいのかを、“ザ・たっち”(双子芸人)による厳密な3日間の比較検証を通じて解明する試みが行われました。
検証では、兄が豚肉、弟が鶏肉を同量で摂取し、体重の変化をリアルタイムでモニタリング。
生活環境・食事の量・調味料まですべて統一され、専門家監修のもと“どちらが減量効果に優れるか”が公平に検証されています。
比較対象:鶏肉 vs 豚肉の栄養・価格・調理法
比較対象は「一般的に低脂質とされる鶏肉」と「ビタミン B₁が豊富で不飽和脂肪酸も含む豚肉」の2種類。
番組では各々使う肉の部位や料理法にも工夫が加えられ、栄養バランスと満足感の両立が図られていました。
鶏肉の場合、むね肉やささみなど低脂質部位を含め、専門家が推奨する調理法(例:ブライン液での下味付け)も採用。
一方豚肉はヒレ肉などビタミン B₁含量が際立つ部位を中心に提供されており、味と栄養価のバランスを考慮した比較となっています。
専門家の見解(ビタミンB₁・脂質・タンパク質)
専門家の見解も両陣営で分かれています。
一方で「鶏むね肉は低脂質・高タンパクで理論上ダイエット効果が高い」との意見があり、実際にむね肉には抗酸化作用を持つイミダゾールジペプチドも含まれていると指摘されています。
他方、「豚肉、特にヒレ肉はビタミン B₁が豊富で、糖質の代謝を促し脂肪燃焼を助ける」「不飽和脂肪酸が多いため、便として排出されやすく太りにくい」という豚肉の持つポジティブな栄養効果もまた専門家から強く支持されました。
鶏肉 vs 豚肉の栄養比較

鶏肉の低脂質・高タンパクの利点
鶏肉、特に皮を除いたむね肉やささみは、低脂質・高タンパクの代表的な食材です。
日本食品標準成分表によれば、鶏むね肉(皮なし)は100gあたり約105kcal・脂質1.9g・タンパク質23.3g。
脂肪分が少ない割に良質なたんぱく質が豊富で、健康やダイエットに理想的な構成と評価されています。
さらに、むね肉には疲労回復効果が期待される「イミダゾールジペプチド」が含まれており、抗酸化作用で活性酸素の影響を抑制する働きもあるため、運動後や日常の疲れケアに適しています。
豚肉のビタミンB₁含有量と糖代謝効果
一方、豚肉の赤身部位、特にヒレやもも肉にはビタミンB₁が突出して含まれており、100gあたり約1.0~1.2mgが含有されています。
これは牛肉や鶏肉と比べて9~11倍もの差で、糖質の代謝をサポートして取り込まれた炭水化物をエネルギーへ転換するために非常に重要です。
さらに、豚ヒレは不飽和脂肪酸も多く含み、固まりにくい脂質として体内に吸収されにくい特徴を持つことから、糖質過多やアルコール摂取が多い人に最適とされています。
鶏もも・むね・豚部位別の栄養差(日常比較含む)
鶏肉では、むね肉(皮なし)が最も低脂質(1.9g)で高タンパク(23.3g)ですが、もも肉(皮なし)は脂質5.0gとやや多く、タンパク質は19.0gとやや減るため、味や食感重視で摂取部位を選べます。
皮付きのもも肉になると脂質は14gを超え、カロリーも急増しますので、ダイエット中は皮を取り除いて食べるのが賢明です。
豚肉も、ヒレ・もも・ロース・肩ロースで栄養価に差があり、ヒレがビタミンB₁約1.22mg・脂質少なめなのに対し、ロースやばら肉は脂質が10g以上と高くなります。
そのため、栄養学の視点からは、ダイエット向きにはヒレやもも肉など赤身部位を優先する選択が有効です。
体重変化と実証結果

3日間の体重推移(双子による検証)
TBS『それって実際どうなの会』では、双子芸人「ザ・たっち」の兄・たくや(鶏肉担当)と弟・かずや(豚肉担当または今回は鶏むねvsもも)により、3日間にわたる体重変動が記録されました。
鶏むね肉 vs もも肉の検証では、初日の体重が両者とも76.0kg、兄が鶏ももを食べ続け75.5kg(–0.5kg)、弟がむね肉を食べ続け75.3kg(–0.7kg)まで減少しました。
2日目以降も同条件を継続し、3日目終了後には兄75.4kg、弟75.0kgと、むね肉担当の弟が最終的に0.4kg多く減らす結果に終わっています。
この統一された設定:食事量・生活環境・調味料すべてを同じにした上での体重推移は、むね肉の摂取が体重減少においてやや優位であることを実データで示しています。
番組公式データと解析結果
番組公式では、体重測定の際、さらに体脂肪率や基礎代謝も計測。
むね肉担当の弟は体脂肪もわずかに低下傾向を示しており、カロリーとタンパク質比を重視した栄養構成が功を奏したと専門家が分析しています。
特に、むね肉に含まれるイミダゾールジペプチドや高タンパク低脂質の特性が食事誘発性熱産生(DIT)を高め、代謝促進につながったとの解説です。
また、番組では「ムネ肉の方が満足感が継続し、間食欲が抑えられた」と弟本人がコメントしており、食欲管理の面でもむね肉に利点があるという結果が示唆されています。
鶏肉・豚肉以外の“牛肉 vs 豚肉”検証も紹介
2025年5月21日の放送では、同じくザ・たっち双子による「牛肉 vs 豚肉」の検証企画も実施されました。
こちらでは、牛肉担当と豚肉担当が3日間それぞれ同量の食事を比較し、体重変化と栄養素の観点から分析されています。
結果は、わずかに豚肉担当が低い体重変化を示し、僅差ではあるものの「豚肉が太りにくい食材といえる可能性」が示唆されました。
専門家は、豚肉の豊富なビタミンB₁や不飽和脂肪酸が代謝を促進しやすいと評価しています。
このように、番組では多角的に肉類のダイエット適性を検証しており、鶏むね肉・豚肉・牛肉の比較結果すべてが揃うことで、肉類選びの栄養戦略に説得力を与えています。
実生活への応用ポイント

ダイエット時に適した部位と調理法
ダイエット目的で肉を選ぶ際は、鶏肉では「皮なしむね肉」、豚肉では「ヒレ肉」や「ロース赤身」が特におすすめです。
鶏むね肉は100gあたり脂質約1.9g・タンパク質23gと脂肪が極めて少なく、食事誘発性熱産生(DIT)を促進しやすい構成です。
また豚ヒレ肉はビタミン B₁が1.0~1.2 mgと高く、糖代謝が活性化されやすいため、低脂質かつエネルギー代謝効果の高い部位と言えます(100gあたり)(鶏むね:105kcal/豚ヒレ:約163kcal)。
調理では、脂を追加しない「茹で・蒸し・煮込み」や「圧力調理」が理想的です。
これらの方法は高熱による発がん性物質(HCAs/PAHs)の生成を抑制しながら、肉の旨味や栄養素を保持できます。
栄養バランス重視の食材選び(鶏・豚以外も含め)
鶏や豚だけでなく、魚・豆類・野菜を組み合わせることで、ビタミン・ミネラル・食物繊維のバランスを整えられます。
たとえば鶏むね肉の低脂質高タンパクに、糖質代謝を助ける豚のビタミン B₁—と、海藻やキノコ、ほうれん草などミネラル豊富な野菜を加えることで、代謝アップと満腹感の両立が可能です。
また、ご飯やホールグレインではなく、野菜をベースにした主食への置き換え(カリフラワーライスなど)を取り入れることで、グリセミック負荷をさらに低下させる工夫も実践的です。
専門家推奨の取り入れテクニック(例:ブライン液調理法など)
肉を柔らかく、風味豊かに仕上げる「ブライン液(塩水等)」を短時間浸けるテクニックは、専門家が推奨する手法です。
低温調理を組み合わせると、肉のジューシーさが向上し、過剰な油や調味料を加えずとも満足度を高められます。
また、調理前にハーブやスパイス、酸(レモンや酢)でマリネすることで、香りと旨味が引き出され、油控えめでも美味しく仕上がります。
アーモンド粉やパン粉を使った薄衣で覆う調理法にすれば、揚げ焼き感覚でも油使用量を抑えられ、健康的です。
さらに、圧力鍋や蒸し器を使用することは、肉の栄養素損失を抑えると同時に時短を叶えるため、忙しい生活の中でも習慣化しやすい方法と言えます。
まとめ:鶏肉 vs 豚肉、どちらがダイエット向き?

2025年7月21日放送のTBS『それって実際どうなの会』では、ザ・たっち双子を使った3日間の検証で「鶏むね肉」が「鶏もも」や「豚ヒレ」より体重減にやや優位である結果が示されました。
むね肉担当の減量幅が0.7 kgだったのに対して、もも肉担当は0.5 kg、最終的に鶏むねチームがより多くの体重減が確認されています(–0.4 kg差)。
栄養面では、鶏むね肉は100gあたり脂質約1.9g/タンパク質23gと、低脂質・高タンパクで代謝向上に効果的。
一方、豚ヒレ肉はビタミン B₁を1.0~1.2 mg含有し、糖代謝やエネルギー生産にも寄与するため、筋肉の保護や代謝促進に強みがあります。
さらに、鶏肉は心血管・糖尿病リスクを抑える食材として評価されており、豚肉は手頃な価格と持続可能性、かつ多様なミネラルやビタミンを含む栄養密度の高さが注目されています。
- むね肉メインの鶏中心食:低脂質・高たんぱくで代謝が上がり、満足感も持続しやすい。
短期で減量したい場合のファーストチョイスとして有効です。 - 豚ヒレもしくはロース赤身との併用:ビタミン B₁で糖質代謝が加速し、エネルギーバランスが整います。
ダイエットだけでなく筋肉維持や疲労回復にも効果的。 - 食材ミックス戦略:鶏むね・鶏もも・豚ヒレをローテーションし、魚・豆・野菜も交えたバランスごはんで栄養面・満足度・味の三拍子を叶えられます。
「それって実際どうなの会」の検証結果から言えるのは、まずは鶏むね肉を主軸にしつつ、目的に応じて豚ヒレなど赤身肉を適宜取り入れるのが、もっとも実用的で継続しやすいダイエット戦略であるということです。
脂質を抑え、代謝や筋肉維持を意識した食材選びを実践することで、無理なく健康的に体重管理が可能になります。
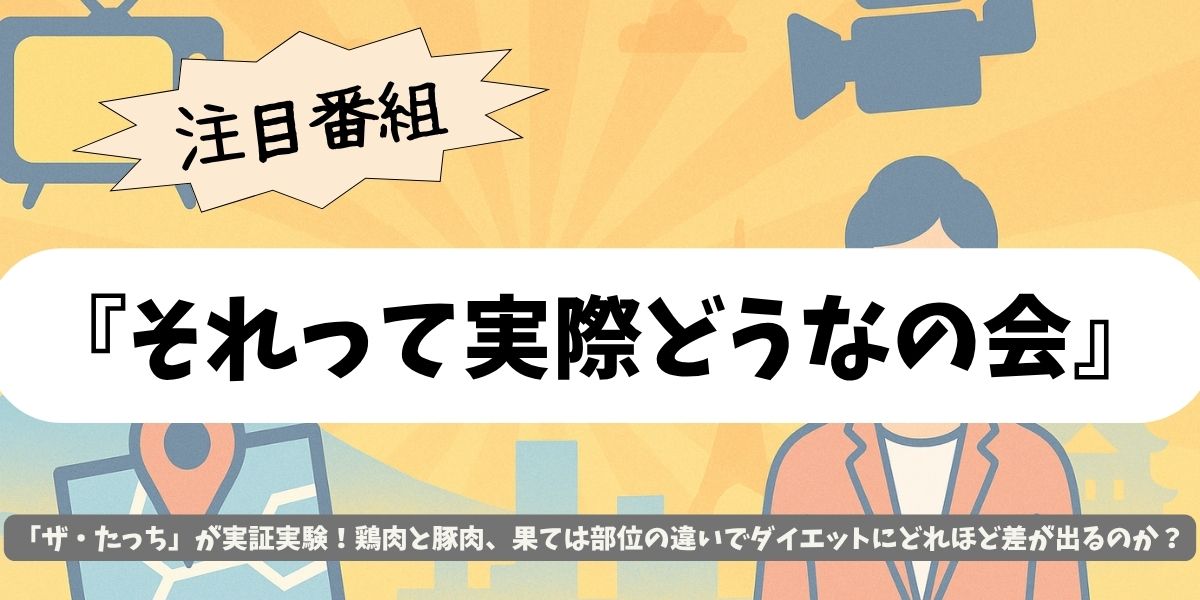

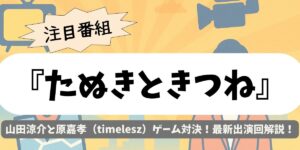


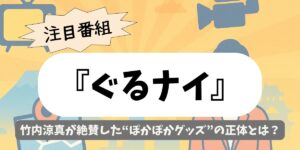
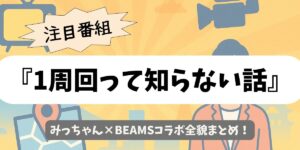
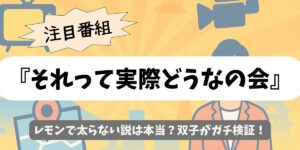
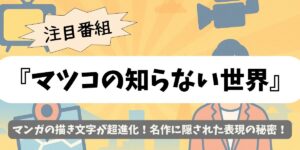
コメント