テレビ番組『世界の何だコレ!?ミステリー』で話題になっている「神奈川 ピラミッド」。
その正体は、神奈川県綾瀬市深谷中に位置する日蓮宗・大法寺の境内にそびえる、見た目も名前もユニークな納骨堂「ぴらみ堂」です。
県道45号(中原街道)と深谷交差点の目と鼻の先という、人々の行き交う中心地に2019年に建立されたその形状は、遠目にも一目で“ピラミッド”とわかる異彩を放ち、通行人だけでなく地元住民の間にも「道路沿いにピラミッドが現れた」と噂を呼んでいます。
設計は“功徳を積む”仏教的信条を石積みに込むことで表現し、明るい白河石を百段重ね上げ、高さ約5〜5.5メートルにまで及ぶ堂々たる造形です(建築面積:約62.4㎡)。
地下には逆ピラミッド形の空間も設けられ、納骨と礼拝を兼ねた宗教的な構成へと仕上げられています。
建立の背景には、住職の菊池重忠氏が「この場所を地域の名所として、誰もが心で祈りを捧げられるような拠点にしたい」という想いがあり、地の歴史性と仏教的信仰をかけ合わせた礼拝空間として設計されたことがうかがわれます。
町の人々は、“ピラミッド”という日常には馴染みのないフォルムに、不思議と親しみや祈念の感覚を重ねるようになりました。
ところが、こうした“現代の祈りの場”がテレビではまるで古代遺跡のように紹介されることで、その本来の宗教的意味や現代建築としての背景が見過ごされてしまうのはもったいないことです。
実際にはこれは、エンタメが“謎”を煽る演出ではなく、地域に根ざした信仰と建築が結びついて生まれた、希少なランドマークなのです。
本記事では、この“神奈川の道路沿いピラミッド”の正体を、設計背景や信仰的意義、現地の見どころとして整理し、テレビの刺激的な切り口を超えて、じっくり理解できる内容でお届けします。
大法寺「ぴらみ堂」の立地と由来

どこにある?(県道45号・深谷交差点そば/住所と地図)
神奈川県綾瀬市深谷中、県道45号(通称・中原街道)と深谷通りが交差する地点に、大法寺がそっと佇み、その境内に異彩を放つピラミッド型の構造物が見つかります。
住所は「綾瀬市深谷中6‑23‑1」に確定しており、歩行者にも運転者にも自然と目に留まるような位置に設置されています。
地理的には古来から人々が行き交った街道沿いとして歴史を感じさせるロケーションであり、寺がその道筋に寄り添って建立されたこと自体に、地域との深い関わりを感じさせます。
2019年建立・永代供養塔の役割と宗教的意義
このピラミッド型建造物は「ぴらみ堂」と呼ばれ、2019年に大法寺の永代供養塔として建立されました。
日蓮聖人とゆかりの深い「びわみ堂」がかつてこの地にあったことが名称の由来であり、「ぴらみ堂」と名付けられたのはこの歴史的背景が反映されています。
永代供養塔とは、後継者がいなくても寺が永続的に供養を行う施設であり、この形式をピラミッドという形式で具現化したことには、地域への信仰と祈りを未来につなげようという意図が感じられます。
テレビ取材の経緯と話題化の流れ
綾瀬市の公式ロケーションサイトでも「テレビ取材対応実績あり」と明記されており、このユニークな構造が映像メディアから注目されていることが伺えます。
2025年8月27日に放送される予定のフジテレビ系バラエティ番組『世界の何だコレ!?ミステリー』でも、「神奈川 ピラミッド」「道路沿いに謎のピラミッド」として紹介されることが予告され、その注目度はさらに高まっています。
その結果、情報ブログやSNSでも「神奈川にピラミッドがある!?」と話題になり、地域のみならず全国的にも話題性を帯びつつあります。
デザインと構造(100段の石積み・高さ・素材)

白河石“百段”の意味と高さ約5.5 mのスケール
大法寺の「ぴらみ堂」は、明るい色合いが印象的な白河石を約百段積み上げる手法によって形作られており、その段数は「賽の河原」における積み重ねの行為と重なって、仏教における「功徳を積む」という象徴的意味も内包されています。
段の積み重ねによる高さは最大約5.5メートルに達し、これは高さとして視覚的な存在感だけでなく、山岳や古代建築のモニュメントのような印象も与え、地域のランドマークとして成立するスケール感を持っています。
地下の“逆ピラミッド”と内部構成(納骨・礼拝空間)
外観が印象的なだけでなく、「ぴらみ堂」には地下に向けた逆三角錐形の空間—いわゆる“逆ピラミッド”が構築されています。
これは、古代エジプトのピラミッドにおける「再生」や「魂の帰還」の概念を想起させる設計意図で、死者の魂への祈りと再生を象徴する装置として機能します。
内部は地上部分が納骨を担い、地下部には礼拝空間があり、外の静けさから一転、祈りが内在する静謐な空間構成を実現しています。
外壁の白河石と合わせて、床も同素材の水磨き仕上げが用いられており、穏やかな光を間接照明が支えることで、訪れる人に安らぎを与える空間となっています。
小型(ペット用)ピラミッドの併設
「ぴらみ堂」の主構造に隣接して、小型のピラミッド型構造が配置されています。
これはペット専用の納骨塔として設計されたもので、敷地にゆとりと配慮の深さを感じさせる設計です。
小型塔の建築面積は約4㎡程度とされ、外観は主塔と同様に白河石の積み上げによるデザインが踏襲されており、視覚的にも美しくまとまりがあります。
また、この併設により、大法寺の境内が人々だけでなく、ペットとの別れにも寄り添う場所であることが伺えます。
現地の見どころと参拝マナー

道路沿いからの外観・撮影ポイントと注意事項
綾瀬市の県道45号(中原街道)沿い、深谷交差点付近に佇む「ぴらみ堂」は、その立地ゆえに車窓からも視界に入り、自然と目を引く存在です。
明るい白河石が積み上げられた百段構造は、晴天の日には光を反射して存在感がさらに際立ち、昼間は特にフォトジェニックです。
また、夕暮れ時には西日によって柔らかな陰影が生まれ、時間帯ごとの印象の変化を楽しむことができます。
ただし、道路沿いという立地の特性から、歩行者通路が狭く、交通量の多い場所でもあります。
撮影の際は歩道や車道に立ち入らないよう十分に注意を払い、可能であれば車をしっかり駐めてから静かに立ち止まって見守る形が望ましいです。
地元自治体のロケ地案内ページによれば、駐車場が完備されていると記載されており、撮影や見学の際はそちらの利用が推奨されます。
参拝・見学時の作法と境内での配慮
「ぴらみ堂」は永代供養塔として設置されており、宗教的な場としての品位が保たれています。
参拝者として訪れる際には、軽いお辞儀や手を合わせることが無理のない範囲で心がけられると、建てた意図を尊重する姿勢が伝わります。
さらに内部には納骨室や礼拝空間があるとされ、直接内部へ入るには寺側の許可が必要である可能性があります。
公式には「テレビ取材対応実績あり」などの案内はあるものの、内部の見学には事前に寺または市役所へ問い合わせるのが礼儀を重んじる態度と言えるでしょう。
また、参道や境内の維持の観点から、ゴミの持ち帰りや静粛な行動、礼拝空間への配慮などが求められます。
観光気分だけではなく、信仰の場としての側面にも思いを巡らせることが大切です。
周辺スポットと併せて巡るモデルコース
「ぴらみ堂」周辺には歴史的・文化的に興味深いスポットが点在しています。
例えば、寺のすぐ近くには地域のローカル神社などもあり、徒歩圏で静かな参拝や散策が可能です。
また、綾瀬市周辺には古くからの街道沿いの風景や、地元で愛される和菓子屋さんやカフェもあるため、参拝後に地域の“日常の魅力”を感じられる散歩コースとしてもおすすめです。
さらに、綾瀬市はアクセスが容易なため、横浜や東京方面に戻る途中に立ち寄る立地としても便利。
歴史的建築や地域の信仰に触れた後、ちょっとした食事やカフェ休憩を組み込んで、心も体も満たされる旅程が作れます。
メディアでの扱いと“ピラミッド”誤解の整理

『世界の何だコレ!?ミステリー』予告内容の要点
フジテレビ系のバラエティ番組『世界の何だコレ!?ミステリー』は、2025年8月27日に放送予定で、番組予告では「神奈川に道路沿いに謎のピラミッドが出現」と紹介されています。
この紹介文からは、視聴者にとって「古代遺跡かも?」という驚きやミステリー性が強調されており、一般の納骨施設とは異なる“謎”として演出されていることが読み取れます。
この表現方法は、構造物をミステリーの対象として掘り下げるエンタメ手法として有効であり、一見して“ピラミッド”という視覚的インパクトを狙った狙いが感じられます。
視聴者の「本当にピラミッド?」「なぜそこにあるの?」という疑問を刺激する構成によって、話題性と注目度を高めようという意図がうかがえます。
“古代遺跡”ではなく現代の宗教施設である事実
とはいえ、実際の「ぴらみ堂」は、あくまで2019年に設置された現代の永代供養塔です。
大法寺が建立したこの構造物は、日蓮聖人ゆかりの「びわみ堂」の伝統を踏まえ「ぴらみ堂」と名付けられ、街道沿いという立地も「参拝しやすく、地域の祈りをまもる」という意図から選ばれたものです。
したがって、古代文明の遺構とは一線を画し、宗教文化と建築デザインによる現代的ランドマークとして理解することが、正確な見解と言えます。
他地域の“ピラミッド状”事例との比較(沖縄・東京湾など)
日本国内には、見た目がピラミッドと称される構造が複数存在しますが、その背景はさまざまです。
例えば、沖縄県・北大東村には「大東ピラミッド」と通称される構造物があり、これは漁港造成などで発生した石灰岩を積み重ねた人工構造物です。
外見はピラミッドに似ていますが、観光名所として風景の一部になっており、宗教施設ではありません。
一方、東京湾アクアラインにある川崎側の換気施設は、ピラミッド形状を模した浮島換気所としてデザインされており、意匠上の理由で取り入れられた建築形態です。こちらも宗教的・歴史的意義とは無関係です。
これらと比較すると、綾瀬市・大法寺の「ぴらみ堂」は“形”が似ていてもその機能や成り立ちがまったく異なるため、単純に「ピラミッド」として括るのは誤解を招くといえます。
まとめ

「世界の何だコレ!?ミステリー 神奈川 ピラミッド」で注目される大法寺の「ぴらみ堂」は、単なる“謎のピラミッド”ではありません。
2019年に綾瀬市・中原街道沿いに建立されたこの永代供養塔は、日蓮聖人ゆかりの古堂を踏まえ「祈りを未来へつなぐ」という強い意図を込めて設計された、地域と信仰が融合した現代の宗教遺産ともいえる施設です。
建築家の押尾章治氏による設計は、仏教思想の「功徳を積む」象徴として、100段もの白河石を積み上げる造形美により、地域のランドマークとして存在感を放ちます。
その高さ約5.5mというスケールも、視覚だけでなく信仰の重みを感じさせるデザインとして機能しています。
さらに、地下部に配置された逆ピラミッドフォルムは、納骨・礼拝空間として、死と再生、内と外、生と死といった二層構造の思想に通じる構成です。
形式と宗教性が緻密に結びついたその空間性は、“ただの奇妙な形”を遥かに超える意味を持っています。
また敷地内にはペットのための小型ピラミッドも併設されており、人だけでなく愛する存在との別れにも寄り添う場としての配慮が感じられます。
メディアがミステリー性を強調し、「なぜここにピラミッドが?」という驚きを演出するのも理解できます。
しかし、それは形式への誤解を生む危険もあります。
実際には、過去・現在・未来をつなぐ祈りの拠点として、大法寺が地域に願いを込めて創造した建築です。
私自身、この「ぴらみ堂」を通して感じたのは、物語と場所が密接に重なり合った建造物の力です。
奇抜さに惹かれて見に来た人が、その背後にある信仰の考えや祈りの重みを知るほど、この場所の魅力は深まっていく。
道路沿いに出現した“ピラミッド”は、実は私たちの心に対しても問いかけてくる、そう感じました。
テレビ放送をきっかけとして、もしこの場所を訪れる機会があれば、ぜひ“ミステリーのピラミッド”という表層だけでなく、「祈り」「功徳」「再生」といった深層のコンテクストにも目を向けてほしいと思います。
それこそが、この「神奈川の道路沿いピラミッド」が現代において人を惹きつける、本当の理由ではないでしょうか。
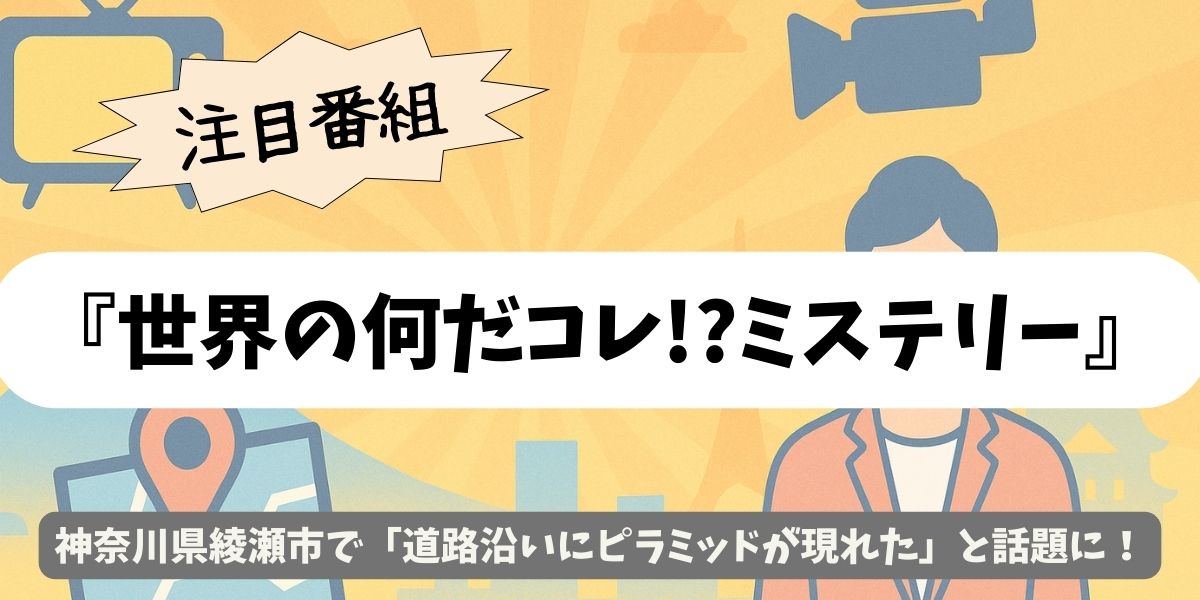

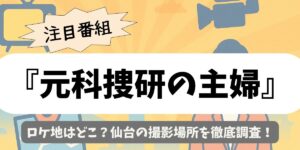
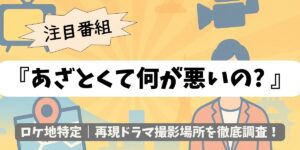

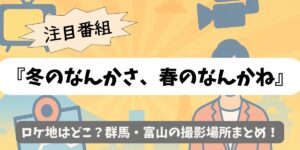
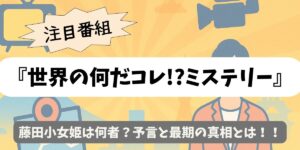

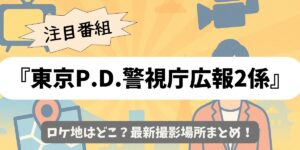
コメント