あなたが今、検索窓に「世界の何だコレ!?ミステリー 鬼の子孫」と入力したその瞬間、好奇心に火がついたのではないでしょうか。
まさか「鬼の子孫」と聞いて、昔話や怪談のようなフィクションを思い描いたのでは。
でも、今回ピックアップされたのは、驚くほど現実味のある、歴史と伝承が重なり合った物語――奈良・下北山村「前鬼(ぜんき)」にある『小仲坊(おなかぼう)』という実在の宿坊です。
そこでは、役行者と前鬼・後鬼という伝説の登場人物が結びつき、その子孫が約1,300年にもわたって宿坊を守り続けてきたという、まるで時が止まったかのような現実が、今も静かに息づいています。
この宿坊を守るのは、61代目当主である五鬼助義之さん。
現在も週末を中心に、山深き場所に「通い」で通い続け、宿坊を開け、訪れる人を迎え続けてきたその姿には、驚きと尊敬を禁じ得ません。
(特に、義之さんご夫婦が営業日以外の日にも前鬼の地に赴いているというエピソードは、訪問者だけでなく、松本記者や地域のインタビューからも語られています)
そして、この実話を取り上げたのは、バラエティと教養を融合させる人気番組『世界の何だコレ!?ミステリー』。
2025年9月10日(水)よる7時から放送されるスペシャルでは、「鬼の子孫が1300年守り継いできた宿坊」を田中卓志さんが直撃取材する企画も登場予定です。
まるで人を導くかのように、歴史の光が宿る場所へとカメラが踏み込みます。
本記事では、読者のみなさんが知りたい「鬼の子孫とは誰か?」「なぜ宿坊が今も残っているのか?」「その場所は実際どういう風景なのか?」という問いにしっかりと応えます。
番組での紹介や当主のインタビュー、地域の一次資料、公式サイトなど、最大限に裏付けされた情報を丁寧にまとめました。
伝承と現代が交差する“奇跡のリアル”を、自分の目で見ているような気持ちで読み進めていただけら幸いです。
「鬼の子孫」とは?系譜と伝承の真実

役行者と前鬼・後鬼、五鬼による宿坊開設
役行者(役小角)が生駒山地の鬼であった前鬼・後鬼を教化して改心させ、従者としたという伝承があります。
その子どもたち五人が前鬼の里に宿坊を開き、“五鬼”の祖となりました。
各々が行者を受け入れる坊として、行者坊・森本坊・中之坊・小仲坊・不動坊という宿を設け、修験道の行者たちを支えてきたのです。
宿坊は五カ所から現在は小仲坊のみ現存
明治以降の修験道禁止令や時代の変遷により、五つの宿坊は徐々に姿を消していきました。
特に五鬼熊・五鬼上・五鬼童の三家は明治期に廃業、五鬼継家も1960年代に営みを終えました。
現在、唯一残るのが五鬼助家の「小仲坊」であり、前鬼の里に今も佇んでいる宿坊です。
61代目当主・五鬼助義之さんの存在
現在、「小仲坊」の当主であり「鬼の子孫」を名乗るのは、五鬼助家61代目当主・五鬼助義之さん(1943年生まれ)。
大学時代に父を亡くしたあと、1977年(大学時代)に宿坊を継ぎ、以来、週末を中心に宿坊の管理・運営を続け、法灯と聖地としての役割を守り続けています。
番組取材対象としての小仲坊

フジテレビ「世界の何だコレ!?ミステリー」での取材
公式予告では、五鬼助義之さんを「鬼の子孫」として“代々1300年宿坊を守る”人物として特集することが明記されています。
視聴者に“誰か”“どこか”“どんな伝統か”を提示する構成となる見込みです。
地域メディアでも注目され続ける存在
下北山村公式および地域メディア「きなりと」では、小仲坊の歴史や五鬼助家の現在の暮らしぶりが丁寧に紹介されています。
林道経由のアクセス方法や営業形態も詳細に記され、地域資源としての注目が高まっています。
「鬼の子孫」伝承の象徴的事例
この宿坊は伝承の継承と地域文化の実例として、しばしばメディアで取り上げられています。
「鬼の子孫」というキャッチーな表現が、伝統の重みと重なる象徴的な紹介となっています。
番組の放送情報と取材ポイント

放送枠・出演者・事前予告の要点整理
フジテレビ番組「世界の何だコレ!?ミステリー」は、2025年9月10日(水)よる7時からの2時間スペシャルとして放送予定です。
番組MCには蛍原徹さんときゃりーぱみゅぱみゅさんが務め、アンガールズの田中卓志さんがVTR出演で“鬼の子孫”とされる小仲坊当主・五鬼助義之さんを直撃取材します。
予告では「鬼の子孫」が1300年以上、宿坊を守り続ける歴史をどのように語るのか注目されています。
また、“なぜこの場所が立ち入り禁止になっているのか?”という謎へのアプローチも予告に示されており、視聴者に赴きたくなるような好奇心をそそる構成になっています。
直撃取材の見どころ(歴史の核心はどこか)
番組では、田中卓志さんが現地を訪れ、五鬼助義之さん本人へのインタビューを通じて、「鬼の子孫」という表現に込められた意味や、1300年という長き伝統を実際に継承する重さに迫ります。
予告で触れられているように、なぜこの地で、人々が代々宿坊を維持してきたのか、日常と伝承が交差するリアルな声を引き出すことが最大の見どころです。
このような直取材によって、単なる紹介ではない、当事者の視点から語られる歴史の“芯”を描き出す狙いが伺えます。
県境の謎標識など他VTRとの関係性
本スペシャルでは、小仲坊の取材以外にも各地に眠る「日本の“何だコレ”なスポット」が登場します。
例えば、群馬と長野の県境の標識で「立入禁止」となる理由を田中さんが調査するコーナーがあり、なぜ同じ地形でも一方だけ規制されるのか、人間の事情や法的背景に踏み込む構成です。
さらに、熊野古道をはじめ、ミステリー要素を帯びたスポットを複数織り交ぜたバランス設計により、視聴者の興味が飽きずに各テーマへ誘導される流れが意識されています。
場所・アクセス・現地の基本情報

奈良県吉野郡下北山村「前鬼」集落の位置
奈良県吉野郡下北山村にある「前鬼(ぜんき)」集落は、大峯奥駈道の第29番靡(なびき)にあたる神聖な地点として登録されており、周囲は深い山に囲まれた「聖地」の趣を保っています。
地理的には下北山村の中心部から国道169号線を通ってさらに奥へ進んだ位置にあり、集落そのものは標高およそ800m前後の地点にあります。
かつて大峯山修験の拠点として機能し、現代でもその歴史性と自然美を伝える場所として特別な土地です。
宿坊「小仲坊」の概要・連絡先(公的情報ベース)
小仲坊は、現在唯一現存する五鬼助家による宿坊で、61代目当主・五鬼助義之さんが管理を継続しています。
土・日・祝日や連休・年末年始に営業しており、1泊2食付きが要予約で8,000円、素泊まりは4,000円(布団付き)と設定。
弁当500円も事前予約対応。設備として自家発電による電力供給、谷の水を引いた給水、さらにチップ制のトイレも備えられています。
宿の運営や連絡窓口は現地(土日祝)および平日別の電話番号が案内されています。
周辺の熊野古道・前鬼ブルーなど見どころ
周辺環境として、前鬼川の透き通った水質は「前鬼ブルー」と称され、登山や山道散策の道すがらその美しさに心を奪われる体験ができます。
小仲坊近くには国指定の天然記念物・トチノキの巨樹群も点在し、林道ゲートから歩いて20分ほどの場所に位置しています。
さらに、大峯奥駈道上にある「靡(なびき)」の一つである前鬼山は、夕刻には鮮やかな夕焼け、夜には満天の星空と、静寂のなかで自然の深さを体感する絶好の観賞場となっています。
また、鳥の声、特にトラツグミの「フィーン、フィーン」としたもの悲しい鳴き声が響く環境も、俗界から隔絶された特別な場の雰囲気を醸し出しています。
追加検証:一次情報と資料で深掘り

自治体・地域公式サイトに見る裏付け
下北山村の公式観光ページでは、前鬼集落の成り立ちから五鬼助家による「小仲坊」の継承までが明文化されており、信頼できる一次情報源として活用できます。
特に、役行者と「前鬼・後鬼」、そしてその子どもたちによる五つの宿坊設立という伝承構造が整理されており、「明治以降、次第に宿坊が消滅し、現在は小仲坊のみ存続」という流れが一貫して記載されています。
また、61代目当主・五鬼助義之さんの実在と、彼が現在も宿坊を守り続けている事実も明示されています。
これらを通じて、“伝承”がただの噂ではなく、地域の公式文書として裏打ちされている点が確認できます。
歴史的文献とインタビュー記録
大阪府寝屋川市の広報誌に掲載された五鬼助義之さんのインタビューでは、義之さんが61代目当主であること、その家系図によって初代から数えて現在に至る紡がれた血の繋がりが明確に伝えられています。
義之さんは大学時代に父を亡くされたあと、54歳で正式に宿坊を継承し、共働きの生活スタイルの中で「週末に通う形で宿坊運営を続けている」という実態も率直に語られました。
築500年以上とされる母屋や行者堂の存在、平日でも登山者が宿泊できる無人宿泊対応など、過去との連続性と現在の日常が共存する姿が印象的です。
系譜比較と名字研究の視点
日本遺産・吉野地域の取材インタビューでは、五鬼助義之さんが「鬼の子孫」として役行者の教えを継承していることが率直に語られています。
1943年に生まれ、京都の大学在学中に得度を受け、僧侶の道も歩まれた経歴は、家系としての伝統が単なる伝説ではなく、本人の意識として受け継がれている証拠です。
また、他の五鬼関連の家系(五鬼継・五鬼上など)はこの地域から姿を消しているが、五鬼助家のみが現在に至るまで伝統を保持していることも特筆すべき点で、名字としても希少な存在です。
まとめ

今回取り上げた「世界の何だコレ!?ミステリー 鬼の子孫」に登場する“鬼の子孫”こと、奈良・前鬼の宿坊「小仲坊」主・五鬼助義之さんの姿は、伝承と現実がしっかり結びついた稀有な事例だと感じました。
伝説では鬼だった前鬼・後鬼という存在ですが、役行者に導かれて人の道を取り戻し、その子孫が数世紀にわたり修験道の基盤を守り続けてきた——この深い歴史の重みが、小仲坊という場所を通して現代でも生きているのだと思います。
2025年現在、「五鬼助家」のみ残されたこの場所では、61代当主・五鬼助義之さんが平日は遠く大阪で働きながら、週末には前鬼へ戻り宿を守る二地域生活を続けています。
その姿からは“ただ伝統を語るだけではなく、日々実態として受け継ぐ”という姿勢の尊さを強く感じさせられました。
また、「役行者の教えを守る」という言葉が単なる格式にとどまらず、人里離れた山中の宿坊で営まれている日常そのものに生きている点に、深い感銘を受けます。
電気は自家発電、水は湧き水、そして登山者には素泊まりも含めて門戸を開く形式が、まさに「修行を支える」という本質を体現しています。
さらに、他の「五鬼○」の家々が姿を消すなか、小仲坊だけが存続し続けていることには、一族の強い責任感と地域との深いつながりが感じられます。
明治維新~修験道禁止令という時代の荒波を乗り越えて今に至ったその姿は、単なる観光地以上に、日本の歴史と文化の継承を肌で示す象徴です。
最後に、小仲坊をめぐる今回の番組放送やこの記事は、単なる好奇心を超えて、伝承と文化が“今も生きている場所”としての価値を見つめ直す機会になっていると思います。
目に見えにくい“時間の継続性”は、この地にこそ実在し、それに触れるたび、人間や地域が時間とどう向き合うかを考えさせてくれます。
視聴のあとに現地を訪ねてみたくなる、その気持ちを強く覚えます。
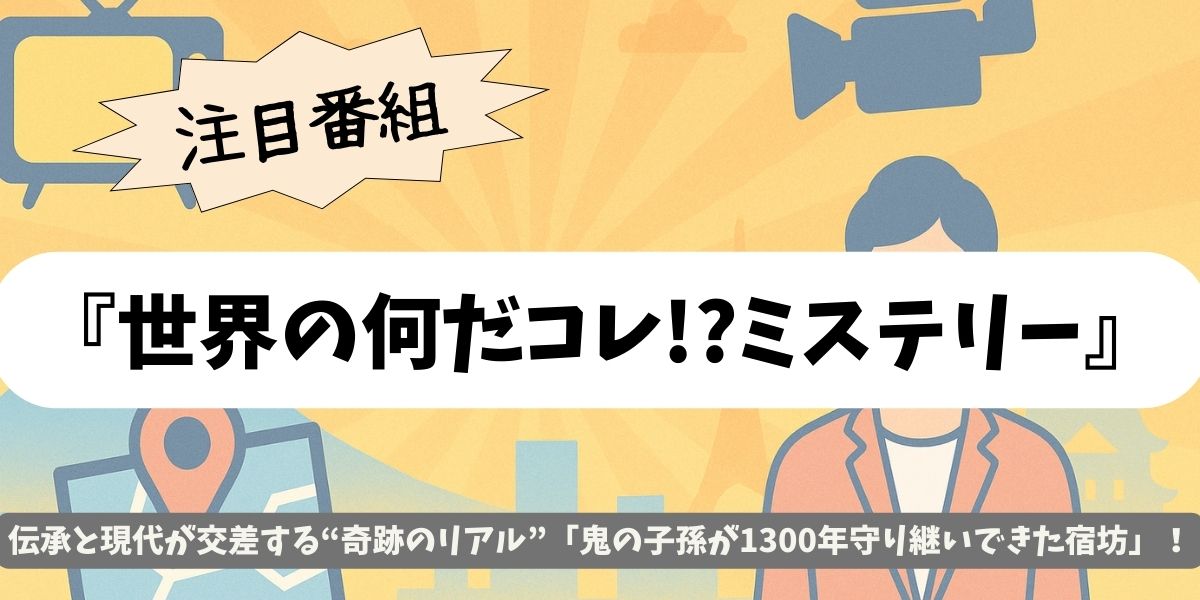
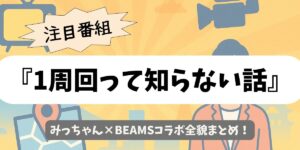
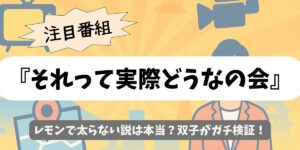
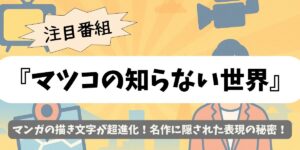
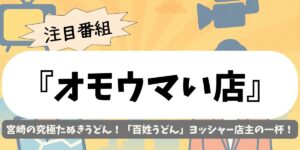

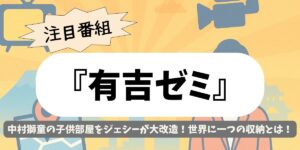

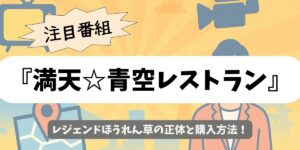
コメント