東京・渋谷駅。
“スクランブル交差点”や最新ファッションの発信地としてその名を知らない人は少ないでしょう。
しかし、同駅の“地下世界”に足を踏み入れたことがある人となると、その数はぐっと減るかもしれません。
実は、地上だけでなく地下も含めた全体構造が「迷宮」「ダンジョン」と呼ばれてきた背景には、路線・階層・改札・出口・動線が複雑に重なり合った事実があるのです。
例えば、渋谷駅は地上3階建て、地下5階に渡る構造を持ち、複数の鉄道会社・路線が階層・方向を変えて交差しています。
そのため、「どこから出たらいいのか分からない」「同じ階だと思ったら上下移動が必要だった」といった体験を、少なからぬ利用者が語っています。
そんな渋谷の地下空間に迫る特集が、2025年10月29日(水)放送予定の 奇跡体験!アンビリバボー「渋谷 地下ダンジョン」です。
番組の予告では「謎の駅」「リアル8番出口」「代々木公園の地下施設」といった刺激的なキーワードが映し出され、“ここを知れば渋谷徒歩が変わる”とも思える内容となっています。
この特集をただ“驚きの映像”として受け止めるのではなく、「なぜ渋谷の地下が迷いやすいのか」「その構造・再開発・案内制度がどう変化しているのか」を理解しておくと、番組を見る目が変わります。
本記事では、最新の公式資料と報道をもとに「渋谷地下ダンジョン」が何者なのか、その全体像と歩き方のヒントを整理しました。
番組予習としても、次の実地散策のお供としても役立つ内容にしています。
いざ、地上の喧騒を抜けて“地下の迷宮”へ。
ですが、安心してください。迷うだけで終わらせないために、知っておきたいポイントも併せてお伝えします。
放送概要と見どころ

放送日・時間・放送局
2025年10月29日(水)19:00〜20:54にフジテレビ系列で放送予定です。
フジテレビ公式の「次回オンエア」および複数の番組表サイトで同日時・内容が告知されています。
地域によってチャンネル表記は異なりますが、同一日時の2時間スペシャル枠で編成されています。
予告に登場するキーワードと企画意図
番組告知では「渋谷の地下は大迷宮」「立ち入り禁止エリアに潜入」「暗闇に潜む謎の駅」「辿り着けないリアル8番出口」「代々木公園の地下に巨大な極秘施設」といった刺激的なワードが並びます。
これらは“渋谷駅の複雑さ”や“都心インフラの地下側面”に焦点を当てる構成を示しており、視聴者は迷宮的な地下動線や未公開エリアの存在に迫る企画だと理解できます。
SNS上の番組公式ポストでも「渋谷駅のダンジョン化」を強調しており、再開発と技術が背景にあることが示唆されています。
出演者・進行(現在体制)
進行はおなじみのバナナマン(設楽統・日村勇紀)と小室瑛莉子アナ。
ゲストには金城碧海(JO1)、ゆうちゃみが予定されています。
これらの顔ぶれは各局の番組情報ページで明記されており、企画の“探索・検証”トーンに合わせて、スタジオトークでも“迷宮”の謎解き的な盛り上がりが期待できます。
渋谷「地下ダンジョン」とは何か

立体交差と縦移動が生む迷走構造
東京・渋谷駅周辺の地下構造は、その地形的・路線的な特殊性から「地下ダンジョン」と形容されるに至っています。
まず地形の観点では、渋谷駅付近が“谷地形”である点が構造の複雑化を促しています。
渋谷区が発表する「渋谷駅中心地区の大規模再開発特集」でも、駅周辺が「JR山手線・埼京線と銀座線が立体交差し、建物とホームが一体化した複雑な環境・構造を抱えている」と明記されています。
地上・地下で各鉄道・地下鉄・私鉄が縦横に入り組んでおり、たとえば地下3階、地下5階といった数層輸送施設が並ぶため、乗り換え・移動時に「上下移動」「長い階段/エスカレーター移動」が発生します。
さらに、複数の鉄道会社が乗り入れているため改札・通路が各社仕様で分かれていたり、再開発や直通運転に伴う構造変更が断続的に行われた結果、利用者から「行ったり戻ったり」「階段を上がったと思ったら別の通路だった」という声が絶えません。
実際に、インターネットWatchの記事でも「再開発で歩行者ルートは改善されるものの、地下・地上・高架を横断する通路が増え、結果的に『分かりにくさ』も残る」と指摘されています。
このように“縦に深く”“複数階層が錯綜”という構造から、渋谷駅周辺の地下通路・連絡通路が「ダンジョン(迷宮)」と呼ばれてきたのです。
読者が「渋谷地下ダンジョン」という表現で捉えている“迷いやすさ”“階層が深い”“分かりにくい通路”の背景には、まさにこの立体交差+縦移動構造の複雑さが横たわっています。
2008年以降の副都心線開業・東横線地下化の影響
構造の複雑さに拍車をかけたのが、鉄道の地下化・直通運転・路線網の刷新といった変化です。
具体的には、副都心線の開業や、東横線の地下化が渋谷駅周辺の地下構造を大きく変えました。
例えばWikipediaの「渋谷駅」項目には、東横線・副都心線が地下5階にあるという記載があり、地下化による深層化が確認できます。
また、鉄道・都市再開発の公表資料「100年に一度の大規模再開発、渋谷駅街区計画」では、「JR山手線・埼京線・銀座線が立体交差する複雑環境の中、駅施設の見直しを進めてきた」と明記されており、長年にわたる再編の累積が“入口・通路・出口”の構成を一筋縄でないものにしていることがうかがえます。
特に2008年以降の東横線地下化により、高架ホームから地下ホームへ移行したことで、利用者の視点では「以前の記憶と違う階段」「改札位置が変わった」など混乱を呼び、そこが“迷いやすさ”の象徴となってきました。
こうした変化が積み重なった結果、地下構造として“深い階層”“複雑な連絡通路”“縦横に交差する通路”というダンジョン性を帯びてきたのです。
再開発と案内改善(アーバンコア等)の最新動向
この渋谷地下構造の“ダンジョン化”に対し、近年では都市再生・再開発を通じて改善が図られています。
例えば、渋谷区の公式広報では「すでに渋谷ヒカリエや渋谷ストリームなどのビルはアーバン・コアを取り入れており、地下2階・地上5階の多層階をつなぐ歩行者動線が整備されている」と報じています。
さらに、2025年5月公表の資料では「駅前のさらなる快適性・回遊性向上のため、広場空間と歩行者動線を再編、防災性・安全性の強化を含む都市基盤施設の変更」を進行中であると記されています。
これらの改善策のひとつが「アーバン・コア」「サブアーバン・コア」という概念で、地下改札や商業施設を含めた階層間動線を整理・明確化するもので、地下の“迷宮”視点を少しでも緩和しようという試みが進んでいます。
例えば、ビルと駅とが階層的に連結された構造をかわりに「地上・地下・デッキ」を一体的に扱うことで、利用者の流れを整理しようとしているわけです。
ただし、通路や出口の改変が進む一方で、利用者側の“以前の印象”や案内の変化に追いついていない部分も依然としてあり、番組で取り上げられる「地下ダンジョン」的な迷いやすさは、最新の改善施策をもってしても完全に消えたわけではありません。
こうした背景を知ることこそ、番組「渋谷地下ダンジョン」が示す“迷宮”の正体理解につながります。
予告トピックの事実整理

「リアル8番出口」:渋谷駅の出口番号制度と迷いやすさの要因
2025年現在、渋谷駅では地下出口・出入口番号として「A〜D エリア+番号」の番号体系が導入されており、地下通路や改札から地上へ出る際の案内が改善されています。
具体的には、ハチ公前広場周辺を「Aエリア」、渋谷ヒカリエ方面を「Bエリア」、渋谷ストリーム方面を「Cエリア」、桜丘町側を「Dエリア」と大きく4つのゾーンに分け、たとえば「A2」「B5」などの番号で出口を示すしくみです。
「リアル8番出口」という文脈は、ハチ公前広場に近い出口が「A8」と定められていることから来ており、かつて「8番出口」という呼び方があったことへの言及とも読めます。
実際、出口番号変更の際に「ハチ公前を“8番”にあわせよう」という報道もありました。
このような番号体系の改定にもかかわらず、利用者が“迷いやすい”と感じる背景には以下の要因があります。
- 駅自体が複数の路線・複数の改札を持つ巨大ターミナルであるため、どの改札から出るかで直結出口が変わる。
- 地上出口・地下出口・改札口・連絡通路・商業施設が複雑に結びついており、番号体系だけでは到達先が直感的でない。
- 過去から番号の変更・再編があったため、旧番号を頭に入れている人には混乱材料となる。
例えば、2019年11月1日から出入口番号が大改定されたという案内があります。
以上を踏まると、「リアル8番出口」という語句には「ハチ公口近辺で出口番号に迷ってしまう」「実際に出口番号を確認しても目的地に辿り着けない」という視聴者体験を示すキーワードとして機能しており、番組が“渋谷地下ダンジョン感”を演出する際のキーフレーズとも言えます。
このように、出口番号制度そのものが改善されつつあるにもかかわらず、利用者が感じる“ダンジョン化”の原因として、制度変更や複雑な構造が作用していると言えます。
「謎の駅」:未供用施設・旧設備の所在と公開範囲
“謎の駅”という表現は、渋谷駅構内・地下において一般にあまり使われていない・供用されていない通路・ホーム・連絡通路が存在しており、それが視覚的にも“迷宮”“裏通路”のように感じられるという点を指していると考えられます。
例えば、東急東横線が2013年に渋谷駅地下化された際、地上・旧ホーム・旧駅舎の取り壊し・再構築が進んだことに伴い、地下に数層のホームや通路、スロープ・動く歩道などが配置されています。
また、地下には雨水を貯留する施設「あめちょ」も存在し、渋谷駅東口地下広場直下に最大4,000トンを貯留可能な構造が整備されており、「駅地下で何が起きているのか分からない」という印象を強めています。
これらは地上利用者からは通常見えない領域であり、番組が“謎の駅”“立入禁止エリア”などをキーワードに取り上げている背景には、こうしたインフラの“裏側”を取り上げる意図があると読み取れます。
さらに、再開発中の渋谷駅では、2027年完成予定と言われていたものが一部で2034年まで延長される見込みとなっており、駅構内・地下通路・施設の整備が途上であることも「未完成」「使いづらい通路」が混在する原因になっています。
このように、「謎の駅」は単なる見世物ではなく、実際に駅・地下・再開発・未使用構造がかかわった事実に基づくキーワードであり、番組がこの構造を舞台に“探索”を演出しようとしていると理解できます。
「代々木公園の地下施設」:公表されているインフラの種類と目的
「代々木公園の地下施設」というキーワードは、実際には代々木公園の公園整備事業「Park-PFI計画」において、地下1階・地上3階建て施設(店舗、スポーツ施設、学童支援施設等)が計画・建設されており、2024年度からの供用開始が予定されています。
また、渋谷駅東口地下の雨水貯留施設「あめちょ」(先述)も、渋谷駅周辺を貫流していた地下水・渋谷川・宇田川などと関係し、地上だけでなく地下インフラが並行整備されている構図が見えます。
このような“地下施設”は、駅から代々木公園方向へ徒歩圏で接続されており、商業施設・公園・駅・地下インフラが重なり合う領域であるため、一般来訪者には「どこが地下で何の施設か分からない」といった感覚を抱きやすい構造になっています。
番組の予告にこのキーワードが登場するのは、こうした“地上の顔”とは異なる“地下の顔”を視聴者に紹介し、「普段気付かない渋谷の地下空間」を掘り下げようという狙いと捉えられます。
渋谷地下を歩き切る実践ガイド

最短動線の作り方:路線別に“縦→横”の順で考える
渋谷駅で迷いにくいコツは、まず「縦(上下移動)を一気に片づけてから、横(通路移動)で目的の改札・出口へ寄せる」ことです。
とくにJR各線は2020年にホーム配置が大きく最適化され、埼京線ホームが山手線ホームの隣へ北側に移設、その後山手線は内外回りが同一島式ホームになりました。
上下移動の回数が減ったため、JR⇄JRの乗換やJRから地上改札への到達がシンプルになっています(まず必要階まで上下=縦、その後に目的方向へ水平移動=横)。
東京メトロ銀座線は2020年1月3日にホームを約50〜130m東側(ヒカリエ寄り)へ移設。
銀座線からヒカリエ方面や明治通り側に向かう際は、最初に“上がる/下がる”を完了させ、同一フロアで横移動するのが最短になりやすい配置です(移設により柱本数の削減・動線の見直しが行われました)。
東急東横線・東京メトロ副都心線(共用ホーム)や田園都市線・半蔵門線と京王井の頭線の間は上下動線が多く、所要時間が延びがちです。
実測系の案内でも半蔵門線/田園都市線⇄井の頭線の乗換はおおむね5〜6分が目安とされます。
最初に必要階までエスカレーター等で上がり切り(縦)、同じ階で改札と連絡通路へ寄せる(横)順序を徹底するとブレが減ります。
新通路・乗換動線を使いこなすコツ(最新再開発エリア)
再開発で導入された「アーバン・コア(Urban Core)」は、谷地形の渋谷を地上〜地下まで一気通貫で結ぶ立体アトリウム。
ここに多数の大型エスカレーター・エレベーターが集約され、上下移動の“幹線”として機能します。
まずアーバン・コアで必要階へ縦移動→同一階で目的方向へ水平移動という使い方が、複雑な迷いを最小化します。
設備面では2024年時点で大規模な昇降設備の整備が完了しており、縦移動のボトルネック解消に寄与しています。
また、JR山手線外回り・内回りの同一島式化と埼京線ホームのJR側寄せは、JR構内の東西連絡とホーム間移動を短縮し、アーバン・コアと組み合わせることで「乗換はまず縦、次に横」というセオリーを実行しやすくしました。
銀座線ホームの東方移設(ヒカリエ寄り)も、明治通り側・ヒカリエ側への水平移動距離を明確化しています。
これら“新しい前提”を頭に入れて動くと、旧来の感覚よりも短いルートを選びやすくなります。
具体例として、JR(山手・埼京)→銀座線は、まずアーバン・コア等で銀座線と同じ階層へ“縦移動”してから、ヒカリエ寄りの新ホームへ“横移動”するのが最短動線になりやすい構造です。
逆方向も同様に、銀座線からJRへは先に必要階へ上下し切ってから、島式化された山手線/隣接する埼京線側へ水平移動します。
迷子回避チェックリスト(到着前に確認すべき3点)
- 目的“エリア”を先に決める(ハチ公・西口/東口・ヒカリエ側 など)
渋谷は出口の名称が多い一方、主要面=ハチ公側(西)・東口(ヒカリエ側)という“大きな面”で考えると迷いにくくなります。
JR改札の中央・南・新南・西(ハチ公)・東など主要ゲートの位置関係も事前に把握しておくと、当日の“横移動”判断が早くなります。 - “まず縦”を徹底(必要階に上がる/下がる→同一階で横へ)
乗換や出口到達で迷う多くのケースは、上下・水平を細かく交互に繰り返してしまうことが原因です。
まず必要階層まで一気に移動し、その階で案内に沿って水平移動するのが近道です。
JRのホーム最適化(埼京線移設/山手線島式化)と銀座線ホームの東方移設によって、このセオリーが取りやすい構造になっています。 - “時間がかかる組合せ”を把握(半蔵門線・田園都市線⇄井の頭線など)
地下深い路線や別会社のターミナル間は上下動線が長く、半蔵門線/田園都市線⇄井の頭線は5〜6分が目安。ピーク時はさらに延びます。
時間に余裕を見つつ、最初に上下を片づけてから同一階で改札・通路方向へ寄せるとブレが抑えられます。
まとめ

渋谷の“地下ダンジョン”を正しく楽しむコツは、放送の最新予告で強調された「謎の駅」「リアル8番出口」「代々木公園の地下施設」といったトピックを、実際の整備・番号体系・動線改善の“事実”と結びつけて理解することです。
番組は2025年10月29日(水)19:00〜放送予定で、渋谷駅の知られざる地下側面や立入禁止エリアの検証が見どころ。
視聴前に概要を押さえておくと、映像の意味がクリアになります。
まず出口番号。
渋谷は2019年11月1日から出入口番号をA〜D+番号に再編し、ハチ公前は「A8」と明確化されました。
これが“リアル8番出口”の背景で、旧番号に慣れた人ほど混乱しやすいポイントです。
視聴後に現地へ行く人は、目的地が西側(ハチ公・道玄坂)か東側(ヒカリエ・明治通り)かを先に決め、「A/B/C/Dどのエリアの何番に出るか」を地図で確認しておくと迷いにくくなります。
動線は「縦→横」の順が鉄則。
とくに2020年のJR渋谷駅工事で埼京線ホームが北側へ約350m移設し、山手線と並列になったこと、銀座線ホームが2020年1月にヒカリエ寄りへ移設されたことにより、上下移動→同一階での水平移動という“セオリー”が取りやすくなりました。
乗換・出口到達で迷いがちな人ほど、先に必要階へ上がり切る/下り切る意識が効きます。
さらに、渋谷の谷地形を貫く「アーバン・コア(Urban Core)」が上下動線の“幹線”として機能。
スクランブルスクエアやヒカリエなどの主要施設と接続する歩行者ネットワーク整備も公的資料で確認できます。
番組で“迷宮感”が強調されても、現地では大コアで縦移動→同一階で目的方向へ水平移動を意識すれば、攻略は難しくありません。
最後に、“謎の駅”“地下施設”という言葉は演出だけではなく、再開発で生じた未利用空間やインフラ施設が実在する事実にも根ざしています。
こうした前提を知っておくと、番組の“驚き”が単発の驚愕ではなく、「なぜそう見えるのか」を理解する知的体験に変わります。
放送を楽しんだあとは、出口エリアと縦→横の動き方を意識して実地で歩き、“渋谷地下は攻略できる都市装置”という視点で確かめてみてください。
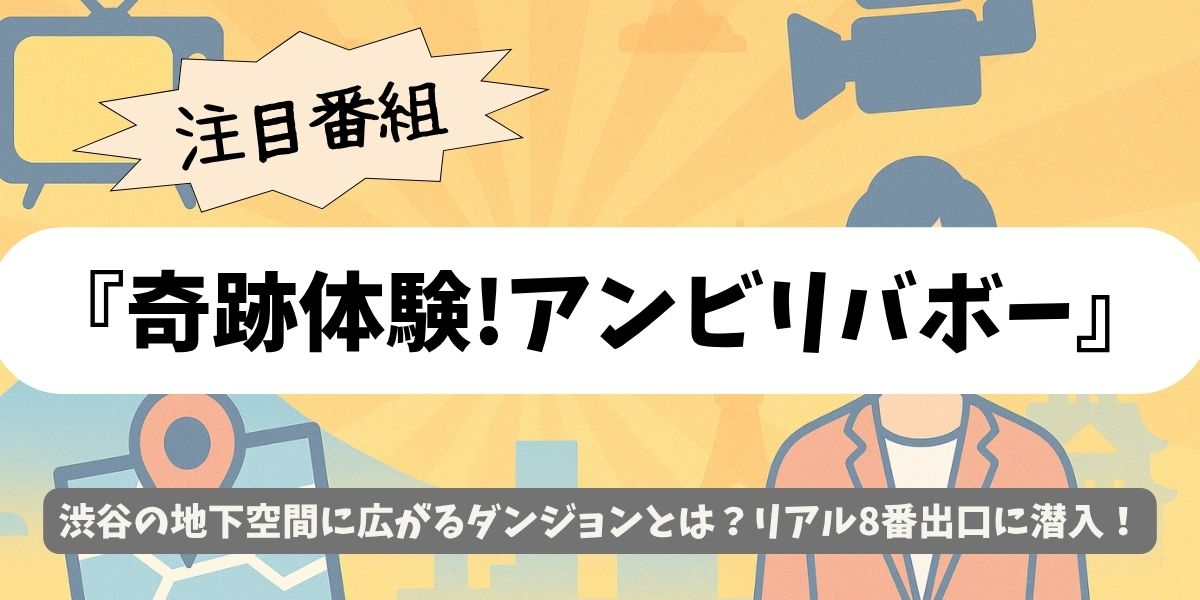

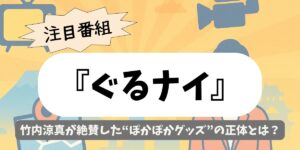
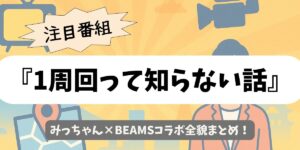
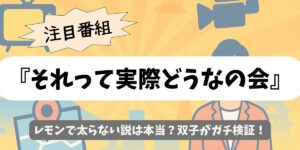
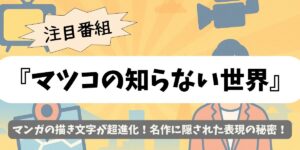
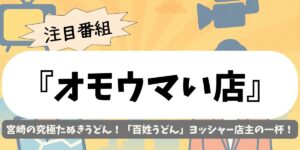

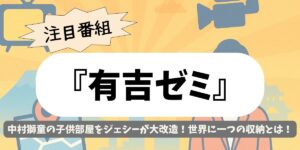
コメント