東京都八王子市にそびえる 高尾山。
ケーブルカーで清滝駅からわずか数分、都心から電車でおよそ1時間というアクセスの良さから、気軽に山と自然を味わえる観光スポットとして人気を集めています。
そんな高尾山が、テレビ番組 なりゆき街道旅 の紅葉シーズン特集回「高尾山!名物グルメ&絶景&サウナも」というテーマで取り上げられるにあたり、検索キーワード「なりゆき街道旅 高尾山 名物」を入力して訪れる方々のために、山の名物グルメから名所、最新トレンドスポットまでを網羅した案内を用意しました。
まず、天下の名物として知られる「とろろそば」や「天狗焼き」、そしてごま団子や鮎の塩焼きといった山麓ならではの食文化がしっかり今も根付き、訪問者のハートをつかんでいます。
例えば公式サイトでは、ケーブルカー高尾山駅前の「高尾山スミカ」にて1個250円の天狗焼きが登場し、「まわりはカリッ、中はモチモチ」の生地と「北海道産の黒豆あん」を特徴とするスイーツとして紹介されています。
さらに、グルメ案内サイトによれば「とろろそば」は、参拝登山を目的とした人々へ“消化がよく滋養になる食事”として古くから提供されてきた背景があるとも指摘されています。
さらに注目すべきは、高尾山が単なる“食べる山”ではなく、自然、信仰、最新施設が共存する“体験の舞台”になっている点。
例えば、山中にある 高尾山薬王院 は、天平16年(744年)創建という長い歴史を持ち、開運・厄除けの信仰スポットとして今も参拝客を集めています。
一方で、近年では「登山後にサウナで整える」といったニュートレンドもあり、麓にオープンした最新サウナ施設も登場しています。
こうした“山+グルメ+癒やし”という構図が、番組で紹介される「名物」という枠を超えた魅力を形作っているのです。
このような背景を踏まえ、「なりゆき街道旅 高尾山 名物」で検索される方が求めているのは、単に“名物が何か”という情報だけではありません。
そこで本記事では、番組で取り上げられたであろう“名物グルメ”と“名物スポット”を、最新の公式・グルメ案内情報に基づいて整理しました。
とろろそば、天狗焼き、ごま団子、開運スポット、さる園、そして最新施設――これらを“高尾山名物巡り”として、自分自身で旅程を組めるように詳細にご紹介します。
「なりゆき街道旅 高尾山 名物」で検索してこの記事にたどり着いたあなたは、この後の構成を辿れば、まるで番組の旅に同行しているかのように高尾山を堪能できるでしょう。
さあ、秋の紅葉に染まる登山道へ、名物グルメとともに出かけましょう。
見どころ総ざらい!なりゆき街道旅「高尾山周辺の旅」とは

放送日・出演者・ルートの概要(紅葉シーズンの高尾山周辺を巡る旅)
フジテレビ系「なりゆき街道旅」では、特集回として「紅葉シーズン高尾山!とろろそば&5千個売れる天狗焼&サウナも」というタイトルの回が編成されています。
番組表サイトの情報によると、放送は11月16日(日)12:00〜14:00の2時間スペシャル枠で予定されており、紅葉が見頃を迎える時期の高尾山をたっぷり取り上げる構成です。
出演者欄には、MCのハナコに加え、バレーボール元日本代表の大林素子さん、そして三代目 J SOUL BROTHERS の山下健二郎さんの名前が並んでおり、公式サイトや番組公式X(旧Twitter)でもこの3人で「高尾山周辺の旅」を楽しむことが告知されています。
事前に公開されている番組詳細によると、この回では「登山者数世界一」と紹介される高尾山を舞台に、名物とろろ蕎麦や天狗焼といった定番グルメに加え、鮎の塩焼きやごま団子まで山の恵みを味わい尽くすことが予告されています。
さらに、「サル園の可愛いお猿さんたちに癒やされる」「今年オープンした最新サウナで、登山の疲れをリフレッシュ」「別世界の鳥料理店」といったキーワードも並び、麓から山腹・周辺エリアまでを立体的にめぐる旅であることが読み取れます。
実際の高尾山観光では、京王線・高尾山口駅からケーブルカー清滝駅まで徒歩約5分、そこから山腹の高尾山駅まではケーブルカーで約6分というアクセスルートが一般的で、ケーブルカー駅周辺がグルメや名物スポットの集まる拠点になっています。
番組の説明文に登場する「サル園」や「最新サウナ」「鳥料理店」はいずれも高尾山口駅〜山腹〜麓のエリアに実在する施設と一致しており、視聴者がそのまま旅程のモデルにしやすい構成になっているのが特徴です。
番組で紹介される高尾山の名物グルメ一覧(とろろそば・天狗焼・鮎の塩焼き・ゴマ団子ほか)
番組詳細では、高尾山グルメとしてまず「名物とろろ蕎麦」が挙げられています。
高尾山は古くからとろろそばの山として知られており、参拝客や登山客に消化がよく滋養のある山の幸を提供する料理として広まったとされています。
高尾山口駅周辺から登山道の茶屋まで、とろろそばを名物に掲げる店が数多くあり、各店がそば粉の配合やとろろの粘り、つゆの味付けに工夫を凝らしているのが特徴です。
例えば、ふもとの人気店「栄茶屋」では自然薯を使ったそばと山菜料理、川魚料理が看板メニューとして紹介されており、登山前後に立ち寄る人が多いことが観光サイトやグルメメディアでも伝えられています。
次に注目されているのが「1日5千個売れる大人気グルメ」として番組側も強調している高尾山名物「天狗焼」です。
高尾登山電鉄が紹介する高尾山名物によると、天狗焼はカリッと香ばしい生地の中に甘さ控えめの黒豆あんを詰めたお菓子で、ケーブルカー高尾山駅前の複合施設「高尾山スミカ」で販売されています。
高尾山専門サイト「高尾山マガジン」でも、2007年の販売開始以来、行列の絶えない人気商品となっており、週末には購入制限(1人12個まで)が設けられるほどの人気だと報じられています。
番組紹介文には、とろろそばや天狗焼に加えて「鮎の塩焼き」「ゴマ団子」も名物として明記されています。
高尾山の麓にあるそば処「栄茶屋」では、川魚料理も名物とされており、季節限定で天然鮎の塩焼きを提供していることが店の公式サイトや特集記事で紹介されています。
こうした川魚の塩焼きは、山里らしい素朴な味わいと炭火の香ばしさが魅力で、紅葉シーズンの高尾山グルメとしても定番になっています。
「ゴマ団子」については、山腹の茶屋「ごまどころ 権現茶屋」が特に有名です。
運営会社や観光サイトの紹介によると、権現茶屋の看板商品「ごまだんご(三福だんご)」は、黒ごま・金ごまをふんだんに使った団子で、1本に約2,300粒ものごまが練り込まれていると言われています。
炭火で香ばしく焼き上げ、甘味噌やみたらし、特製しょうゆだれなど数種類からタレを選べるスタイルが評判で、登山の途中に一息つく茶屋として多くの登山者に親しまれています。
このように、「なりゆき街道旅 高尾山周辺の旅」で予告されているグルメは、いずれも高尾山エリアで実際に長く愛されてきた定番メニューです。
とろろそばでエネルギーを補給し、下山後には天狗焼やごま団子を片手に甘いおやつタイム、そして川魚の塩焼きで山と清流の恵みを味わう――番組情報をベースに、高尾山らしい一日をイメージしやすいラインナップになっています。
開運スポット・さる園・最新サウナ&鳥料理店など“名物スポット”のラインナップ
今回の「高尾山周辺の旅」では、グルメだけでなく「開運ご利益スポット」「サル園」「今年オープンした最新サウナ」「別世界の鳥料理店」といったキーワードが予告文に並び、名物スポット巡りも大きなテーマになっています。
高尾山の「開運スポット」として外せないのが、山腹に位置する真言宗智山派の古刹・高尾山薬王院です。
薬王院は約1,200年以上の歴史を持ち、飯縄大権現を本尊とする霊場として、厄除け開運・家内安全・商売繁盛など幅広いご利益があると紹介されています。
高尾登山電鉄や公式サイトでも、境内に点在する天狗像や八大竜王堂などがパワースポットとして取り上げられ、「開運や魔除けなど多くのご利益をもたらす」と説明されています。
番組の「開運ご利益スポットも続々発見」という一文は、こうした信仰の山・高尾山ならではのスポット巡りが含まれることを示しています。
予告に登場する「サル園」は、高尾登山電鉄が運営する「高尾山さる園・野草園」を指していると考えられる表現です。
この施設は、京王線高尾山口駅からケーブルカーで高尾山駅へ上がり、そこから徒歩3分ほどの場所に位置する観光スポットで、公式案内でもケーブルカー高尾山駅からのアクセスが詳しく記載されています。
園内ではニホンザルの群れを観察できるほか、山の野草を紹介するエリアもあり、家族連れや登山の休憩スポットとして人気です。
「今年オープンした最新サウナ」について、高尾山の麓では2025年7月に、クラフトビール醸造所を併設したサウナ専門施設「TAKAO 36 SAUNA」がオープンしています。
公式サイトによると、所在地は京王線・高尾山口駅から徒歩2分の高尾町で、営業時間は11:00〜20:00(月曜定休)と案内されています。
サウナエリアには、高尾山の山並みを眺められるバレルサウナや、地下水を利用した水風呂などが用意されており、「サウナ×クラフトビール」をテーマにした新しい観光拠点として紹介されています。
番組の予告文にある「今年オープンした最新サウナ」という表現と、オープン時期や立地が一致しており、登山後に立ち寄れる“ととのいスポット”として高尾山エリアで注目されています。
さらに、「別世界の鳥料理店」というフレーズは、高尾山口駅からシャトルバスでアクセスできるいろり炭火焼料理店「うかい鳥山」を連想させます。
同店は奥高尾の広大な敷地に合掌造りの建物などが点在する日本料理店で、公式サイトや観光ガイドでは「山間の澄んだ空気に包まれた隠れ座敷」「非日常的な空間で炭火焼き料理を味わえる」と紹介されています。
メニューにはいろりで焼き上げる地鶏や牛肉のほか、鮎の塩焼きなど川魚料理も含まれており、庭園内の炭火焼き処で職人がふっくらと焼き上げる鮎が名物のひとつとされています。
このように、「なりゆき街道旅 高尾山周辺の旅」の事前情報からは、高尾山ならではの開運スポット、高尾山さる園・野草園のような癒やしの動物スポット、そして登山後に楽しめる最新サウナや里山の鳥料理店といった、“山の魅力を丸ごと体験できるラインナップ”が用意されていることがわかります。
紅葉シーズンに高尾山を訪れる視聴者にとっても、そのまま旅のモデルコースとして活用しやすい内容と言えるでしょう。
高尾山といえばコレ!名物とろろそばの魅力と人気店

なぜ高尾山は「とろろそばの聖地」なのか(薬王院参拝と精進料理の歴史)
東京都・高尾山で「とろろそば」が名物として定着している背景には、山岳信仰と参拝文化、山の恵みに根ざした精進・滋養食という複数の要素が関わっています。
まず、山腹に位置する高尾山薬王院は、天平16年(744年)に開かれた由緒ある寺院で、薬師如来を本尊とし、修験・信仰の霊山として参拝客が古くから訪れていました。
参拝や登拝で体力を消耗した人々に対し、「消化の良い麺+滋養たっぷりのとろろ」という組み合わせが、参道沿いや山中の茶屋で提供されるようになったという説があります。
特に、自然薯や長芋など粘りのある山の芋をとろろにし、そばとともに出すことで、山道を登る参拝者・登山者の“休憩・補給食”として受け入れられてきたのです。
さらに、観光化が進む中でもこの伝統を受け継ぎ、「とろろそば=高尾山」のイメージが定着。郷土文化や観光グルメとしても根付き、複数のガイドメディアでも「高尾山名物」として紹介されています。
このように、高尾山が「とろろそばの聖地」と称されるのは、単なる名物という枠を超えて、信仰・歴史・山の食文化が重なった結果であり、登山・参拝が連動する山のグルメとして長年親しまれてきた背景があるのです。
番組のとろろそばシーンとリンクする、ふもと〜山頂の老舗&人気店
「なりゆき街道旅 高尾山 名物」のテーマで注目したいのが、ふもとから山頂まで巡るモデルコース内に位置する“とろろそば”提供店です。
代表的な店舗として、麓に位置する とろろそば・とろろめし 日光屋(八王子市高尾町2264)は、京王高尾山口駅徒歩2分という恵まれた立地で、「とろろそば・とろろめし」の専門店として長年営業しています。
口コミでは「大和芋のすりおろしを長芋で割った自然薯そば」「甘さ控えめのつゆ、やや幅広の平打ち麺」といった特徴が語られており、登山前の“軽めランチ”としても人気です。
また、麓から参道を登る途中や山頂直下にある茶屋も見逃せません。
例えば、山頂近くの 曙亭(東京都八王子市高尾町2176)は、「とろろそば・うどん 1000円」「見晴らし抜群」の店として紹介されています。
山頂付近の立地を活かし、そばを窓際で楽しみながら遠景を望めるという“登山後のご褒美”感も魅力です。
このように、ふもと・参道・山頂の各エリアに老舗から人気店までバリエーション豊かな“とろろそば提供店”が揃っており、「なりゆき街道旅」番組でもその流れに沿ったロケーション設定が想定できます。
訪問者は、ケーブルカーや登山道のルートに応じて、自分のペースで“名物とろろそば”を味わえる選択肢が豊富にある点が、高尾山の魅力です。
景色重視・コシ重視・家族連れ向け…目的別・高尾山とろろそばの選び方
とろろそばと言っても、訪問の目的やタイミングによって「どこで」「どういうそばを」選ぶかで満足度が変わります。
高尾山では目的別に選び方を整理すると以下のようになります。
〈景色重視〉
山頂付近のそば処や展望のある茶屋で、とろろそばを注文するなら、窓外に広がる自然や都心・富士山方面の眺めを重視。
曙亭のように展望台に近い店では、そばとともに景色を楽しむ“贅沢”な時間が味わえます。
〈コシ・味重視〉
麓・参道にある老舗そば店では、そばの太さ・打ち具合・つゆの配合など、純粋に「そばの味を楽しむ」ためのポイントが高いです。
例えば、「打ちたて」「十割そば」「太平打ち麺」という記述も見られ、そば好きが訪れる価値のある店が揃っています。
〈家族連れ・軽め休憩向け〉
登山の出発前・途中・下山後の時間帯で立ち寄るなら、メニュー豊富で小さい子ども連れでも入りやすい店舗がおすすめ。
ふもとの「日光屋」では座席あり・そば+とろろめしなどセットメニューありという仕様で、登山初心者や家族連れにも安心と紹介されています。
これらを踏まて、訪問前に「登頂後ゆっくり味わいたい」「風景とともにそばを楽しみたい」「登山前に軽く立ち寄りたい/子ども連れ」という目的を整理しておくと、より満たされたグルメ体験に繋がります。
番組の旅路としても、「とろろそばをどこで」「どんなシーンで」食べるかがロケーション・演出・視聴者動線の要になるでしょう。
1日5000個売れる!? 高尾山スミカ「天狗焼」と食べ歩き名物

黒豆あんがぎっしり!天狗焼とはどんなお菓子?場所・行列・売り切れ時間の目安
まず、天狗焼について詳しく見ていきましょう。
高尾山名物として知られるこのスイーツは、山の駅「高尾山スミカ」(東京都八王子市高尾町 2182)内で販売されています。
この天狗焼の最大の特徴は、「北海道産黒豆餡(あん)」を中にふんだんに使っている点です。
公式情報によると「生地はまわりカリッ、中はモチッとした食感。
中身のあんこは甘さ控えめで黒豆の風味が活きている」という記述があります。
実際に訪問者のレビューによると「皮が薄めでパリッとしており、黒豆餡がぎっしり」「豆の粒が存在感あり、通常のあんことはひと味違う食感」などの声が多く見られます。
販売価格は、1個 250円(税込)が公式に案内されており、まとめ買い用には6個入りや10個入りの箱詰めもあります。
行列ができることも多く、特に紅葉シーズンなどのピークタイムには「10 : 00台〜11 : 00台までに整理券が配られた」「12 : 00前後には待ち列で20〜30分」「午後には売り切れ終了となるケースあり」といったレビューが散見されます。
したがって、「この時間に行けば確実」という保証はありませんが、狙い目としてはケーブルカー「清滝駅」出発直後(10 : 00頃)窓口オープン直後を目指すと比較的スムーズに購入できる可能性が高まります。
また、複数個買って帰る予定であれば、焼き立てを味わいたいなら列が短いうちに、持ち帰り用なら少し時間をずらして訪問するのも一案です。
ごま団子・団子ストリート・ソフトクリーム…番組で映る高尾山食べ歩きグルメ
続いて、「食べ歩きグルメ」的な視点で、ごまだんごやソフトクリームなど、番組で映えそうな高尾山の名物を見ていきます。
まず、ごまだんごは高尾山の登山道中腹、具体的には男坂・女坂の合流地点近くにある茶屋「ごまどころ 権現茶屋」で炭火焼にて提供されています。
こちらの団子は「1本に約2,300粒のゴマが練り込まれている」と紹介されており、黒ゴマ・金ゴマという2種類の味が選べる点も特徴です。
さらに、タレも「江戸甘味噌」「東京みたらし」「特製醤油ダレ」の3種類から選べるという贅沢仕様。
ごまだんごを頬張りながら山道をゆるりと登る―それが高尾山ならではの“食べ歩き体験”として人気です。
また、山口駅やケーブルカー清滝駅周辺には「食べ歩きメニュー」が豊富で、焼き団子だけでなくソフトクリーム(季節限定フレーバー含む)、鮎の塩焼き、揚げたてコロッケなどが並ぶ「団子ストリート」的な雰囲気も醸し出しています。
特に紅葉シーズンや秋の休日は訪問客が多く、グルメ系店頭の行列も珍しくありません。
先の番組予告にあった「食べ歩きグルメ」部分には、ごまだんごをはじめこうした軽食系メニューが含まれていると解釈できます。
ストリートを歩きながら「何を買おうか」という選択肢が複数ある点が、高尾山の魅力です。
天狗焼+ごまだんごの“ハシゴ”も可能で、甘味系だけでなく、そば処での食事後に“デザート散策”をするのもおすすめです。
実際に訪れた人のレビューでは「そばを食べた後、下山前にごま団子を買って休憩」「焼き立てソフトクリームを持って展望台へ」という流れが多く記録されています。
紅葉シーズンに失敗しない高尾山食べ歩きルートと混雑回避テクニック
紅葉シーズンの高尾山では、登山者・観光客ともに増加し、ケーブルカー・売店・茶屋の混雑が予想されます。
そのため、食べ歩きを含めたグルメ巡りをスムーズに楽しむためにはルートと時間帯の工夫が重要です。
以下、具体的なテクニックを整理します。
- 早出発&ケーブルカー活用
京王線「高尾山口駅」からケーブルカー「清滝駅」経由「高尾山駅」への利用を予定する場合、8 : 30〜9 : 30に駅到着を目指すと、ケーブルや売店の混雑が少ない傾向です。
朝一番に「天狗焼」購入→軽く食べ歩き→登山開始という流れを作れば、待ち時間を減らせます。(実際に「10 : 00前に天狗焼窓口に並び始めた」「11 : 30には売り切れ情報あり」という報告あり) - 山頂直行+下山時食べ歩き戦略
登山ルートを1号路(表参道)で山頂まで直行し、山頂でそばを食べた後、下山時に中腹〜麓で“食べ歩きストップ”を入れるプランが有効です。
例えば、薬王院を通過→「ごまどころ 権現茶屋」でごまだんご休憩→「高尾山スミカ」で天狗焼購入、という順序にすると、昼過ぎのピーク時でも比較的スムーズに食事・スイーツ体験を楽しめます。
レビューによると、「午後には団子・天狗焼ともに列ができていた」「売切れ店あり」という報告が多くあります。 - 平日・早期訪問がベスト
週末・祝日は登山者数が増え、10 : 00〜13 : 00が最も混雑する時間帯です。
できれば平日か、週末でも8 : 00台に駅到着しておくと、茶屋前ベンチ確保・窓口待ち時間の短縮につながります。
また、紅葉のピーク(例:11月中旬)を過ぎた12月初旬でも「紅葉+少し人が少ない」という利点があります。 - 持ち帰り&焼き立て狙いの注意点
天狗焼・ごまだんごともに「焼き立てをその場で味わう」ことが最大の魅力です。
持ち帰り用の場合でも、売店で「温め方」などが案内されています。
ただし、持ち帰り用にすると冷めて味が変わる可能性があるため、タイミング調整がカギです。
このようなルート・時間帯・戦略を抑えておけば、紅葉を背景に高尾山を登りつつ“名物グルメ&食べ歩き”を気持ちよく楽しむことができ、番組で紹介されていたシーンを自分自身で再現することも可能です。
紅葉・開運・動物・サウナまで!“名物スポット”を番組風にめぐる

薬王院の開運スポットめぐり(六根清浄石車・願叶輪潜・八大竜王堂・倶利伽羅龍など)
山の信仰が息づく 高尾山 薬王院 は、参拝・登山者双方から“開運の地”として親しまれています。
天平16(744)年に 行基菩薩 によって開山されたとされるこの寺院は、飯綱大権現を本尊に、長い歴史のなかで修験・山岳信仰の拠点として発展してきました。
参詣ルートを歩くと、「六根清浄石車」「願叶輪潜(ねがいかなうわくぐり)」「八大竜王堂」「倶利伽羅龍王堂」といった霊験あらたかなスポットが点在しています。
例えば「六根清浄石車」は巡ることで六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)を清めるという思想に基づいており、参拝者がぐるりと回す様子が見られます。
さらに「願叶輪潜」は、小さな輪をくぐることで願いが叶うと伝わる通路型の仕掛けで、山道の途中にあって“体を動かしながら参拝する”体験を提供。
やや息を切らすタイミングですが、それもまた“登拝感”を高めています。
「八大竜王堂」「倶利伽羅龍王堂」はいずれも水・龍の信仰を象徴しており、雨乞いや水源保全、厄除けといった祈願に訪れる人も多いです。
参道脇に静かに鎮座するこれらの堂宇は、紅葉期には背景となる木々の色づきと相まって、神秘的な雰囲気を醸し出します。
このように、薬王院では“ただ登る”だけでなく、数々の開運スポットを巡りながら心身を整えていくという流れが構築されており、番組「なりゆき街道旅」の旅路で紹介される“名物スポット”として十分な説得力があります。
高尾山さる園・野草園で紅葉とニホンザルに癒やされる楽しみ方
麓からケーブルカーやリフトを使ってアクセスできる 高尾山さる園・野草園 は、登山の合間に立ち寄りやすい癒やしのスポットです。
公式案内によると、この施設は山上駅から数分の距離に位置しており、ニホンザルの群れを観察できるとともに、東京都内では珍しい高山性野草・植物も展示されています。
紅葉の時期には、鮮やかに色づいた木々がサルたちの背景となり、撮影スポットとしても人気があります。
サル達が岩間を移動したり、落ち葉の上で遊ぶ姿が観察でき、「登山の途中の一休みスポット」として家族連れや登山初心者にも特に支持されています。
また、野草園のエリアにはベンチや展望デッキが整備されており、紅葉を眺めながら軽食を取ったり、写真を撮ったりと、“山の自然と動物を感じる”時間をゆったりと過ごせるのが魅力。
登山道を直登するイメージだけではなく、こうした癒やしパートを含む旅程に組み込むことで、番組で描かれる“グルメ+自然+動物”という構図がリアルに実現されます。
高尾山口の最新サウナ「TAKAO 36 SAUNA」と高尾エリアの鳥料理の名店で締めくくる夜
登山を終えたあとに立ち寄れる“名物スポット”として見逃せないのが、2025年7月12日にオープンしたサウナ施設 TAKAO 36 SAUNA。
公式プレスリリースでは「都心から約45分、世界的観光地 高尾山 の麓にクラフトビール醸造所を併設したサウナ施設」と紹介されており、1階には醸造タンク、2・3階にサウナルームという構成です。
施設の特徴として、3F「山 yama」ではバレル型サウナや開放的な露天風呂・外気浴テラスが用意されており、4人以上がゆったり入れる地下水を使用した水風呂も備わっています。
こうした“森林・山風・水”を感じる癒やしの空間は、登山で体を動かした後の“ととのい”体験として極めて新鮮です。
さらに同じ高尾山エリアでは、伝統的な鳥料理の名店 うかい鳥山(奥高尾・山里の合掌造り建築・炭火焼料理)が、山の景色とともに炭火焼の地鶏・牛肉・鮎の塩焼き等を提供しており、登山のクライマックスとして理想的な“山麓ディナー”の場になっています。
このように、“登山・ご飯(とろろそば)→食べ歩き(天狗焼・ごまだんご)→自然&動物(さる園)→開運参拝(薬王院)→サウナ&ビール→鳥料理ディナー”という一連の流れを高尾山で描くことができ、番組で紹介される旅の終着地としても妥当です。
紅葉の余韻の中、汗を流して冷えた体をサウナで温め、山里の鳥料理で締める――そんな“名物スポット巡り”は、視聴者・読者にとって魅力的な旅のモデルとなるでしょう。
まとめ(なりゆき街道旅をきっかけに高尾山名物を満喫しよう)

「なりゆき街道旅【紅葉シーズン高尾山!とろろそば&5千個売れる天狗焼&サウナも】」の番組情報を見ると、検索キーワードそのままに、“高尾山の名物”がぎゅっと詰まった内容であることが分かります。
番組紹介には、名物とろろそば、鮎の塩焼き、ごま団子、1日5千個売れる天狗焼、開運ご利益スポット、サル園、そして“今年オープンした最新サウナ”と“別世界の鳥料理店”までが並び、まさに「高尾山に行ったら何を食べて何を見ればいいか?」という検索意図にそのまま答えるラインナップです。
高尾山のとろろそばは、薬王院への参拝客の疲れを癒やすため、滋養のあるとろろをそばに載せて出したのが始まりとされています。
今では麓から山頂まで十数軒のそば店が軒を連ね、元祖とされる「竹乃家」系の店や、江戸時代創業の老舗「高尾山 高橋家」など、それぞれが独自のとろろそばを提供しています。
一方、天狗焼は高尾山スミカで販売される黒豆あん入りの焼き菓子で、公式サイトでも「まわりはカリッ、中はモチモチの生地に甘さ控えめの黒豆あん」「食べ歩きグルメ人気No.1」と紹介される、高尾山を代表するスイーツです。
価格は1個250円(税込)、営業時間は10:00〜16:30(冬期は16:00)と案内されており、混雑日には行列・売り切れも起こるほどの人気ぶりです。
さらに、紅葉と一緒に巡りたいスポットとして、開運スポットが点在する高尾山薬王院、ニホンザルと野草が楽しめる高尾山さる園・野草園などが番組でも取り上げられます。
そして、2025年7月12日にオープンした「TAKAO 36 SAUNA」は、高尾山麓でクラフトビール醸造所を併設する最新サウナ施設として、登山後の“ととのい”スポットになっています。
高尾山は、新宿から電車で約1時間で行ける“日帰りの山”でありながら、歴史あるグルメと最新スポットが同時に楽しめる貴重なエリアです。
今回の「なりゆき街道旅」をきっかけに、検索で情報を集めているあなたも、ぜひ公式サイトや最新の営業情報を確認しつつ、自分だけの「高尾山名物めぐりコース」を作ってみてください。
紅葉シーズンは混雑するものの、早い時間帯の出発やルート選びを工夫すれば、番組さながらの“高尾山グルメ&名物旅”を十分に再現できるはずです。
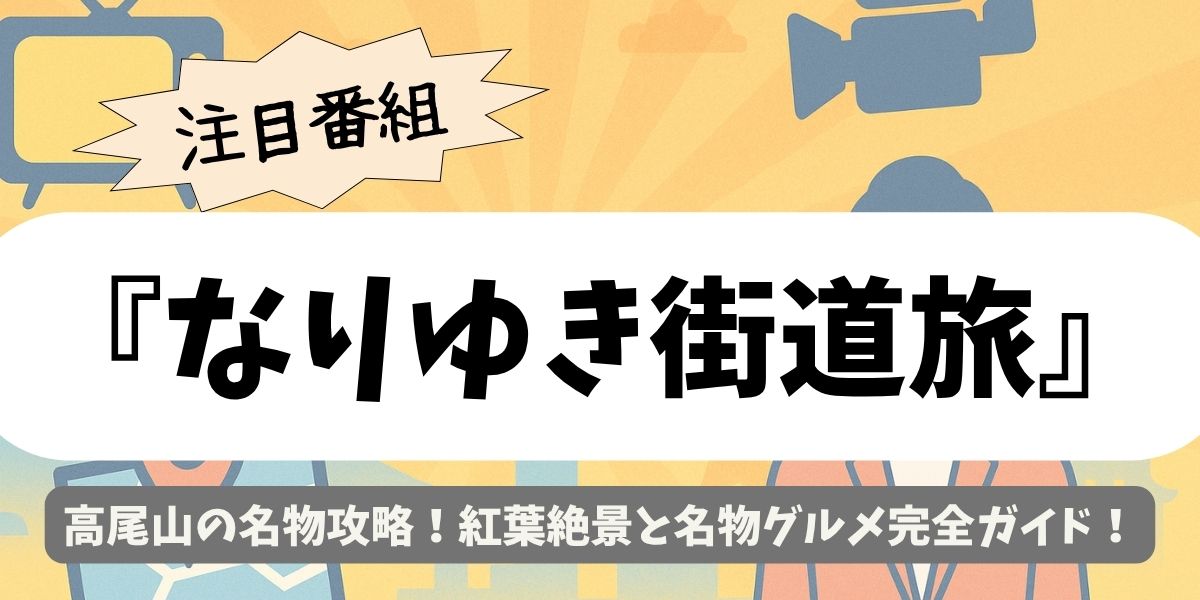
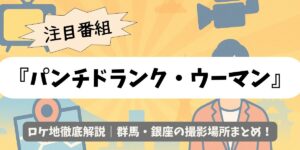
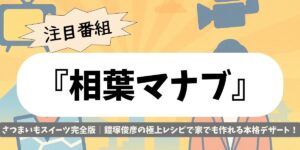
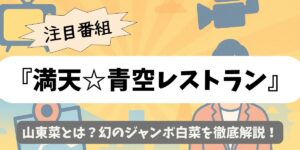
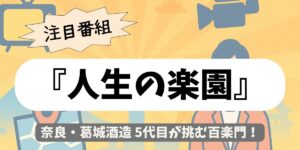
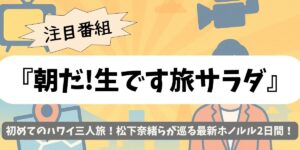
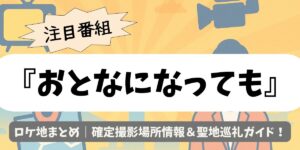
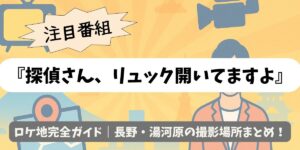

コメント