北海道・富良野の広大なラベンダー畑は、訪れる人々を魅了し続けています。
しかし、この美しい風景がどのようにして生まれ、現在に至ったのかをご存知でしょうか。
その背景には、地域の人々の情熱と努力、そして時代の波に翻弄されながらも守り抜かれた歴史があります。
富良野でのラベンダー栽培は、1950年代に香料用として始まりました。
しかし、1970年代に入ると、安価な合成香料や輸入香料の台頭により、ラベンダー農家は厳しい状況に追い込まれ、多くの農家が栽培を断念しました。
そんな中、ファーム富田の富田忠雄氏は、ラベンダー畑を観光資源として活用する道を模索し続けました。
1976年には、同農園のラベンダー畑が国鉄のカレンダーに採用され、その美しい風景が全国に紹介されたことで、多くの観光客が訪れるようになりました。
このように、富良野のラベンダー畑は、地域の人々の情熱と努力、そして偶然の出来事が重なり合い、現在の美しい風景を形成しています。
その歴史を紐解くことで、私たちはこの風景の背後にある物語を知ることができるでしょう。
富良野のラベンダー栽培の歴史
ラベンダー栽培の始まりと発展
富良野地域におけるラベンダー栽培は、戦後の1948年(昭和23年)に上富良野町で始まりました。
当時、曽田香料株式会社がフランスからラベンダーの種子を輸入し、北海道の気候が栽培に適していることから、上富良野町の農家21戸が試験的に栽培を開始しました。
その後、ラベンダー栽培は富良野地域全体に広がり、最盛期の1970年(昭和45年)には、約250戸の農家が230ヘクタール以上の面積で栽培を行い、北海道全体でのラベンダーオイル生産量は5トンに達しました。
衰退の危機とその要因
しかし、1970年代初頭からラベンダー栽培は衰退の危機に直面しました。主な要因として、以下の点が挙げられます。
- 安価な合成香料の台頭
化学の進歩により、安価で品質が安定した合成香料が市場に出回り、天然のラベンダーオイルの需要が減少しました。 - 輸入香料との価格競争
戦時中に中断されていた香料の輸入が再開され、価格競争が激化。国産ラベンダーオイルの価格が高く、採算が取れなくなりました。 - 契約栽培の打ち切り
主要な買い手であった曽田香料が1973年(昭和48年)にラベンダーオイルの買い取りを停止し、多くの農家が栽培を断念せざるを得なくなりました。
地域住民の取り組みと挑戦
このような状況下でも、一部の農家はラベンダー栽培を続けました。
例えば、ファーム富田の富田忠雄氏は、観賞用としてのラベンダー栽培に転換し、1976年(昭和51年)に旧国鉄のカレンダーにラベンダー畑の写真が採用されたことを契機に、観光客が増加しました。
また、地域の観光協会や行政もラベンダーを観光資源として位置付け、ラベンダーまつりの開催や観光施設の整備など、地域活性化のための取り組みを進めました。
これらの努力が実を結び、富良野のラベンダー畑は現在、国内外から多くの観光客を魅了する存在となっています。
50年前に起きた奇跡的な出来事
転機となった具体的な出来事とは?
1976年(昭和51年)、北海道富良野市のラベンダー畑に「奇跡」と呼ばれる転機が訪れました。
ラベンダー栽培が衰退し、多くの農家が撤退する中で、ファーム富田の創業者・富田忠雄氏は観賞用ラベンダーの栽培を細々と継続していました。
その年、旧国鉄(現在のJR北海道)が発行する「SLと四季の花」をテーマとしたカレンダーに、ファーム富田のラベンダー畑が掲載されたのです。
この1枚の写真が全国的に大きな反響を呼び、多くの人々が「一目このラベンダー畑を見たい」と富良野を訪れるようになりました。
当時、ラベンダーは商業作物としてはほぼ終焉を迎えていましたが、この偶然ともいえる掲載が、富良野ラベンダー復活のきっかけとなり、観光資源としての価値が再評価されるようになったのです。
外部からの支援とその影響
カレンダーの影響で観光客が増加する中、地元の自治体や観光協会も支援に乗り出しました。
上富良野町・中富良野町・富良野市などは、1980年代に入ると「ラベンダーの里づくり」を地域振興政策に掲げ、道路沿いや公共施設にラベンダーを植栽するなど、景観づくりを積極的に進めました。
特に1987年には、富良野線に「ノロッコ号」という観光列車が運行開始され、ラベンダー畑駅(臨時駅)などが整備されることでアクセスが飛躍的に向上。
JR北海道や観光庁の協力を受けて、ラベンダー観光は広く道外にも認知されるようになります。
また、NHKの連続テレビ小説『北の国から』などの映像作品により、富良野そのもののイメージも「美しい自然のある場所」として定着し、地域全体がラベンダー観光を支える環境になっていきました。
ラベンダー畑再生への道のり
観賞用ラベンダーの注目が集まったことで、再びラベンダー栽培を志す農家が現れ始めました。
ファーム富田では、ラベンダーの品種改良や播種・苗づくり、肥料管理など、研究と実践を重ね、安定的な観賞用ラベンダー栽培を確立。
さらに、ラベンダーから抽出する精油やポプリ、ラベンダーソフトクリーム、化粧品など、観光客向けの商品開発も進み、農業と観光が融合した「観光農業モデル」の先駆けとして全国に知ら
現在の富良野ラベンダー畑の魅力
観光名所としての発展と現状
富良野地域のラベンダー畑は、国内外から多くの観光客を魅了する存在となっています。
特に有名なのが「ファーム富田」で、約20ヘクタールの敷地内に5ヘクタールのラベンダー畑が広がっています。
ここでは、ラベンダーだけでなく、コスモスやポピーなど多彩な花々が咲き誇り、訪れる人々を楽しませています。
また、「日の出公園ラベンダー園」も人気のスポットで、小高い丘一面にラベンダーが広がり、展望台からは十勝岳連峰を望む絶景が楽しめます。
さらに、「北星山ラベンダー園」では、観光リフトに乗って山頂からラベンダー畑や富良野の街並みを一望でき、多くの観光客に親しまれています。
ラベンダー畑がもたらす地域経済への影響
ラベンダー畑は、富良野地域の観光産業の中心的存在となっており、地域経済に大きく貢献しています。
観光客の増加に伴い、地元の宿泊施設や飲食店、土産物店なども活況を呈しています。
特に、ラベンダー関連の商品や体験プログラムは観光客に人気で、地域の特産品としての地位を確立しています。
例えば、「フラワーランドかみふらの」では、ラベンダーを使った押し花ハガキや香り袋作りなどの体験メニューを提供し、観光客に好評を博しています。
これらの取り組みは、地域の雇用創出や経済活性化にも寄与しています。
訪れる際のおすすめスポットとイベント**
富良野地域を訪れる際には、以下のスポットやイベントがおすすめです。
- ファーム富田
ラベンダー畑の代表的存在で、ラベンダーソフトクリームや関連グッズも楽しめます。 - 日の出公園ラベンダー園
展望台からの眺望が魅力で、7月中旬には「ラベンダーフェスタかみふらの」が開催され、ライトアップや各種イベントが行われます。 - 北星山ラベンダー園
観光リフトで山頂へ上がり、ラベンダー畑と富良野の街並みを一望できます。毎年7月には「なかふらのラベンダーまつり&花火大会」が開催され、多くの人で賑わいます
これらのスポットやイベントは、富良野のラベンダーの魅力を存分に味わうことができるため、訪れる際にはぜひチェックしてみてください。
ラベンダー栽培の未来と課題
持続可能な栽培への取り組み
富良野地域では、ラベンダー栽培を持続可能にするためのさまざまな取り組みが進められています。
例えば、「富良野井上農園」では、遊休地となっていた山を活用し、化学肥料を使わないオーガニックハーブの栽培を行っています。
この農園では、自然の雨水に頼るなど、環境負荷を最小限に抑えた農業を実践しています。
また、上富良野町の第9次農業振興計画では、農業生産基盤の充実や環境に配慮した農業の促進が掲げられており、ラベンダー栽培農家の減少に対して早急な対策が必要とされています。
気候変動が与える影響と対策
地球温暖化による気候変動は、富良野地域のラベンダー栽培にも影響を及ぼす可能性があります。
富良野市では、地球温暖化対策実行計画を策定し、温室効果ガスの削減や気候変動への適応策を推進しています。
この計画では、農業分野における気候変動の影響評価や適応策の検討が重要視されています。
具体的な対策として、気候変動に関するセミナーの開催や、農業従事者向けのワークショップを通じて、気候変動への理解を深め、適応策を検討する取り組みが行われています。
次世代への継承と教育の重要性
ラベンダー栽培の継続と発展には、次世代への継承と教育が不可欠です。
中富良野町立なかふらの学園では、地域の特性を生かした教育プログラムを通じて、子どもたちに地域資源の大切さや持続可能な社会の構築について学ぶ機会を提供しています。
また、NPO法人C.C.C富良野自然塾では、環境教育プログラムを全国に展開し、次世代に自然環境の重要性を伝える活動を行っています。
これらの取り組みは、ラベンダー栽培を含む地域の自然資源を守り、持続可能な形で次世代に引き継ぐための重要なステップとなっています。
まとめ
富良野のラベンダー畑は、その美しさで多くの人々を魅了し続けています。
しかし、その背景には地域の人々の情熱と努力、そして時代の変遷に伴う挑戦と復活の物語が存在します。
近年、富良野市は「ゼロカーボンシティ」の実現を目指し、地球温暖化対策に積極的に取り組んでいます。
また、NTTドコモとの協働により、「持続可能な森づくり」に関する基本合意書を締結し、森林保全活動や環境教育を推進しています。
さらに、地域の特産品を活用した地産地消の推進や、観光資源としてのラベンダー畑の維持・発展にも力を入れています。
これらの取り組みは、地域経済の活性化と持続可能な社会の構築に寄与しています。
富良野のラベンダー畑は、単なる観光名所にとどまらず、地域の歴史、文化、そして未来へのビジョンを象徴する存在です。
訪れる際には、その背景にある物語や取り組みに思いを馳せながら、美しい風景を楽しんでいただければと思います。
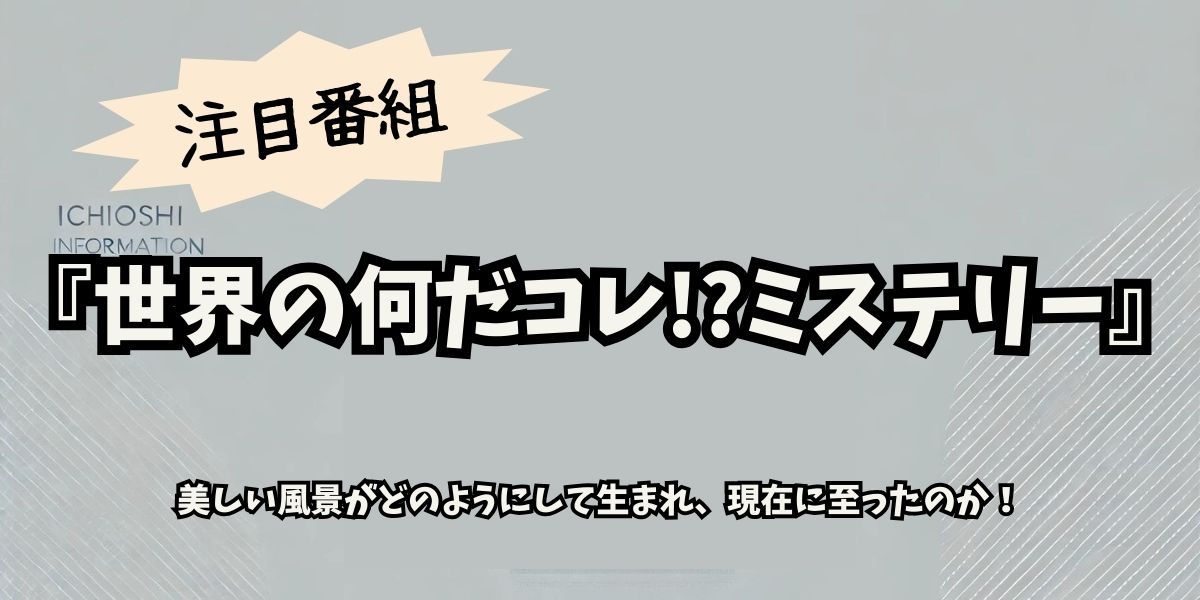
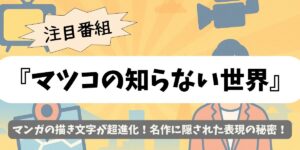
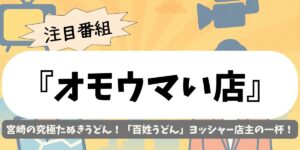

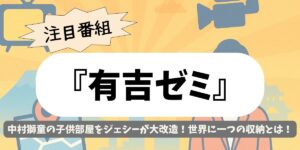

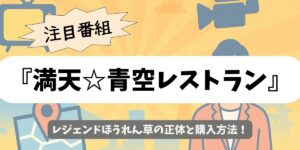
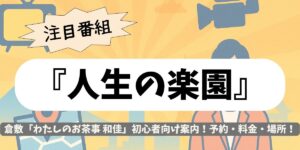

コメント