石破茂総理がいつからいつまで首相を務めたか――このシンプルながらも多くの検索ユーザーが抱く疑問に、できる限り正確にお答えしたいと思います。
石破総理は、2024年10月1日に第102代内閣総理大臣として正式に発足し、その後11月11日には第103代に改組されました。
これにより、制度上は“2つの内閣”と見なされつつも、私たち国民には連続した政治リーダーシップとして受け取られる複雑な経緯です。
その後、石破政権は2025年7月の参議院選挙での苦戦をはじめ、衆参両院で議席を失うという異例の連敗に直面しました。
これにより党内の求心力が揺らぎ、「政権の継続がかえって党を分裂させる恐れがある」との判断から、2025年9月7日、自らの辞意を表明。
その辞任は国内だけでなく、金融市場にも波及し、円安の進行や国債金利の上昇など、即座に反応が表れました。
在任期間の全体像(開始日・最終日・通算日数)

第102代:2024年10月1日〜11月11日(在職42日)
第102代は、2024年10月1日に衆参両院の首相指名を経て発足し、同年11月11日まで続きました。
官邸の「歴代内閣」ページに在職期間:令和6年10月1日〜11月11日/在職日数:42日と明示されています。
第103代:2024年11月11日〜2025年9月7日(辞任表明まで)
第103代は2024年11月11日に再指名・組閣され、官邸サイトでは「〜現在」と記載されています。
もっとも、2025年9月7日に石破総理が辞任を表明した事実が主要報道で確認でき、後任選出までの間は職務執行内閣として継続する扱いです。
通算日数の考え方(当日含む概算で342日)
在任期間を開始日2024/10/1から辞任表明日2025/9/7まで当日を含めて数えると概算342日となります(第102代と第103代を連続として通算)。
官邸の各ページで開始・切替日が確認でき、9/7辞任表明は報道で裏づけられます。
第103代:2024年11月11日~2025年9月7日(辞任表明まで)
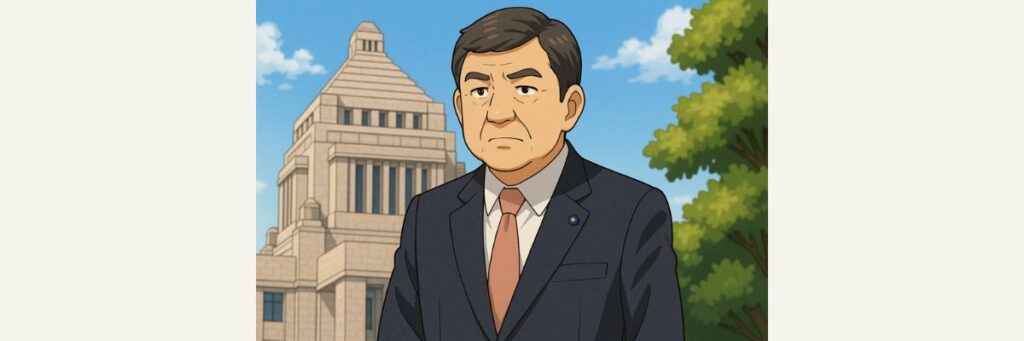
第103代就任の背景とその意味
石破総理が第103代として再出発したのは、2024年11月11日ですが、これは単なる続投ではなく、新たな「組閔替え」による正式な改組として扱われています。
内閣の区分では「第102代」から「第103代」への切り替えと位置づけられ、訓練された政治記録上の区切りです。
実務としては継続的な政権運営であったとしても、制度上は内閣の再構成が成立した日として扱われています。
官邸の公式記録において、第103代の始まりはこの日と明記されており、党内外に対して新たな政権体制への移行を象徴する重要な日とされています。
政権継続中の取り組みと困難
第103代としての在任中、石破総理政権は、内政と外交双方で難局に直面しました。
まず、国内では物価上昇や生活費圧迫への国民の不安が高まり、社会の不満を鎮める政策が喫緊の課題となりました。
これに対し、総理は支援を模索しましたが、参議院選挙での大敗を含む三連敗に直結する形となり、政権の立て直しは困難を極めました。
外交面では、米国との通商交渉を進め、約5,500億ドル規模の投資拡大と引き換えに自動車関税の引き下げを実現しました。
これは重要な外交成果である一方、国内への恩恵や党内の評価には限界があり、総理の支持を支えるには至りませんでした。
辞任表明に至る最終局面
2025年7月の参議院選挙で大敗を喫したことを皮切りに、党内からの退陣要求や党分裂の懸念が高まりました。
その後も石破総理は「政権の空白を避ける」意向を示しつつ踏みとどまりましたが、それに応えるように、最終的には2025年9月7日に自ら辞意を表明しました。
その理由として、「党内の分裂を回避するため」と説明し、政権継続よりも「党の結束と安定」を優先する判断がされたのです。
この辞任表明は、直近の報道で一斉に取り上げられ、政治体制の不安定化の兆候として国内外に衝撃を与えました。
在任中の主要トピックと年表

2024年10〜11月(第102代)の主な決定・人事
石破総理は第102代として着任初期の10月から11月にかけ、目覚ましい政策と人事を推進しました。
まず、2024年10月1日の就任会見では、前政権の経済路線を継承しつつ、「国民の家計を守る」目的で、物価上昇の抑制や生活支援に着手しました。
また、日本銀行に対して緩やかな金融政策を一つの流れとして維持するよう要請し、デフレ脱却の継続を期待していると述べました。
さらに、10月27日の衆議院解散・総選挙に向けて、党内のスキャンダル絡みで不正疑惑があった候補者への公認見直しを行い、党の体質改革とクリーンなイメージ回復を図りました。
11月には第103代として組閣され、新たな内閣人事が行われました。
2024年11月〜2025年9月(第103代)の政策と国政選挙
第103代として再出発後、石破政権は半導体やAI産業の強化策に注力しました。
11月11日には、国内半導体とAI分野を支えるため、10兆円規模の支援を柱とした3年〜6年計画を発表。
北海道での生産インフラ整備を促進する内容で、2030年に向けて総額50兆円規模の公民連携投資と見込まれ、経済の成長動力として意義あるものでした。
その後、11月26日には主要労使の交渉の場で、2025年の賃上げの必要性を前面に掲げ、労働組合や企業に対して、高い賃上げ実現を求めました。
これは実質賃金の回復と国内消費の喚起を狙ったものであり、10年後に最低賃金を42%引き上げる長期目標も示されました。
加えて、LDPが衆参議院とも過半数を失ったことで、野党との協働による政権運営を志向。
特に安全保障政策や災害対策などにおいて、対話を通じた合意形成をはかる姿勢を見せ、閣僚には秋の経済対策の策定準備を指示するなど、政権として持続可能性を模索しました。
2025年7月参院選の敗北〜9月7日辞任表明の流れ
2025年夏の参議院選挙は石破政権にとって転機となりました。
選挙での敗北により、与野党の勢力バランスが逆転し、政権への信任が揺らぎました。
これを受けて、財政政策への批判や党内からの退陣圧力が高まりました。
さらに、9月5日には秋の経済対策策定の意向を改めて示しつつ、自身の責任を感じる発言も報じられました。
そして9月7日、石破総理は党内の分裂を避ける目的で辞任を決断し、その旨を記者会見で表明。
後任選出まで「職務を継続する」としつつ、自らの政権を幕引きました。
この発表は主要メディアで一斉に報じられ、政治的ムードは大きく転換しました。
特に、対米関係で進めていた大型投資促進・関税緩和の協定を決定した直後だった点も注目に値します。
なぜ辞任に至ったのか(背景と今後)

党内分裂の危機回避としての辞任判断
2025年7月の参議院選挙において与党のLDPが議席を大幅に減らし、参議院での過半数を失ったことが契機となりました。
その後、党内では複数派の支持を得て総裁選の前倒しを求める動きが加速。
これを受け、石破総理は、党が内部分裂するリスクを避けるために自ら退く判断を下したと報じられています。
NHKや複数報道によれば、「党の結束を最優先した」と明言し、この一手が結果として辞任につながった点は、政局の混乱回避を優先する政治判断の象徴です。
選挙連敗によるリーダーシップへの信認低下
石破政権のもと、2024年10月の衆院選、さらに2025年夏の参院選を含めた二度にわたる連敗は、政権運営の正当性を大きく揺るがす要因となりました。
その結果、国民からの支持は急落し、党内でも「責任を取るべきだ」との声が日増しに強まりました。
こうした中で、辞任は選挙結果によるリーダーへの信認低下への対応として不可避な決断と報じられています。
政策成果と相反する政治的圧力
外交面では、米国との間で日本車の関税削減や戦略的投資を含む大型貿易合意をまとめるなど、一定の成果がありました。
しかし、これら実績にもかかわらず、党内の反発や世論の冷え込みは続き、「成果があっても支持の基盤回復には至らなかった」との評価が見られます。
党内からは「成果よりも選挙結果の受け止め方が重視されるべき」との見方もあり、成果と政治的圧力とのギャップが辞任を促す一因になりました。
【まとめ】石破総理の在任期間と辞任までの全体像
石破総理は2024年10月1日に第102代内閣として発足し、その後11月11日に第103代内閣として再始動。
以降、国政の中枢として在任中多くの難題に直面しました。
特に2024年10月の衆議院選挙、そして2025年7月の参議院選で与党が議席を失い続け、国民の支持低下と党内からの圧力が増大しました。
石破総理は就任直後から、米国との通商交渉で交渉を主導し、自動車関税の引き下げを含む投資合意をまとめるなど、外交面で一定の成果も収めました。
その締結後、ようやく辞意を表明したと言われています。
しかし、これらの外交成果にもかかわらず、連続する選挙敗北の重圧と、党内での亀裂の兆しが辞任を避けられない状況へと導きます。
総理として最後には「党の分裂を避ける」判断を最優先し、2025年9月7日、正式に辞任を発表。
後継の選出に向けて緊急の党内リーダー選挙を指示し、後任が決まるまで職務継続の意向も示されました。
この辞任発表は、日本国内のみならず金融市場にも即時の影響をもたらし、円売りが加速し、30年国債利回りが過去最高水準へ上昇するなど、政治的不確実性が市場心理に直接的な動揺を与えました。
次期候補として、財政拡張的な政策を指向する高市早苗氏や、比較的穏健な姿勢で党の刷新派を代表する小泉進次郎氏などが名前を挙げられ、“リーダー像”を巡る党内議論が次期政権の焦点となる見込みです。
石破総理の政権は、就任直後から数々の困難に晒されながらも、成果を追求し続けました。
そして最終的には、選挙結果と党のまとまりを鑑み、“退くことで次への橋渡しをする”という決断に至りました。
これは「結果に責任を持つ政治のあり方」として、現代日本政治における重要な一幕であったと感じます。
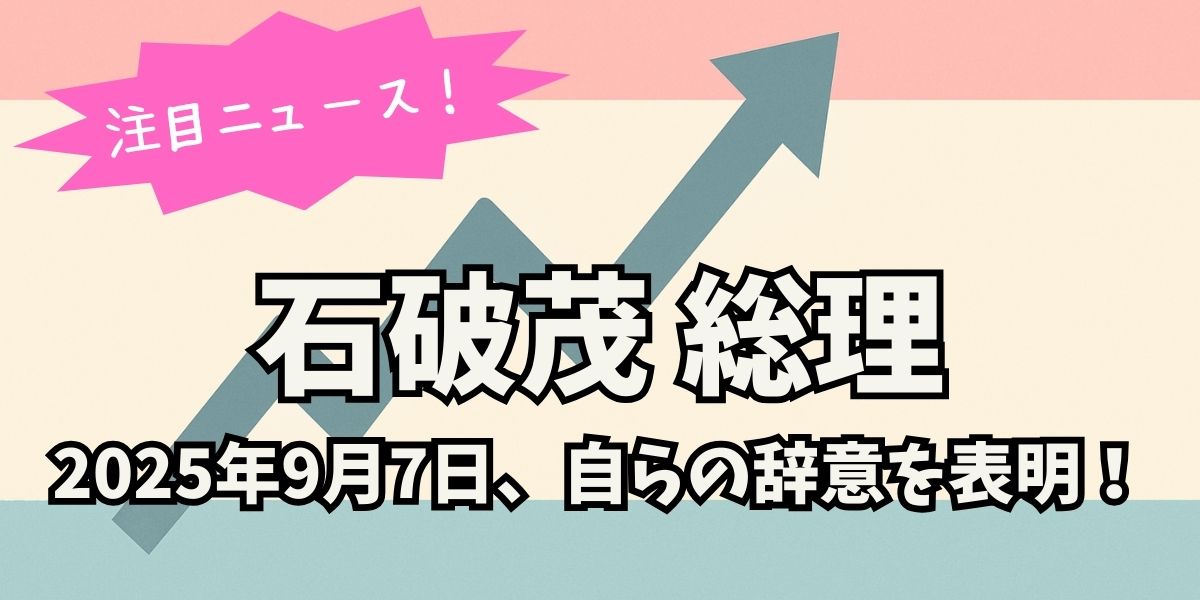
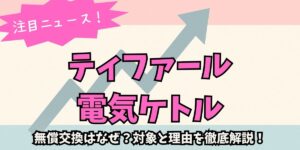
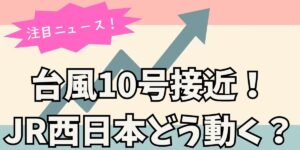



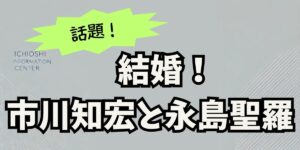
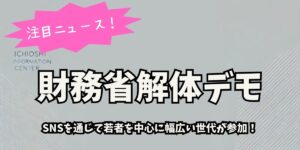
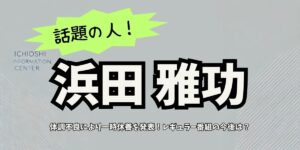
コメント