四国の深山、標高約500メートルの“天空の郷”・家賀集落に、時が止まったような屋敷――「家賀乃里 古城(けかのさと こじょう)」があります。
築260年の古民家を一棟まるごと貸切にしたこの宿は、テレビ朝日の 『人生の楽園』 で2025年8月23日(土)に紹介されました。
放送の舞台は、亡き夫の故郷を再び活気ある地にしたいと願う枋谷(とちたに)京子さん(74歳)が、藍栽培と民泊を通じて地域の再生を目指す取り組みでした。
番組では、藍の畑や囲炉裏を囲む郷土料理、収穫体験などが感動的に映し出されています。
場所は徳島県美馬郡つるぎ町貞光字家賀道上474。
アクセスは、徳島自動車道・美馬ICから車で約20分、JR小島駅からも車で38分と、マイカーでの訪問に便利です。
設備は現代スイッチも充実しており、エアコン・Wi‑Fi完備、一棟貸切で最大6名まで利用可能。
夕食・朝食付き料金は、利用人数に応じて6,000円台~1万円台に設定されており、気軽に非日常を楽しめる宿として支持されています。
特徴は単なる宿泊では終わらない点です。藍の収穫や加工、郷土料理づくり、山菜採りや囲炉裏を囲んだ交流など、地域文化に触れる多彩な体験が魅力です。
新たな“食べる藍”スイーツや藍パウダー、そして自然と共にある時間は、身体だけでなく心を解放してくれます。
さらに注目すべきは、家賀(けか)集落自体が「にし阿波の傾斜地農耕システム」として世界農業遺産に認定されている点。
急傾斜の畑を守るための“茅(かや)マルチ”や石垣農法といった、環境と共に成り立つ知恵がその風景に息づいています。
滞在を通して、ただ見るだけでなく、感じ、学び、土地そのものに溶け込む旅体験が可能なのです。
場所・基本情報・アクセス 詳細解説

所在地と建物構成
古民家宿「家賀乃里 古城(けかのさと こじょう)」は、徳島県つるぎ町美馬郡つるぎ町貞光字家賀道上474に位置しています。
築約260年の藁葺き古民家を一棟貸切で提供する民泊で、木の温もりと歴史ある情景をそのまま体感できる宿です。
最大6名まで宿泊可能で、寝室は二部屋、マットレスでの寝具スタイルが特徴です。
アクセス手段と交通所要時間
車でのアクセスは、徳島自動車道の美馬ICから約20分ほど。
公共交通を利用する場合、JR徳島駅から車で約1時間15分、またはJR貞光駅からタクシーや送迎の相談が可能です。
小島駅からは車で約38分です。駐車場も完備されており、アクセスの柔軟さが魅力です。
宿泊の流れと料金設定
チェックインは15:00以降(最終受付20:00)、チェックアウトは翌10:00です。
料金は一泊二食付き(夕・朝食)で、1名利用で12,180~17,980円、2名では6,090~8,990円など、人数に応じた料金体系が適用されます。
1組貸切でプライベートな滞在が可能です。
宿の特徴と体験

藍の栽培と「食べる藍」としての活用
家賀乃里 古城の特徴として最も際立つのが、「藍の栽培再生」とそれを「食べる藍」として取り入れた点です。
地元の伝統に根ざした藍栽培(2019年に復活)は、無農薬・無化学肥料の有機的な方法で行われ、傾斜地に茅を用いた土壌保全(“カヤのマルチ”)など自然に寄り添う手法が今も息づいています。
そこで育った藍を乾燥・粉末化し、「家賀の藍粉」として加工。
これを夕食に使った「藍の天ぷら」は宿泊者の話題になる名物料理です。
繊細な青い色彩と、ほんのりしたほろ苦さや爽やかさを楽しめる“食のアート”として人気を集めています。
さらに、藍粉はホットケーキやヨーグルト、そうめんなど日常の食材にも使われるスーパー素材。
健康志向の来訪者にとっては抗酸化・整腸といった機能性も魅力です。
伝統農法と世界農業遺産の暮らしを体感
家賀乃里 古城が位置する家賀集落は、「にし阿波の傾斜地農耕システム」として世界農業遺産にも認定されており、急傾斜(最大斜度40度)を活かして段々畑ではなく、石垣と茅による水と土の循環を支える独自農法が今も継承されています。
宿の周辺では、そうした環境をガイド付きで散策する体験も可能です。
茅で覆った畑、石垣の構造、伝統的な土の保全技術などを一緒に巡ることで、ただの観光では味わえない「土と人の知恵」を五感で感じる旅が体験できます。
囲炉裏の古民家と宿泊の過ごし方
築約260年の古民家を再生した「家賀乃里 古城」は、一棟貸切で宿泊可能な点が大きな魅力です。
囲炉裏と太い梁をそのまま残した内装は、まるで祖父母の家に帰ったような懐かしさと温もりを感じさせます。
古民家では、囲炉裏端での郷土料理や山菜・川魚の料理、囲炉裏を囲む団らんなど、自然と文化が溶けあう時間を味わえます。
春夏秋冬、それぞれに映える里山の風景を眺めながら、ゆったりとした時間が流れます。
体験プログラムと地域との交流
家賀乃里 古城では、宿泊者が地域文化に深く触れるプログラムが充実しています。
藍の収穫・藍染め・加工体験、山菜採り、地元食材を使った料理づくりなど、暮らし全体を体験できる内容が揃っています。
また、抱えるのは単なるアクティビティではなく、地元住民との自然な交流。
農作業や里山散策を通じて“暮らしそのもの”に触れ、共に食卓を囲むことで、生まれる地域との新たな絆もあります。
周辺の見どころ・学び

自然体験型合宿施設「家賀の郷 清笹」
「家賀の郷 清笹」は、2024年4月24日に開業した木造2階建ての自然体験型宿泊施設です。
1階にはギャラリーやマルシェとして使える共有スペースとキッチンが備えられ、2階には4人部屋と6人部屋がそれぞれ2部屋ずつ設けられています。
この施設は“にし阿波の傾斜地農耕システム”という世界農業遺産地域に位置し、宿泊者には斜面農法や集落散策などを体験する機会が提供されています。
たとえば、「SDGs体験ツアー(2024年10月開催)」では、茅刈りや“コエグロづくり”(茅を活用した土壌保全手法)といった伝統的な農法を実践する企画が行われ、地域の環境保全と歴史理解の双方に触れる機会となりました。
さらに、地元の農業体験や藍染め、竹筒晩茶作りまで、多彩なプログラムが用意されています。
これらの体験を通じて、宿泊者は地域の文化や自然、持続可能な暮らしの営みを五感で学ぶことが可能です。
「家賀散策」と茅葺き体験
つるぎ町の観光プログラム「家賀散策〜羽釜おにぎりと春の恵み〜(2025年6月実施)」では、世界農業遺産地域に位置する家賀(けか)集落をガイド付きで歩き、伝統農法や乾物文化が今も生活の根底にある様子を実際に体感できます。
散策の最後には、茅葺き屋根の家屋にて羽釜で炊いたご飯を使ったおにぎりづくりを体験し、季節の山の恵みを活かしたおかずとともに味わう、本格的で温かな里山体験が組まれています。
このプログラムは、訪問者が家賀集落の暮らしを理解するだけでなく、自然との共生や伝統技術の継承についても実感できる貴重な場となっています。
「家賀城跡」と忌部集落の歴史資産
家賀集落には、かつて忌部氏の分家である麻殖因幡守持光が拠点を置いた「家賀城」が存在しました。
その城跡は、児宮神社の上方の森に石碑とともに現存しています。
文献「貞光町史」によると、1552年(天文21年)、持光は三好山城守康長の攻撃により討ち死にし、家賀城は焼失。
その後、現在は遺構が明確には残っていないものの、地名とともに歴史の記憶として地元に伝わっています。
一方、児宮神社そのものは家賀集落の氏神で、斎主命(いわいぬしのみこと)を祀る由緒ある社です。
神社の裏手には、「灰塚」と呼ばれる小さな塚(斎主命の陵とされる)が残されており、地域に根ざす神話と歴史を感じさせます。
伝統宗教施設「西福寺」の痕跡
家賀集落の中心部には、かつて忌部神社の別当寺として栄えた「西福寺」が存在しました。
創建は奈良時代の神亀年間(726年)で、弘法大師ゆかりの寺として真言宗に転じた歴史を持ちます。
しかし、1569年(永禄9年)の火災、さらに1697年(元禄9年)、1748年(延享4年)と度重なる火災により衰退。1913年(大正2年)にも全焼し、最終的には昭和15年(1940年)に、麻殖氏ゆかりの地である家賀道上に本堂と回廊が再建され、今日に至っています。
こうした歴史的な痕跡は、家賀の深遠な宗教的背景と、地域の文化的な継承がいかに厚かったかを物語っています。
『人生の楽園』放送回の要点

放送日・番組の要旨
テレビ朝日系『人生の楽園』は「天空の郷 藍畑と古民家宿 〜徳島・つるぎ町」を2025年8月23日(土)18:00〜18:30に放送。
舞台は徳島県つるぎ町の家賀(けか)地区で、標高500m超の山肌に広がる集落の風土と、藍の栽培、古民家を活用した“自然体験型の宿”の取り組みが特集されました。
公式の番組情報では、急傾斜地に点在する集落の活気を取り戻そうとする奮闘が紹介されています。
枋谷京子さんの取り組み
主人公は枋谷京子さん(番組情報上は74歳)。
亡き夫の故郷である家賀集落の再生を願い、藍の栽培を再開しつつ、都会からの来訪者を受け入れる“自然体験ができる宿”を始めました。
番組の公式資料では、耕作放棄地や空き家が増えた集落に人の流れを呼び戻すための実践として、藍畑づくりと古民家宿の運営を挙げています。
世界農業遺産に認定された地域景観の中で行われている点も明記されています。
最新情報の確認先(公式・予約・地図/SNS)
放送内容の一次情報はテレ朝の公式プレスページと番組サイトで最新を確認できます。
番組回の掲出タイトル・放送日時・要旨は公式に掲載され、テレビ情報サイトでも同内容が反映されています。
宿の実在情報(所在地・アクセス・連絡先・チェックイン/アウト等)は主要予約サイト(楽天トラベル等)や地図サービスに登録があり、住所は「徳島県美馬郡つるぎ町貞光字家賀道上474」、アクセスは徳島道・美馬ICから車で約20分等が案内されています。
放送当日の告知や話題はX(旧Twitter)でも共有されました。必要に応じて、これらを組み合わせて事前確認すると確実です。
まとめ

「番組で見た“家賀乃里 古城”はどこにあって、どうやって行き、何が体験でき、予約や最新情報はどこで確かめればいいの?」——その答えは次のとおりです。
まず、“家賀乃里 古城”は徳島県つるぎ町・家賀(けか)集落にある一棟貸しの古民家宿で、住所は「徳島県美馬郡つるぎ町貞光字家賀道上474」。
チェックインは15:00(最終20:00)、チェックアウトは10:00。アクセスは徳島自動車道・美馬ICから車で約20分が目安です。
現地の地図・連絡先(050-5444-6620)や基本情報は主要予約サイトにも掲載があります。
まずは空室や料金の最新状況を予約サイトで確認してから計画を立てるのが確実です。
番組『人生の楽園』では、2025年8月23日(土)18:00~18:30の回で、つるぎ町の“天空の郷”を舞台に、藍を育てて民泊を営む取り組みが紹介されました。
番組の放送情報と回の概要はテレビ朝日の公式ページや番組広報ページ、TV情報サイトでも確認できます。
放送回タイトルや要旨に加え、「標高500m超の山肌に広がる集落」「藍の栽培と自然体験ができる宿」というキーワードで押さえておくと、現地のイメージが掴みやすいはずです。
体験の“軸”は二つ。ひとつ目は、地域で受け継がれてきた藍の営みと食・暮らしに触れること(藍の畑や里山の暮らしに寄り添った滞在)。
ふたつ目は、世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システム」のフィールドに身を置き、急斜面の環境と人の知恵がつくるランドスケープを学ぶことです。
集落一帯は“段々にせず斜面のまま耕す”独自の知恵が評価されており、背景を知ったうえで歩くと風景の見え方が変わります。
周辺の拠点としては、体験型宿泊施設「家賀の郷 清笹」が2024年4月に開業。
ギャラリーや多人数で使える客室を備え、傾斜地農耕や集落散策などのプログラムを展開しています。
“家賀で過ごす”時間を厚くしたい方は、古民家宿での滞在と合わせて体験の受け皿として検討すると動線がスムーズです。
最後に、計画時のチェックリストです。
- 住所・連絡先・チェックイン/アウト・駐車場:予約サイトの施設ページで最新を再確認(住所・時間・TELの一次情報がまとまっています)。
- 放送内容の復習:テレ朝の番組広報ページやTV情報サイトの該当回で概要を確認。現地で「何を見る/体験するか」を具体化しやすくなります。
- 学びの背景資料:GIAHS(世界農業遺産)の公式解説で“斜面のまま耕す”地域文脈を予習。現地散策の理解が深まります。
- 体験の受け皿:家賀の郷 清笹の開業情報・プログラムを確認し、旅程に組み込み。
“泊まる”だけでなく、“風土に触れる”旅にしたい方にはベストな舞台です。
まずは住所・アクセス・空室と、番組で語られた趣旨(藍と暮らしの再生)を公式情報で押さえ、次に世界農業遺産の文脈と周辺拠点を重ねて行程を組む——この順番で進めれば、放送で見た世界を無理なく体感できます。
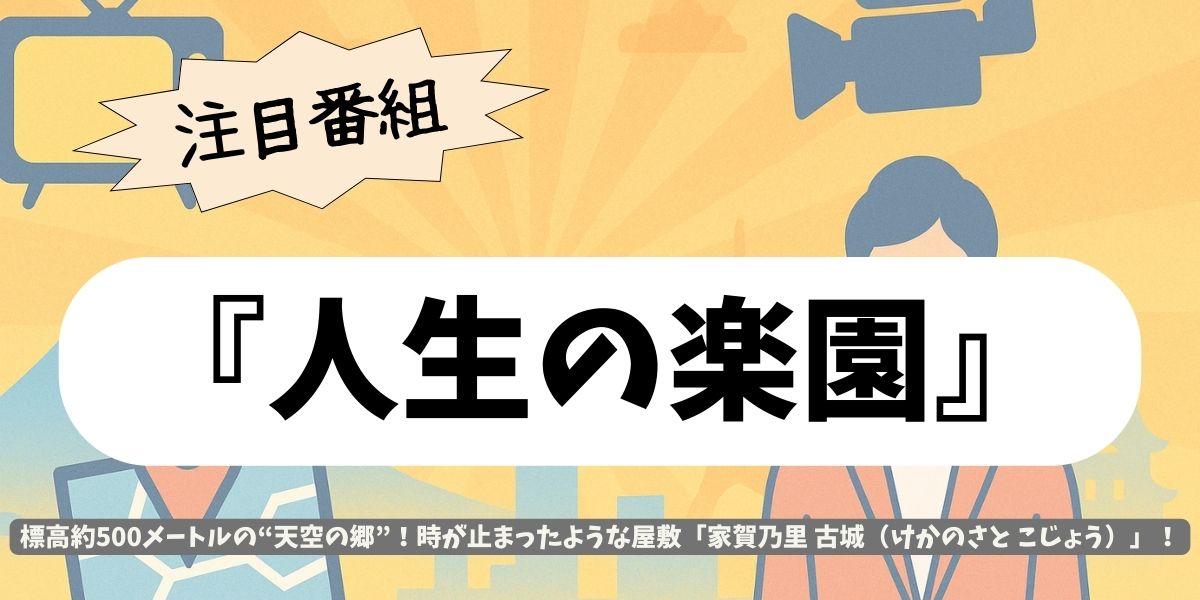

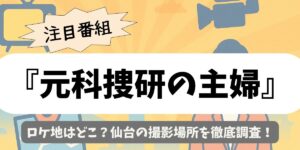
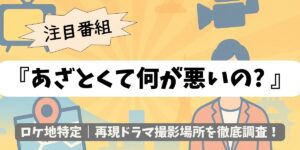

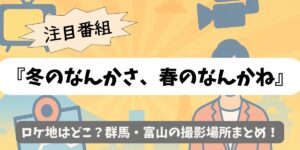
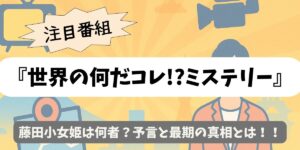

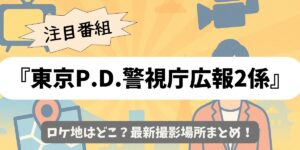
コメント