「マツコの知らない世界」10月28日(火)放送回のテーマは、ズバリ“毒の世界”。
番組公式サイトでは「空前ブーム!人類の未来救う〖毒〗衝撃映像連発SP」「図鑑超えの新事実」などのキャッチコピーが掲げられており、従来の“危険だから近づくな”というだけの“毒”ではなく、学び・驚き・実践の三領域で捉え直す構成になっていることが明らかです。
この回で紹介されるのは、例えば「ゾウ2頭を倒すカエル!?」「世界最大のミツバチが襲う!」といった衝撃的な映像とともに、毒をめぐる最新の研究動向――糖尿病・脳腫瘍治療への応用も視野に入れた“毒と医療”の接点――さらに、私たちの身近に潜む毒生物との出会い方、遭遇時の具体的な対処法まで。
そのため、「ただテレビを眺める」だけではもったいない、“知ることで安全に、活かすことで未来につながる”知見を得られる回として位置づけられています。
もしあなたが、「毒生物の驚き映像を見たい」「普段聞かない“毒の活用研究”について知りたい」「アウトドアや日常で毒生物に出会った時の備えを知っておきたい」といった検索意図を持ってこのキーワードを打ったのであれば、本記事はまさにその期待に応える構成です。
放送前に押さえておくべきポイント、放送中に注目すべき視点、放送後に知識として残すべき整理までを網羅。視聴前でも、視聴後でも価値ある読み物としてご活用いただけます。
さあ、未知なる「毒の世界」へ。一緒にその深淵を掘り下げていきましょう。
放送概要と見どころ(放送日時・テーマ・新事実の方向性)

放送日時・配信情報(TBS/TVer/リアタイ)
2025年10月28日(火)よる8時55分から、マツコの知らない世界 が 「毒の世界」特集 として放送されます。
放送局は TBSテレビ 系、リアルタイム配信も対応しており、TVerやTBS FREEなどの公式配信サービスで視聴可能になる旨、番組公式サイトで案内されています。
また、公式のSNS(X/旧Twitter)でも「次回10/28(火)よる8時55分〜☠️毒の世界」などと予告投稿があります。
この日時・配信情報を事前に押さえておくことで、録画予約・見逃し配信のチェックを行う視聴者にとって、確実に視聴できる準備が整います。
特集テーマ「毒」—図鑑超えの“新事実”要約
この回のテーマは「毒」という、一見ネガティブだが実は多角的・応用的に注目されているジャンルです。
番組公式ページでは「空前ブーム!人類の未来救う〖毒〗衝撃映像連発SP」「図鑑超えの新事実」と明記されています。
具体的には、「ゾウ2頭を倒すカエル!?」「世界最大幻のミツバチが襲う!」など、生物の“毒”が持つ想像を超えたパワーと、それを科学・医療がどう応用しようとしているかまで言及。
つまり、この特集では「ただ毒生物を紹介する」だけでなく、「毒を知ることで人類の未来にどう関わるか」という“新事実”視点が軸になっていることが要約できます。
注目トピック(新薬開発・禁断映像・最新毒事情)
番組が掲げる注目トピックは大きく3つ挙げられています。
1つめは「新薬開発」。
番組情報では「毒から糖尿病・脳腫瘍の治療薬開発も…!?人類の助けになる最新毒活用法」という文言が記載されており、毒の医療応用という観点が強調されています。
2つめは「禁断映像」。
予告では「弱小生物が一発逆転する最終兵器・毒パワーに迫る」「世界最大幻のミツバチが襲う!衝撃映像にマツコ驚愕」という言葉が使われており、普段目にしない“危険&驚き”映像の披露が見どころです。
3つめは「最新毒事情」。
番組説明には「空前ブーム!」「図鑑超えの新事実」「毒生物と出会ったら?実践できる危険対処法紹介」という記載があり、情報としての“毒”に対する理解・警戒・活用という三方向のアプローチがされることが読み取れます。
これらのトピックを事前に知っておくことで、番組視聴時に「この場面は医療応用の説明だ」「この映像は禁断映像だ」と整理しながら見ることができます。
登場ゲストと検証ポイント(平坂寛さんの取材と発言整理)

体当たり取材の見どころ(危険生物リポート)
今回のマツコの知らない世界「毒の世界」特集で、ゲスト出演する平坂寛さんは、“体当たり取材”を軸に活動する生物ライター/YouTuberです。
公式告知によると、「ゾウ2頭を倒すカエル!?」「世界最大幻のミツバチが襲う!」など、図鑑ではまずお目にかかれない衝撃的な生物映像が多数登場する予定です。
平坂さん自身のインタビューでも、“図鑑や書籍に載っている「危険です」「刺されたら痛いです」だけでは、生物の本当の力は分からない”という考えを持ち、実際に毒を持つ生物に刺されたり噛まれたりする経験を通して「痛みや症状、効き目の強さ」を体感してデータ化していることが報じられています。
番組ではこの“体当たり”取材映像を、マツコ・デラックスさんとのトークとともに紹介。
「弱小生物が一発逆転する最終兵器・毒パワー」というキャッチフレーズが出ており、ただ“危ない映像”を見せるだけでなく、「なぜその生物が毒を持つのか」「その毒がどう使われているのか」まで深掘りする演出が明確に意図されています。
このため視聴者としては、単なる“驚き映像ショー”としてではなく、「生物学的背景/生態系の中で毒が果たす意味」を意識して取材映像を見ることで、より理解が深まる設計になっていることが読み取れます。
発言・データの出典確認(科学的根拠の位置づけ)
番組製作側が「図鑑超えの新事実」と謳っている以上、紹介される発言・データがどれだけ一次ソースに近いかがカギになります。
例えば、平坂さん自身が「世界最強の猛毒魚『オニダルマオコゼ』に刺されてみた」という動画を公開しており、その体験談が今回の特集でも素材として扱われる可能性が高いです。
ただし、そのような“刺されてみた”系の体験はあくまで個人が行った実験的な行動であり、学術論文としてのエビデンスとは異なります。
番組側が“新事実”として扱うためには、現地取材+文献チェック+医学/毒理学的な裏付けが必要です。公式告知には「糖尿病・脳腫瘍の治療薬開発も…!?」という文言があり、毒を医療応用する研究の話題も提示されています。
視聴者が注意すべきは、番組内で提示される「最新研究」「応用可能性」の情報が“発展途上の仮説段階”であるケースがあることです。
そこで本記事では、紹介される可能性の高いデータと、それらの出典・限界について“出典確認の視点”を持つことを推奨します。
たとえば、平坂さんの活動記録/YouTube動画では“刺された感覚・痛み”までは報告されているものの、「治療薬として実用化されている」という形では明示されていません。
番組視聴後には、紹介された生物名・毒名・研究機関・論文名などを自分で検索し、「この情報は公開論文か?実験段階か?」「安全対策はどうなっているか?」というチェックをすることで、視聴体験から「納得できる知識」に変換できます。
SNS/公式予告との一致点・相違点
番組公式SNS(X/Instagram)では予告キービジュアル・キャプションで「10月28日(火)よる8時55分〜」「空前ブーム!毒」「図鑑超えの新事実」「体当たり取材映像」などが明記されています。
特にXアカウントでは「#毒の世界」「#マツコの知らない世界」というハッシュタグ付き投稿が10月に入り数回確認されています。
この点、“配信時間”“テーマ”“ゲスト”といった基本情報は公式告知と一致しており、番組構成の信頼性が高いと言えます。
例えば、「ゲスト:平坂寛さん」の記載は複数番組表サイトでも確認可能です。
一方で、“映像内容の詳細”や“研究データの深さ”については、あくまで予告文言に留まっているため、実際の放送でどれだけ掘り下げられるかには不確定要素があります。
視聴者が「新事実」と期待する部分に対して、SNS予告で煽られた期待値と放送実際の内容とのギャップが発生する可能性があるため、視聴前に「予告=放送本編では省略される可能性あり」という前提を持つことも大切です。
このように、SNS/公式予告との一致点・相違点をあらかじめ把握しておくことで、番組視聴の際の“期待値”を適切に管理でき、放送終了後も「ここは映像あった/ここは触れられなかった」という振り返りがしやすくなります。
番組で語られる“毒の新事実”を深掘り(研究・医療応用)

毒と新薬開発(糖尿病・脳腫瘍などの可能性)
番組公式ページによると、今回の特集は「毒から糖尿病・脳腫瘍の治療薬開発も…!?人類の助けになる最新毒活用法」というサブタイトルが打たれています。
具体的には、長らく“危険で避けるべきもの”とされてきた毒性生物・物質が、逆転の発想で「ヒトの病気を治す鍵」になりうるという研究の潮流が紹介される模様です。
例えば、海洋生物学科の 糸井史朗 教授が手がける“フグの赤ちゃんが母親由来の毒で守られている”研究が、10月22日付で紹介されており、今回の放送でその成果が取り上げられると明記されています。
毒性物質はその強さゆえに、通常は「毒=害」という認識が強いですが、一定条件下でヒト用の薬剤に応用できるという発想も近年活発です。
たとえば神経細胞の受容体を標的とする毒ペプチドを、過剰な細胞興奮を抑える薬とする研究などが世界的にも進行しており、本特集ではその“毒+応用”の具体例が紹介されることになります。
視聴者として注目したいのは、「どの毒物質が」「どの病気を狙って」「どのステージで応用可能性があるのか」という点。
放送後には、紹介された生物/毒名/研究機関名を自身でも追ってみる価値があります。
さらに、番組予告には「空前の毒ブーム!人類の未来救う新薬開発に…」という強めのキャッチもあり、毒研究が単なるマニアックな話題ではなく、医療・産業という実用面で脚光を浴びていることが強調されています。
ただし実用化までにはまだ多数のハードル(安全性、毒性制御、コスト、法的規制等)があるため、番組内で「治療薬としてすでに実用化された」など明確な断言があるかどうか、その点も注視しておいた方が良いでしょう。
生態学的視点(弱者の逆転戦略としての毒)
本特集でも扱われているキーワードに「ゾウ2頭を倒すカエル!?」というあまりにもインパクトある見出しがあります。
このフレーズが示す通り、体の小さな生物が“毒”という兵器を持つことで、サイズや筋力で勝る大型生物に対抗する構図が自然界には多く存在します。
つまり、生態学的には「毒を武器にする弱者が逆転する戦略」と捉えることができます。
番組ではこのような生物の実例を映像とともに紹介するとのことで、視聴者は“なぜこんなに強力な毒を持つのか”“毒という武器を進化させる意味”を生物進化論的な視点から理解する機会となります。
この“逆転”の構図は、単に驚き映像を楽しむだけで終わらず、「毒=加害」という単純図式を超えて、「どういう生態的条件で毒が選択されてきたか」をひもとく興味深い切り口でもあります。
また、番組告知では「世界最大幻のミツバチが襲う!衝撃映像」なども予告されており、生態的に“攻撃・防御両面”で毒を持つ生物に光を当てる構成と見られます。
視聴者として有効なのは、ただ映像を「すごい!」と見るだけでなく、「この種がなぜ毒を持つのか/どんな環境にいるのか/その毒がどんな作用を持つのか」を問う姿勢です。
これによって、生物の進化や生態の奥深さをより深く感じることができます。
世界最大級ミツバチほか話題生物の基礎知識
番組公式には「世界最大幻のミツバチ」「ゾウ2頭を倒すカエル」など、なかなか聞き慣れない“話題生物”の名前が並んでいます。
「世界最大幻のミツバチ」とは、一般に最大級のミツバチとして知られる メガハニー・ビー(学名 Megachile pluto、オオカバマルハナバチ)が想定されている可能性があります。
この種は体長3 cm以上に達し、翅の音も大きく「世界最大のミツバチ」とよばれています。
また、「ゾウ2頭を倒すカエル」という表現も非常に大きなインパクトがありますが、これは比喩的表現か、あるいは体の小さな生物が強力な毒を持つことを伝える演出でしょう。
いずれにしても、視聴時には「どんな生物か」「どんな毒を持つか」「人間との関係はどうか(危険性/応用性)」という視点で見ておくと、内容理解が深まります。
さらに、話題生物として登場する生物は「極限環境」「先進的な進化」「生物多様性の象徴」として位置づけられており、番組は単なる紹介に留まらず「生物学的奇跡/自然の驚き」として毒生物を扱う構成となっているようです。
視聴前には、紹介される生物の名前をメモしておき、放送後に自分で更に調べる“楽しみ”も持っておくと、知的な楽しさが増すでしょう。
安全とリスクコミュニケーション(実践的対処法)

遭遇時の行動フロー(番組で紹介の対処法整理)
番組公式サイトでも、今回の「毒の世界」特集では“毒生物と出会ったら?実践できる危険対処法紹介”と明記されています。
実際に、毒をもつ生物に遭遇した際には「どのような初動行動をとるか」が事故被害を軽減する鍵となります。
まず第一に、遭遇した生物を不用意に触らず「距離を取る」ことが最優先です。
例えば、野外で毒蛇や毒虫を発見した際にはその場から静かに離れ、むやみに追ったり刺激を与えないことが基本であると、神奈川県などでは明確に「草むらや藪などでは肌の露出を避け、長袖・長ズボンを着用」するなど対策を推奨しています。
次に、もし接触・咬傷・刺傷が発生してしまった場合には、速やかに「出血・腫れ・激痛」といった症状の有無を確認しながら、救急医療機関に連絡するという流れが推奨されています。
毒物劇物中毒に関しては、「事故発生後はまず医療機関に受診。
受診時に毒物の種類・量・侵入経路を伝えることが重要」などのガイドが出ています。
番組ではこのあたりを「体当たり取材映像+専門家の解説」で視聴者にわかりやすく提示する予定であり、遭遇時の即時対応を「覚えておくべき具体的アクション」として整理してくれることが予想されます。
視聴者としては、放送時に提示される「生物名」「症状の動き」「初動の行動パターン」をしっかりメモしておくことで、いざという時の知見として身につけられます。
国内で注意すべき毒生物の基礎リスト
日本国内にも、日常生活・レジャー・山間部・海辺などで毒をもつ生物が存在し、番組でも「私たちのすぐそばにも潜む毒生物」という視点が提示されています。
公式告知に「図鑑超えの新事実」とありますが、まずは基礎知識として“国内で注意すべき代表例”を押さえておくと、番組内容の理解が深まります。
例えば、山や藪では「マムシ」や「ヤマカガシ」などが咬傷事故の報告が多く、海辺では「ヒョウモンダコ」が浅瀬に潜む例があり注意喚起されています。
また、蜂類・ハチの刺傷も非常に多く、特にスズメバチやアシナガバチは警戒色を持つため“近づかない”が基本とされています。
このように「何を注意すべきか」「どんな生物が危険か」を事前に把握しておくことで、番組で紹介される“珍しい毒生物”の衝撃をよりリアルに捉えられます。
さらに、遭遇リスクがある場所(藪、川辺、サンダル・半袖で入る場所)を自身の行動範囲に照らしてあらかじめチェックしておくことも有効です。
例えば、大分市の資料では「草刈りやキノコ採り、農作業中などに手を咬まれることが多い」とあり、半袖・半ズボン・素足は特に危険と示されています。
番組の視聴前にこうした“国内基礎リスト”を頭に入れておくと、紹介される生物が“遠い世界の話”ではなく「自分にも関係しうる存在」として捉えられ、知識としての価値が高まります。
アウトドア/都市部での予防チェックリスト
毒をもつ生物との遭遇を「ゼロ」にすることは難しいですが、リスクを大幅に低減するための予防策はいくつも存在します。
番組でも「実践できる危険対処法紹介」として、外出前・帰宅後・日常生活段階でのチェックポイントを提示する可能性が高いです。
公式告知にもこの文言があります。
まず、外出前には、肌の露出をなるべく減らす長袖・長ズボンの着用、靴下+靴、ズボンの裾を靴の中へ入れるなど“隙間侵入”を防ぐ工夫が推奨されています。
例えば、アウトドア専門ブログでは「袖口を手袋の中へ」「ズボン裾を靴下で覆う」など細部への配慮が重要とされています。
次に、帰宅直後には、衣類や靴を外に置かず屋内に持ち込まずシャワーまたは入浴して身体をチェックする習慣も有効です。
神奈川県のサイトでは「帰宅後は作業着を家の中に持ち込まず、入浴してマダニがついていないか確認を」と明記されています。
都市部・住宅地においても油断は禁物で、庭先・公園・散歩道などで毒性のあるクモやアリの存在が報告されています。
対策としては「草むら・穴・石の下に手を入れない」「裸足・サンダルを避ける」「ペットや子どもを遊ばせる場所の地面を確認する」などの基本行動が挙げられています。
番組放送中には、こうした“予防チェックリスト”が映像とともに提示されるでしょう。
視聴者としてはスクリーンキャプチャやメモを取り、「自分の場合どういう対策をするか」を併せて考えることで、ただ見て終わるではなく「自分の生活に役立てられる知識」へと昇華させることができます。
まとめ
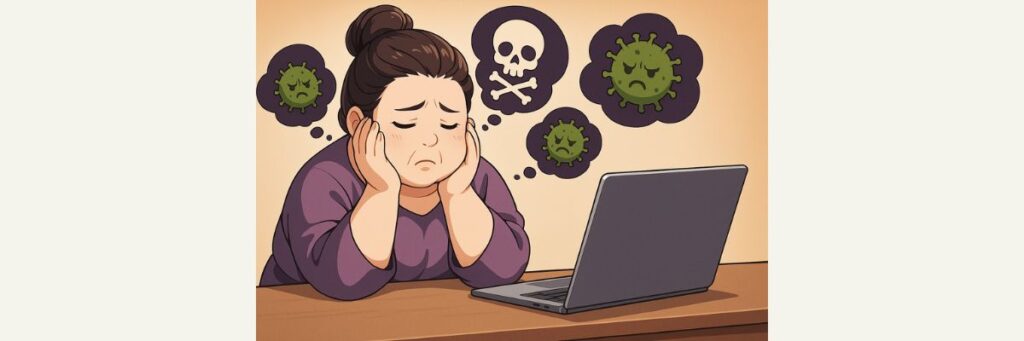
「マツコの知らない世界『毒の世界』」は、放送日時が2025年10月28日(火)20:55で確定し、公式サイト・番組表・TVer告知・公式SNSで一貫して“図鑑超えの新事実”“禁断映像”“毒の医療応用”“遭遇時の実践的対処法”が押し出されています。
視聴者がまず押さえるべきは、この回が“怖さ”だけでなく科学・医療・安全の3本柱で毒を捉え直す構成である点です。
放送直前の情報源としては、TBS公式ページ、MBS番組ページ、TVerの同時配信案内、そして番組公式Xや出演告知のポストが有効でした。
内容面では、「弱者の逆転戦略としての毒」や「毒を手がかりにした新薬開発」といった切り口が明確に示唆されています。
具体的なティーザーには「ゾウ2頭を倒すカエル!?」「世界最大の“幻”ミツバチ」「スズメバチVSツキノワグマ」など、普段は触れにくい現象を“現場映像+解説”で理解させる狙いが見て取れます。
視聴時は、各シーンで(1)生物名/毒の種類(作用機序)、(2)提示される研究の成熟度(基礎・臨床・実用化)、(3)生活者としての安全行動の3点をメモしておくと、見終えた後に知識として残りやすく、情報の誇張とファクトを切り分けやすくなります。
安全面については、番組が事前にうたう「毒生物と出会ったら?実践できる危険対処法」が要点。
屋外では“近づかない・触らない・刺激しない”が初動の基本で、万一の刺傷・咬傷時には症状の推移を確認しつつ速やかに医療機関へ。
国内でもマムシ・ヤマカガシ・スズメバチ類・ヒョウモンダコ等の注意喚起が自治体資料で継続して行われていることを踏まえ、長袖長ズボン・足元保護・草むらへ素手を入れないといった“地味だが効く”予防策を日頃から徹底しておくのが現実的です。
配信動線は、地上波+TVerほか公式配信という案内が出ています。
リアタイ視聴が難しい場合は、TVerの番組ページやアプリを事前に用意しておくと確実です。
放送後に検証を進める際は、番組で挙がった生物名/毒名/研究機関名を手掛かりに一次情報(論文・公式発表)へ当たるのが近道。
まずは本放送で提示される“主語(誰が/どこで)”と“動詞(何を示した)”を正確に拾い、科学的根拠の段階を見極める視点を持ちましょう。
最後に筆者の所感として——今回の特集は、エンタメ×教養×安全教育のバランスが良く、毒への“一枚岩の恐怖”イメージを「仕組みを知り、安全に向き合い、社会に活かす」へとアップデートしてくれる内容になりそうです。
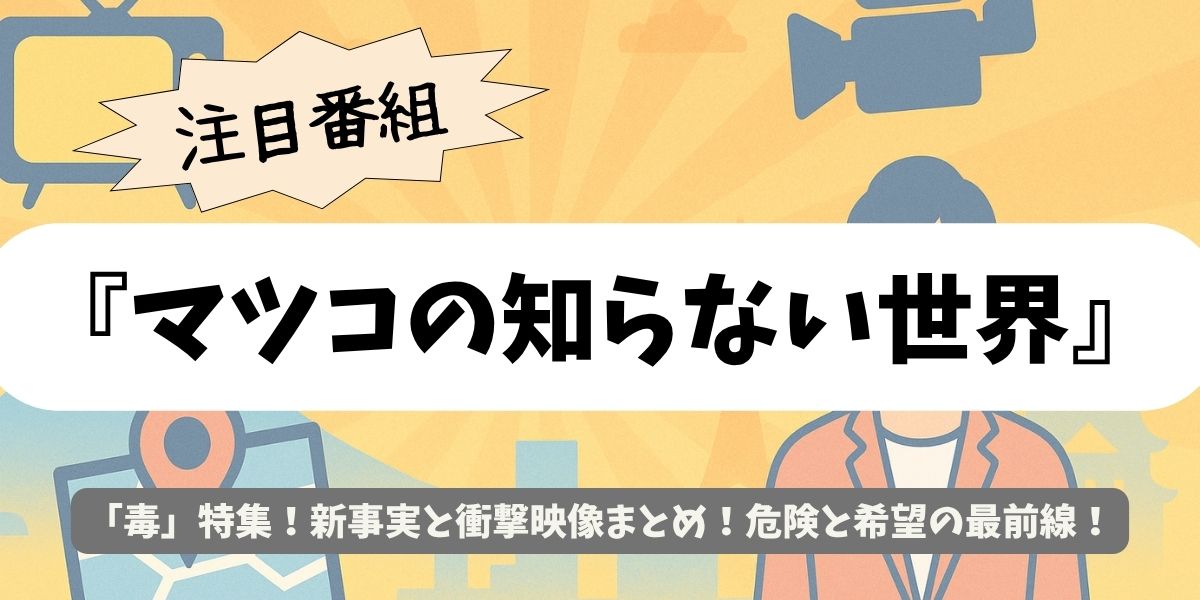

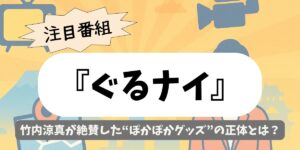
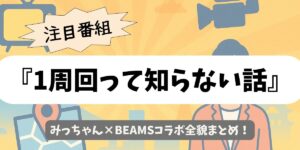
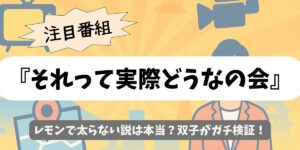
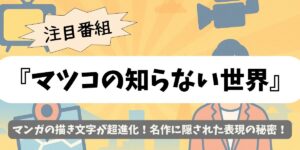
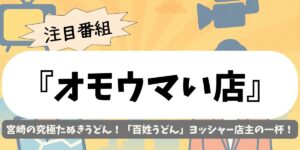

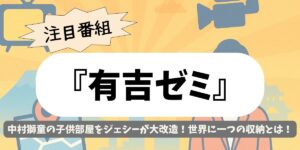
コメント