ご当地バーガーはこれまで、「旅先の軽食」「変わり種グルメ」の域を出ない存在でした。
ところが、2025年9月30日放送の「マツコの知らない世界 ハンバーー最前線は道の駅だSP」では、道の駅が「本気のバーガー基地」に変貌を遂げている現場が紹介されます。
番組告知によれば、全国の道の駅で“すだち丸ごと”“トロトロ白なす”“巨大しいたけ”といった、東京・都市部ではなかなか出会えない食材を使った個性派バーガーを21選で一挙公開するとのこと。
この放送の狙いは、「具材が旨い&安いで本格化」「流通と地産地消(秘)アイデア」「農家野菜バーガー」「この秋行ける北関東ルート」など、素材・経営・ルート設計の裏側にまで切り込む点にあります。
恐らく視聴者は、「この番組を見たあとすぐにでも出かけたい」「どの道の駅で、どのバーガーを食べるか決めたい」と思うはずです。
読者のあなたも、そんな気持ちを抱えてこのキーワードで検索しているのではないでしょうか。
「マツコの知らない世界 道の駅 ご当地ハンバーガー」と検索する人の多くは、“番組で紹介されたバーガー情報を先取りし、実際に足を運びたい”という目的を持っています。
本記事では、その検索意図に応え、放送直後でも迷わず行動できるよう次の情報を詳しく整理します。
- 番組で取り上げられた代表的バーガーの名称・素材・提供駅
- 道の駅ご当地バーガーが“安くて旨い”と言われる理由と背景
- 北関東で1日で回れるルートや時間配分のコツ
- 食材別(すだち、白なす、しいたけ、地場肉)で特徴を整理
- 価格と具材密度から見るコスパ重視派向け選び方
この導入を読んだあと、あなたは「どの駅に行くか」「どのバーガーを優先するか」「移動スケジュールはどう組むか」がすっと見えてくるはずです。
さあ、旅のプランを固めて、番組で得た情報をそのまま“現場”に持ち込みましょう。
放送回のテーマと背景 — なぜ「道の駅ご当地ハンバーガー」なのか

今回の放送テーマと概要
2025年9月30日放送の「マツコの知らない世界 ハンバーー最前線は道の駅だSP」では、「道の駅 × ご当地ハンバーガー」に焦点を当て、全国で注目を集めている“個性的な食材を使ったバーガー”を21選として紹介する構成です。
番組告知には「すだち丸ごと・トロトロ白茄子・巨大しいたけ」など、通常のハンバーガーとは異なる素材を前面に打ち出すとの記載があり、視聴者の期待を高めています。
また「1日で回れる北関東絶品ハンバーガールート」も取り上げると告知されており、単なるグルメ紹介にとどまらず、実際の巡回プランにも踏み込んでいます。
なぜ道の駅で「ご当地バーガー」が増えているのか
この流れには、以下のような背景があります。
- 流通コストの削減・地産地消強化
道の駅という地域拠点を活用し、地元農産物や特産品を直接材料として利用することで、流通経費を抑えつつ差別化できるという構造があると、番組告知で触れられています。
- 消費者の“旅グルメ化”志向の高まり
旅先で「その土地でしか食べられないものを食べたい」という欲求を満たす役割として、道の駅がローカルバーガーを売り出すケースが増えてきたと、番組紹介文中にも“ご当地名産品を使った個性爆発バーガー”と記されています。
- 素材の目新しさ・話題性
たとえば「巨大しいたけ」や「トロトロ白茄子」「すだち丸ごと」など、視覚的にも話題になる素材を使うことで、SNSで拡散されやすく、バーガー自体が“観光目玉”になりやすいのです。
番組告知でもこれらの語句が強調されています。
これらの要素が重なり、道の駅ご当地バーガーは今、急速に脚光を浴びているという構造になります。
番組で注目されている代表的な例
現時点で番組告知や関連メディアで名前が挙がっている “代表バーガー” を、信頼できる情報ソースをもとに整理します。
| バーガー名 | 道の駅/提供地 | 特徴素材・見どころ |
| おいしかバーガー | 三重県・道の駅奥伊勢おおだい | 鹿肉パティ使用、バンズに茶葉を練り込む |
| しいたけバーガー | 和歌山県・道の駅 水の郷日高川 龍游 | 肉厚しいたけを主役に据える |
| 修善寺バーガー | 静岡県・道の駅 伊豆月ヶ瀬 | 「あまカツ」など魚系やわさび系を組み合わせた種類展開 |
| 青の国バーガー | 岩手県・道の駅 青の国ふだい | 昆布メンチ+地元バンズ、限定数量 |
これらは、番組放送前に比較的確実に名前が出ている例です。
「21選」のすべてが現時点で公表されていないため、このような具体例をピックアップして、視聴者が事前に注目できるようにしておくのが有効です。
エリア別:今秋行ける“北関東ルート”と主要スポット

1日モデルコース(北関東)※番組言及ルートに沿って
番組公式ページには「1日で回れる北関東絶品ハンバーガールート」も紹介すると明記されています。
北関東とは、主に茨城・栃木・群馬とその近隣を指すルートが想定され、以下のようなモデルコースが現実的です。
- 道の駅A(例:栃木県)→ 朝出発、まずは栃木ならではの食材を使ったバーガーを狙う
- 道の駅B(例:群馬県)→ 中間地点で肉系・ボリュームバーガー
- 道の駅C(例:茨城県)→ 地元産野菜や水産系を使った変わり種バーガー
- 帰路途中/寄り道:温泉・直売所・軽食処で途中休憩しながら
たとえば、栃木で「とちおとめを使ったスイーツ系バーガー」、群馬で「上州豚バーガー」、茨城で「レンコンや地元の豚肉バーガー」など多彩な素材を挟むことで、1日で味の変化を楽しめます。
本モデルコースでは、各駅での移動距離や滞在時間を配慮し、「バーガーを食べる」「直売所をのぞく」「観光要素を入れる」の三点をバランスさせたプランが有効です。
また、売り切れや営業時間終了に備え、訪問順序に余裕を持たせつつ、始発駅と終点駅を決めてから逆ルートも想定しておくのも賢い方法です。
時間配分と混雑回避のコツ(開店/売切れ傾向)
北関東を中心とする道の駅では、ハンバーガー提供が開店直後〜昼過ぎにピークを迎える傾向が予想されます。
なぜなら、観光客や通行車両が昼食時を狙って流入する時間帯だからです。
番組告知には「具材が旨い&安いで本格化」「売切れ」への言及も含まれており、売り切れリスクが一定程度高いことを示唆しています。
具体的には、
- 開店後すぐ(10:00〜11:00頃)に最初の道の駅を訪れてバーガーを確保
- 次の道の駅では、到着時間を昼どきより少し前後にずらす
- 端午〜午後遅め(14:00〜15:00以降)は売切れの可能性が高くなるため、後半の駅では在庫確認をしながら向かう
- 各駅間の移動時間には余裕をもたせる(特に山間部や交通渋滞が見込まれる区間を避ける)
また、混雑傾向を避けるためには「最初のバーガー駅に早めに到着」「主要駅をピーク時間帯の通過駅にしない」「予備の駅をルートに組み入れる」といった工夫が有効です。
近接スポット・温浴&直売所の寄り道プラン
バーガー巡りを単なる“食べ歩き”で終わらせないために、近隣の観光スポットや温浴施設、直売所を組み込むのがポイントです。
道の駅には往々にして地元野菜の直売所や果樹園、足湯などが併設されており、訪問者を飽きさせません。
たとえば、
- 直売所併設型道の駅:バーガーを食べた後、地元採れたて野菜や果物を購入
- 温浴施設・日帰り温泉:移動の疲れを癒しつつ次の目的地へ向かう
- 観光名所:近隣に名城、滝、展望所などがあれば散策をはさむ
こうした寄り道を織り交ぜることで、旅自体にゆとりと楽しみを持たせられます。
特に午後の時間帯に「温泉 or 景色スポット → 次の道の駅」への流れを意識すると、時間的にも空間的にもメリハリが生まれます。
なお、番組告知では「この秋行ける北関東ルート」として「道の駅バーガー巡り+周辺拠点利用」を紹介すると明言されています。
食材別:その土地でしか味わえない名産バーガー

すだち・白なす・巨大しいたけ系(野菜主役)
番組告知には、「すだち丸ごと」「トロトロ白茄子」「巨大しいたけ」といった、視覚的・味覚的なインパクトを持つ食材がキーワードとして挙げられています。
- すだち丸ごとバーガー
- 徳島県・道の駅くるくるなるとの「すだちと阿波どりのフライドチキンバーガー」では、すだちをスライスではなく「丸ごと1粒」の形で使うという特徴が報じられています。
- この使い方により、爽やかな酸味と香気が口の中で一気に広がり、脂っぽさを抑えながらも余韻を残す構成が可能になります。
すだちを主張するバーガーの存在は、東京や都市部ではなかなか出会えない個性です。
- 白なすバーガー
- 千葉県・道の駅しょうなんでは、「白なす(通常の茄子と異なる白い皮とやわらかな果肉)」を使ったバーガーが紹介されています。
- 白なすは果肉がやわらかく、加熱するとトロリとした食感になるため、噛んだ瞬間とろけるような口当たりを狙える素材です。
ナス本来の甘みや水分感を活かしつつ、肉パティやソースと合わせることで“野菜だけど主役になるバーガー”という印象を形にできます。
- 巨大しいたけバーガー
- 和歌山県の「道の駅 水の郷日高川 龍游(りゅうゆう)」で提供されている「龍神しいたけバーガー」は、肉パティではなく厚切りしいたけをメインに据える構成で注目されています。
- 特徴として、しいたけそのものの食感や旨味を活かすため、あえて火を通しすぎずジューシー感を残した調理法が選ばれているようです。
ソースや添え物の野菜で味の立体感を補佐し、きのこ好きやベジタリアン層にも訴求できる設計になっています。
これらの“野菜・果実系素材”バーガーは、肉中心スタイルとは異なる味のアプローチを提示しつつ、「その土地でしか出せない」唯一無二の存在感を放つ戦略的な一品たちです。
地場肉・魚介・果実ソース系(ジューシー&個性)
野菜素材に加え、多くのご当地バーガーは地域の肉・魚介、或いは果実を活かしたソースを組み合わせた構成で“ジューシーさ+地域性”を打ち出しています。
- 阿波どり × すだちバーガー
- 先述の「すだち×阿波どりフライドチキンバーガー」では、徳島名産の地鶏「阿波どり」を使ったフライドチキンを主軸に据え、そこにすだちの酸味を重ねる構成になっています。
- この肉×果実のハイブリッド構成により、鶏の旨味と脂をすだちの風味で切り返すコントラストが生まれ、後味が重くなりすぎない点が工夫です。
- 鹿肉 × 茶バンズバーガー
- 三重県・道の駅奥伊勢おおだいの「おいしかバーガー」では、鹿肉を使ったパティが使われています。
- さらに、バンズに地元のお茶(大台茶など)を練り込む仕様が取り入れられており、地域の産物を重層的に使う設計になっています。
肉質のしっかりした鹿肉と、茶の香りが融合することで、通常の牛・豚パティにはない体験を創出しています。
- 魚介 × ソース系融合バーガー
- 静岡・伊豆月ヶ瀬の「修善寺バーガー」シリーズには、川魚「あまご(あまご茶屋キッチンカー)」を使ったあまごカツが採用されている構成が紹介されています。
- この魚系バーガーでは、淡白な魚のうまみを損なわないように、わさびやピクルス、柑橘ソースなどのアクセントを加える工夫が見られます。
- 魚肉の風味を活かしつつ地域性を打ち出す典型例です。
これらの構成は、「単なるバーガーではなく、その地域らしさを肉・魚・果実で表現する料理」として成立する戦略性をもった設計です。
“農家野菜バーガー”の取り組み(8000個超ヒット事例など)
番組告知には、「8000個以上ヒットした農家野菜バーガー」の文言も含まれており、単発の目玉商品ではなく、定番メニューとして支持される構造を持つバーガーがすでに存在していることが示唆されています。
この背景には、生産者直結型販売と季節野菜の余剰活用という戦略が見え隠れします。
過剰に収穫された野菜を“バーガー素材”に転用したり、地元農家が原料を供給しやすい流通ルートを確保したりすることで、コストを抑えつつ独自性と利益性を両立する設計が可能になります。
実際、地元野菜を主役に据えたバーガーの成功例として、多めに仕入れた旬の野菜を一品バーガーにまとめて“目玉商品”化し、話題性を高める事例も報じられています。
こうした取り組みが、「道の駅ハンバーガー」を単なる“立ち寄りグルメ”から“看板商品化”へと引き上げつつある流れのひとつです。
この方向性は、今後新規参入する道の駅にも応用可能なモデルであり、番組でこの裏側が語られる可能性も高いと見られます。
価格と満足度:道の駅バーガーはなぜ“安くて旨い”のか

流通短縮と地産地消の強み
道の駅のご当地バーガーが“価格の割に満足度が高い”と言われる最大の理由は、中間流通を短縮し、地域の生産者と直結した供給設計にあります。
今回の番組告知でも「具材が旨い&安いで本格化…流通と地産地消アイデア」と明示され、地域の食材を近距離で調達することで新鮮さとコストの両立を図っていることが示されています。
学術的な整理でも、道の駅レストランは“地産地消メニュー”で地域の食の魅力を提供し、差別化と集客性を高める取り組みが進んでいると報告されています。
言い換えると、産地に近い=鮮度が高い=味で勝負できるため、輸送や廃棄のリスクが小さく、結果として価格に還元しやすい構造です。
実例として、三重県「道の駅 奥伊勢おおだい」では、大台茶を練り込んだ自家製バンズ×鹿肉パティという“地域×地域”の組み合わせで「おいしかばーがー」を提供。
売りのポイントをバンズ・パティ・野菜まで地元で固めることで個性とコスト最適化を両立しています。
一方、徳島「道の駅くるくる なると」では、阿波どり×すだちといった特産の掛け合わせに加え、すだち唐辛子/すだち七味など地元加工品まで使う“地産の連鎖”で価値を底上げ。
原価は上がっても供給距離が短く在庫回転が効くため、“高付加価値を納得価格で”という設計が成立します。
総じて、近接調達(短サプライチェーン)×地場加工の組み合わせが、「旨いのに手が届く」価格を支えています。
ボリューム比較(単価・具材密度の見方)
“コスパ”を見極めるには、単に値段だけでなく具材の密度や構成を見るのが有効です。
たとえば三重「おいしかばーがー」は600円(税込)で、鹿肉パティに加え、大台茶入りバンズ+地元レタス/トマト+わさび茎の醤油漬け入りマヨという多層構成。
価格帯は控えめでも、地元食材が重ねて入る=味の情報量が多い点が満足度を底上げします。
対して徳島「阿波チキ辛バーガー」は1,650円(税込)とプレミアム帯ですが、阿波どりフライドチキンに“すだち唐辛子”ソース+上から“すだち七味”まで重ねる仕様で、大ぶりなメイン具材×複数の地元調味により“旅行グルメ”としての充足感を設計。
価格あたりの満腹感だけではなく、地域体験価値(希少性・話題性)を含めて評価すべきタイプです。
さらに“肉以外が主役”のケース。
和歌山「道の駅 水の郷日高川 龍游」では、肉厚しいたけをメインに据えるバーガーが名物。
訪問記録でも昼過ぎには残り少ないといった“売れ筋”の様子が記されています。
大径しいたけ=見た目の満足感と噛み応えが強く、肉に頼らずとも満足度が高い“密度の作り方”の好例です。
価格は施設により変動しますが、主役具材の大きさ・厚み・調理工程を観察することで、値段の裏にある手間と質が読み解けます。
コスパ重視派の選び方チェックリスト
- “地元×地元”の掛け合わせを探す
- バンズ(粉・茶)/パティ(鹿・鶏・魚)/野菜・果実(すだち等)まで同一地域内で完結している構成は、味の一体感と鮮度が出やすく、結果的にコスパが高くなりがち。
番組告知のキーワード「地産地消」「安い&旨い」にも合致します。
- バンズ(粉・茶)/パティ(鹿・鶏・魚)/野菜・果実(すだち等)まで同一地域内で完結している構成は、味の一体感と鮮度が出やすく、結果的にコスパが高くなりがち。
- “限定・季節”の但し書きを読む
- 夏限定の徳島「阿波チキ辛バーガー」のように、季節素材や限定スパイスを使う商品は、価格が高めでも体験価値が上乗せされます。
“限定=高い”で切らず、具材の希少性と作り込みをチェック。
- 夏限定の徳島「阿波チキ辛バーガー」のように、季節素材や限定スパイスを使う商品は、価格が高めでも体験価値が上乗せされます。
- 価格だけでなく“具材密度”を見る
- 三重「おいしかばーがー」のように600円で多層構成の例がある一方、プレミアム帯はボリューム+調味の多段設計で満足度を設計しているケースが多い。
写真や店頭POPで厚み・主役具材のサイズ・ソースの段数を確認すると“値段の理由”が見えます。
- 三重「おいしかばーがー」のように600円で多層構成の例がある一方、プレミアム帯はボリューム+調味の多段設計で満足度を設計しているケースが多い。
- “売切れ時間”の傾向を意識する
- 名物バーガーは昼過ぎに残数が減るケースが散見されます。
満足度=買えたかどうかでも左右されるため、午前〜昼前行動が基本。
- 名物バーガーは昼過ぎに残数が減るケースが散見されます。
- 番組キーワードをヒントにSNS/公式を照合
- 「すだち丸ごと」「白なす」「巨大しいたけ」など番組告知のワードを手掛かりに、道の駅の公式・観光協会ページでメニューと価格を確認。
“地元の連鎖”が見える商品ほど、食後の満足度がブレにくいです。
まとめ:放送で“行き先と注文内容”を一気に決めよう

今回の「マツコの知らない世界」は、道の駅のご当地ハンバーガーが“安くて旨い”理由を、流通短縮と地産地消の工夫、そして“北関東を1日で回れる実用ルート”まで含めて見せてくれる回です。
放送日時は2025年9月30日(火)20:55〜。
放送直後は各道の駅の在庫や混雑が普段以上に動く可能性が高いので、午前中の訪問・在庫確認・代替候補の用意を前提に旅程を組むのが得策です。
番組が示すキーワード――「すだち丸ごと」「トロトロ白なす」「巨大しいたけ」「8000個超ヒットの農家野菜バーガー」「この秋行ける北関東ルート」――はいずれも“現地でしか出せない味の理由”を端的に表しています。
視聴後にそのまま計画へ落とし込むなら、素材ワード×地名でSNSや公式を照合し、営業時間・価格・限定有無を必ず確認しましょう。
具体例として、徳島「道の駅くるくる なると」の「阿波チキ辛バーガー」(夏限定・税込1,650円)は、阿波どり×すだち唐辛子×すだち七味という“地元の連鎖”が価値の核。
「旅の体験価値」重視派に刺さるプレミアム帯の設計です。
一方、栃木「道の駅しもつけ」には税込400円で満腹感を得られる“しもつけまんぞくバーガー”のような“価格インパクト型”もあり、コスパ重視派の受け皿も太いのが道の駅バーガーの面白さ。
行き先の優先度は
①地域らしさ(素材の独自性)
②提供時間帯(売切れリスク)
③価格帯(体験価値とのバランス)
の順で決めると迷いません。
和歌山「水の郷 日高川 龍游」のしいたけバーガーのように“肉以外が主役”の成功例は、見た目の満足感+厚みのある食感で“価格≠満足度”を体感できる好例。
写真で“主役具材のサイズ感”をチェックしてから現地へ向かうと、後悔が少なくなります。
筆者の所感としては、道の駅バーガーは「その土地の台所」を丸ごと挟み込むメディアになってきた、という点に尽きます。
鹿肉×茶バンズ(奥伊勢おおだい「おいしかバーガー」)のような“地域×地域の多層設計”は、輸送を短く・鮮度を高く・個性を強くという三拍子を、手の届く価格からプレミアムまで階段状に並べてくれる。
放送で刺さったキーワードを手がかりに、まずは1件、午前中に確保。
売り切れに備えて第2・第3候補を“同ワード系の近隣駅”で用意――この動線が最短距離で幸福度を上げると考えます。
最後に、放送後の動きが早いのもこのテーマの特性。
番組ページ(TBS/MBS)→各道の駅公式・観光協会→直近の告知(リリースやX投稿)の順で当日の提供・価格・限定を再確認してから出発しましょう。
これで「どこで、何を、いつ食べるか」が、ブレずに決まります。
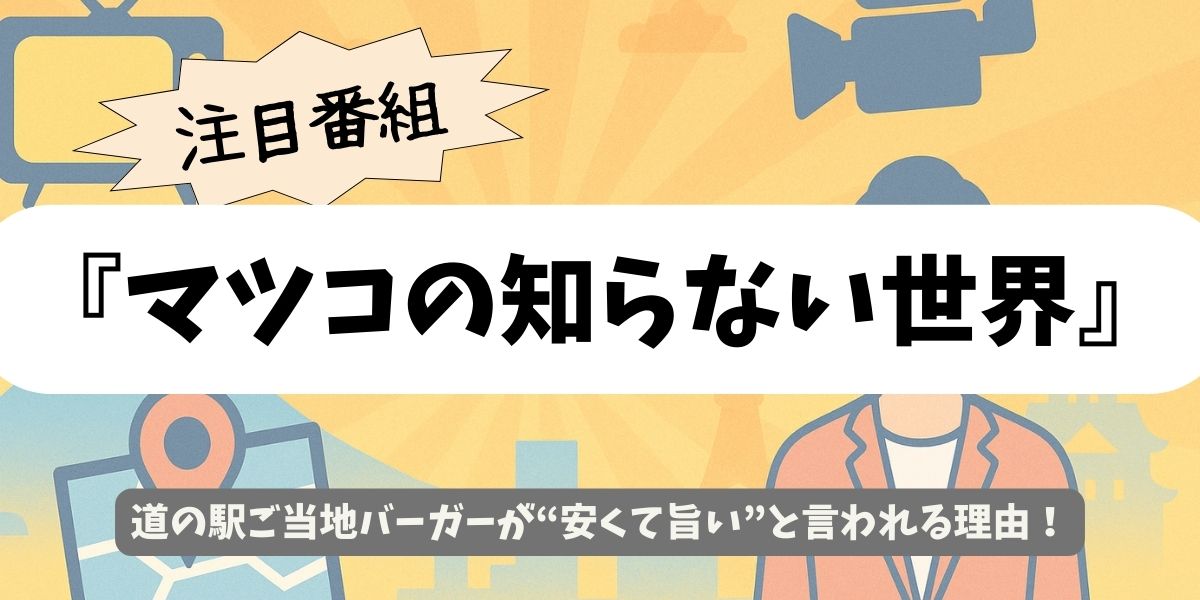
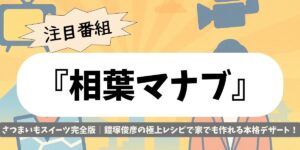
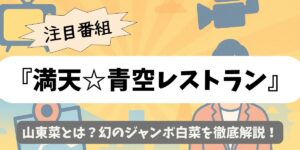
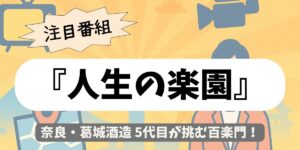
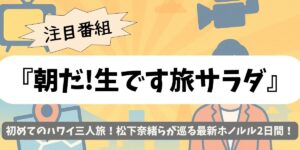
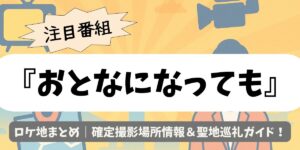
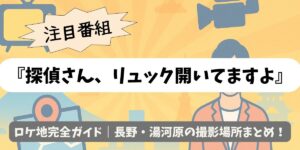

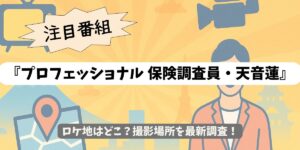
コメント