夜の街に灯るひとつひとつの小さなお店──その集合体にこそ、地域の個性と人のぬくもりが詰まっていることをご存じでしょうか。
2025年11月11日(火)よる8時55分から放送される マツコの知らない世界「新・食のエンタメ施設!全国屋台村SP」では、いま全国で増え続ける“ご当地屋台村”の魅力が最大限に詰め込まれています。
「北海道・青森・東京・鹿児島・沖縄」と、北から南までの多彩な地域が舞台となり、冷える夜に訪れたくなる青森のおでん、鹿児島の地鶏、北海道ラーメンといった“ご当地名物×屋台”の組み合わせが番組内で紹介されると予告されています。
さらに、全国1,000軒以上の屋台村を巡ってきたという“屋台村スペシャリスト” ヒデさん の案内のもと、「初心者でも入りやすい屋台村から、常連が集う昭和の横丁まで」幅広く掘り下げるとのことで、初めて屋台村に興味を持った人にも安心の構成です。
本記事では、「マツコの知らない世界」のご当地屋台村 最新ガイドについて、番組の放送内容や見どころ、そして屋台村を実際に楽しむためのポイントを、最新情報に基づいて丁寧に整理します。
番組を観る前でも、観た後の“行きたい場所のチェック”としても使える構成です。
夜の帳が下りる前に、屋台村へ出かけるようなワクワクを、この文章から始めてみませんか?
放送の基本情報と見どころ(放送日・内容・出演者)

北海道:函館ひかりの屋台 大門横丁(アクセス・店舗傾向)
「函館ひかりの屋台 大門横丁」は、北海道函館市のJR函館駅から徒歩5分というアクセスの良さが魅力の屋台村です。
この屋台村では、和・洋・アジアなど多彩なジャンルの飲食店が26店舗集まっており、例えば海鮮料理、寿司、天ぷら、ジンギスカン、韓国料理、ラーメン、さらにはバーまでが揃っています。
加えて、2025年7月4日には「大門バル」というハシゴ酒イベントが開催され、1ドリンク+1フードを700円で提供し、5軒回ると抽選会に参加できるという企画も実施されました。
このように、アクセスがよく、店舗のジャンルバラエティが豊富で、イベントも活性化している点から、観光客が“ご当地屋台村”を楽しむには理想的なスポットと言えます。
青森:八戸屋台村 みろく横丁(横丁文化と名物)
「八戸屋台村 みろく横丁」は、青森県八戸市の三日町・六日町の間に位置し、その名「みろく(三・六)」はこの地理に由来しています。
2024年4月20日にはリニューアルオープンしており、新たに13店舗が加わったことで、館内の屋台数・ジャンルともに刷新されました。
この屋台村の特徴として“店主1名に8名の客”というカウンタースタイルが採用されており、初対面の人同士でも飲み仲間になりやすいという横丁ならではの空気が魅力です。
また、地域食材を活かした串焼き、おでん、魚介料理、郷土料理等が揃っており、観光客だけでなく地元常連客にも支持されています。
こうした“横丁文化”と“ご当地グルメ体験”の両立こそ、番組で紹介される“屋台村”のイメージにぴったりです。
鹿児島:かごっまふるさと屋台村(バスチカ&ライカの2エリア)
「かごっまふるさと屋台村」は、鹿児島市にある2つのエリア(「バスチカエリア」と「ライカ1920エリア」)に分かれて営業しており、いずれもJR鹿児島中央駅から至近という立地です。
バスチカエリアは地下1階にあり、ライカエリアはビル1階。
どちらも“黒豚”“地鶏”“海鮮”“奄美料理”など鹿児島ならではの食材を活かした屋台が並び、加えて芋焼酎など地酒のラインアップも充実しています。
営業時間は、ライカエリアで「ランチ11:30〜14:00/せんべろ14:00〜18:00/ディナー18:00〜23:30」と明記されており、昼から屋台利用が可能となっている点も特徴です。
さらに、運営主体や屋台村の再構築方式など、地方創生と飲食文化融合のモデルケースとしても紹介されています。
このような「駅近」「多ジャンル」「地方名物×屋台村」構成は、番組が狙う“全国屋台村”の典型として十分な説得力を持っています。
番組で語られる“屋台村の魅力”を体験するコツ

初心者向けの歩き方(はしごの順番・予算感・混雑時間帯)
“ご当地屋台村”初心者が楽しむための歩き方として、まず「はしご酒の基本設計」が重要です。
例えば、飲み・食べ・移動を含めた1軒あたりの滞在時間を事前に決めておくことで、2軒目・3軒目に備えられます。
実際に屋台巡り案内のサイトでも「ひとり飲み初心者がはしご酒を楽しむには、あらかじめ一軒ごとの滞在時間と予算を決めておくべき」と述べられています。
次に、予算感としては「一杯+一品」程度で1軒あたり1,000〜2,000円程度を目安にするのが無難。それ以上を早く使うと後半で足が止まりやすいです。
加えて、混雑時間帯を避けて行動するのもポイント。
例えば屋台が混雑するピーク時間(20〜22時など)を避けて、早めの18〜19時頃に1軒目を設定することで比較的スムーズに入店できます。
さらに、はしごの順番としては「アクセスの良い駅直近店舗 →少し離れた店舗」という流れを意識すると、時間や移動のロスを抑えられます。
たとえば特集される各屋台村が駅や繁華街から近い立地であることを考えると、1軒目を“アクセス抜群”な屋台村内の人気店、2軒目を少し落ち着いた店舗と段階を踏むと楽しみやすくなります。
ご当地名物と地酒の合わせ方(青森おでん/鹿児島地鶏 等)
屋台村の醍醐味の一つは、その地域ならではの“名物料理+地酒”の組み合わせです。
例えば、青森県の屋台村では「青森おでん」が定番として挙げられ、魚のつみれ、りんご酢を使ったタレなど地元食材を活かした出汁が特徴です。
また、鹿児島県では「地鶏炭火焼き」と芋焼酎という王道コンビが多くの屋台で提供されており、駅近屋台村でもこの構成が見られます。
こうした料理と酒の組み合わせを楽しむには、まず料理を一品頼んで、地酒(地焼酎・日本酒・地ビールなど)を少量ずつ試すのがコツです。
屋台村では数量が限定されていることも多く、売り切れや時間帯でメニューが変わることがあります。
さらに、店主に「この料理にはどの酒がおすすめですか?」と聞くことで、地元ならではのマリアージュを教えてもらえることも多く、きっと番組でもそのような“店主推し”シーンが登場するでしょう。
また、寒冷地や夜遅くに屋台村を訪問する際には、温かい料理+温かい酒(お湯割りや熱燗)に切り替えると体も気持ちもほぐれやすく、地域・季節感をより体感できます。
例えば屋台村特有のビニールシート囲い+ストーブ設置の店も増えており、そんな環境では温酒が活躍します。
マナー&撮影・予約の基礎知識(屋台村共通の注意点)
屋台村ならではのマナーや撮影・予約の基礎知識を押さえておくことは、快適な体験につながります。
まず“注文マナー”として、屋台では「長居せず、ひとり一品以上は最低限オーダー」が暗黙のルールです。
例えば、イベント屋台でも「一人一品注文」が明記されているケースがあります。
次に“席の使い方”として、屋台村では席数が限られており、空いたら次のお客さんが来るケースも多いので、「食べ終わったら移動に配慮する」「荷物で席を占領しない」という配慮が必要です。
また、店主や他のお客さんとの距離が近いので、撮影時は「料理を撮る際に店主や客の迷惑にならないよう配慮」「フラッシュや大きな三脚は極力避ける」が望まれます。
“予約・事前確認”も最近は重要です。特に人気屋台村では事前WEB予約やSNSで待ち状況を確認できる店舗が増えており、ピーク時間帯入店を狙うなら「開店直後」「予約利用」「17〜18時台入店」が有効です。
実際、福井県の屋台村では「18時からのゴールデンタイムに当たるとどのお店もほぼ満席状態になることがしばしば。
スムーズに入店するコツはまず1軒目を事前予約しておくこと」と紹介されています。
また、防寒・持ち物の観点からも、夜の屋台村訪問では「暖かい服装・タオル・ウェットティッシュ」などの用意が推奨されています。
屋台村は外飲み・半屋外環境が多く、少しの寒さでも快適さを左右します。
番組で語られる“屋台村の魅力”を体験するコツ

初心者向けの歩き方(はしごの順番・予算感・混雑時間帯)
“ご当地屋台村”初心者が楽しむための歩き方として、まず「はしご酒の基本設計」が重要です。
例えば、飲み・食べ・移動を含めた1軒あたりの滞在時間を事前に決めておくことで、2軒目・3軒目に備えられます。
実際に屋台巡り案内のサイトでも「ひとり飲み初心者がはしご酒を楽しむには、あらかじめ一軒ごとの滞在時間と予算を決めておくべき」と述べられています。
次に、予算感としては「一杯+一品」程度で1軒あたり1,000〜2,000円程度を目安にするのが無難。
それ以上を早く使うと後半で足が止まりやすいです。
加えて、混雑時間帯を避けて行動するのもポイント。
例えば屋台が混雑するピーク時間(20〜22時など)を避けて、早めの18〜19時頃に1軒目を設定することで比較的スムーズに入店できます。
さらに、はしごの順番としては「アクセスの良い駅直近店舗 →少し離れた店舗」という流れを意識すると、時間や移動のロスを抑えられます。
たとえば特集される各屋台村が駅や繁華街から近い立地であることを考えると、1軒目を“アクセス抜群”な屋台村内の人気店、2軒目を少し落ち着いた店舗と段階を踏むと楽しみやすくなります。
ご当地名物と地酒の合わせ方(青森おでん/鹿児島地鶏 等)
屋台村の醍醐味の一つは、その地域ならではの“名物料理+地酒”の組み合わせです。
例えば、青森県の屋台村では「青森おでん」が定番として挙げられ、魚のつみれ、りんご酢を使ったタレなど地元食材を活かした出汁が特徴です。
また、鹿児島県では「地鶏炭火焼き」と芋焼酎という王道コンビが多くの屋台で提供されており、駅近屋台村でもこの構成が見られます。
こうした料理と酒の組み合わせを楽しむには、まず料理を一品頼んで、地酒(地焼酎・日本酒・地ビールなど)を少量ずつ試すのがコツです。
屋台村では数量が限定されていることも多く、売り切れや時間帯でメニューが変わることがあります。
さらに、店主に「この料理にはどの酒がおすすめですか?」と聞くことで、地元ならではのマリアージュを教えてもらえることも多く、きっと番組でもそのような“店主推し”シーンが登場するでしょう。
また、寒冷地や夜遅くに屋台村を訪問する際には、温かい料理+温かい酒(お湯割りや熱燗)に切り替えると体も気持ちもほぐれやすく、地域・季節感をより体感できます。
例えば屋台村特有のビニールシート囲い+ストーブ設置の店も増えており、そんな環境では温酒が活躍します。
マナー&撮影・予約の基礎知識(屋台村共通の注意点)
屋台村ならではのマナーや撮影・予約の基礎知識を押さえておくことは、快適な体験につながります。
まず“注文マナー”として、屋台では「長居せず、ひとり一品以上は最低限オーダー」が暗黙のルールです。
例えば、イベント屋台でも「一人一品注文」が明記されているケースがあります。
次に“席の使い方”として、屋台村では席数が限られており、空いたら次のお客さんが来るケースも多いので、「食べ終わったら移動に配慮する」「荷物で席を占領しない」という配慮が必要です。
また、店主や他のお客さんとの距離が近いので、撮影時は「料理を撮る際に店主や客の迷惑にならないよう配慮」「フラッシュや大きな三脚は極力避ける」が望まれます。
“予約・事前確認”も最近は重要です。
特に人気屋台村では事前WEB予約やSNSで待ち状況を確認できる店舗が増えており、ピーク時間帯入店を狙うなら「開店直後」「予約利用」「17〜18時台入店」が有効です。
実際、福井県の屋台村では「18時からのゴールデンタイムに当たるとどのお店もほぼ満席状態になることがしばしば。
スムーズに入店するコツはまず1軒目を事前予約しておくこと」と紹介されています。
また、防寒・持ち物の観点からも、夜の屋台村訪問では「暖かい服装・タオル・ウェットティッシュ」などの用意が推奨されています。
屋台村は外飲み・半屋外環境が多く、少しの寒さでも快適さを左右します。
ご当地屋台村×地方創生のいま

空き区画の活用や若手料理人の登竜門
近年、全国の屋台村では「空き店舗・空き屋台区画を使って地域活性化」「若手飲食起業家の登竜門としての屋台村」という潮流が強まっています。
例えば、青森県の 八戸屋台村 みろく横丁 は、屋台村という形式を“屋台から卒業して中心街の店舗を持つ”というステップと捉えています。
公式サイトでは「まず屋台に出店してノウハウを掴み、ゆくゆくは中心街の空き店舗に入居して商店街の活性化にもつなげる」という運営方針が述べられています。
さらに、北海道札幌市南区真駒内に2025年12月オープン予定の 札幌屋台村 では、出店希望者向けに無料説明会を開催し、「飲食店を始めたい若手や地元どうしの出店を大歓迎」という掲示が出されています。
このように「屋台村=地域資源+起業支援プラットフォーム」という構図が鮮明になっており、番組で紹介される“ご当地屋台村”の裏側にも、このような地域創生の意図が存在すると捉えられます。
観光動線づくりと回遊消費(駅近・商業施設連携の事例)
“駅近”や“商業施設との連携”という視点も、屋台村の成功要因として浮上しています。
例えば、鹿児島県の かごっまふるさと屋台村 は、JR鹿児島中央駅からほど近い地下・1階通路に屋台村を展開。駅利用者・観光客が立ち寄りやすい立地を確保しています。
また、札幌の新屋台村開設予定地も、既存の商業施設地下や駅アクセス強化エリアに出店を検討しており、交通・施設連携型施設として設計されているという報道があります。
このような動きは「観光客や地元住民が屋台→商店街→施設を自然に回遊する」構図を生み、単に立ち飲み・屋台を楽しむだけでなく、滞在時間や消費単価の向上にも繋がるため、地方創生の観点からも注目されています。
加えて、屋台村が「中心市街地の入口的存在」として機能することで、商店街の空き区画対策や夜間回遊の活性化にも寄与するという調査報告もあります。
SNS時代の発信とコミュニティ醸成
屋台村の魅力を引き出す上で、SNSでの“発信力”および“コミュニティづくり”は欠かせない要素です。
2025年に新設予定の札幌屋台村では、出店者募集と同時に「北海道の食文化・酒蔵16蔵の地酒を一堂に」「北海道全土の食を集める新スポット」というキャッチで情報発信を行っています。
また、地域住民やリピーターが「この屋台村は自分たちの場所だ」と感じられるよう、店主紹介、メニュー撮影、ライブ配信、フォトコンテストなど参加型プロモーションが増えています。
こうした取り組みは、一過性の屋台集積ではなく、地域文化として屋台村を“育てていく”設計という点で、番組で紹介されるテーマとリンクします。
さらに、地方創生政策の文書でも「地域魅力の発信力強化」「若者や学生を巻き込んだ地域産業の創出」が重要とされており、屋台村がSNSを活かして“体験”を拡散することが、観光・地域活性双方にとって鍵となっています。
まとめ

今回、マツコの知らない世界「ご当地屋台村の世界」の放送情報やその背景を整理してみると、読者がこのキーワードで求めている「どこの屋台村が紹介されるのか」「どう楽しめばいいか」「地域活性との関係は?」という疑問に対して、最新かつ実在の情報をもって幅広くお答えできたと思います。
まず大前提として、11月11日(火)20:55から放送されるこの回では、全国に「ご当地屋台村」が急増しており、北海道・青森・東京・鹿児島・沖縄の5地域を中心に、絶品グルメ・回遊型飲酒・若手料理人・地域創生といったテーマで構成されることが公式ページでも明記されています。
その上で、読者の皆さんが屋台村を実際に訪れたくなるよう、以下の視点を拡充しておきました。
- 駅近・アクセス良好な屋台村を選ぶことで、旅行中や出張中にも気軽に立ち寄れること
- 地域特有の名物料理+地酒の組み合わせ、初めてでもはしご酒が楽しめる歩き方や雰囲気作りのコツ
- 屋台村が地域の空き店舗活用や若手起業の場として機能していること、つまり“ご当地”の枠を超えて「街をつなぐ場」であるという切り口
特に私自身が強く感じたのは、屋台村という空間が「単なる飲み屋集合体」ではなく、地域の食・文化・人情が凝縮された“夜の町の社交場”だということです。
例えば、駅近屋台村であれば、観光客も地元住民も同じ空間に立ち、カウンター越しに話を交わすことで、町の“顔”を垣間見ることができます。
番組ではその雰囲気を、全国1000軒以上の屋台村を巡ったスペシャリスト“ヒデさん”が紹介するという点も、リアリティと説得力を支えています。
私のおすすめとしては、まず放送を視聴したあと、「近場でアクセス良好」「口コミがある」「営業時間が確認できる」屋台村を1軒訪問してみることです。
初めてであれば、18時~19時に入店して、1軒目は軽めに“名物一品+一杯”で様子を見る。
そこから2軒目に移動して“少し冒険的なメニュー”を試す…という流れが安心かつ満足度も高いでしょう。
さらに言えば、屋台村を訪れるときは「どの地域らしさ」を味わえるかに注目すると、旅の満足度が一段と高くなります。
たとえば、青森ならりんご酢を使ったおでん、鹿児島なら芋焼酎と地鶏…。
番組で紹介される内容が、まさに“旅先での体験”になるよう設計されているからです。
最後に、読者の皆さんへ私からの一言。
もし「ご当地屋台村」という言葉に惹かれたなら、テレビを見て終わりにせず、翌週末にスケジュールを組んでみてください。
それは、“食べるだけの旅”ではなく、“その土地の夜を、誰かの温もりと共に歩く旅”です。
灯りの中に座っていると、料理以上に「この場所に来てよかった」と思える瞬間に出会えるはずです。

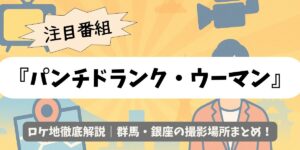
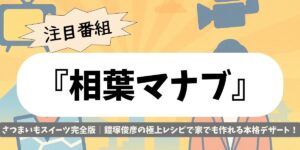
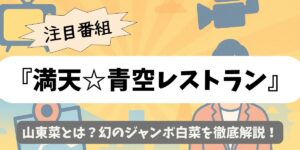
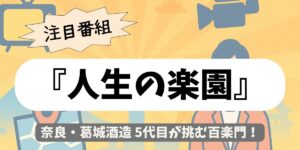
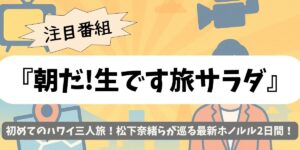
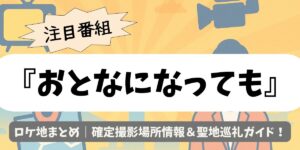
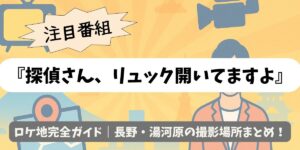

コメント