こんにちは。2025年9月6日放送の『満天☆青空レストラン』で紹介された食材が、長野県・原村の“朝採れセルリー(セロリ)”でした。
「セロリってちょっと苦手…」という方も、「信州の高原野菜って本当に美味しそう!」と思われた方も、この記事にはぜひ目を通してほしいと思います。
『満天☆青空レストラン』で取り上げられた原村のセルリーは、「高原 × 朝採り × 職人技」の三拍子そろったセルリーで、その香り・シャキシャキ感・甘みは想像以上。
美味しい理由を知りたかったり、実際に味わってみたい方にとって、知っておくべき情報が満載です。
原村の標高は900〜1,300m。八ヶ岳山麓の寒暖差のある土地で、深夜〜早朝に収穫された「朝採れセルリー」は、水分が失われにくく、香り豊かで甘みも際立ちます。
しかもJA信州諏訪の通販では “原村産 朝採れセルリー” として、収穫当日に発送される新鮮さが保証されます。
これらの条件が揃って、セルリー本来の良さが最大限引き出されます。
テレビでは宮川大輔さんと藤森慎吾さんが、“星空の下での収穫体験” や “採れたてセルリーの絶品メニュー(マヨ味噌まるかじり、タコ芋炒め、和風ハンバーグ、セルリー味噌、ミネストローネなど)” を楽しむ様子が紹介されました。
まるで野菜の新しい一面を見たような感動が視聴者にも伝わったことでしょう。
この記事では、なぜ原村のセルリーが特別なのか、どこで手に入るのか、どう調理すれば美味しく楽しめるのか──といった情報を網羅的に、かつ最新のデータをベースにご紹介します。
産直や通販の現状、地元直売所の最新営業情報、番組で披露されたレシピ、さらには保存方法や選び方のコツまで、すべてをひとつの記事でわかるように構成しています。
放送回の基本情報と見どころ

ロケ地・食材の概要(長野県原村の“セルリー”)
2025年9月6日放送の『満天☆青空レストラン』では、舞台は長野県・諏訪郡原村で、“セルリー”と呼ばれるセロリが取り上げられました。
原村は標高およそ900〜1,100mの高原地帯で、昼夜の気温差が大きく、冷涼な気候と清らかな水源に恵まれており、温度にもデリケートなセロリの栽培に最適な場所です。
この地域で育つセルリーは、JA信州諏訪地域におけるセロリ生産全体の多くを占めており、特に夏には全国シェアの約90%に達します。
収穫は深夜~未明(だいたい深夜1時ころから)に行われ、気温が低い時間帯に摘み取ることで、鮮度、シャキシャキ感、甘みを最大限に保つ工夫がなされています。
この“朝採れ”状態こそが、番組でも強調されたセルリーの魅力の柱です。
ゲスト・収穫シーンの注目ポイント(夜間〜明け方収穫)
番組では、MC・宮川大輔さんとゲスト・藤森慎吾さんが、星空の下、深夜から収穫作業に参加するシーンが放送されました。
特に注目すべきは、「夜間の涼しい空気の中で収穫することで、セロリに余分な水分の蒸散を防ぎ、みずみずしさと香りを強く保っている」という、産地ならではのこだわり。
藤森さんは「地元・長野にこんな美味しいセルリーがあったとは」と感動の声を上げ、収穫の価値を体感していました。
番組内メニュー・連動お取り寄せの有無
番組では「香る!セルリーのフルコース」として、セルリーを生かした複数の料理が紹介されました。内容は以下の通りです。
- セロリまるかじり(マヨ味噌添え):そのまま“まるかじり”で香りと甘さをダイレクトに楽しむスタイル。
- セルリーとタコ・芋の中華炒め:オイスターソースなどを使った風味豊かな一品。
- セルリー入り和風ハンバーグ:細かく刻んでタネに混ぜ、ふんわり&爽やかさをプラス。
- セルリー味噌:みじん切りのセルリーを信州味噌と混ぜた、ご飯のおともにぴったりの調味料。
- セルリーミネストローネ:ミネストローネの旨みを深める野菜スープ。
加えて、諏訪のところてんも登場し、地元色のあるフルコースになっていました 。
お取り寄せに関しては、現時点で「原村朝採れセルリー」としての通販商品は見当たりませんが、一般的な長野県産セロリは楽天などで取り扱いがあります。
また、朝市や直売所での販売が主体である点も強調されていました。
長野県セルリーとは(特徴・旬・選び方)

「セルリー」という呼称とJA信州諏訪の産地性
長野県では一般的な「セロリ」という呼び名よりも、ひらがなに近い「セルリー」という発音が根付いています。
これは「celery」のフランス読みの影響ともされ、明治時代に松本市周辺で商業栽培が始まった当初から定着した言い回しです。
中でもJA信州諏訪(原村・茅野市・諏訪地域)は全国でも指折りの「セルリー」産地。特に夏季は国内の生産シェアが90%に達する圧倒的な存在感を誇り、「日本一」の地位を揺るぎないものにしています。
諏訪地域から湧き出る清らかな水、そして八ヶ岳を背にした高原の冷涼な環境が、セルリーの栽培に理想的な舞台を提供していると言えるでしょう。
生産量日本一の背景(冷涼な高原気候・歴史・技術)
長野県はセロリの年間総生産量で全国1位を確保しており、とくに夏のセルリー出荷はそのほとんどを占めています。
この成功の鍵となっているのが、原村や諏訪地域の標高600〜1,100mという冷涼かつ乾燥気味の高原環境。
昼夜で大きく温度差があるこの土地では、セロリの細胞にストレスがかかることで糖分を貯め込み、香りや甘みが引き立つようになります。
さらに、気温管理が難しい野菜であるセルリー栽培には高い技術力が求められます。
温度が15~25℃の範囲で適切に管理しないと、芯がなくなったり、逆に花が咲いてしまったりするため、徹底した温度調整の下で育てられています。
また、“諏訪3号”という品種はJA信州諏訪独自の交配種で、原村・茅野市・富士見町限定の栽培圏内で育てられ、その高い品質が全国へ供給されています。
旬・出荷期(5〜11月)と新鮮な見分け方
長野県産のセルリーは、一般的に5月中旬(早ければ5月初旬)から11月下旬まで長期にわたって出荷されるのが特徴です。
これは他県では短期の出荷に止まることが多いセロリに比べて、圧倒的な供給量と期間を誇ります。
また、原村のセルリーは夜間から夜明けにかけて収穫され、そのまま予冷庫に運びこまれて急速冷却され、新鮮な状態が保たれてから出荷されます。
この「朝採れ、朝出荷」のシステムにより、鮮度・甘み・シャキシャキ感が一般のセロリを大きく上回ります。
実際、収穫直後のセルリーを口にした際は「甘くシャキシャキして臭みがない」といった高評価が多く、そのみずみずしさはまさに高原の恵みの賜物です。
選ぶ際には、茎の緑色が鮮やかで、葉にツヤやハリがあるもの、そして重みがあり乾燥していないものが「当たり」の目安です—そうした見た目は味や食感の良さと直結しています。
おいしく食べる(レシピ・下ごしらえ・保存)

生で味わう(サラダ・ディップ・浅漬け)
長野県産のセルリーは、生で食べるとその香りと歯ごたえが際立ちます。
農家さんの間でも「やっぱり生が一番」との声が多く、例えばスティックに切ったセルリーに味噌とマヨネーズを好みで混ぜたディップを添えれば、自然の甘さと香りが引き立つ定番の味わいとなります。
さらに、夏場の時期には塩と昆布でさっと作る浅漬けや、酢とハーブを使ったピクルスも人気で、一度に量を仕込んで冷蔵庫で保存しておけば1週間ほど楽しめる保存性のあるアレンジに。
火を通す(炒め物・スープ・かき揚げ)
火を通してもセルリーはその風味を損なわず、さまざまな料理に活用できます。
特にミネストローネやポトフのようなスープには、香味野菜としてのセルリーがコクと深みを追加してくれます。
また、細かく刻んでハンバーグのタネに混ぜると、口当たりが爽やかでふんわりした仕上がりに。
一方、葉の部分はかき揚げやてんぷらにすることで、香りと食感どちらもが存分に楽しめる一品になります。
下処理と保存(葉の活用・冷蔵/下茹で)
セルリーを調理する前に行いたいのが下処理と保存の工夫です。
まず茎の表面にある固い筋はピーラーか包丁でそぎ落としておくと、さっと火が通り、食感が柔らかくなります。
新鮮なまま保存するには、葉と茎を切り離し、それぞれ新聞紙やキッチンペーパーで包んでからポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で立てて保存するのが有効です。
この方法だと鮮度やシャキシャキ感が1週間ほど持続します。
茎がしんなりしてしまった場合には、冷水に根元を浸してしばらく置けば、みずみずしさが復活し、調理に使いやすくなります。
買える場所・お取り寄せ・現地情報

産直・直売所・道の駅(原村・諏訪エリアの目安)
長野県原村でセルリー(セロリ)を現地購入したい場合、最も確実なのは地元の直売所を訪れることです。
原村中心部、八ヶ岳エコーライン沿いにある「たてしな自由農園 原村店」では、瑞々しい高原野菜が豊富に並び、セルリーもその代表的な品目として季節に応じて販売されています。
店内は広く、観光案内所やカフェ、焼きたてパンなども併設されており、買い物と一緒に地域の食や風景も堪能できます。
さらに、夏季限定で開催される「原村高原朝市」も見逃せません。
例年、7月中旬から9月下旬まで、毎朝6:30ごろから八ヶ岳自然文化園駐車場近くで、収穫したての野菜がずらりと並びます。
新鮮さとともに高原の朝の空気も味わえる現地ならではの体験です。
また、八ヶ岳農業大学校が直営する「八ヶ岳農場直売所」でもセルリーを含む高原野菜や加工品が購入可能です。
学生たちが真心込めて育てた作物が並ぶ場として、品質の高さに定評があります。
これらは、直売所や朝市を複数回巡ることで、より旬で豊かなセルリーに出会えるルートとしておすすめです。
通販・ふるさと納税の動向と注意点
最新の通販情報として、2025年9月時点ではJA信州諏訪公式通販サイトにて「原村産 朝採れセルリー」が出品されているのが確認されています。
価格は参考価格で2kgあたり約1,800円+送料となっており、収穫からその日に発送されるため鮮度に優れているとのことです。
発送時期は9月上旬〜中旬で、収穫状況により変動する点は念頭に置いておきましょう。
ただし、Amazonや楽天など一般的な通販モールで「原村」指定のセルリーを見つけることは現時点で困難で、通常の長野県産セロリ商品に留まるケースが多いようです。
ふるさと納税については、現時点(2025年9月)では原村やJA信州諏訪のセルリーを返礼品として扱っている明確な情報は見つかっていませんが、今後も地元のPR強化や番組効果を受けて、掲載される可能性は否定できません。
気になる方は、JAや原村の公的サイトを定期的にチェックするとよいでしょう。
原村を訪ねるための基本情報(見頃時期・畑風景)
原村のセルリーを現地で体験し味わうには、訪問時期の選定が重要です。
旬の時期—とくに7月中旬から9月下旬—には高原特有の昼夜の寒暖差によって野菜に甘みとみずみずしさが加わり、畑の景色も緑鮮やかで絶好のタイミングです。
朝市開催中は特に朝どれの瑞々しいセルリーが並びます。
原村には、長く続くセルリー畑が点在し、まるで絵のような景観が広がっています。
特に夕方の散水風景は幻想的で、「絶景」として観光にもおすすめです。
村内の道沿いや農園の近くで見ることができ、写真撮影にも最適です。
アクセスとしては、中央自動車道・諏訪南ICから車で約8分ほど。
公共交通では茅野駅からタクシーで20分ほどの距離にあり、訪問前には直売所の営業状況や朝市の開催時間などを公式サイトで確認すると安心です。
まとめ:信州・原村の「朝採れセルリー(セロリ)」がもたらす食の新体験

『満天☆青空レストラン』(2025年9月6日放送)で紹介された長野県原村のセルリー(セロリ)は、標高900〜1,100mの高原地帯で昼夜の寒暖差を生かして育てられ、国産セロリの夏場シェアの約90%を占めるほど、国内トップの生産地です。
深夜1時頃から行われる収穫は、気温が低く水分ロスを防げる時間帯に集中しており、そのまま市場へと鮮度を保ったまま届けられます。
こうして実現する「朝採れ」の状態は、シャキシャキの食感と甘み、そしてえぐみの少なさを兼ね備えた、他では味わえないセルリーの魅力を生んでいます。
JA信州諏訪管内においては、セルリー販売額が野菜部門の約50.3%を占める主力商品であり、地元経済を支える存在でもあります。
放送では、「香る!セルリーのフルコース」として以下のレシピが披露され、家庭に取り入れやすく魅力的な提案となりました。
- セロリまるかじり(マヨ味噌添え)
- セルリーとタコ・芋の中華炒め
- セルリー入り和風ハンバーグ
- セルリー味噌(ご飯のおとも)
- セルリーミネストローネ
さらに、原村の「たてしな自由農園 原村店」では、ブロッコリーやレタスなどとともに瑞々しいセルリーを直に手に取れる販売の場があり、現地の高原野菜文化を体験できます。
一方で、ネット通販については「原村産朝採れセルリー」は現時点では出回っておらず、発見できるとすれば地元直売所や県のアンテナショップに限られるのが現状です。
このように、信州・原村のセルリーは、自然条件・高度な栽培技術・産地のこだわりが見事に融合した、まさに「極上のセロリ」です。
TV放送を通じて、家庭でも簡単にできるアレンジレシピとともにその魅力が伝わり、多くの「苦手だったけれど、これは別物」という声を呼んでいます。
もし地元直売所や観光での訪問が可能であれば、その瑞々しい味と香りをぜひその場で体感してみてください。
きっと野菜に対する見方が変わりますし、食卓が一段と豊かになるはずです。
読んでくださってありがとうございました。
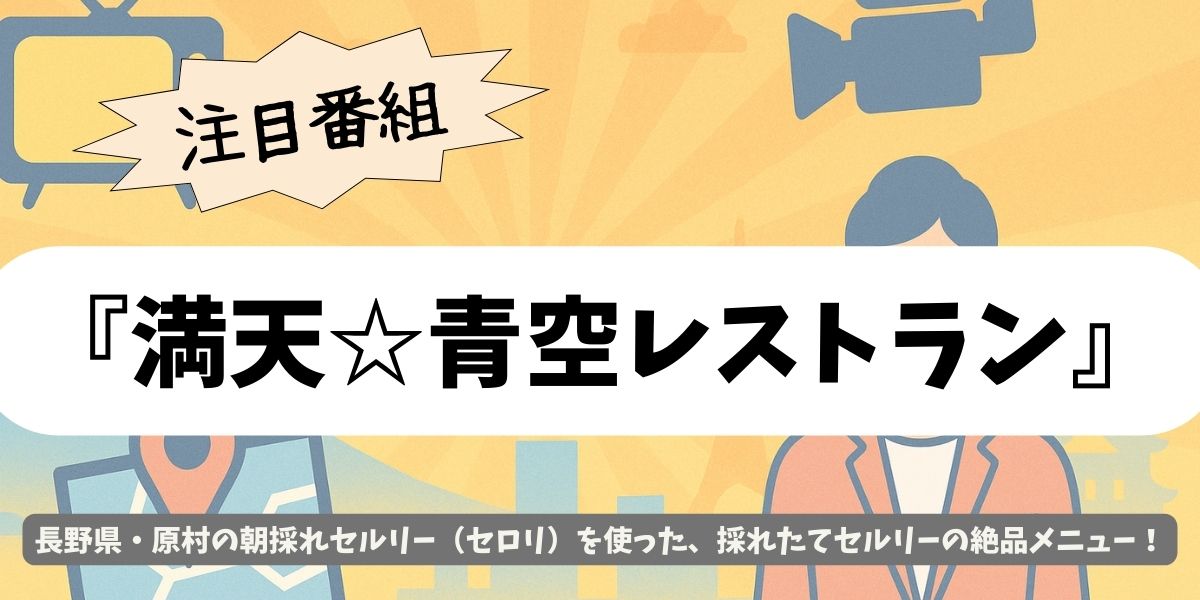
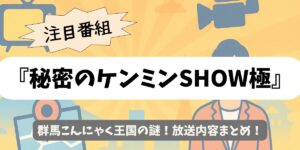
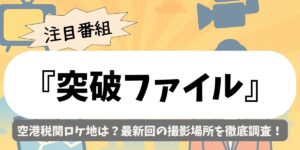
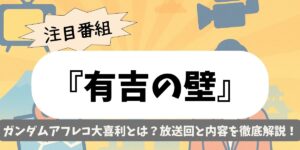
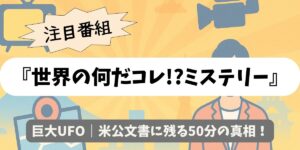
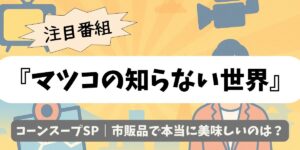
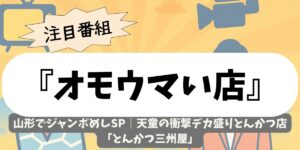
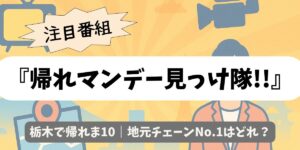

コメント