2025年8月1日放送の『沸騰ワード10』では、伝説の家政婦・志麻さんが自身で購入した築120年の古民家を舞台に、俳優・玉木宏さんと奥平大兼さんが初めて参戦して再生プロジェクトを展開。
柱の金輪継や50kg石材の縁側据え付けなど、DIYを超える精密作業と快進撃の晩ご飯が大きな見どころとなりました。
番組では、東京から離れた土地にある敷地約40坪+建物3棟という環境で、母屋と納屋を古民家再生の舞台とし、石造りの流し台や見事な梁、高天井といった価値ある構造を活かす改装が進行中です。
さらに、2年以上経過しても完成に至らないリアルな現状も強調され、視聴者の関心を集めています。
実際のVTRでは、重さ50kgの天然石の据え付けにおいて、玉木さんがレベル器でミリ単位の高さ調整を行う場面、そして柱の精密な切断と金輪継での継手修復など、技術と体力の両輪を駆使する作業が強く印象に残ります。
また、料理パートでは「7種海鮮ブイヤベース」が登場し、作業の合間に味わう豪華な晩ご飯が話題となりました。
この記事では、8月1日放送『沸騰ワード10』における志麻さんの古民家再生プロジェクトの全貌を、最新の進行状況・技術的施策・食の魅力・今後の展望という角度から丁寧に読み解きます。
まさに「伝統×DIY×食×暮らし」の融合を体現したこのシリーズの見どころを、視聴者の立場で実感できるようにお届けします。
番組放送内容と概要

志麻さんの古民家プロジェクト概要
2025年8月1日放送回では、“伝説の家政婦”志麻さんが自ら購入した築120年の古民家を舞台に、その再生プロジェクトの最新ステージを紹介。
番組は、約2000坪の放置地を含む広大な敷地で、母屋や納屋を再構築しながら、自力による開拓と改修の模様を密着取材しました。
志麻さんは過去に購入を決めたこの物件を、“高天井と梁、縁側、石造りの流し台”という特徴を評価したうえで選んだとされ、今回のシリーズで具体的に再生作業を進めています。
ゲスト出演者と参戦内容(玉木宏&奥平大兼)
この回には俳優・玉木宏さんと奥平大兼さんが初参戦し、古民家再生プロジェクトに意欲的に参画しました。
特に玉木さんは、志麻さんの指導のもと「巨大縁側」づくりに挑戦し、50kgにも及ぶ天然石の据え付けや、極めて精密な母屋柱の切断作業を体験。
1ミリの誤差も許されない継ぎ手加工という過酷な工程に奮闘する姿が大きく取り上げられました。
放送回の見どころ(過酷作業と美食エピソード)
放送の中核は、志麻さんたちが実施するDIY作業の数々。
例えば、縁側下に重さ50kgの石を据える作業、母屋の柱を金輪継による伝統技術で継いで再建する工程、さらには納屋の曳家(建物移動)に至るまで、肉体的にも技術的にも相当な負荷がかかる工程を映像で克明に描写しました。
また、作業の合間には志麻さんが振る舞った「7種の海鮮ブイヤベース」が登場し、玉木さんが思わず悶絶する美食シーンも見どころの一つとなりました。
築120年・2000坪 古民家の特徴と歴史

母屋と納屋の構成と歴史背景
志麻さんが購入した築120年の古民家は、母屋を中心に納屋が2棟ついた構成となっており、敷地全体は約400坪(約2000㎡)の広さです。
購入時点では40年以上人が住んでおらず、建物は全体的に痛みが目立ちました。
番組では、母屋の高い天井、太い梁、縁側、さらには石造りの流し台といった構造的特徴が注目され、「昔ながらの造りを活かす価値」が選定基準だったと紹介されています。
20年以上放置された土地と竹林、自力開拓の経緯
約20年以上放置された土地には、足の踏み場もないほど竹林が繁茂し、敷地の排水が著しく悪化していました。
番組では竹を120本以上伐採し、畑の水はけ改善も兼ねた大規模な整地作業風景が放送されました。
志麻さん自身や支援スタッフが竹と格闘しながら土地を再生する様子は、自然と向き合うリアルな努力として描かれていました。
土地選びの理由(高天井・梁・石造り流し台)
番組内で志麻さんは、古民家を選ぶ際の決め手として「高い天井」「立派な梁」「縁側」「石造り流し台」という4要素を挙げています。
特に石流し台は、現代では珍しい素材であり、「キッチンが私の主戦場」である自分には理想的な存在だったとのこと。
それらの建物要素が“素材の味をそのまま楽しむ料理”を生む環境として強く影響していることが語られています。
DIY再生工事の工程と技術

縁側石据え付け作業(50kg石材の使用)
番組では、志麻さんと玉木宏さんが共同で巨大な縁側の土台づくりに取り組み、重さ約50kgの天然石を縁側下に据えるシーンが見どころでした。
石は平坦性が求められるため、玉木さんがレベル器を用いて一ミリ単位で位置を調整。
志麻さんが「この石が土台の安定と料理スペースの演出になる」と語るなど、機能性と美観を兼ね備える配置が意識されていました。
一般家庭ではまず見ることのない重機を使わない手作業による据え付け作業は、番組としても技術と体力が試される場面です。
母屋柱の切断・金輪継による伝統工法
築120年の母屋では、損傷部のある柱を一度取り外し、1ミリの誤差も許されない切断調整を施したうえで、伝統技術「金輪継(かなわつぎ)」で元の位置に戻す工程が行われました。
玉木さんは錐(きり)や鑿(のみ)を使い、志麻さんの監督のもと精密作業に集中。
番組は、伝統工法の緻密さと、古材の価値を守る作業の丁寧さを視覚的に伝えています。
この継ぎ手作業により、建物の歴史を尊重しながら強度を維持する改修法が紹介されました。
曳家作業による納屋の移動(台車・移築技術)
今回の放送では、納屋を移設して新たなスペースに再活用するための曳家(ひきや)作業にも密着。
12トン級ともされる納屋を、助っ人たちと協力して台車と滑車を使ってゆっくり移動させる場面が映し出されました。
曳家中、地盤沈下で母屋が傾くピンチもあり、緊張感のある作業ながら、スタッフや地元助っ人が土嚢を並べて地盤強化する様子は、DIYの先を行く“再生工事”ならではといえる展開でした。
番組ならでは食・交流シーンと独自要素

史上最高晩ご飯「7種海鮮ブイヤベース」の振る舞い
番組によれば、8月1日放送回で振る舞われた「7種海鮮ブイヤベース」は、志麻さんならではの豪華メニューです。
地元で調達した新鮮な魚介を7種類用い、深鍋でじっくり煮込むことでスープに旨味が染み出し、ゲスト陣も「驚くほど濃厚」と賞賛していました。
スタジオでも「一皿で満足感が得られる」と話題になり、食の魅力が放送回全体を通して大きな感動を呼びました。
玉木宏さんも「忘れられない味」と語っており、作業の合間にこれほどの料理が出てくる構成は、番組のサプライズ性にもつながっていました。
土地で採れた野草・フルーツ活用の料理エピソード
また、志麻さんは現地で自ら採取した野草や果実を活用し、自然との共存を意識した料理を披露しました。
ノビルやヤブカンゾウ、ミント、ミョウガといった身近な食材を収穫し、引っ越しそばやドリンク、サラダなどに取り入れておもてなし。
野菜や果実をその場で加工することで、土地の季節感を食事に直結させる暮らしのスタイルが視聴者にリアルに伝わりました。
これらの料理は「地産地消」「自然との調和」を象徴し、番組のテーマ性を強めています。
地元助っ人や芸能人との交流シーン
番組では、助っ人として地元住民や著名人が複数回登場し、交流シーンが印象的に描かれました。
特に土屋アンナさんとそのお子さんが曳家作業や竹林伐採に参加し、家族ぐるみで古民家再生に関わる姿が紹介されました。
また、タイムマシーン3号や芸能人たちも土嚢運びや基礎づくりを手伝い、作業現場に賑わいを添えました。
こうした多彩な人々との協働風景は、プロジェクトの本質である「地域と共に進む再生」を象徴しています。
古民家再生プロジェクトの現在地と今後の見通し

改装の進捗状況(曳家完了/図書館計画進展)
最新の放送情報によれば、志麻さんの築120年古民家改装プロジェクトは、母屋の曳家移動と納屋の再配置が完了し、空いた納屋が「図書館スペース」へと生まれ変わりつつあります。
2025年2月の放送では、図書館の壁・屋根・床張り作業がいよいよ最終段階に差しかかり、ミリ単位の調整が求められる「鎧張り」など、精緻な内装技術が導入されました。
引越し後2年以上経過した現在も、「まだ家が完成していない」と志麻さん自身がSNSで述べており、改装作業が継続中であることが明らかになっています。
今後の作業予定と放送予告(次回の注目ポイント)
今後の展開では、図書館スペースの仕上げに加え、台所や浴室など生活動線に関わる部分の改修が予定されています。
過去の放送では、収納設計や断熱対策の強化、湿気対策の導入が課題として挙げられていました。
次々回以降の放送では、家事導線を意識した「動線改善策」や、古材を活かした家具設置のシーンが公開される可能性が高く、リノベーションの完成度が視聴者の注目ポイントとなります。
視聴者反響やSNS上の話題(番組関連投稿まとめ)
番組放送後、視聴者からSNSで多数の反響が発生。
特に図書館として再活用される納屋の内装や、志麻さんのこだわり料理に対するコメントが目立っています。
また、改装中のトラブルや失敗も含めたリアルな現場描写に対して「まるで自分も参加している気持ちになれた」といった感想も多数投稿されています。
番組公式X(旧Twitter)では、視聴者から「DIYの参考になった」「料理だけでなく住まいとして魅力的」といった声が寄せられ、番組の影響力の大きさがうかがえます。
まとめ

築120年の古民家再生プロジェクトは、志麻さんが選び抜いた伝統的な建築要素──高天井・梁・縁側・石造り流し台──を最大限活かす形で進行しており、母屋と納屋の再構築や大規模な開墾・整地作業を経て、今も着実に工事が継続中です。
重さ50kgの天然石を縁側下に据え付ける際の1ミリ単位の施工、母屋柱に施された金輪継による伝統的継手工法、そして巨大な納屋の曳家作業といった、DIYの域を超えた高度な技術と体力が求められる工程が次々と登場し、視聴者に強い印象を残しています。
料理シーンもプロジェクトの魅力を支えています。
特に7種類の海鮮を用いた“史上最高晩ご飯”とも称されるブイヤベースや、土地で採れた野草や果実を取り入れたメニューは、自然と共に暮らす豊かな食文化をリアルに体感できる構成でした。
さらに、土屋アンナさんをはじめ藤岡弘、ティモンディ、高岸宏行さん、岩田アナなど、多彩な地元助っ人や芸能人との協働作業・交流シーンが、古民家再生のプロセスに人間味を加えています。
図書館スペースの腰板張りや巨大本棚設置の手伝い、崩壊寸前の台所解体など、共に作り上げていく姿勢がプロジェクトの根幹を支えていました。
現在、納屋は図書館スペースとして改装が終盤に入り、西洋風石畳の床や10m級の丸太を使った屋根ひさしなどが完成に近づいています。
SNS上でも「まるで自分も作業に加わった感覚」「DIYの参考になる」「志麻さんの暮らしに引き込まれた」といった視聴者の声が続出し、番組への反響も非常に大きい状況です。
このプロジェクトは単なるリノベーション番組を超え、「伝統×食×人との交流」という複層的な体験を提供してくれています。
志麻さんが持つ料理の感性と、DIY技術への真摯な取り組み、そして地域社会を巻き込む温かい協力体制が、まさにこのプロジェクトの核です。
視聴者としては、次回以降に登場する台所や浴室の動線改善、収納設計、断熱・湿気対策などの生活空間改修に大いに期待が高まります。
番組が提示する「完成へ向けたラストスパート」がどのように見せてくれるのか、今後の展開にも目が離せません。
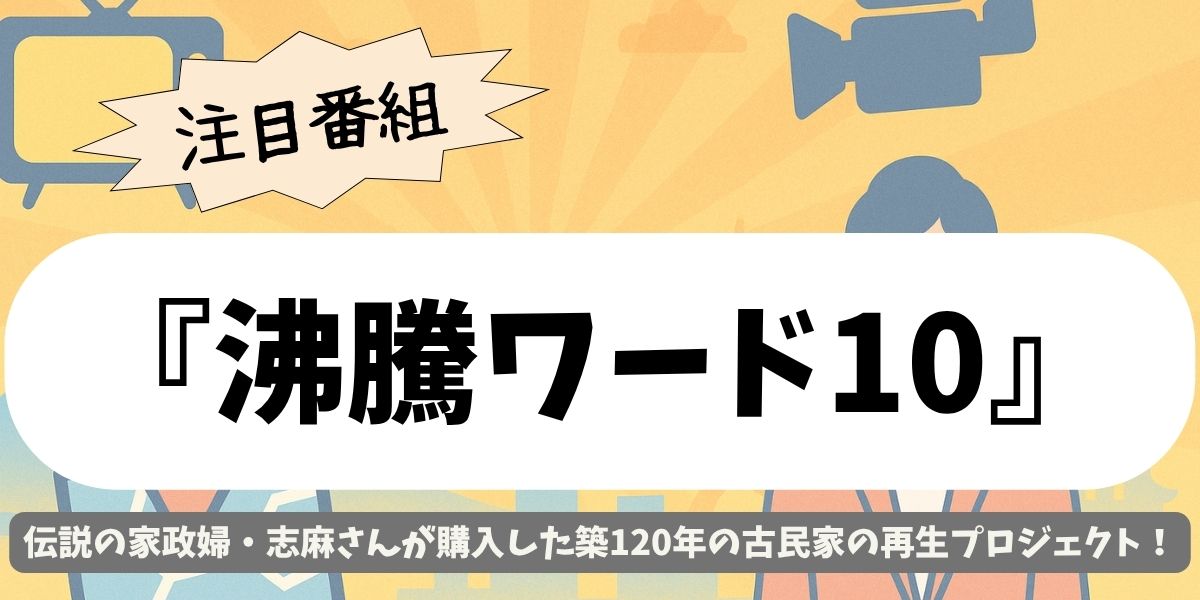

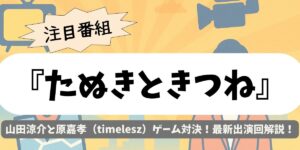


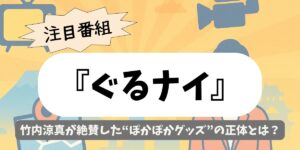
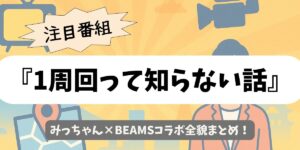
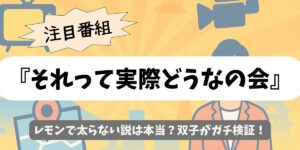
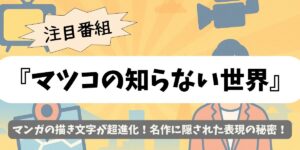
コメント