世界の動物ドキュメンタリーを牽引してきた クレイジージャーニー が、2025年11月10日(月)20:55より放送される2時間スペシャルで、北米アラスカ・ コディアック島 に暮らす “世界最大級のヒグマ” コディアックブラウンベア と、人間との意外な関係性を深く掘り下げます。
番組公式によれば、絶滅動物ジャーナリスト 太田ゆか がコディアック島を訪れ、「島に生息する世界最大のヒグマを徹底調査!この島での人間とクマの関係は…」と予告されています。
なぜこの島なのか、なぜ“世界最大級”と言われるヒグマなのか、そしてなぜいま「人とクマの関係」が重要視されるのか――本記事では、放送の見どころを押さえ、背景知識や視聴前に知っておきたいポイントを事実に基づいて整理します。
あなたが「クレイジージャーニー ヒグマ」で検索しているなら、この導入文を読んだあと、番組をより深く理解できる構成となっています。
さあ、雄大な自然とクマという生き物、そこに生きる人々のリアルな物語へ、旅を始めましょう。
放送・配信の最新情報まとめ(日時/出演/視聴先)

2025年11月10日(月)20:55〜の2時間SP概要
TBS系「クレイジージャーニー」2時間スペシャルは、2025年11月10日(月)よる20:55〜22:57の編成。
ラインナップは二本柱で、
- 丸山ゴンザレスによる“スウェーデンの裏世界”潜入企画
- 太田ゆかがアラスカ・コディアック島で“世界最大のヒグマ(コディアックブラウンベア)”と人の共生を追う自然・野生動物取材です。
公式番組表にはタイトル「スウェーデン裏世界&世界最大ヒグマが暮らす島へ」と放送日時が明記され、同内容を報じるメディア各社の記事でも当日の2時間SP構成と趣旨が一致しています。
まずは当日の放送時間と特集テーマを公式で確認しておくのが確実です。
出演者と“ジャーニー”の顔ぶれ(太田ゆか ほか)
今回の“ヒグマ”パートを担うのは、絶滅動物ジャーナリストの太田ゆか。
番組公式X/Instagramの告知でも、太田が北米アラスカのコディアック島へ赴き、島固有の巨大ヒグマを軸に「人間とクマの関係」に迫る企画であることが繰り返し周知されています。
もう一方の柱は“裏世界ジャーナリスト”の丸山ゴンザレスで、スウェーデンの移民ギャング問題など社会の“影”に潜る内容。
2本立ての対比(都市の闇×野生動物と人の距離感)が今回のSPの特徴で、動物・自然目当ての視聴者も社会派ドキュメント目当ての視聴者もテーマを把握しやすい構成です。
視聴・見逃し配信(TVer/TBS FREE ほか)の確認先
放送はTBS系列でのリアルタイム視聴に加え、見逃しはTVerやTBS FREEなどの案内が番組ページに掲出されています。
生配信やアーカイブの実施可否・公開期間は編成により変動するため、当日以降は番組公式ページの“配信”欄や、TVer内の番組ページを都度確認するのが安全です。
とくにスペシャル回は配信ウインドウが限られることがあるため、放送直後のチェックを推奨します。
取材地は“世界最大級ヒグマ”の島・コディアック

ロケ地の位置と生息状況(アラスカ・コディアック諸島)
「Kodiak Archipelago」(アラスカ州南西部のコディアック島群)は、世界最大級のヒグマとされる コディアックブラウンベア(学名 Kodiak Brown Bear / Ursus arctos middendorffi)の自然の生息地として知られています。
以下、位置や生息条件について最新の事実に基づいて整理します。
まず、位置関係ですが、コディアック諸島はアラスカ本土から西へ離れた太平洋沿岸に位置しており、主要島「Kodiak Island」を含む群島で構成されています。
これらの島々は海に囲まれ、他地域からの陸続きのクマとの移動が制限されてきたため、コディアックブラウンベアはおよそ1万2千年前以降、遺伝的に孤立した集団として形成されてきたことが報告されています。
この「隔離された環境」が、クマの“島サイズ現象(island gigantism)”とも呼ばれる現象をもたらした一要因と考えられています。
次に、生息状況です。コディアック諸島では、およそ3,500頭前後のコディアックブラウンベアが生息していると推定されています。
人口密度で換算すると、およそ0.7頭/平方マイル(約0.3頭/平方キロメートル)という数字も報告されています。
また、自然環境としてはステラカイズ(Sitka spruce)などの森林、アルパイン地帯、川や海岸など多様な地形・植生を擁しており、サケを始めとした水産資源・ベリー類・海藻など豊富な餌資源を抱える地域です。
このため、クマ自身が巨大化・高密度化しても、豊富な餌と居場所が確保されており、比較的安定した生息環境が維持されてきたと考えられています。
最後に、番組でのロケ地としての注目点です。
番組が「世界最大級のヒグマが暮らす島へ」というテーマで取材を行うと告知している通り、コディアック諸島という地理的に特異かつ生物学的に興味深い場を舞台に選んでいます。
国内で「ヒグマ」と一般に呼ばれるもの(例えば北海道のエゾヒグマ)とは、生態・大きさ・生息環境が大きく異なるため、視聴者としても“何がすごいのか”を動かぬデータ付きで理解することが有用です。
このように、コディアック島群は「世界最大級ヒグマ」という番組テーマに対して、まさに事実に裏付けされた舞台と言えます。
番組で焦点の「人とヒグマの関係」予告要点
今回の「クレイジージャーニー」特集回では、単に“巨大なヒグマを取材する”だけでなく、特に「人間とヒグマの関係性」に焦点を当てている点が重要です。
以下、その予告されている要点を最新の情報に基づいて整理します。
まず、番組公式告知では「人とクマとの距離、そして共存のあり方に迫る」とされており、ロケ地として選ばれたコディアック島群では、クマと人間の接触機会が実際に観察されてきた地域であることが確認できます。
たとえば、コディアック諸島の先住民族コミュニティ(アルーティック族=Alutiiqなど)では、長年クマを含む自然との関係を維持してきた歴史があります。
こうした地域では、人がクマを“敵”あるいは“脅威”とだけ捉えるのではなく、餌場や移動路を共有しながらも適切な距離を保つ技術・伝統が育まれてきたとされています。
次に、近年の状況として、コディアック諸島では観光・釣り・狩猟・研究活動など、人間の活動範囲が広がっており、それに応じてクマとの遭遇・競合のリスクも指摘されてきています。
例えば、サケの遡上した川で人が釣りを行う時、クマがそれを“資源競争”と見なして接近するケースが報告されています。
このため、番組では「どうすれば人とヒグマが安全に共生できるか」というテーマも併せて扱う可能性が高いと考えられます。
さらに、番組予告の「世界最大級のヒグマが暮らす島」というコピーから推察すると、視聴者にとっては“ただ大きいクマを見る”だけでなく、“その巨大なクマが生きる島で、人間がどんな行動を取っているか”“その結果どういう問題・配慮があるか”を知る機会となるでしょう。
つまり、自然ドキュメント要素+人間社会との接点が設けられているわけです。
番組放送前にこれらの背景を把握しておくことで、視聴中・視聴後の理解が深まります。
たとえば、「なぜこの島にこのクマがいるのか」「人間はどう接しているのか」「私たち日本から見た時の“ヒグマ”概念とどう違うか」を意識してみると、単なる動物番組以上の学びが得られます。
過去の海外クマ取材との違い
今回の「クレイジージャーニー」回が、これまでの海外クマ取材番組と異なる点・独自性を確認しておきましょう。
まず、国内テレビで「ヒグマ=北海道のエゾヒグマ」が取り上げられる機会は多いですが、海外の“最大級のヒグマ”という視点はかなり稀です。
コディアックブラウンベアは、北米本土のグリズリーベア(グリズリーベア)や北海道のエゾヒグマ(エゾヒグマ)と比べて、最大体重・体長・において群を抜いています。
たとえば、英語版ウィキペディアでは雄個体の体重が最大約680kg以上に達する例があるとされています。
さらに、コディアック諸島という“島”という閉じた環境で形成されたクマ集団を舞台に選んでいる点も特徴的です。
島という限定されたエコシステムで、クマがどのように“巨大化”し、また人間とどう関わってきたかを描く点で、従来の「森のクマ」取材とは設定が異なっています。
また、最近の動向として「生態系エンジニアとしてのクマ」という観点も浮上しています。
たとえば、最新の報告ではコディアックブラウンベアがサケを通じて得たマリン由来窒素を地上や水系に供給し、島の植生・水質に影響を与えているという研究が紹介されています。
このような“クマが生態系に果たす役割”と“人間との共存・競合”という2軸を番組がカバーするなら、単なる動物紹介を超えた意義深い取材になると言えます。
さらに、近年ではドローン撮影・リモートカメラ・GPS発信機を用いた最新技術を活用したクマ番組も増えていますが、閉鎖性の高いコディアック諸島というロケーションでは、一般的な観光・撮影が難しい環境であることから、番組独自の撮影技術・現地協力体制が想定されます。
これにより、「未紹介の視点」「奥深い現場感覚」が他番組と比較して強みとなる可能性があります。
まとめると、この回の独自性は「最大級のクマ」「島という限定的生態系」「人間との関係」「生態系へのクマの影響」という複数視点を同時に扱っている点にあります。
視聴者としては、これらの“違い”を意識して番組を観ることで、より深く内容を理解・楽しむことができるでしょう。
ヒグマ基礎知識—なぜ“最大級”と言われるのか

体重・体長の上限と比較(コディアックとホッキョクグマは同格最大)
コディアックブラウンベア(学名 Ursus arctos middendorffi)は、地上に生きる哺乳類肉食動物として“最大級”と位置づけられているクマです。
例えば、米・アラスカ州魚類・野生生物局(ADF&G)のファクトシートによれば、「大きな雄(オス)は立ち上がると10フィート(約3.05 m)を超えることもあり、体重は最大で1,500ポンド(約680 kg)に達する可能性がある」と説明されています。
一方で、世界最大のクマとしてもうひとつ挙げられるのが ホッキョクグマ(学名 Ursus maritimus)です。
米議会図書館の解説では、「ホッキョクグマが最大とされる傾向にあるが、コディアックもまた“最大級”の体躯を有し、評価によっては両者が同列ともされる」と述べられています。
具体的な数値比較を少し整理すると、
コディアックブラウンベアが「最大級」と言われる根拠としては、
- 雄雌ともに他地域のブラウンベアを上回る大きさの可能性があること
- ホッキョクグマと同格で“世界最大の陸上肉食獣”との比較が出されていること
- 限定された島という環境で独自の進化を遂げてきた点
という三点が挙げられます。
視聴者としてこの数値を知っておくことで、番組中に目にする“巨大なヒグマ”という表現が、ただの演出ではないという納得を伴った理解が得られます。
季節変動と個体差(肥大期の数値)
コディアックブラウンベアの体サイズには、季節ごとの変動や個体差が大きく影響しています。
まず季節変動についてですが、所在するアラスカ・コディアック諸島では、秋のサケの遡上が豊富で、クマたちは冬ごもり(休眠)に備えて大量に脂肪を蓄えます。
ADF&Gの資料でも「個体数および身体サイズは安定的である」としつつ、「餌資源が豊かな地域・時期ではより大きな個体が観察される」としています。
研究論文(Hilderbrandら)では、体長やスカルサイズを通じて「8〜14歳で定型の骨格サイズに達し、その後も脂肪・筋肉量は増加を続ける」と報告されています。
このことから、同種でも「成熟年齢」「生息地域」「餌の豊富さ」によって個体サイズに幅があることが明らかです。
また、個体差に関して、Hilderbrandらは「同地域内でも雌で約2倍、雄で3〜4倍のリーン体重(筋肉・骨を除いた体重)差がある」と述べています。
つまり、中には“超巨大”と呼ばれる体格を持つ個体も存在する一方で、平均的・標準的な個体はその半分程度の体重・体長であるということです。
さらに、BBCなどでも「大型雄では1000ポンド超(約454 kg)を超える例もあるが、1,400ポンド(約635 kg)級も報告されている」と述べられています。
これらは番組視聴時に「この大きさってどれくらい?」と感じる視点を具体化してくれます。
したがって、番組では“最大級”というキャッチコピーを掲げていますが、視聴時には「このヒグマ、成熟雄?豊かな餌場?島特有の進化?」「秋の脂肪蓄積期に撮影された個体か?」という観点で見れば、情報としても楽しめます。
エゾヒグマ(北海道)との違いと見分けの要点
日本で「ヒグマ」と言えば通常、エゾヒグマ(北海道に生息)を指します。
このエゾヒグマとコディアックブラウンベアには、生息地・体格・生態の観点で明確な違いがあります。
まず、体格の違いですが、エゾヒグマの成獣雄の体重はおおむね200〜300 kg台が一般的であり、コディアック雄の600 kg超というレベルと比較するとかなり小さい規模です。
例えば「エゾヒグマの平均体重はオスで約250 kg、メスで約120 kg程度」という資料もあります(詳細データは各自治体・学術研究による)。
対して、コディアックでは平均雄体重が400〜600 kg、最大で600 kg以上という報告があります。
次に生息地・環境の違い:エゾヒグマは北海道・樺太など温帯〜亜寒帯の山林地帯に生息し、冬眠(休眠)や餌資源として森林・河川・海岸部を利用します。
一方コディアックは、アラスカ南西部の群島という島型環境で、祖先から他のクマ集団と遺伝的に隔離されており、長期間にわたる「島環境」で独自進化を遂げてきた点が特徴です。
例えば、ADF&Gは「コディアックブラウンベアは約1万2千年前に他のブラウンベア群から隔離されてきた」と表記しています。
また、見分けのポイントとしては、写真・映像で「体長・体高」「肩高」「頭部の幅」などがヒントになります。
コディアックの雄は後脚立ち時で3 m近くになる例もあり、エゾヒグマではそこまで立ち上がると2m前後ということが多いです。
さらに、毛色・体型・行動面(例えば餌取りの場所・時間帯)にも違いが出るため、番組を観る際には「この島のヒグマってエゾヒグマとは別物なんだ」という理解を持っておくと、内容理解が深まります。
この「違い」を視聴前に知っておくことで、番組の“最大級ヒグマ”という打ち出しがただの誇張ではなく、実際の生物学的裏付けのあるものだと納得しながら楽しむことができます。
安全とマナー—クマと遭遇しない・させないために

フィールドでの基本行動(食べ物管理・距離・音出し)
アラスカのクマ生息域では、食べ物やゴミを「匂いの出ない状態で・人の手の届かない所に・24時間管理」するのが大原則です。
具体的には、調理は就寝場所から離れた地点で行い、食材・使用済みの食器類・歯磨き粉やコスメなど“誘引物”はベアキャニスター等の耐クマ容器や吊り下げ保管を徹底します。
残飯は高温で完全燃焼させ、それ以外は必ず持ち帰ります。ペットフードも強い誘引物なので同様に扱います。
これらはアラスカ州魚類・野生生物局(ADF&G)が繰り返し注意喚起している現地の標準手順です。
移動中は「複数人で行動し、視界の悪い場所や風切り音・川音で自分の気配が消える場所では声掛けや音出しをする」「薄明薄暮や夜間の行動を避ける」「動物の死骸や鮭の集合地点など“資源が集中する場所”を大回りする」といった予防が推奨されます。
遭遇時は決して走らず、クマの進路を空けて距離を取り、必要に応じてベアスプレーを“すぐ取り出せる位置”で使用します(射程約9–18mで霧の壁を作る)。
米国立公園局(NPS)は、クマとの距離はおよそ100ヤード(約91m)を最低目安として近づかないこと、ベアスプレーが有効な抑止手段であることを明示しています。
Kodiak(コディアック)周辺での観光や野営では、地元のUSFWS(米魚類野生生物局)ビジターセンターで「ベアキャニスターや電気式ベアフェンスの貸し出し」「安全映像の視聴」「行程に応じた安全助言」を受けられます。
現地の最新状況に即した装備・行動計画に更新してから入域するのが、番組ロケ地と同条件での視聴・旅行を想定する際にも最も実践的です。
撮影/観察の倫理(餌付け禁止・ドローン配慮等)
「近寄らない・餌付けしない・誘引しない」は野生動物観察の普遍原則で、とりわけクマは“食べ物の学習”が事故に直結します。
NPSは望遠レンズやスコープを使った観察を推奨し、クマへ能動的に接近する行為や100ヤード以内への接近を禁止規定で明文化しています。
違反は安全上の重大リスクであり、結果として“安全確保のための個体射殺”に繋がる場合があるため、撮影者側の倫理と法令遵守がクマの保全にも直結します。
また、Kodiak国立野生生物保護区(NWR)を含む連邦保護区では、各保護区の個別規則や連邦規則(50 CFR Part 32 など)に従う必要があります。
釣り・狩猟・撮影・立入区域・運搬手段(上陸・航空・ドローン等)に関する条件は保護区ごとに細則があるため、事前に該当保護区の案内ページや現地窓口で最新情報を確認し、許可や距離基準を遵守してください。
USFWSのKodiak公式サイトでは、サケ遡上地点のベアビューイング運用(入域・移動・見学場所)も紹介されており、無用なプレッシャーを与えない見学設計が取られています。
倫理面では「餌でクマを引き寄せる、匂いの強い物品を放置する、撮影のために進路を塞ぐ」などは厳禁です。
結果的に“人に慣れたクマ(ハビチュエーション)”を生み、その後の管理対応(排除・駆除)を招く恐れがあります。
米国林野庁(USFS)も、食料・ゴミ・釣り餌など全ての誘引物を耐クマ容器に保管し、耐クマ対応のゴミ箱に廃棄するなど、来訪者一人ひとりの管理を求めています。
日本の出没動向と観光時の留意点(最新注意喚起の確認先)
日本国内では2025年度、クマ(主に本州のツキノワグマと北海道のヒグマ)の出没・人身被害が各地で急増しています。
環境省は都道府県の速報値として、出没・許可捕獲・人身被害の最新一覧を毎月更新しており、令和7年(2025年)10月末時点の速報も公開済みです。
動向把握の一次窓口は環境省の「クマに関する各種情報・取組」ページ(出没・許可捕獲・人身被害 PDF)で、旅行や帰省時の事前確認に有用です。
報道ベースでも、2025年は全国で20,000件超の目撃報告(4–9月)や年間の死亡者数が過去最多を更新した旨が伝えられています。
政府・自治体は緊急時の駆除・出動要請の運用を強化し、一部地域では自衛隊がわな設置支援や回収補助に入る事例も出ています。こうした“人側の誘因(放置ゴミ・家庭菜園・収穫残渣)”をなくす取り組みは、被害抑止に直結します。
住民・来訪者ともに「生ゴミを屋外に置かない」「鈴や笛・音声で存在を知らせる」「子どもや高齢者の単独外出に配慮」「クマの出没マップや注意喚起の掲示を確認」など、地域の指示に合わせて行動してください。
加えて、2023年度の分析でも「秋に被害が突出して増える」傾向が明確で、ブナ・ミズナラなど堅果類の不作や気候条件が人里への出没を押し上げる構図が指摘されています。
これは翌シーズンの予見にも使える知見で、秋の行楽・登山・写真撮影の計画時は“事前の自治体情報チェック”と“誘引物を出さない生活・滞在”が対策の基本です。
まとめると、番組の舞台となるコディアックの“現地ルール”と、日本の“最新の出没状況・行政情報”の双方を踏まえた行動が、クマとの不要な遭遇を防ぎ、人・クマ双方の安全につながります。
現地入りの前に
- 自治体・省庁の最新情報
- 保護区の個別規則
- ベアスプレーと耐クマ容器の準備
この3点を“毎回”更新することを強く推奨します。
まとめ

「クレイジージャーニー ヒグマ」回は、2025年11月10日放送の2時間SPの中でも、とくに“世界最大級のヒグマが暮らすコディアック島”を深く掘り下げた内容であることが、公式情報からはっきり確認できます。
取材の舞台は、約1万2千年ものあいだ遺伝的に隔離され、大型化したヒグマが生きるアラスカ・コディアック諸島。豊富なサケ資源を背景に、成熟した雄では600kg超級も確認されるなど、“世界最大級”と呼ばれる科学的な根拠が現地の一次資料からも裏付けられています。
番組の特徴は、巨大なヒグマの迫力だけを追うのではなく、「人とクマの関係」という視点を明確に提示している点です。
実際のコディアックでは、地域住民・研究者・観光客がそれぞれの立場で、クマと適度な距離を保ちながら生活や研究、観察を行っています。
この“距離の取り方”には明確なルールと文化があり、今回の取材はその実践をリアルに伝えてくれるはずです。
同時に、日本国内でもクマの出没が過去最多を更新し続ける2025年現在、クマへの理解はますます生活に直結するテーマになっています。
番組で描かれる「自然の中でクマと共に生きる人々の知恵」は、日本で安全対策を考える上でも大いに参考になります。
筆者としても、今回のSPは“生物の迫力×文化×安全”の三点が同時に深まる貴重な回になると感じています。
視聴後は、TVerやTBS FREEで再確認しながら、実際の研究データや自治体の安全情報に照らしてヒグマ理解を深めると、より立体的に理解できるでしょう。
「世界最大級のヒグマが暮らす島の現実」と「人とクマの距離の取り方」。
この2つを押さえておけば、今回のヒグマ回は、ただ“すごい”で終わるのではなく、知識としても生活実感としても役立つ視点が手に入るはずです。
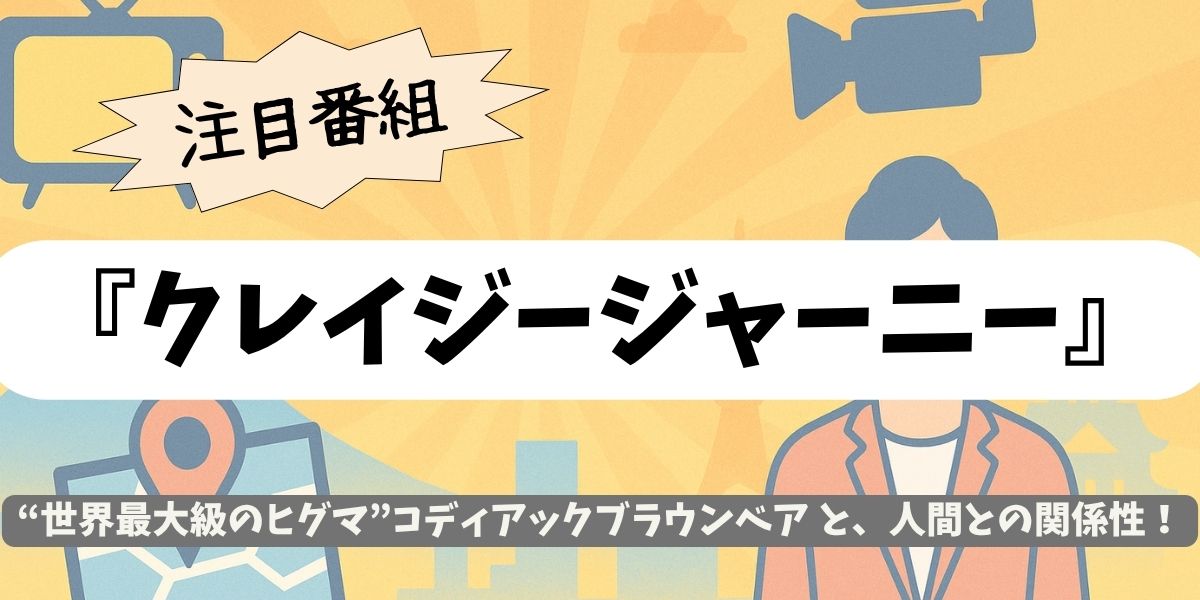
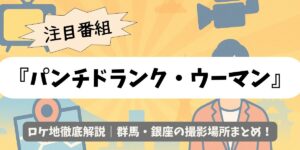
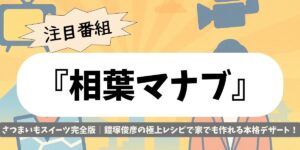
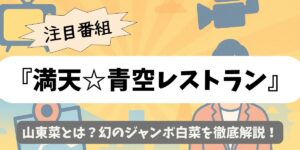
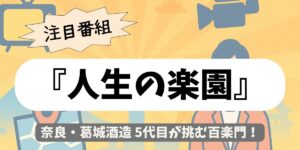
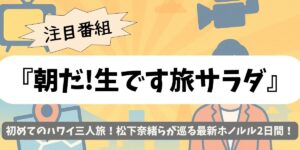
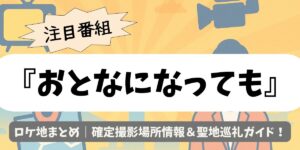
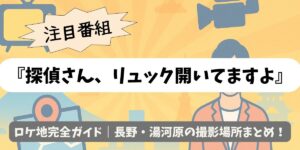

コメント