2025年4月から5月にかけて放送されたNHKの人気番組『ブラタモリ』では、「伊勢神宮への旅」と題し、タモリさんが三重県桑名市から伊勢神宮までの約90kmの道のりを歩きながら、伊勢路の歴史や文化、地形の魅力を探求しました。
このシリーズは全5回にわたり、最終回となる第五夜では、斎宮跡や二見浦の夫婦岩、伊勢神宮の外宮を訪れ、伊勢信仰の深層に迫りました。
斎宮跡では、約660年間続いた斎王制度の歴史や、発掘された遺構・遺物から当時の文化や生活が紹介されました。
二見浦では、夫婦岩の間から昇る朝日が神聖視され、古代からの自然信仰が今も息づいていることが示されました。
外宮では、東向きに建てられた社殿の意味や、豊受大神を祀る背景が解説され、内宮との関係性が浮き彫りになりました。
このシリーズを通じて、伊勢路が単なる参拝の道ではなく、時代ごとの人々の信仰や暮らしが交差する文化の道であることが明らかになりました。
タモリさんの視点で描かれた伊勢の旅は、視聴者にとっても新たな発見と感動をもたらしたことでしょう。
今後、伊勢神宮を訪れる際には、斎宮跡や二見浦など、番組で紹介されたスポットを巡ることで、より深く伊勢の歴史と文化を感じることができるでしょう。
また、伊勢路の宿場町や地元グルメを楽しむことで、江戸時代のお伊勢参りの雰囲気を体験することもできます。
『ブラタモリ』の伊勢神宮への旅シリーズは、伊勢の魅力を再発見する素晴らしい機会となりました。
これを機に、伊勢の地を訪れ、歴史と文化に触れてみてはいかがでしょうか。
伊勢神宮への旅、完結編!斎宮・二見浦を巡る
斎宮跡と斎王の歴史
三重県明和町に位置する斎宮跡は、古代から中世にかけて伊勢神宮に仕えた未婚の皇女「斎王(さいおう)」が暮らした場所です。
斎王制度は天武天皇の時代(7世紀後半)に始まり、約660年間続きました。
選ばれた斎王は、京都の初斎院で1年間の潔斎生活を送り、その後、500人を超える大行列「斎王群行(さいおうぐんこう)」を組んで伊勢へ向かいました。
この旅は20日以上を要し、沿道の村々では大歓迎を受けたと記録されています。
斎宮では、掘立柱建物跡や儀式に使われた土器・青磁・白磁などの高級陶器、木簡(もっかん)、化粧道具や装飾品などが発見されており、斎宮が宗教施設だけでなく、政治や文化の中心でもあったことがわかります。
現在、斎宮歴史博物館ではこれらの出土品や再現模型を通して、当時の斎宮の姿を学ぶことができます。
また、隣接する「さいくう平安の杜」では、平安時代の宮殿の一部を復元した建物があり、訪れた人は当時の雰囲気を体感できます。
毎年秋には「斎王まつり」が開催され、斎王群行を再現した行列が町を練り歩き、古代の伊勢神宮と都をつなぐ信仰の旅路が現代にも受け継がれています。
二見浦の夫婦岩と地形の神秘
伊勢への旅の途中、斎宮跡から足をのばして訪れるのが「二見浦」です。
この地は、お伊勢参りの前に身を清める「浜参宮」が行われた場所として知られています。
二見浦の象徴とも言えるのが、大小2つの岩がしめ縄で結ばれた「夫婦岩」です。
古くから夫婦円満や縁結びの象徴として信仰を集め、今も多くの参拝者が訪れます。
夫婦岩は、男岩(おいわ)と女岩(めいわ)が並び立ち、太いしめ縄で繋がれています。
毎年5月と9月には神事によってこのしめ縄が掛け替えられ、神聖な結びの象徴が保たれています。
特に注目すべきなのは、夏至の時期にだけ見られる絶景です。
6月頃、朝日が夫婦岩の間から昇る光景は神々しい美しさで、多くの人がその瞬間を一目見ようと集まります。
この光景は、自然信仰と地形の神秘が融合した、まさに神の力を感じる時間といえるでしょう。
伊勢神宮外宮の謎
伊勢神宮の外宮(げくう)は、内宮(ないくう)と並ぶ重要な社であり、豊受大神(とようけのおおかみ)を祀っています。
外宮は、内宮に先立って参拝する「先宮(さきみや)」の習わしがあり、伊勢参りの際にはまず外宮を訪れるのが一般的です。
外宮の特徴の一つに、社殿が東向きに建てられている点があります。
これは、太陽が昇る東を向くことで、神々しい光を直接受けるという意味合いがあるとされています。
また、外宮の成立背景には、天照大神(あまてらすおおみかみ)の食事を司る神として、豊受大神を迎えたという神話があり、内宮と外宮の関係性を示しています。
このように、外宮には独自の歴史と信仰が息づいており、伊勢神宮全体の構造や配置に込められた意味を理解する上で欠かせない存在です。
伊勢路の魅力を再発見
桑名から始まる伊勢路
伊勢路の旅は、三重県桑名市から始まります。
江戸時代、熱田神宮から桑名までの「七里の渡し」は、東海道唯一の海路であり、伊勢参りの玄関口として多くの旅人が利用しました。
桑名には「伊勢国一の鳥居」と称される大鳥居が立ち、ここから伊勢神宮へと続く道が始まります。
また、桑名城跡や九華公園など、歴史的なスポットも点在し、旅の出発点としてふさわしい風情が漂っています。
宿場町の歴史と文化
伊勢路には、四日市、鈴鹿、津、松阪などの宿場町が点在し、それぞれが独自の歴史と文化を育んできました。
四日市は、江戸時代に東海道の宿場町として栄え、現在も当時の面影を残す町並みが魅力です。
鈴鹿市神戸の三差路には、江戸時代の旅人を迎えた老舗旅館「油伊旅館」があり、当時の建築様式を今に伝えています。
津市では、築城の名手・藤堂高虎が築いた津城があり、城下町としての歴史を感じることができます。
松阪市は、江戸時代に商人の町として栄え、現在も松阪商人の邸宅や資料館が残り、当時の繁栄を物語っています。
地元グルメの魅力
伊勢路の旅では、各地の地元グルメも楽しみの一つです。
桑名の焼きハマグリは、木曽三川の淡水と伊勢湾の海水が混ざり合う環境で育ったハマグリを使用し、柔らかく旨味のある味わいが特徴です。
鈴鹿市の名物「とんてき」は、厚切りの豚肉をにんにくと濃口しょうゆベースの特製ソースで焼き上げた料理で、ボリューム満点の一品です。
また、伊勢路は「餅街道」とも呼ばれ、多くの名物餅が存在します。
お福餅、なが餅、立石餅、けいらん、へんば餅、二軒茶屋餅、安永餅、赤福餅など、各地で個性豊かな餅が旅人を迎えてくれます。
タモリさんの視点で見る伊勢路
地形と歴史の関係
『ブラタモリ』では、伊勢神宮の内宮が河岸段丘の上に位置していることが紹介されました。
この地形は、五十鈴川の流れによって形成されたもので、古代から神聖な場所とされてきました。
また、伊勢路沿いの地形も、旅人の往来や宿場町の発展に大きな影響を与えており、タモリさんは地形と歴史の密接な関係に注目していました。
現地の人々との交流
番組では、タモリさんが地元の人々と交流する場面が多く見られました。
四日市市では、東海道と伊勢路の分岐点となる三差路を訪れ、地元の方々から当時の旅人の様子や町の歴史について話を聞いていました。
また、桑名市では、地元の名物である焼きハマグリを楽しみながら、地域の食文化について学んでいました。
歴史的な建造物の探訪
タモリさんは、伊勢路沿いに残る歴史的な建造物にも注目していました。
津市では、江戸時代の宿場町の面影を残す建物や、松阪市では、松阪商人の邸宅などを訪れ、それぞれの建物が持つ歴史や背景について解説していました。
これらの建造物を通じて、伊勢路の歴史と文化の深さを感じ取ることができました。
まとめ
『ブラタモリ』の「伊勢神宮への旅」シリーズは、2025年4月5日から5月10日まで全5回にわたり放送され、ついに完結を迎えました。
このシリーズでは、タモリさんが三重県桑名市から伊勢神宮までの約90kmの道のりを歩き、伊勢路の歴史や文化、地形の魅力を探求しました。
最終回となる第五夜では、斎王が暮らした「斎宮跡」や、禊の地「二見浦の夫婦岩」、そして伊勢神宮の外宮を訪れ、伊勢信仰の深層に迫りました。
斎宮跡では、約660年間続いた斎王制度の歴史や、発掘された遺構・遺物から当時の文化や生活が紹介されました。
二見浦では、夫婦岩の間から昇る朝日が神聖視され、古代からの自然信仰が今も息づいていることが示されました。
外宮では、東向きに建てられた社殿の意味や、豊受大神を祀る背景が解説され、内宮との関係性が浮き彫りになりました。
このシリーズを通じて、伊勢路が単なる参拝の道ではなく、時代ごとの人々の信仰や暮らしが交差する文化の道であることが明らかになりました。
タモリさんの視点で描かれた伊勢の旅は、視聴者にとっても新たな発見と感動をもたらしたことでしょう。
今後、伊勢神宮を訪れる際には、斎宮跡や二見浦など、番組で紹介されたスポットを巡ることで、より深く伊勢の歴史と文化を感じることができるでしょう。
また、伊勢路の宿場町や地元グルメを楽しむことで、江戸時代のお伊勢参りの雰囲気を体験することもできます。
『ブラタモリ』の伊勢神宮への旅シリーズは、伊勢の魅力を再発見する素晴らしい機会となりました。
これを機に、伊勢の地を訪れ、歴史と文化に触れてみてはいかがでしょうか。
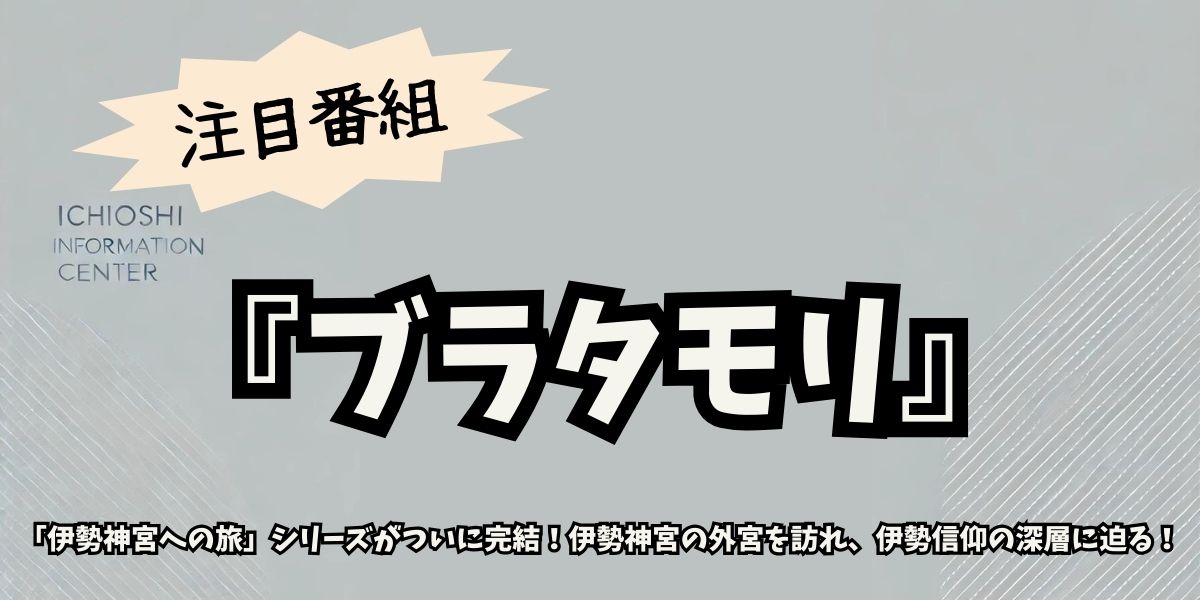
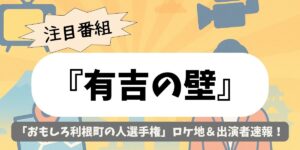

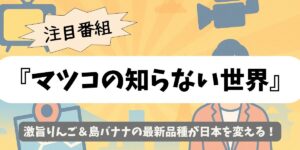
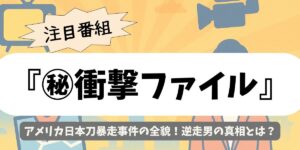



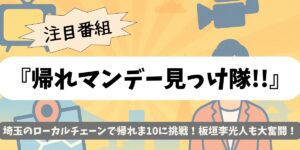
コメント