テレビ東京のバラエティ番組『有吉の深掘り大調査』では、2025年8月7日(木)18時25分~20時58分放送回にて、石川県の山奥にある“小さな秘境集落”を舞台に、35年ぶりとなる赤ちゃんの誕生, いわゆる「秘境ベイビー」の存在に迫りました。
番組では定点カメラ20台を設置し、近藤さん一家の暮らしのリアルな日常を長時間にわたって撮影。
田んぼで泥遊びをする子どもたちの姿や、親が敢えて手出しを控えて子どもに考えさせる育児スタイル、さらには民泊を通した家族の生計と教育にも肉薄しています。
視聴者はこの番組を通じて、都市部では得られない“自然と共に育つ”環境の中で、一家がどのように暮らし、子育てし、地域と関わっているのかを知ることができます。
特に、「縁もゆかりもない場所への移住」「持続可能な暮らしの構築」「幼い子どもが実際に家業を学ぶ」様子など、複数のテーマが交差する内容は、検索ユーザーが求める情報と完全に一致しています。
本記事では、番組で明かされた最新の事実をベースに、秘境で誕生した赤ちゃん、その背景にある移住と暮らし、育児の姿、そして地域活性化への可能性までを体系的に整理し、あなたの知りたい「有吉の深掘り大調査 石川県 秘境ベイビー」の全貌に迫ります。
秘境ベイビーとは何か?番組内容の全貌

35年ぶりの赤ちゃん誕生、集落の背景
石川県の山奥にあるごく小規模な集落では、実に35年ぶりとなる新生児が誕生しました。
近藤さんご一家が移住するまでは、若い世代の定住がなく、地域としても子どもの声が途絶えていたのです。
この希少な「秘境ベイビー」の誕生は地域にとって歴史的な出来事であり、番組ではその背景として過疎化や少子化が進む地方集落の現状を丁寧に描きました。
自然に囲まれた環境で育つこの赤ちゃんの存在は、まるで地域再生の象徴として取り上げられました。
定点カメラ20台で密着撮影された日常風景
番組では定点カメラ20台を使用し、近藤さん一家の暮らしを長時間にわたって記録しました。
朝の田んぼ、日中の庭先、夕暮れ時の食卓の風景など、普段とは異なる視点から日常に潜む子育てのリアルが映し出されます。
機械的な撮影手法ながら、生活の息づかいや自然の音がそのまま伝わり、出演者や視聴者にも強い印象を与えました。
電気や自動化よりも、人と自然とが共存する暮らしの豊かさを静かに伝える映像表現が印象的でした。
田んぼで泥遊び、自然と共に育つ姿
番組の中で特に注目されたシーンが、赤ちゃんや4歳の長男が田んぼで泥遊びに興じる映像です。
親が手を出さず自然を通じて子どもが自ら学ぶ、という子育て方針が明確に描かれました。
田んぼという自然環境が遊び場となり、五感を刺激しながら成長する姿は、多くの視聴者に「自然の中で育つ」という価値を伝えました。
また、親は必要以上に手を出さず、子ども自身に考えさせる方針を取っている点も、教育的視点から注目されています。
こうした育児スタイルは都市部では珍しく、「考える力」を自然環境から引き出す育児として紹介されました。
近藤さん一家の移住と暮らし

千葉出身一家が縁もゆかりもなく移住した理由
近藤さん一家は、千葉県での暮らしから一転、石川県の山奥に移住しました。
その決断には「自然環境を子育てに活かしたい」という強い思いが背景にあります。
千葉での都市型生活に限界を感じていた父母は、子どもを伸び伸び育てられる環境を求め、別段つながりのない地域をあえて選びました。
番組では「縁もゆかりもない土地であえてゼロから始める」という挑戦のプロセスを丁寧に描き、移住決意に至った心情や情報収集の過程が紹介されました。
より自由で自然に寄り添う暮らしを求めた結果、秘境での生活が選ばれたのです。
集落での民泊運営と収入源の仕組み
移住後、近藤さん一家は地域の民泊事業を開始しました。
人口が少ない集落では観光需要は限られているものの、自然体験を求める来訪者に向けて、民泊を通じた交流機会を提供しています。
家族は掃除・ゲストの案内・受付といった業務を分担し、特に4歳の長男も「掃除・案内・受付係」を務め、現場で仕事の流れを学んでいる姿が印象的に映されました。
民泊収入は家計の柱となり、地域資源を活かしながら持続可能な暮らしを支えています。
4歳長男が働く「掃除・案内・受付係」という教育
番組では、幼い長男が家業の民泊に「スタッフ」として参加する様子に焦点が当てられました。
父母は長男に「ただ同行させる」のではなく、実際に掃除・案内・受付という業務を任せることで、子ども自身が責任を持って動く経験を積ませています。
その中で「おもてなしの気持ち」や「来訪者への配慮」を自然に学び取る教育スタイルが映され、幼少期から現場を通じて働くことの意義を体験させる独特の育児方針が伝わっています。
この家庭内の教育環境は、自然や地域コミュニティと連動した実践型の教育として注目されました。
秘境ならではの子育ての特徴

親が手助けせず「考える力」を育む育児方針
番組で特に強調されたのは、親が子どもの行動に過干渉せず、自ら考えさせる育児手法です。
近藤さん夫妻は、子どもが自分で判断し行動するプロセスを尊重し、失敗も含めて成長の一環と見なしています。
泥んこの田んぼ遊びの際、子どもがどうすれば安定して歩けるか、自分で模索している場面が繰り返し映されました。
親は転落や危険性がない限り、あえて介入せず、子どもの五感と判断力に任せることで「思考力」と「自立心」を自然に養う環境を整えています。
自然遊びと地域に根ざした生活体験
秘境という立地の特性を活かし、子どもたちは四季折々の自然の中で育ちます。
田んぼや小川、森といった環境が日々の遊び場であり、獲物の虫や水の流れ、土の温度といった自然現象を肌で感じながら学びます。
番組では、赤ちゃんが手を泥の中に入れて感触に驚くシーンや、兄弟がカエルを観察する姿など、自然との相互作用を通して感覚や好奇心が刺激される様子が映されていました。
地域の行事や散策と連動しながら、豊かな環境が「体験学習」の場として機能していることが印象的でした。
地域社会との関係と子どもの社会性形成
集落に住む住民との日常交流も、子どもの成長に大きく影響しています。
訪れる民泊ゲストの接客を通じて、子どもは自然に「挨拶」「気配り」「他者との関係構築」を学びます。
4歳の長男が「掃除・案内・受付係」としてゲストと接する場面を通じて、おもてなしの基礎や協調性、責任感を楽しみながら体得している様子が紹介されました。
地域の高齢住民との交流も見られ、世代間の関わりが子どもの視野と社会性を広げる役割を担っていることがうかがえます。
番組に見る地域活性化の可能性

秘境集落に光を当てるメディアの力
テレビ東京の「有吉の深掘り大調査」では、35年ぶりに赤ちゃんが誕生した石川県の秘境集落を取り上げ、20台の定点カメラで密着しました。
このような映像取材により、普段メディアで取り上げられない山間部の生活が視聴者の目に触れる機会が生まれます。
地域のリアルな暮らしが大々的に紹介されることで、秘境というイメージが「哀れ」や「閉鎖」ではなく、「自然と共に育つ子育ての場」「これからの可能性ある移住地」として再評価される契機となります。
移住促進と後継者問題へのヒント
番組で紹介された近藤さん一家のような移住者が、地域の未来を形づくる存在となります。
千葉出身ながら縁もゆかりもない土地を選び、そこで子育てと民泊を通じた生活基盤を築いた姿勢は、ほかの地方でも注目されるモデルケースです。
過疎化が進む地域において、新たな移住のあり方や地域の経済・コミュニティを再生する手がかりとして、番組はわかりやすく示しています。
視聴者が感じる共感と地域応援の動機
番組で描かれた自然と共に育つ家族の暮らしや、長男が民泊業務を担う教育的場面は、多くの視聴者の共感を呼びました。
テレビで視覚的に紹介されることで、視聴者自身が「この土地を応援したい」「地方移住に関心が湧いた」と感じる動機が生まれます。
口コミやSNSでの拡散、番組公式アカウントなどを通じた情報共有が、地域への注目を加速させ、潜在的な移住候補者や地域支援者を巻き込むきっかけとなります。
まとめ

番組 「有吉の深掘り大調査」(2025年8月7日放送)では、石川県の山奥にある“秘境集落”で、35年ぶりに誕生した赤ちゃん=「秘境ベイビー」に定点カメラ20台が密着した様子を通じ、自然と都市の価値観の違いや地域の未来について深掘りされました。
この特集は、ただ単に珍しい出来事を伝えるのではなく、自然環境で育つことの意味、親が干渉を控える独特の子育て手法、民泊を活用した持続可能な暮らし、地域社会との共生から生まれる成長の瞬間など、多角的なテーマが交差しています。
例えば、田んぼで泥遊びをする子どもたちの姿は、都市生活とは異なる“自ら身体を使って考える力を育む教育”の場として捉えられており、観る者に強い印象を残しました。
また、千葉出身で縁もゆかりもなかった近藤さん一家が、地域資源である自然と共に移住し、民泊事業を核に暮らしを築いた点は、地方移住と地域活性の新たなモデルとして示唆的です。
本記事で掘り下げたような秘境ならではの育児法や、地域との関係性、そしてメディアを通じて生まれる「視聴者の共感と応援の輪」は、現代の多くの地方集落が抱える課題—少子化・過疎・後継者不在—への一筋の光とも言えます。
筆者としては、この番組が提供した情報を通じて、「移住は特別ではなく、選択肢の一つ」として捉え直せる視点が広がることに意義を感じています。
自然の中で子育てしたい人、地域活性に関心を持つ人、あるいはメディアの影響力がコミュニティにどう作用するのかを知りたい人にとって、有益な内容であると思います。
読者の皆さんがこの特集を通じて、石川県の秘境を知り、地域の未来や家族のあり方を改めて考えるきっかけになれば幸いです。
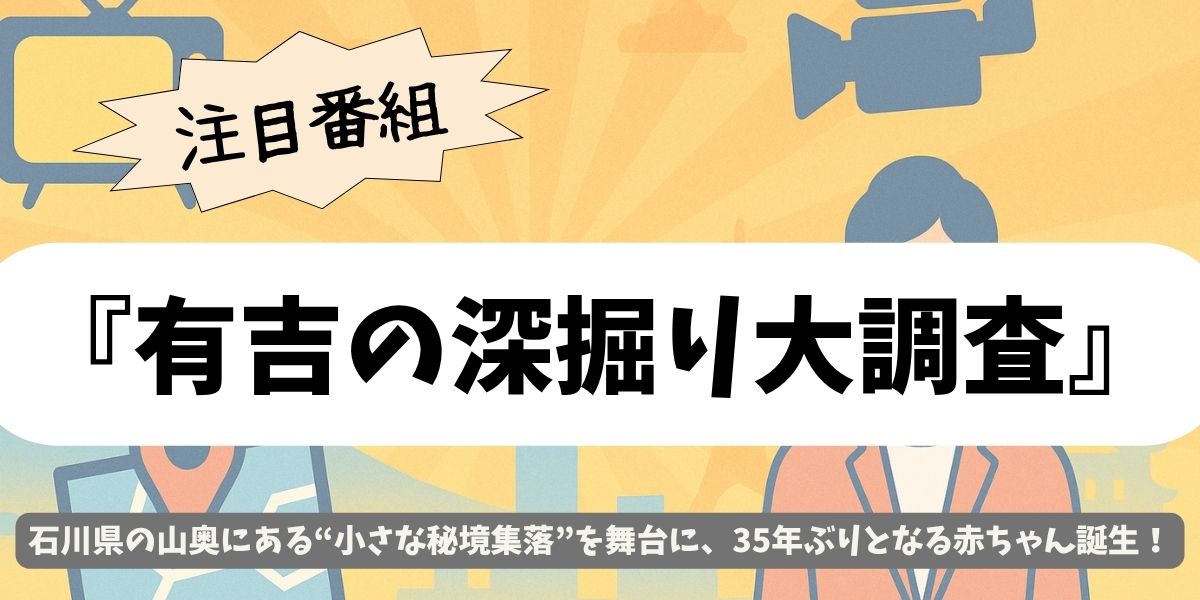
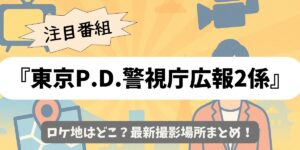
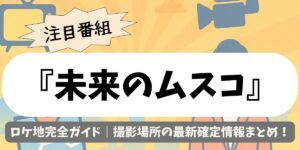


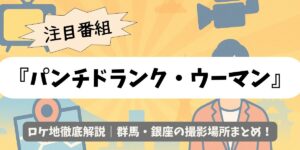
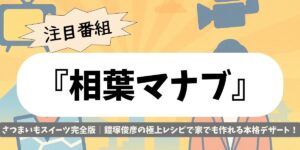
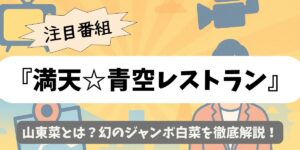
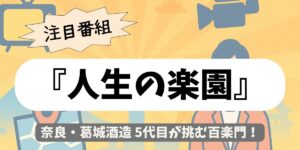
コメント