秋の風がほんのり冷たさを帯び始める季節、「相葉マナブ」では2025年10月12日放送回にて埼玉県松伏町の落花生“おおまさり”を題材に、収穫から絶品レシピまでを一気に紹介すると公式PRで告知されました。
番組側があらかじめ明かしているところによれば、今回取り上げる品種「おおまさり」は、粒が大きく甘みが強い性質を持つ、ゆで豆向きに優れた落花生だとされています。
一方、この「おおまさり」という名前自体は千葉県で育成された極大粒ゆで豆品種であり、既存のゆで用落花生「郷の香」と比べて実の大きさが約2倍、収量も1.3倍以上の実績データが公的資料に残っています。
ただし、こうした魅力がある一方で、番組制作側としては「如何に家庭でも再現できる調理法を示すか」という視点も欠かせないはずです。
そのため、今回の放送では「味噌ピーナッツ」「落花生のコロッケ」「殻ごと煮る味噌汁」「落花生と小松菜の炒め物」といった、手順の明快な料理がラインナップされていることが予告されています。
では、この放送回で得られる“松伏町×おおまさり”の情報、さらにおおまさりという品種そのものの特徴・栽培事情・歴史・家庭での楽しみ方をすべて繋ぎ合わせ、あなたが今すぐ活用できる「落花生おおまさり百科」をお届けします。
最新放送まとめ:2025/10/12 松伏町×おおまさり

放送日時・出演者・ロケ地の概要
2025年10月12日(日)18:00〜18:56 に放送された「相葉マナブ」では、埼玉県・松伏町の農家を訪れて「落花生」を収穫・料理する回がテーマでした。
番組では、相葉雅紀(嵐)をはじめ、小峠英二・澤部佑が出演。ナレーションを神奈月と杉本るみが担当しました。
収穫対象の品種は「おおまさり」。
その場で農家の方から品種の特徴を聞き、収穫作業も体験しています。
紹介レシピ一覧(味噌ピーナッツ/落花生コロッケ/殻ごと味噌汁/小松菜炒め)
今回の放送では、「おおまさり」を使った複数のメニューが披露されました。番組公式PRによれば、主に以下の料理が登場しています。
- 味噌ピーナッツ
- 落花生のコロッケ
- 殻ごと煮る落花生の味噌汁
- 落花生と小松菜の炒め物
これらの料理は、落花生の持ち味(甘み・風味・食感)を活かすことを意図して選ばれており、素材をシンプルに扱うものもあれば、手を加えておかずに仕立てるものも含まれています。
番組公式サイトには、これらのレシピを後追いで確認できることも記載されています。
公式リンク・見逃し対策(番組サイト・PRページ・SNS)
相葉マナブの公式サイトでは、当該放送回の概要や使用したレシピの一部を閲覧できるよう案内されています。
また、PR用ページ「相葉マナブ 埼玉県松伏町の落花生で絶品レシピ!」では番組放送内容や紹介料理のラインナップを要点としてまとめています。
さらに、X(旧 Twitter)や Instagram などの番組公式アカウントでも、放送直後に告知や予告ツイートが出されており、フォローしておけば最新情報を早めに得られます。
見逃し視聴の手段として、テレビ朝日系列の見逃し配信サービスや番組の見逃しページがリンクされているケースが多いため、公式サイトからのリンクをチェックするのが推奨されます。
“おおまさり”とは:特徴・旬・産地の事実

粒の大きさ・甘み・ゆで向きという特性
「おおまさり」は、千葉県が育成したゆで落花生向けの品種で、従来品種と比べて極めて大粒であることが最大の特長です。
千葉県の公式ページによれば、「郷の香(さとのか)」の約2倍の子実重量を持ち、ゆで豆に適した柔らかさと甘みを兼ね備えているとされています。
Wikipedia にも、「甘みが強く実がやわらかいので、ゆで豆に最適である」と明記されており、食味面での強みが公的な資料でも裏付けられています。
また、千葉県の品種解説では、おおまさりが「ナカテユタカと極大粒品種を交配して育成された」ことが記されており、交配育種技術によって粒の肥大化とともに食味が向上された系譜が確認できます。
さらに、千葉県農林水産研究センターなどの技術資料では、「子実が柔らかく、甘みがあり、ゆで豆に適する」性質が強調されており、ゆで落花生として扱う際にその特徴を最大限に活かせる品種とされています。
ただし一方で、「大株で栽培しづらい」「病気に弱い」などの課題も指摘されています。千葉県が発表する「おおまさりネオ」の育種背景紹介には、おおまさり原品種の短所(病気耐性・草勢安定性など)を改善する目的があったと記されています。
このように、「大きさ・甘み・ゆで適性」はおおまさりの主要な強みでありつつ、栽培の難しさという“陰”の側面も持ち合わせているのが現実です。
旬・収穫時期と生落花生の出回り方
「おおまさり」の旬と収穫時期を把握することは、最も風味を活かすレシピ(例:ゆで落花生)を楽しむうえで非常に重要です。
千葉県公式「落花生栽培の手引」によれば、ゆで豆用の落花生は「開花期から約85日」を目安に収穫日を決めるとされており、おおまさりについてもこの基準が適用されることが示されています。
さらに栽培・出荷ガイドでは、おおまさりは“晩生品種”として扱われ、他品種より少し遅めの時期に収穫が行われることも記されています。
実際、落花生属の栽培事情を扱うサイトでは、おおまさりの収穫・新豆出荷時期を「9月初旬〜9月下旬」が一般的な開始時期とし、早い年では9月中旬から流通が始まるという記録があります。
また、観光農園やイベント案内では、千葉県の“落花生狩り”を9月下旬〜10月中旬頃に実施するケースが多く、おおまさりが市場に並ぶピーク期と重なることが多いとされています。
ただし、気候や栽培条件によって多少前後することがあり、試し掘りを行い、さやの網目がはっきりしているものを目安とするとよい、という農業 Q&A も存在します。
このように、おおまさりの“旬”は主として9月~10月上旬に集中しており、新豆(生の状態で出荷される落花生)はこの期間に最も多く出回る傾向があります。
主要産地のトピック(千葉・埼玉などの生産と流通)
千葉県は落花生の主要産地として知られており、「おおまさり」も千葉県内で栽培される代表的なゆで豆用品種の一つです。
千葉県の落花生品種紹介図鑑では、千葉半立・ナカテユタカ・郷の香・おおまさり・Qなっつの5品種を重点に扱っており、おおまさりはその中でゆで豆用途として位置付けられています。
千葉県庁の資料(千葉県育成品種案内)でも、おおまさりが「平成18年育成、平成22年に品種登録された」晩生・極大粒ゆで豆向け品種であると紹介されており、県内の普及を目指している背景がうかがえます。
なお、千葉以外の地域でもおおまさりを栽培・流通させようとする動きがあるようで、農産物直販所や特産品ショップでは「千葉産おおまさり」「埼玉・落花生おおまさり」などの表示が見られることがあります。
ただし、流通規模としては千葉産が主力となるケースが目立ちます。
また、JA(農協)系が地元産品を宣伝する際、「おおまさり」の入荷案内を出すケースがあります。
たとえば、JAマインズでは「2023年9月20日付」で“入荷開始”の案内とともに、おおまさりの特徴やおすすめの食べ方を紹介しています。
こうした情報を総合すると、おおまさりは千葉を中心に栽培・流通し、他県(たとえば埼玉県など)でも栽培導入の動きがあるものの、流通量の面では千葉県産の比率が高い状態と見られます。
相葉マナブの過去回と系譜で学ぶ

2023年「八街の落花生」回とレシピの傾向
2023年放送の「相葉マナブ」では、千葉県八街市(やちまた市)を訪れて落花生をテーマにした回がありました。
番組バックナンバーによれば、この回で扱われた落花生品種として“おおまさり”が取り上げられ、すべて手作業で収穫をする様子や仕分け作業、それに伴う調理法が紹介されています。
具体的なレシピ例としては、「落花生の春巻きスティック」「落花生餃子」「落花生の黒アヒージョ」「落花生ピラフ」などが登場しており、落花生の風味を生かしながらアレンジ性の高い調理法が試されていました。
この回から見られる傾向として、“落花生そのものを主役にする料理”という方向性と、一手間加えて副菜やおつまみとして楽しむ調理を組み合わせる構成である点が挙げられます。
たとえば、春巻きスティックや餃子といった料理は “落花生そのもの” を特有の食感・風味で活用する一方で、黒アヒージョやピラフはソースや油を伴って別素材との絡みを出す手法です。
また、この過去回では、調理前後に農家の方が落花生の状態を確認する(中実の腐敗チェック、サイズ選別など)映像も挿入されており、生産から料理までを “つなげて見せる”ストーリー構成が取られていました。
2021年「おおまさりネオ」紹介回の位置づけ
2021年10月3日放送回において、「おおまさりネオ」という品種が「相葉マナブ」で紹介された記録があります。
千葉県の落花生販売店のブログで、番組でこの品種が取り上げられたことが紹介されています。
この放送では、「おおまさりネオ」が番組の枠内で紹介され、その食味や扱いやすさが視聴者へアピールされました。
石井進商店のブログ記事によれば、番組をきっかけに「おおまさりネオ」を求める声が上がったという反響が記されています。
こうした回は、単なる調理紹介にとどまらず、新しい改良品種を視聴者に広く知ってもらう役割を果たしており、2025年の「おおまさり」特集へとつながる系譜を形作っています。
つまり、おおまさり/おおまさりネオという品種群を段階的に視聴者に馴染ませる構成がなされてきたとも言えます。
定番レシピの系譜(春巻きスティック/茹で落花生 ほか)
相葉マナブでは、落花生をテーマにする回で“定番化したレシピ”がいくつか見られます。
たとえば、春巻きスティックは、2023年の八街回で紹介されており、今も落花生料理の代表例として引用されることがあります。
また、茹で落花生(殻ごと塩ゆで)そのものは、番組内で度々登場する基本料理です。
たとえば2024年の放送回で「茹で落花生」がレシピとして紹介され、鍋で塩と水でゆっくり40〜50分程度茹でるレシピが提示されています。
さらに、担々麺に落花生ペーストを使うアレンジレシピも過去回で登場しており、シンプルなゆで落花生以外の応用メニューも定着傾向にあります。
2019年放送回では、八街の落花生を使った「落花生の担々麺」が例として紹介されていた記事があります。
これらを通して見える点は、「落花生を素材として活かすだけでなく、他メニューへ応用するアプローチ」が番組として好まれており、“定番 → 変化球” の系譜が明確に描かれていることです。
家で楽しむ“おおまさり”:選び方・茹で方・保存

生落花生の選び方(鮮度・さやの状態)
「おおまさり」をおいしく楽しむためには、まず生落花生の選び方が非常に重要です。以下のポイントを意識するとよいでしょう。
- さや(殻付きの実の外側)の網目と色合い
さや表面に網目(いわゆる“網目模様”)がはっきり出ているものを選ぶと、中の実の成育が十分進んでいる可能性が高くなります。
網目が浅かったり、模様が不明瞭なものは未成熟の可能性があります。
こうした網目の観察は、千葉県などの落花生栽培情報でも選別ポイントとして紹介されています。 - 殻の堅さと変色の有無
殻があまりにも柔らかく、薄く感じるものは内部の実が乾燥していたり品質が落ちかけている可能性があります。
一方、殻に黒ずみや斑点が見られても、殻だけの変色であれば中身に影響がないこともあります(ただし中身を切って確認したほうが安心です)。
落花生専門店の情報でも、殻の黒変は商品表面の条件として注意事項として触れられています。 - 触ってみる重さ感
さやを持ったときに「ずっしり重く感じる」ものを選ぶとよいでしょう。
これは中の実がしっかり詰まっている証拠です。軽く感じるものは中身が乾燥して痩せている可能性があります。 - 販売時期と販売方法
おおまさりの生落花生は、主に **9月初旬〜10月末** 頃の期間限定で出回ります。
また、通販で購入する際には「生落花生」か「茹で済み」かをよく確認することが重要です。
生落花生であれば冷蔵便で届くことが多く、すぐ調理できる状態のものを選ぶべきです。 - さや付き vs. さやなし
さや付きのまま保存された品は、実を乾燥・酸化から保護できるため、時間的余裕がある場合にはさや付きの品を選ぶとよいでしょう。
ただし、保存期間が長いほどリスクも上がるため、できるだけ早く調理する前提で購入するのが望ましいです。
これらを組み合わせて、「見た目」「手触り」「出荷時期」の三点をチェックすることで、品質の良いおおまさり生落花生を選べる可能性が高まります。
失敗しない“相葉マナブ式”基本の茹で方(時間・塩加減・圧力鍋)
「相葉マナブ」で紹介される落花生レシピの傾向を踏まえつつ、最新調理情報を参照して、失敗しにくい基本的な“ゆで方”を以下に示します。
- 洗って汚れを落とす
まず、さや付きのまま流水で軽く洗い、泥やほこりを取り除きます。
さやの隙間や継ぎ目に土やゴミが残っていると味を損なう恐れがあります。
デリッシュキッチンの基本レシピでも、この洗浄工程を最初に挙げています。 - 水と塩の割合
鍋におおまさり・水・塩を入れる際、水の重さに対して2〜3%程度の塩を目安に加えるのが一般的です。
例えば、1.5 Lの水に対して塩45 g(=3%)という配合がよく紹介されています。 - ゆで時間と火加減(水から加熱)
鍋に材料を入れて中火で加熱し、沸騰したら弱火に落とし、30分程度ゆでる方法が一般的な基準です。
特に粒が大きい「おおまさり」の場合は、30分程度では硬さが残ることもあるため、ゆで時間をさらに+5~10分程度延長することも視野に入れます。
ゆでている間、水が落花生よりも低くなるようなことがあれば、適宜沸騰水を足して水位を維持します。 - 余熱でじっくり火を通す
ゆでが終わったら火を止め、そのまま10分程度放置(蒸らし時間)して余熱で仕上げる方法が多く紹介されています。これにより塩気が内部にも行き渡り、風味が増すという効果があります。 - 圧力鍋を使う時の手順
圧力鍋を使えば大幅に時間を短縮できます。
沸騰後に高圧状態になったら弱火にし、10分程度加圧調理し、その後圧力が下がるまで蓋を開けずに放置するという方法が一般的です。
ただし、圧力鍋使用では火加減・蒸らし時間の管理が重要で、少しでも過加熱になると実が煮崩れしやすいため、取扱説明書や試作を基に加減を調整することが望まれます。 - 最終チェックと調整
ゆで終わったら一粒を割って中をチェックし、硬さが残っていれば追加で数分ゆでるなど調整します。
好みに応じてゆで時間を微調整するのがコツです。
また、ゆであがったらすぐに水にさらさず、温かいうちに殻をむくと甘味や風味がよく感じられます。
この手順を守れば、「相葉マナブ」で紹介されそうな質感と風味の近いゆで落花生が実現しやすくなります。
保存方法とアレンジ(作り置き・お弁当・リメイク)
ゆでた後や作り置きを考える際の保存法と活用アイデアも重要です。
最新情報をもとに実用性の高い方法を紹介します。
保存方法
- 茹でたものの冷蔵保存(短期間)
茹で落花生は日持ちがしないため、多くの情報源では冷蔵保存で2〜3日内に食べ切ることを推奨しています。
この場合、完全に粗熱を取ってから水気を拭き取り、密閉容器またはラップで包んで保存するのがよいです。 - 冷凍保存(長期保存)
茹でたおおまさりは冷凍すれば約1か月程度の保存が可能という情報が複数あります。
具体的には、茹でた後に殻付きまたは殻を剥いた状態で、キッチンペーパーで水気を拭き取り、冷凍用保存袋に入れて空気をできる限り抜き、平らにして冷凍する方法です。
津田農園のブログでも、茹でたものを急速冷凍する手法を紹介しており、再度調理する際にはレンジまたは加熱で解凍・加熱する方法が記載されています。
解凍時は電子レンジ(600Wで1〜2分程度)で加熱したり、冷蔵庫で自然解凍してから加熱する方法が一般的です。
ただし、殻付き保存の場合、殻内部に霜が付くと風味を落とす原因になるため、殻を剥いてから冷凍することを勧める情報源もあります。
また、冷凍した生落花生をそのまま熱湯で再加熱する方法を提案する例もあり、凍ったまま調理器具にかけることで風味をなるべく保持する工夫も見られます。 - その他注意点
生落花生のまま長期間放置すると酸化や雑味が出やすいため、購入後すぐ調理することが望ましいという情報も多く見られます。
また、保存時は温度変化や湿気を嫌うため、冷蔵庫内でも安定した温度帯(野菜室や冷蔵室)を選び、湿度管理に配慮するとよいでしょう。
アレンジ・リメイク例
- お弁当での利用
茹で落花生を殻を剥いて少量ずつ小分けし、和物やナッツ風味の副菜としてお弁当に混ぜると、食感と風味のアクセントになります。
冷蔵保存なら2〜3日以内に消費できる範囲での使用がよいでしょう。 - 炊き込みご飯・混ぜご飯
冷凍保存したおおまさりを、米と一緒に炊き込んだり、炊き上がったご飯に混ぜ込んだりするレシピが、保存性と風味を両立させる応用法として紹介されることがあります。 - 炒め物や和え物
ゆでたおおまさりを野菜や肉、調味料と合わせて炒めものに使用することで、落花生の香ばしさと甘みを取り入れた一品に変化させられます。
実際、番組放送回でも落花生を他食材と組み合わせた料理が紹介されている点と整合性があります。 - ペースト・ソース利用
ゆでたおおまさりをすり潰してペースト状にし、ドレッシングや和え衣のベースとして活用する方法も考えられます。
ただし風味の調整(塩気・油分など)は個別に調整が必要です。
これら保存方法やアレンジを組み合わせることで、収穫期だけでなく長期にわたって「おおまさり」の風味を家庭で楽しむことが可能になります。
まとめ

埼玉・松伏町で収穫した「おおまさり」を主役に据えた2025年10月12日放送回は、“ゆで落花生に最適な極大粒”という品種特性を、家庭でも再現しやすい料理で確かに体感できる内容でした。
公式予告とPRでは、味噌ピーナッツ/落花生コロッケ/殻ごと煮る味噌汁/小松菜炒めが並び、収穫〜調理の流れが示されています。
放送の基本情報とメニューはテレビ朝日の公式ページと番組サイトで確認できます。
品種の事実に立ち返ると、「おおまさり」は“郷の香の約2倍サイズ”“甘みが強く柔らかい”という明確な優位性があり、ゆで豆用途で真価を発揮します。
千葉県の公的資料がこの特性を明示しており、系譜上は改良品種「おおまさりネオ」への置き換えも進む流れです(栽培のしやすさや病害抵抗性が改善)。
したがって、視聴後に入手するなら“生の旬”に狙う・産地表示を確かめる・粒の充実を示す網目のはっきりした殻を選ぶ——という基本が、番組の体験価値をそのまま家庭で再現する近道になります。
調理と保存は“塩2〜3%・弱火で約30分+余熱10分”の基準がまず外しません。
粒が特大のため硬さを見ながら数分ずつ延長し、ゆでたてを割って甘みを確かめる。
食べ切れない分は水気を拭いて密閉→冷凍し、必要量だけ都度解凍すれば、放送レシピの副菜・主菜への展開がぐっと楽になります。
これらの手順は大手食品メーカーの基礎解説や専門店の指南とも整合しています。
最後に筆者の所感です。今回の「相葉マナブ」は、産地の“いま”と品種の“強み”を、家庭のキッチンで再現可能な設計で橋渡ししてくれました。
入手は9〜10月の生の旬が最適ですが、冷凍の活用で季節を越えて楽しめます。
まずは基本の塩ゆでで甘みと食感を掴み、次に味噌ピーナッツやコロッケのように“油や発酵のコク”を重ねる——この二段構えが「おおまさり」の魅力を最大化します。
番組のレシピ名や放送回の確認は公式サイト、品種の裏付けは千葉県の資料を手元に置いておくと、迷いなく実践できます。
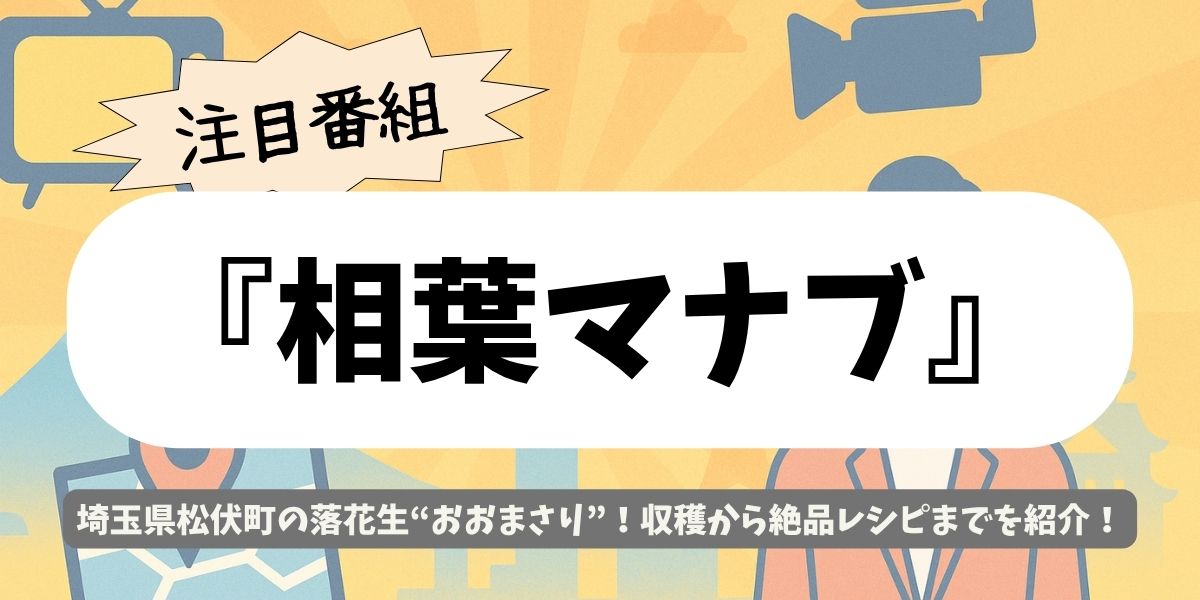



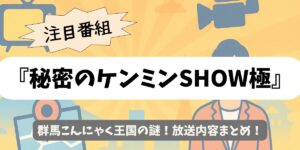
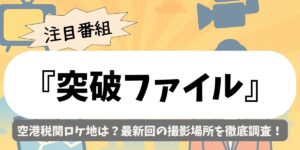
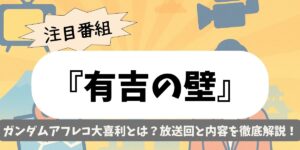
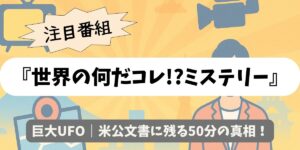
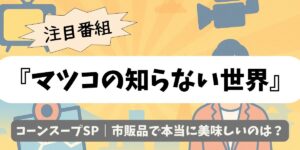
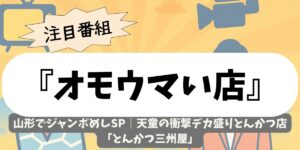
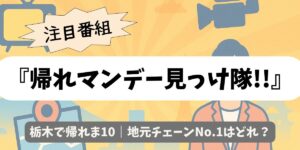

コメント