「アンビリバボー ビッグフット 遺体」で検索しているあなたが知りたいのは、本当に“遺体”は見つかったのか/科学的に裏づけはあるのか/番組で放送される情報はどこまで事実なのか——この3点だと思います。
まず前提として、フジテレビ『奇跡体験!アンビリバボー』は本日2025年10月15日(水)放送回の番組案内で、“日本のテレビ独占取材”“ビッグフットの遺体が発見” “驚愕のDNA鑑定”と強く打ち出しています。
番組表や系列局の告知でも同趣旨の文言が確認でき、テレビ側が話題性の高いテーマとして扱っているのは確かです。
では、その“遺体”とは何か。
鍵になるのが「Dack(ダック)」と呼ばれる標本で、発見者を名乗るチャールズ“スネーク”スチュアート氏がニューヨーク州アディロンダック山地(オールドフォージ周辺)で発見し、2025年8月20日〜9月1日のニューヨーク・ステート・フェアで棺に横たえた状態で展示したと報じられています。
現地ローカル局WSYR(NewsChannel 9)の動画でもフェア会場の“ビッグフット展示”が紹介され、タブロイド紙『The Sun US』は身長約8フィート(約2.4m)、強い悪臭、サラナックのガレージでの保存処理(剥製化)といった具体描写を掲載しています(あくまで出展者側の説明に依拠)。
一方で、「DNA鑑定で決着」という印象を与える言説には注意が必要です。
発見者側はコーネル大学のDNAラボに持ち込んだ/獣医系ラボで“非公式確認”があったなどと語っていますが、研究者名・試験番号・報告書PDFといった第三者が検証可能な一次資料の公開は確認できません。
コーネル大学の公式発表や査読論文も見当たらず、客観的に確定できる科学的裏づけは現時点で提示されていないのが実情です。
こうした状況に対して、懐疑的な論評も目立ちます。科学コミュニケーションの立場から検証的な発信を続けるSharon A. Hill氏は、今回の展示を「金儲け目的の最新ビッグフット・ホークス(でっち上げ)」と批判し、過去の“氷漬け遺体”事件などと同様に証拠の非公開・イベント化を問題視しています。
SNSやコミュニティでも賛否が拡散しており、「まず自分の目で確かめろ」型の宣伝に対し、科学的手続き(サンプル管理・独立機関での再検査・査読公表)の不在が繰り返し指摘されています。
本記事では、番組が触れる“Dack”の実体・展示の経緯・鑑定主張を一次情報に沿って整理し、何が確認済みの事実で、何が未検証の主張かを明確に切り分けます。
番組の“盛り上げ”と科学的検証はしばしば別物です。
「面白い物語」ではなく「検証可能な事実」に軸足を置いて読み解く——そのスタンスで、あなたの問い(真偽の見極め)に直球で答えていきます。
番組の主張と報道内容

放送番組「奇跡体験!アンビリバボー」での紹介内容
フジテレビ『奇跡体験!アンビリバボー』は2025年10月15日放送回の番組案内で、「日本のテレビ独占取材!!ビッグフットの遺体がついに発見された!? 驚愕のDNA鑑定も!!」と告知しました。
福岡のテレビ西日本の番組表でも同趣旨の文言が確認でき、番組として“遺体”と“DNA”を強調していることがわかります。
ただし、これらは放送前(もしくは同日)の告知であり、科学論文や当該大学からの正式発表を意味するものではありません。
遺体と称される“ダック”の発見場所・展示情報
“ダック(Dack)”と呼ばれる標本は、ニューヨーク州北部アディロンダック山地で見つかったと主張され、2025年8月20日〜9月1日にシラキュースで開催されたニューヨーク・ステート・フェアで“遺体”として展示されたと複数の報道・告知が伝えています。
地元局WSYR(NewsChannel 9)はフェア来場者向けに“ビッグフット展示が見られる”と紹介し、タブロイド紙『The Sun US』は発見場所(オールドフォージ)、標本の搬送・保存(サラナックのガレージでの剥製処理)、棺での展示など具体的なディテールを掲載しています。
一方、こうした詳細は主に出展者側の説明に依拠しており、公的機関による現場検証の記録は示されていません。
報道媒体が伝える体長や臭気などの特徴
“ダック”の外見に関しては、身長がおよそ2.4mで全身が濃い体毛に覆われているとされ、強い悪臭がしたという証言も流布しています。
これらはオカルト誌系のウェブ記事やフェア関連の報道・紹介に繰り返し登場する描写で、展示では棺に横たえた“遺体”の周囲に演出(音響・ナレーション映像)が付されていたとの記述もあります。
もっとも、遺体の計測値や臭気に関するデータは学術フォーマットで公開されておらず、客観的な生体組織データ(採取手順、保存条件、第三者立会い、試験機関の報告書など)は提示されていません。
(参考)“DNA鑑定”とコーネル大学の扱いについての現状
出展者側は“コーネル大学で初期DNA検査を行った”“獣医系のラボで非公式に確認があった”などと発信してきましたが、具体的なラボ名・研究者名・試験番号・報告書の公開は確認できず、地域メディアや研究者コミュニティからは疑義が呈されています。
懐疑派の記事や投稿は「Cornellの正式検査は行われていない」「証拠文書がない」と指摘し、現時点で査読付きの学術発表や大学の公式声明は見当たりません。
番組視聴時は、“主張”と“検証済み事実”を明確に区別して受け取るのが妥当です。
主張側が掲げる証拠と鑑定主張
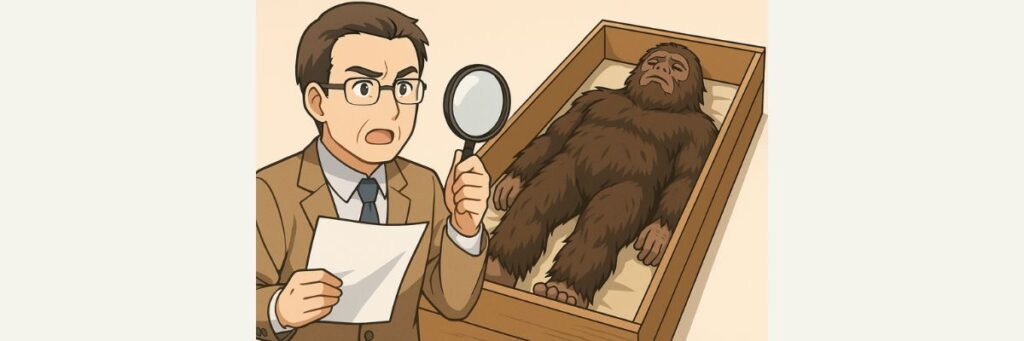
DNA鑑定を依頼したとする主張(コーネル大学関与説)
発見者を名乗るチャールズ“スネーク”スチュアート氏は、アディロンダック山地で見つけたという“遺体(通称Dack)”から採取したサンプルを大学機関に持ち込んだと主張してきました。
米紙タブロイドの報道では、「コーネル大学のDNAラボには断られたが、同大学の獣医学系ラボで“非公式に”確認があった」と語ったとされます。
しかし、研究者名・試験番号・レポート原本などの一次資料は示されておらず、大学側の正式なプレスリリースや査読論文も確認できません。
展示直前・会期中の地域メディアは「鑑定で決着」という断定を避け、“あなた自身の目で判断を”というトーンで紹介。
SNS上でも「フェアで“遺体”を見られる」という話題化と同時に、懐疑的な投稿が目立ちました。
つまり、「鑑定を出した/通った」という主張はあるものの、公的に検証可能な文書化・学術化は現時点で行われていないというのが公開情報からの到達点です。
遺体の外見・解剖的特徴・毛髪・骨格などへの言及
各報道・出展者サイト・動画から拾える外形情報はおおむね一貫しています。
“身長約8フィート(約2.4m)と説明される全身多毛の個体が棺に横たえられ、強い悪臭の痕跡が語られ、保存処理(タクソノミー)が施された”という筋立てです。
スチュアート氏は“腐敗臭を辿って発見した”“サラナックのガレージで保存作業を進めた”と説明しており、フェア会場の展示では演出映像やナレーションが付いたとも伝えられました。
もっとも、骨格計測表・毛髪横断面やキューティクル観察記録・組織の固定条件・採材ログ(誰がいつどこでどのように採ったか)といった生体資料としての基本ドキュメントは公開されていません。
そのため、現時点で外見情報は“主張者が示す視覚素材と場内説明に依拠した描写”の域を出ておらず、第三者の法医・獣医・古人類学的レビューに接続できる客観記録は見当たりません。
餌性・寄生虫の存在などから導かれる生態仮説
地域テレビ局の特集や本人サイトでは、“雑食(omnivore)”“巣作り(nesting)”といったキーワードが語られ、行動圏や生態の仮説が紹介されました。
これらは、発見者側のフィールド経験や観察談に基づく“解釈”として提示されているもので、生体試料からの寄生虫学的所見や胃内容物分析、アイソトープ比分析、マイクロCTによる歯の摩耗評価といった、実証的に生態を裏づけるデータは公表されていません。
研究者コミュニティやカルチャーメディアは、フェアの“遺体展示”が議論を呼ぶ一方、データの非公開と第三者検証不在を問題視しており、鑑定結果やサンプルのチェーン・オブ・カストディ(保全手続き)が共有されない限り、食性・習性への言及は未検証の主張に留まるという立場です。
異論・批判・科学的反証の観点

コーネル大学側の関与否定または否認報道
“コーネル大学で初期DNA検査を実施した”という主張は拡散していますが、2025年10月15日時点で大学公式のニュース/声明に当該案件の記載は見当たりません。
獣医学部(College of Veterinary Medicine)の2025年ニュースアーカイブを通覧しても、“ビッグフット”や“検査報告”に該当する告知・論文紹介は掲載されていません。
したがって、現段階で第三者が検証可能な「大学公式の関与証跡」は確認できず、「検査が行われた/認められた」という言明は未裏付けの主張に留まります。
一方、展示やエンタメ媒体の記事では、発見者側の説明として「コーネルのDNAラボには断られ、獣医系ラボで“非公式に”確認があった」といった非公式関与が語られています。
しかし、研究者名・試験番号・報告書PDF・担当部署などの一次資料は提示されておらず、地元テレビやウェブ媒体も“見て判断してほしい”という語り口に留めています。
すなわち、大学の公式検証と合致する一次情報の開示がないのが現状です。
剥製処理や保存操作の不自然性・現場即処理の技術的妥当性
“Dack(ダック)”はアディロンダックで発見後、サラナックのガレージで保存処理(いわば即席の剥製化)を進めたと説明されています。
ところが、この保存経緯は法医学・獣医学の標準的な生体試料管理(採材ログ、冷鎖、保存試薬、固定条件、汚染対策)と整合しません。
公開情報から確認できるのは“ガレージでの処置”“棺に横たえた展示”というストーリーであり、骨格計測表・毛髪横断面像・組織病理スライド・採材から検査に至るチェーン・オブ・カストディ等の基本資料は提出されていません。
こうした環境下での処理は、分解・腐敗・コンタミのリスクが高まるため、科学的鑑定の信頼性を大きく損ねます。
加えて、一般向けの剥製解説でも剥製は腐敗を“完全に止める”手段ではなく、環境条件や取り扱いによって劣化が進むことが指摘されています。
もしも初期状態が“強い悪臭のする腐敗遺体”だったなら、ガレージ環境での保存作業はDNAやタンパク質の保存性をさらに悪化させる要因になりえます。
ここから導かれるのは、展示映えを優先した演出は確認できる一方で、科学的検証に必要な手順の透明化・再現性の担保が欠落しているという評価です。
過去の“ビッグフット死骸発見”詐欺や偽装例との比較
今回の“ニューヨーク州フェアでの遺体展示”は、2008年のジョージア州「冷凍遺体」事件など、過去の“死骸”主張とパターンが重なります。
2008年のケースでは、氷の中の“遺体”が解凍後にゴム製の着ぐるみと判明。
主要メディアや通信社が“ホラ”として報じ、関係者は“悪ふざけ”を認めています。
過剰な事前宣伝 → 不十分な証拠の提示 → 第三者検証で破綻という一連の流れはUMA界隈で繰り返されており、今回も主張の大きさに対して独立した学術証拠が伴っていない点が酷似しています。
さらに2025年の“ダック”事案では、大学名(コーネル)や“ネアンデルタールとの関連”といった科学ワードがプレスやSNSで喧伝される一方、研究者コミュニティやカルチャー系媒体は“詐欺(hoax)の懸念”“金銭目的のイベント化”を早期から指摘。
展示告知や現地ニュースは“あなたの目で判断を”とし、確証の提示は回避しているのが実情です。
過去の事例と照らすと、センセーショナルな“発見”の語りと、証拠非開示・検証回避という構図が再演されていると評価できます。
この件が示すメディア・UMA報道の課題

視聴率・話題性優先の情報発信リスク
2025年8月のニューヨーク・ステート・フェアでの“ビッグフット遺体”展示は、タレントのナレーション動画や棺型の演出など見世物としての設計が強く、報道も「現地で自分の目で確かめて」と煽るトーンが目立ちました。
番組側も10月15日(水)放送の告知で「日本のテレビ独占取材!!」「驚愕のDNA鑑定も!!」と刺激的に打ち出しており、検証よりも話題化を優先した編集・広報が読み取れます。
こうした文脈では、視聴者に“確定情報”と“主張・演出”の境界が伝わりにくく、事実確認のプロセスが置き去りになりやすい点が最大のリスクです。
専門機関・学術界と民間主張との乖離
出展者は「大学でDNA検査(あるいは獣医系ラボで非公式確認)があった」と語る一方、大学名・研究者名・試験番号・正式レポートなど第三者が検証可能な一次資料は公開されていません。
地域メディアやSNSでも“鑑定で決着”とは言い切らず、真偽はあなた次第の紹介にとどまる例が散見されます。
さらに、現地の検証系コンテンツや懐疑派のレポートは、有料見物イベント化と証拠の非開示を問題視。
結果として、民間側の大胆な主張と学術的に担保された検証のあいだに深い溝が生じ、視聴者は“権威の名前だけ登場するが、学術的裏付けは示されない”という不整合に直面します。
視聴者が判断するためのチェックポイント(一次資料・証拠公開・第三者検証の有無)
本件のようにセンセーショナルな主張が先行するケースでは、次の点を最低限確認するのが有効です。
- 一次資料の所在
検査報告書PDF、研究者名、検体ID、採材ログ、保存条件、分析手順が公開されているか。 - 第三者の検証
大学や研究機関の公式リリースや査読済み論文があるか(番組告知や当事者の談話は一次資料ではない)。 - メディアの提示姿勢
現地ニュースや番組案内が“見て判断を”とだけ促し、確証の提示を回避していないか。 - 過去事例との整合
2008年ジョージア州の“氷漬け遺体”のような偽装・誇大主張の前歴と似たパターンがないか。
こうしたチェックを経て初めて、話題と証拠の比重を冷静に評価できます。
まとめ:視聴者として知っておきたいことと今後のポイント

今回の「アンビリバボーで語られた“ビッグフット遺体”」報道について、公開情報をもとに整理した結論は以下の通りです。
まず、“ビッグフット遺体(愛称:ダック)”が発見・展示されたという話は、現時点でセンセーショナルな主張として注目されています。
ニューヨーク州アディロンダック山地で発見され、2025年8月20日~9月1日にニューヨーク・ステート・フェアで公開されたという報道があります。
体長はおよそ2.4 m、強い臭気があったとの記述も複数メディアに見られます。
ただし、事実として確定できる裏付けは現時点では乏しいのもまた事実です。
主張者側はDNA鑑定を行ったとする言及をしていますが、その検査報告書、研究者名、機関名、試験データの公開は確認できず、大学公式の声明や査読付き論文も確認されていません。
また、本件には過去のUMA/偽物主張の前例を踏まえた批判も数多くあります。
専門家や批評記事では、「見世物化・商業化が先行している」「科学的根拠より興行要素が強い」「証拠非公開・検証プロセスが透明性を欠く」といった指摘が目立ちます。
メディア報道・テレビ番組企画としては、“未確認生物”“DNA鑑定”“テレビ独占取材”といったキャッチーな要素が用いられ、視聴率や話題性を優先する構成になっている可能性が高いです。
フジテレビ番組案内自体も「驚愕のDNA鑑定も!!」といった煽り文句を掲げており、視聴者が“真実かどうか”という判断を求められる構図になっています。
私見を交えると、今回のケースは“話題としてのUMA報道”の典型例になりつつあると感じます。
魅力的なストーリー展開や映像演出が先行し、真偽を検証するための科学的手続き・証拠開示が後追いになっているからです。
視聴者としては、主張をそのまま信じるのではなく、以下の点に注意することが重要だと思います。
- 番組で語られる内容と「検証済みとして公表されているデータ・論文」とを区別する
- 公表済みの一次資料(検査レポート、研究機関の検証、保存手続き資料など)があるかを確認する
- 批判・異論の視点にも目を向け、主張側の言説だけでなく懐疑派も組み合わせて情報を得る
もし今後、大学や公的研究機関が正式に鑑定報告を発表する、あるいは査読付き論文として科学的審査を経た証拠が公開されるような動きがあれば、それはUMA研究の転機になり得ます。
その日が来るかどうか、引き続き見守る価値はあるでしょう。
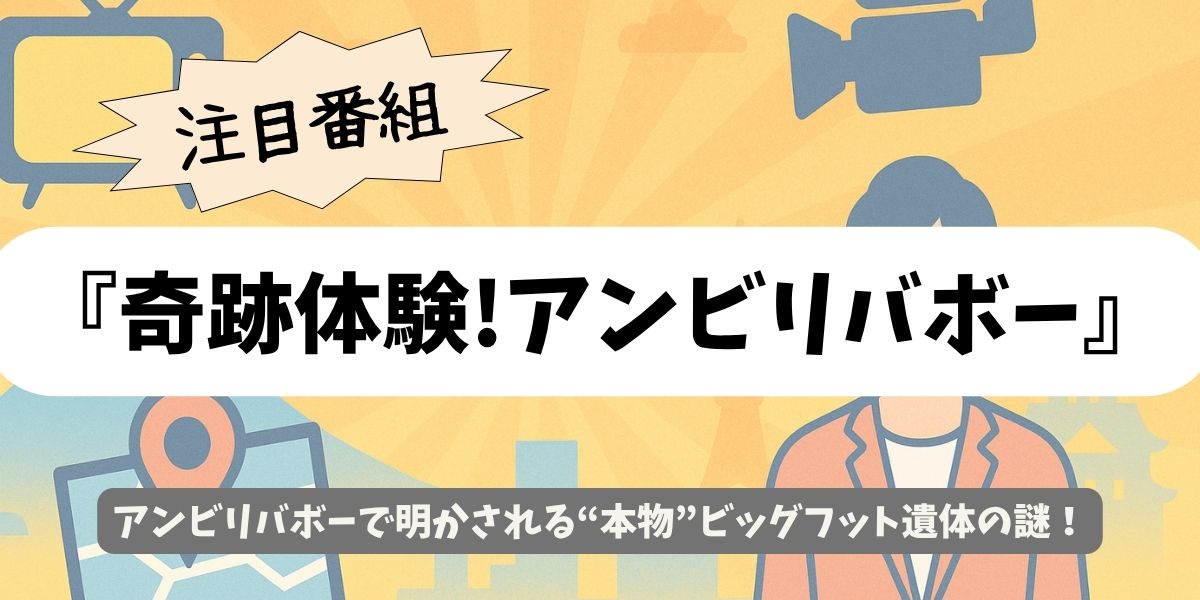
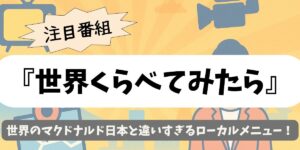

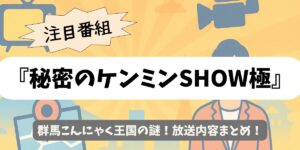
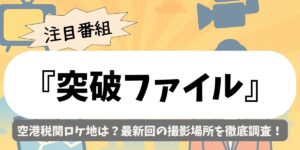
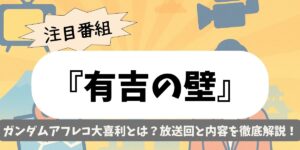
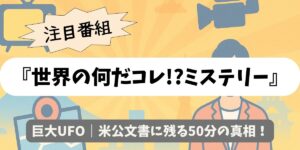
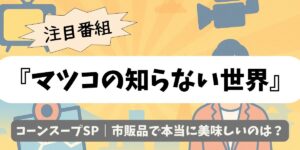
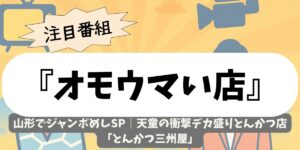
コメント