日本の“発酵グルメ”ブームが止まりません。
中でも「納豆」は、腸活・健康志向の高まりとともに、かつてない注目を浴びています。
そんな中、TBSのバラエティ番組『マツコの知らない世界』が、2025年9月23日(火)20:55~の放送回で「市場規模2800億円超!技術が進化し今ご当地納豆が物凄い!北海道群馬熊本の大人気納豆マツコ本気味比べ/納豆不毛の地・関西の旨タレ事情」と題し、全国各地の“ご当地納豆”を徹底的に取り上げることが発表されました。
この番組告知には、「取り寄せ◎」「全国熾烈競争の実態」「激レア納豆スタジオ大集結」「マツコ本気味比べ」という表現があり、ご当地納豆の味・製法・個性・流通経路など、視聴者が「どれが美味しいか」「なぜその味になるのか」「どこで買えるか」を知りたくて検索するニーズすべてに応える内容になることが予想できます。
加えて「納豆不毛の地・関西」でタレが独自進化しているという文言もあり、地域ごとの味の違いについての比較や背景が掘り下げられることが期待されるため、「ご当地納豆」について検索する人は、単に有名な納豆を知りたいだけでなく、その“個性”“違い”“購入可能性”を含んだ情報を求めているはずです。
そこで本記事では、「マツコの知らない世界 ご当地納豆」が紹介する最新トピックを、自分で予習できるよう整理しました。
ご当地納豆ファンはもちろん、「納豆って苦手だけどちょっと試してみたい」という人にも、この記事を読めば“ご当地納豆の世界”がぐっと身近になります。ぜひ最後までお付き合いください。
放送概要と最新トピック(放送日時・ゲスト・見どころ)

2025年9月23日(火)20:55〜の放送基本情報
『マツコの知らない世界 ~納豆市場が過去最大!超進化ご当地納豆ガチ査定~』は、2025年9月23日(火)の20時55分~に TBS を中心とする系列で放送されます。
放送枠は90分を予定しており、番組表には「納豆市場が過去最大!技術が進化し今ご当地納豆が物凄い!北海道群馬熊本の大人気納豆マツコ本気味比べ」「納豆不毛の地・関西の旨タレ事情」などの見どころが並んでいます。
また、番組は全国ネットで放送され、TBSのほか、地方テレビ局の系列放送予定が確認されており、リアルタイム配信も TBS FREE や TVer 等で行われる予定です。
視聴者は地上波だけでなく、インターネットを通じても番組をチェックできる体制になっています。
ゲスト「村上竜一」プロフィールと納豆活動
番組には、ご当地納豆の世界を紹介する専門家として村上竜一さんがゲスト出演します。
公式番組情報で「ご当地納豆の世界…村上竜一さん」と明記されており、彼がナビゲーター的役割で登場することが発表されています。
村上竜一さんは、「納豆マガジン」など、納豆にフォーカスしたメディアやプロジェクトに関わっており、ご当地納豆の製造背景、風味の違い、発酵・タレへのこだわりなど“納豆愛”を語れる人物として知られています。
また「激レア納豆スタジオ大集結」という番組予告文にも名前が結びつけられており、数々の地域の納豆を比較紹介するキーパーソンになることが予想されています。
さらに、彼は視聴者へのお取り寄せ推奨/食べ比べの視点で語ることが番組内容に含まれており、「取り寄せ◎」という表現が公式番組説明に含まれているのも特徴です。
つまり、ただ知識を紹介するだけでなく、実際に購入可能で話題になっている納豆を紹介する“使える情報提供者”としての役割も持っています。
番組が掲げる3大見どころ(市場規模・地域対決・マツコ査定)
番組の告知から明らかになっている見どころは、おおむね以下の三つです。
- 市場規模の拡大
「納豆市場が過去最大!」「市場規模2800億円超」という表現が番組タイトル・番組公式案内に使われており、今や納豆が単なる健康食品や伝統食を超えて、ビジネス/食文化として拡大を続けていることがキー論点です。 - 地域別ご当地納豆の対決・比較
北海道・群馬・熊本など、地域ごとに人気の納豆が登場し、その違いを「スタジオ大集結」で比較することが予告されています。
また、「関西の旨タレ事情」など、特定地域で発酵やタレなどが独自進化している話題も取り上げることが示されています。
地域色・食文化の差異に焦点が当たる内容です。 - マツコの“ガチ査定”と視聴者参加の要素
番組説明には「マツコ本気味比べ/納豆大好きマツコのマイベスト納豆が今宵決定!?」という一文があります。
つまり、ただ紹介・解説するだけでなく、マツコ・デラックスが納豆を実際に試食して評価する「査定」が大きな見どころ。
視聴者としては「どの納豆が選ばれるのか」「その評価基準は何か」を注目して見る楽しみがあります。
これら3点が視聴者が「マツコの知らない世界 ご当地納豆」で検索する際の期待に応える核となる要素です。
ご当地納豆の“今”—腸活ブームと市場拡大の背景

「市場規模2800億円超」は何を示すのか
最新の調査によると、2024年の日本の納豆市場(家庭用+業務用を含む)は、前年比6.6%増で2874億円という数字が全国納豆協同組合連合会から報告されています。
これは、「納豆市場が過去最大」という番組告知の裏付けでもあり、市場が縮小傾向にあった時期を経て、再び消費量・販売金額ともに拡大していることを示します。
この拡大の背景には複数の要因が挙げられます。
ひとつは “腸活(腸内環境改善)” や発酵食品ブーム。
健康意識が高まる中で、納豆の持つ栄養素(納豆菌、大豆たんぱく質、ビタミンK2など)が注目されており、日常的に取り入れる人が増えています。
また、物価高が続く中で、納豆は比較的価格が手頃であり、保存も簡便、調理の工程も少ないという特長があり、家庭での食の選択肢として重宝されていることも市場拡大の一因です。
さらに、納豆メーカーが国産大豆や風味・タレ・粒の種類など差別化商品を積極的に出すようになってきており、“ただ安い”だけではない価値のある納豆を求める動きが強まっているのもポイントです。
技術進化で高まる“個性”(粒・発酵・タレ・組み合わせ)
最近の納豆市場で特に注目されているのが、「個性を出す」ための技術進化です。
たとえば粒の大きさだけでも、小粒・大粒・極小粒などさまざまなタイプがあり、それぞれの嗜好(食感、噛み応えなど)に応じて選ぶ消費者が増えています。
風味・香りに影響する発酵の温度や湿度管理、発酵時間などの熟練技術も進化しており、生産者側の工夫が味のバラエティを生んでいます。
公式番組案内では「激レア納豆スタジオ大集結!」という言葉が使われ、普通には手に入らないタイプの納豆が比較検証されることが示されています。
タレ(調味料)の工夫も顕著です。従来の醤油+辛子・出汁系から一歩進んで、「たっぷりタレ」「甘めタレ」「出汁が濃いタレ」「薬味入り」「果汁入り」「発酵調味料を組み合わせたタレ」など、味の側でも“ご当地独自性”が前面に出るようになっています。
これにより、納豆が“ご飯のお供”だけでなく、そのまま酒の肴や副菜、あるいは調理素材として使われるシーンも増加中です。
番組告知にも「タレ」のキーワードが入っており、関西で“旨タレ”文化の進化が目立つとして紹介されています。
また、豆の種類や産地を掛け合わせた“組み合わせ型”商品も増えてきており、希少な在来種大豆と特色あるタレを組み合わせるなど、風味・香り・見た目を総合的に高める努力が進んでいます。
これはご当地納豆が「差別化競争」のステージに入ってきていることを意味します。
関西で進化した“旨タレ”文化の台頭
「納豆不毛の地・関西」という表現が番組告知に出ていますが、その背景には伝統的に納豆の消費量や納豆文化が東日本ほど深く根付いていないという事情があります。
にもかかわらず、近年関西で注目されているのが「タレ」による味付けの工夫です。
特に、においやクセを抑える甘め・出汁ベース・麹を使ったものなど、タレによって納豆のハードルを下げる商品・家庭の工夫が広まりつつあります。
番組タイトルにも「関西の旨タレ事情」というフレーズがあり、この変化が視聴者の関心を引く重要なポイントです。
また、食文化の違いとして、関西では出汁文化が強く、うどん・そば・お好み焼きなどで出汁を取る文化が根付いていることから、納豆のタレにも出汁を生かしたタイプが馴染みやすいという土壌があります。
そのため、単に醤油ベースのタレではなく、いりこ・鰹・昆布など和風だしを効かせたもの、さらに甘さを少し加えた“甘出汁タレ”のようなものが支持を得る傾向にあります。
公に発表されている製品・予告一覧でも「旨タレ」「甘めのタレ」のワードが目立ちます。
さらに家庭・小売・ご当地メーカーレベルで、タレだけを別売りしたり、新しい味付けタレを試すキャンペーンが行われており、消費者が“Taster(試す)”層になってきていて、関西での納豆タレ文化の進化は、単なる一過性ではなく、持続的なトレンドになりつつあることがうかがえます。
地域別・注目ポイント(北海道/群馬/熊本 ほか)
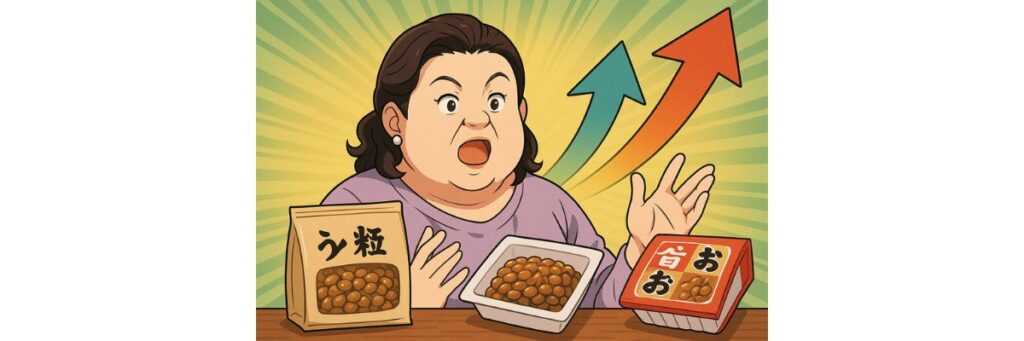
北海道—原料・製法で勝負する実力派
北海道からは「豆の文志郎」の鮭節納豆(しゃけぶし納豆)が注目されています。
公式番組情報で「激レア納豆スタジオ大集結!」の中に北海道の納豆が含まれており、この鮭節納豆がその代表格とされています。
この納豆の原料には「北海道産ゆきしずか大豆」が使われ、甘みと豆のコクを重視した設計になっています。
さらに、鮭節を加えることで海の旨味と発酵の風味が融合し、普通の納豆とは異なる“魚介の旨み+納豆菌の香ばしさ”が楽しめるものになっているのが特徴です。
製法にも工夫があります。豆の蒸し方・発酵時間を調整し、粒が崩れにくく、粘りも適度でありつつ口当たり良く仕上げています。
また、付属のタレや味付け「おかか(鮭節味)」などの風味付けで、混ぜてから食べる際の香り立ちが高い、食べ始めから仕上げまで“北海道らしさ”を感じさせる設計になっています。
販売形態でもオンライン・実店舗の両方で入手可能です。
「豆の文志郎 本店」(登別市)では全商品を扱うほか、本店限定の商品もあり、オンラインショップや楽天/Yahoo!などのECサイトでも鮭節納豆は扱われています。
群馬—老舗×新興が生む多様性
群馬県からは「粕川納豆」の逢納豆(あわせなっとう)が注目されています。
番組公式情報に「北海道・群馬・熊本…激レア納豆スタジオ大集結!」とある中で、逢納豆はその中核をなす存在として紹介されており、地域の在来種大豆を使うことで“土地の個性”を活かす取り組みが色濃い商品です。
逢納豆の原料としては、自家栽培の地塚大豆のほか、「黒千石大豆」という、色も風味も特徴的で希少性の高い大豆が使われています。
これにより、他の納豆にはない“見た目の色合い・豆皮の風味・香りとコク”が際立ちます。
製造プロセスにもこだわりがあり、蒸しや発酵の温度管理、そして豆の蒸し上げ時間を通常より長めにとることなどによって、豆の甘さや旨味を引き出すように設計されています。
これにより、食感がしっかり感じられるタイプが多く、粒感とねばりのバランスが重視されているのが特徴です。
販売面では、粕川納豆はオンライン販売に加えて、群馬県内に直営店舗を持ち、「お土産・ギフト・単品」での取り扱いもあります。
新しい店舗(前橋市六供町)もオープン予定で、地元での存在感を強めていることが分かります。
熊本—九州流アレンジとご飯のお供力
熊本県からは「マルキン食品」の元気納豆 九州本仕込みが番組紹介の中に含まれており、九州地域ならではの味つけや食文化との親和性が強く出ているご当地納豆です。
公式番組情報が「北海道・群馬・熊本の大人気納豆」などとしており、熊本の納豆が比較対象の一角で紹介されています。
特徴として、まずタレの味付けが「甘口(あまかたれ)」が基本で、他に「だし醤油」タイプや「焼きあごだし入りたれ」といったバリエーションが展開されています。
これにより、納豆が苦手な人や、強めの風味をあまり好まない層にも受け入れやすい仕上がりとされています。
また、加えて九州の醤油文化・だし文化が根強いため、甘みや柔らかさが重視される傾向にあります。
熊本の元気納豆はそれを反映しており、豆そのもののクセをやわらげつつ、毎日のご飯のお供として“食べやすさ”と“満足感”を両立させる工夫がされています。
流通・購入手段としては、マルキン食品公式サイトおよび楽天市場などオンラインショップで購入可能であり、熊本県内スーパーマーケットなどでも品揃えがされていることから、“地元の支持+オンライン対応”の両輪型で広がりを見せています。
マツコの“マイベスト納豆”と視聴・購入のガイド

マツコのガチ査定—選考軸と評価のポイント
今回の放送は、「市場規模2800億円超」「北海道・群馬・熊本の大人気納豆」「納豆不毛の地・関西の旨タレ事情」「マツコ本気味比べ」といったキーワードで告知されています。
つまり、スタジオには“ご当地ならでは”の個性派が集まり、豆そのもの(産地・粒の大きさ・食感)/発酵・香り/タレ(甘口・だし・麹などの工夫)/入手性(取り寄せ可否)といった観点を含めて“食べて比べる”構成であることが公式情報から読み取れます。
最終的な「マイベスト納豆」の銘柄は放送内で発表される体裁で、事前に結果は公開されていません。
したがって本記事では、番組が提示している比較の焦点(地域性・タレの進化・“激レア”性)を視聴時のチェックポイントとして整理し、放送後に公式の案内で確定情報を確認する、という見方が正確です。
なお、放送告知は番組公式ページ、番宣動画、公式SNSで同一トーンで告知されています。
見逃し&同時配信の視聴方法(TVer/各配信の導線)
視聴経路は複数あります。
番組ページに、TBS系のリアルタイム配信として「TBS FREE」「TVer」「Paravi」が案内されています。
放送と同時の配信(地域や端末条件によって視聴可否・仕様は異なることがあります)に加え、TVerの番組シリーズページからは最新回の見逃し配信にアクセスできます。
リアルタイム・見逃しともに、配信可否や公開期間は回ごとに変動するため、放送日(今回は2025年9月23日[火]20:55〜)の前後に公式ページとTVer側の表示を確認するのが確実です。
お取り寄せ・購入のコツ(公式や地域ECの探し方)
今回のテーマには「取り寄せ◎」という文言が明記されています。
まずは番組公式ページの記載や、放送当日のテロップ・エンドロールで出典元(メーカー・店舗名)をチェックし、各社の公式サイトや直営オンラインショップを探すのが基本線です。
あわせて、地域のECモール(地方百貨店EC、道の駅オンライン、自治体運営の特産品サイト)は、ご当地限定品の在庫が反映されやすく、季節ロットや限定タレなどテレビ登場品に近い仕様を見つけやすい利点があります。
人気放送直後は需要が急増し在庫が動きやすいので、メーカー公式が案内する正規取扱店(実店舗/EC)のリストを基点に再入荷通知を設定したり、配達地域とクール便条件を先に確認しておくとスムーズです。
案内の根拠は、番組が「取り寄せ◎」「激レア納豆スタジオ大集結」と明示していること、ならびに市場拡大・輸出増など“買えるチャネルの広がり”を示す業界・公的資料にあります。
まとめ

「マツコの知らない世界 ご当地納豆」の回を見て・調べてみると、ご当地納豆の今が以下のように整理できます。
まず、納豆市場の勢いが確実に上がっているということです。
2024年の国内納豆市場(家庭用+業務用)は前年比6.6%増で約2874億円に達したというデータが、全国納豆協同組合連合会から出ています。
物価高・物流費の上昇にもかかわらず、納豆は価格帯・調理の手軽さで消費者に選ばれており、“腸活”“健康志向”の追い風も功を奏しているようです。
次に、ご当地納豆の個性・差別化要素がはっきりしてきた点。
番組では、北海道・群馬・熊本、といった地域の納豆が“粒・原料・タレ・発酵技術”などの観点で厳選されて紹介され、「激レア納豆」「スタジオ大集結」という表現が使われていることから、普通のスーパーで見かけない珍しいタイプの納豆への注目が高まっていることがわかります。
また、味付けやタレの工夫が、ご当地差を出す重要な鍵として浮かび上がっています。
特に関西地域では、「納豆不毛」と言われてきた納豆文化をタレで補う動きがあり、「旨タレ」文化の進化という形で甘み・出汁・香りなどを工夫したタレが支持されていることが番組告知で強調されています。
これにより、納豆が苦手な人や初めての人にも入り口が広がっているという印象があります。
さらに、“取り寄せ可”であることも大きなポイントです。
番組公式案内に「取り寄せ◎」という文言があることから、全国のご当地納豆を実際に手元に届ける仕組み・流通が整ってきており、視聴者が興味を持ったものを自分で購入して試せるという実用性が担保されています。
私見を交えると、今回の特集は「ご当地納豆」がただの郷土食・土産ではなく、味・タレ・発酵時間など“細部”まで差異を出して競うフェーズに入ってきていることが鮮明だと思います。
納豆を選ぶ際の基準が“安さ”だけではなく“風味”“舌ざわり”“タレの調和”といった付加価値へとシフトしてきており、これは食文化が成熟してきた証拠でしょう。
もしこれからご当地納豆を試すなら、「まずは番組でマツコさんが選んだマイベストをチェックすること」「味の好みに合わせてタレ重視・粒重視など自分なりの基準を持つこと」「取り寄せ可能な商品を複数買って食べ比べること」をおすすめします。
ご当地納豆を通じて、毎日の食卓がちょっと贅沢に・楽しくなること間違いなしです。
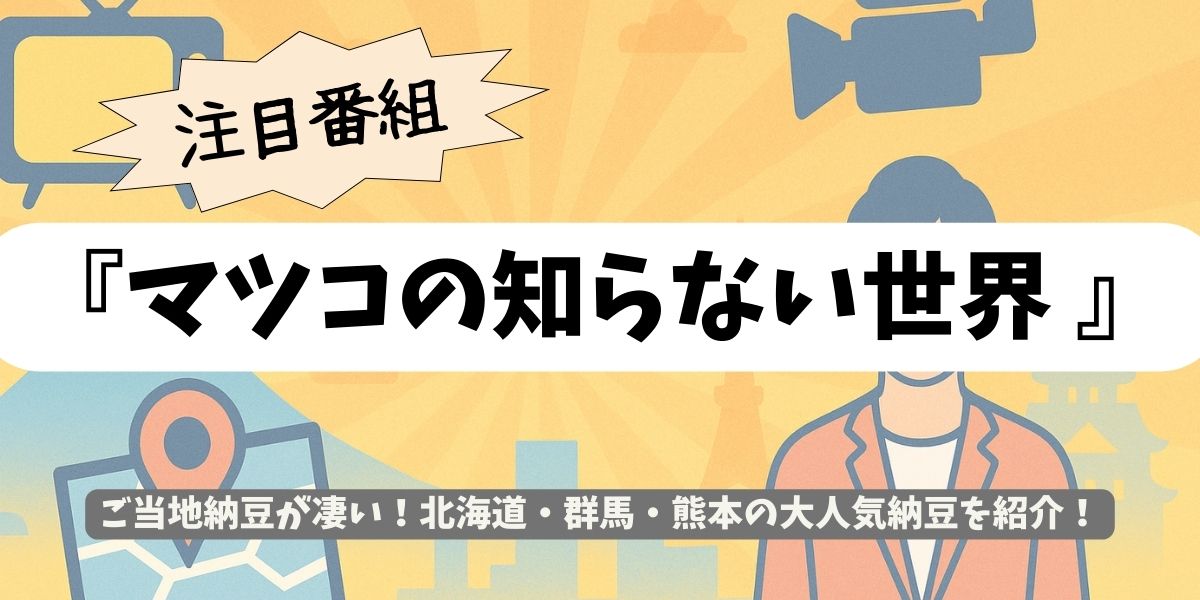




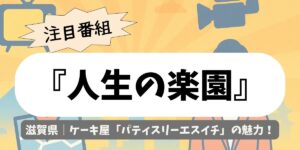


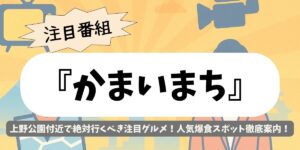
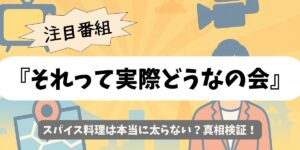
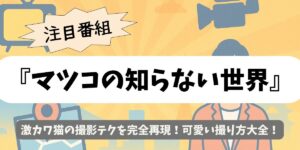

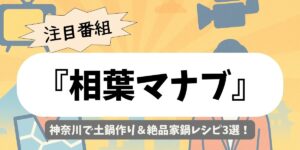
コメント