ティファールの電気ケトルを使っていて「無償交換」の言葉を見かけたあなた。
なぜ無償交換が必要になったのか、そして自分のケトルが対象かどうかを知りたいですよね。
結論から言うと、2021年10月〜2024年7月に製造された特定ロットのティファール電気ケトルで、電源コードを持ってプラグを抜くなどの扱いによる“プラグの破損”が見つかり、その破損が原因で使用中にコンセント近くで発煙または発火する可能性が確認されたため、メーカーが安全対策として「構造の異なる電源プラグを持つ電源プレート」へ無償交換を行うことになりました。
ここではまず、「なぜ無償交換なのか」という原因、「あなた自身のケトルが本当に対象かどうか」という確認方法、「どう交換申請するか」までを順に解説します。
つまり、読者が求めている「無償交換の理由」「対象かどうかの確認」「申込みの方法」がすべて分かる記事です。
最初に“なぜ”がわかれば、不安が和らぎ、“どうすればいいか”がわかればすぐ行動できます。
本記事を読み進めれば、安全に使い続けるための対処法と、無償交換をスムーズに進めるためのステップがクリアにわかるようにしましたので、ぜひ最後までチェックしてください。
無償交換の背景と「なぜ」の核心

対象モデル・製造期間・台数(2021年10月〜2024年7月・28モデル・60製品・約418.5万台)
2025年9月16日、ティファールを輸入・販売するグループセブ ジャパンは、2021年10月から2024年7月までの期間に製造された電気ケトルのうち、特定の製造ロットについて「無償交換」の措置を取ると発表しました。
具体的には、28モデル・60製品が対象となり、その総数は4,185,393台(約418万5393台)です。
この対象モデルには、「アプレシア プラス シュガーピンク 0.8L (BF805774)」「アプレシア プラス カフェオレ 0.8L(BF805170)」など、容量0.8L のアプレシアシリーズを中心とする複数の型番が含まれています。
対象製造期間内であっても、製造ロットが“特定のロット”であることが条件となっており、すべての期間製造品が全て無条件に対象というわけではありません。
発生事象とリスク(発煙・発火の可能性、被害状況)
2024年4月以降に、「使用中にコンセント付近で発煙あるいは発火する可能性」が確認された事故が16件報告されています。
これらのうち、軽度のやけどを負ったユーザーが1名います。
物的損害は大きなものは確認されていません。
これらの事故はいずれも、電源コードを持ってコンセントから抜くなど、プラグ部分に過度の負荷をかける不適切な取り扱いが繰り返されたことが発端になっているとメーカー側は説明しています。
そうした使用方法がプラグ破損を引き起こし、それが発煙・発火の原因と推定されています。
法令上・技術規格上では、該当する電源プラグは日本の基準に適合しており、製造工程での異常は確認されていないと報告されています。
つまり、設計や工場での問題ではなく、「使い方」が主要因として考えられています。
法規適合と不適切使用の関係(メーカー説明の要点)
無償交換の発表において、グループセブ ジャパンは、対象の電源プラグは「日本の規制・技術基準」に適合しており、製造過程でも異常は確認されなかった、としています。
しかしながら、製品の使用において「電源コード部分を持ってプラグを抜く」などの 不適切な使用方法が繰り返されると、プラグに物理的なストレスがかかることにより破損が起きやすくなり、それが結果的に発火・発煙の事象へつながる可能性が高い、との分析です。
また、2024年8月以降に製造された製品には、既に「構造の異なる電源プラグ」が採用されており、これらは今回の無償交換の対象外とされています。
つまり、改良がなされており、新しいモデルでは同様のリスクが軽減されていると見られます。
あなたのケトルが対象かを即確認

型番・ロットの見方(本体底面表示/電源プレートの識別ポイント)
お手持ちのティファール電気ケトルが無償交換対象かを確かめるためには、本体底面を確認することがまず重要です。
グループセブ ジャパンが公開した確認方法によれば、底面には「ラベル」が貼られており、そのラベルの中に製品品番(たとえば “BF805774” や “KO3901JP” など)と、4桁の番号が印字されています。
この「4桁の番号」は製造時期を示しており、左側の2桁が「製造された週」、右側の2桁が「製造された年」です。
例えば「4221~2522」という表記であれば、2021年の42週から2022年の25週までの期間に製造されたものが含まれるという意味です。
ただし、例外があります。本体の「ウォッシャブル 0.8L」モデルのみ、ラベルではなく本体底面への刻印で製品品番と4桁番号が表示されています。
貼られたラベルが剥がれていたり汚れて見えにくい場合でも、この刻印を探して確認することが必要です。
また、ラベルの形(扇形・長方形)、色枠の配置(青枠・赤枠でそれぞれ製品品番/4桁番号)、レイアウト等はモデルによって異なる可能性があります。
公式発表には「ラベルの形やサイズ、印字内容やレイアウトが写真と異なる場合がある」と明記されていますので、表示の位置やフォントが多少違っていても焦らず照合してください。
該当例と非該当例(写真・図解前提の構成)
以下は対象製品に該当する例と該当しない例の典型例です。
実際にお持ちの製品と比較してみてください。
該当例
- 製品名:アプレシア プラス シュガーピンク 0.8L
製品品番:BF805774
4桁番号:5221(2025年9月の発表時の表に含まれる対象ロット) - 製品名:アプレシア ウルトラクリーン ネオ パールホワイト 0.8L
製品品番:KO3901JP
4桁番号が “4421~1324” の範囲内であれば対象。
非該当例
- 製造ロットが2024年8月以降に製造されたもの。
これらには既に構造の異なる電源プラグが採用されており、無償交換の対象外となっています。
たとえ製品品番が対象モデルであっても、ロット番号がこの期間を除いていれば対象外です。 - 4桁番号が別表の対象範囲外であるもの。
例えば、「4221~2522」「2822~4323」などの表記と一致しなければ、対象ではありません。
写真や図がある公式の “別表” と比較するとわかりやすいため、その表をプリントアウトするかスクリーンで開いて手持ちの製品と貼ってあるラベルの書かれている数字・品番が完全一致するかを確認しましょう。
これにより「対象かどうか」が明確になります。
迷った時の確認フロー(公式ページ→型番入力→結果)
対象かわからないときのシンプルな確認手順を以下の流れで行うと確実です。
- ラベルまたは刻印を確認
本体底面を見て、ラベル(または刻印)に「製品品番」と「4桁の番号」があるかをチェックする。
汚れや色あせで見づらい場合は拡大鏡や明るいライトを使う。 - 公式サイト/別表を確認
ティファールの無償交換案内ページに、対象モデルと対象ロットの一覧表(別表)が掲載されています。
製品品番と4桁番号の両方がこの表に含まれていれば対象です。 - オンラインで結果を確認
公式の「電源プレート無償交換特設ページ」から、型番・ロット番号を入力または該当モデルを探して、該当するかどうかを調べられます。
電話窓口でも確認可能です。 - 対象なら使用を一時中止
もし手元のケトルが対象一覧と一致した場合、無償交換品が到着するまで、その電気ケトルの使用を中止するようグループセブ ジャパンは呼びかけています。
安全のために電源プラグ部分に過度の力をかける取り扱いを避け、確認できるまで控えましょう。 - 交換申請
対象と確認できたら、公式の交換受付窓口(Web/電話)を通じて申込を行います。
以降の手続きは交換申込後案内されます。
無償交換の申し込み手順と必要情報
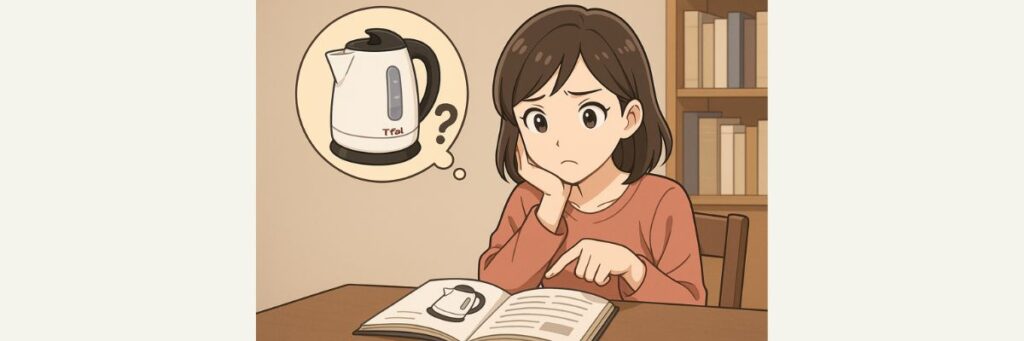
受付窓口(電話・Web)と稼働時間/混雑時のコツ
ティファールの電気ケトル無償交換の申し込みは、次の二つの窓口を利用できます。
まずWebの特設ページで、対象製品かどうか確認したのち申し込みフォームで手続きを行う方法。
もう一つは電話による受付で、フリーダイヤルの専用番号「0120-153-020」に電話する形です。
受付時間は午前9時~午後6時(土日祝日含む)となっており、時間帯は混雑を避けるために朝9時直後や昼休み前後を避けると比較的つながりやすいという予想ができます。
混雑時のコツとしては、Web申込ページが比較的軽く済むことが多いため、電話よりWebを使う方がストレスが少ないこと、また問い合わせ内容を予め準備しておく(型番・ロット番号・購入時期など)ことで、受付窓口での手続きがスムーズに進むことが報じられています。
申し込みに必要な情報(型番・ロット・購入時期・連絡先)
無償交換を申し込む際に必要な情報は、主に以下の項目です。
- 製品品番
本体底面のラベルまたは刻印で確認できる品番。
例:「BF805774」「KO3901JP」など。 - 4桁の番号(ロット番号表示)
製造週・年を示す番号で、製品品番とともに対象リストと一致する必要があります。
番号範囲や形式が別表に記載されています。
例えば「4421~1324」「4221~2522」など。 - 購入時期または使用開始時期(もしあれば)
購入日までは必須ではないものの、窓口で問い合わせがあった際に、問い合わせ対応のために聞かれる可能性があります。
公式文書では主に品番と4桁番号の照合が基準です。 - ご自身の連絡先情報
氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなど、交換品を送付するための配送先情報。
これも申し込みフォームや電話窓口で必要になります。
公式発表内で「下記窓口から申し込みをお願いいたします」とされており、その申込ページでは連絡先の記入欄が設けられていることが確認できます。
これらの情報をあらかじめ準備しておくことで、電話でもWebでも手続きに余計な遅れが出にくくなります。
発送~交換完了までの流れ(梱包・配送・所要の目安)
発表内容によると、無償交換が確定した場合の一連の流れは以下の通りです。
- 申し込み受付
特設ページまたは電話窓口で上記情報を提出。
該当製品であることが確認されると申し込みが承認されます。 - 交換品の発送
交換用の電源プレート(構造の異なる新プラグ付き)が、メーカーまたは事務局から送られてきます。
発送時期は申込確定後順次、という表現が公式文書にあり、具体的な到着日数は記載されていません。 - 旧電源プレートの返却方法
旧プラグを取り外したりする指示があるか、または事務局から返送用の梱包方法・ラベルなどが案内される可能性があります。
公式発表には「無償交換のお申込み窓口」「交換品を送付する」旨はあるものの、返送手順の詳細(梱包材・送料負担など)は明確にはすべての文書で記載されていません。 - 交換完了/確認
新しい電源プレートが届いたら、古いものを新しいものに交換します。
取扱説明書や公式サイトに交換方法の案内がある可能性が高く、使用前に動作確認をすることが推奨されています。
事故防止の観点から、正しくはめ込むこと、またプラグ部分に過度な力をかけないことが強調されています。
所要の目安時間については、公式には申し込みから交換品が届くまでの日数は明言されていません。申込数や在庫状況によって変動する見込みです。
したがって、早めに申し込むことが安全・安心につながるといえます。
安全に使うための再発防止&代替策
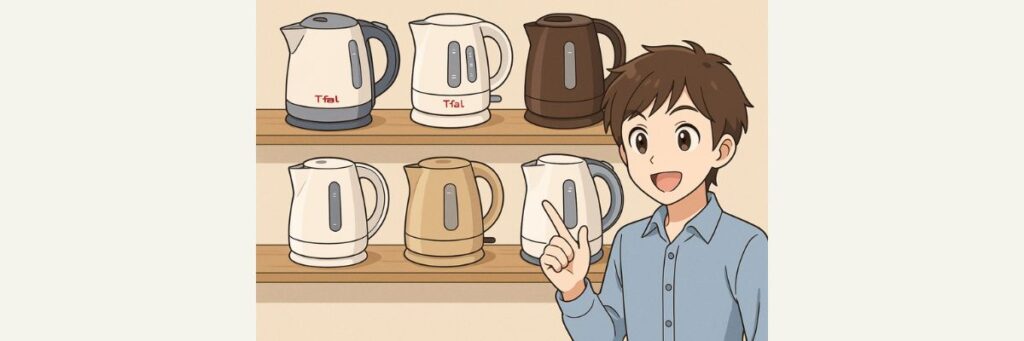
正しい電源プラグの抜き差しとコード取り扱い
ティファール側の発表では、無償交換の主要な原因として、「電源コード部分を持ってコンセントから引き抜く」などの不適切な使用方法を繰り返すことで、プラグに物理的な負荷が生じ、破損→発煙・発火のリスクが高まる可能性があるとしています。
これは、コードではなくプラグ本体を持って抜き差しすることが推奨されている理由の一つです。
また、コードを無理に折り曲げたり、ねじったりすること、巻きつけた状態で保管することもプラグの根元に負荷をかける行為として注意すべきであると指摘されています。
公式発表にはこれらの「不適切な使用方法」の例が挙げられており、ユーザーが日常使用で避けるべき行為として明記されています。
さらに、差し込み・抜く際にはコンセント・プラグの向きがしっかり合っているか確認し、緩みやガタつきがないことをチェックすることが安全性を保つために重要です。
差し込みがゆるいと接触不良が起きやすく、それが発熱の原因になる可能性があります。
ティファールのリコール案内では「コンセント近辺で発煙」という表現があり、これらの使い方・接触条件が深く関係していると分析されています。
家中のケトル安全チェックリスト(タコ足・コンセント劣化等)
電気ケトルを安全に使用するには、プラグそのものだけでなく、電気環境・ケーブル・コンセントの状況も重要です。
以下は、公式発表および報道に基づいたチェック項目リストです。
- コンセントの状態を確認
差込口がぐらついていないか、焼け跡や変色、焦げ臭さがないかを定期的にチェック。
特にプラグを差し込んだ際に“カチッ”と固定されていないと感じる場合は注意が必要です。 - タコ足配線を避ける
複数の電化製品を延長コードや分岐タップで接続するとコンセントへの負荷が大きくなります。
キッチンでは特に消費電力の大きい機器が多いため、できるだけ直接コンセントを使うことが望ましいです。 - プラグ及びコードの損傷チェック
コードの被覆(外側の皮膜)が裂けていないか、根元が緩んでいないか、金属部分が見えていないかを確認。
プラグ本体のピン(差込部分)が曲がっていたり変形していたりしないかも見ておきます。 - 通気性のある設置場所
プラグ・電源プレートを覆い込むような家具裏や布などの近くで使用しない。
発熱時に熱がこもりやすくなり、異常が起きやすくなります。 - 使用頻度と寿命の視点
電気ケトルは毎日使用することが多いため、消耗品のようにプラグやコードの摩耗が進みやすいです。
たとえ外観に問題がなさそうでも、長年使っているものは交換対象モデルであれば早めに無償交換を申し込むという視点が安心です。
これらのチェックを定期的に行うことで、「プラグの破損」などの初期段階の異常を早く発見し、重大な事故を未然に防ぐことにつながります。
公式発表は、今回の事故が“使用上の取り扱い”に起因するとしており、このようなチェックが再発防止策の一部だとされています。
買い替え検討ポイント(温度設定・自動断電・耐久性指標)
無償交換対象外であったり、寿命を迎えていると感じる場合には、新しい電気ケトルを選ぶ際のポイントを押さえておくと安全性・使い勝手が向上します。
以下は、最新発表内容およびメーカー仕様などを踏まえた買い替えの参考指標です。
- 電源プラグの安全設計
今回無償交換対象外になっている、2024年8月以降製造のケトルは「構造の異なる電源プラグ」が採用されており、より破損しにくい設計とされています。
買い替える場合は、この新しいプラグ仕様が確認できることが重要です。 - 自動断電機能および温度制御
沸騰後の自動電源オフ機能や、過熱防止機能などが付いているモデルを選ぶと安全です。
これらの機能があれば、もしプラグやコードに異常があっても、電源がオフになって被害を小さく抑えられる可能性があります。 - 耐久性の高い素材・構造
プラグ根元の補強がなされているもの(丈夫な被覆・コネクタ部の保護キャップなど)、コードがやや太めで取り回しに余裕があるものなどを選ぶと、日々の使用での摩耗・断線リスクを抑えられます。 - レビューおよび保証期間の確認
購入者のレビューで「プラグ根元が弱い」「コードが裂けた」という声がないか調べるのも一つの手です。
また、保証期間が長めであるものは、何かあった際にメーカー対応が期待できるため安心です。 - 容量・用途に合わせた選択
1.0L, 1.2L 等容量は家庭の水の消費量に応じて選ぶこと。
用途が沸かす頻度が高いなら小容量のモデルを複数持つより大きな容量のものを選んで使用回数を減らす方が、プラグ・コードへの負荷が減ることがあります。
ティファールの発表自体では買い替えを直接奨励する文言はないものの、対象外モデルや長年使用している製品については、こうしたポイントに注意した選択が「安心して使い続けるため」の現実的な代替策となります。
まとめ

ティファールの「電気ケトル 無償交換 なぜ?」という疑問への答えは明確です。
2021年10月〜2024年7月に製造された特定ロットの一部で、コードの持ち抜きなど不適切な取り扱いを繰り返すと電源プラグが破損し、コンセント付近で発煙・発火に至る可能性が判明したため、メーカー(グループセブ ジャパン)が電源プレートの無償交換を実施しています。
対象は28モデル・60製品、約418万台と発表されています。
まずはご自宅のケトル底面のラベル(または刻印)で製品品番と4桁番号を確認し、公式の対象一覧と照合してください。
該当すれば使用を一時停止し、すぐ交換手続きを取りましょう。
交換の申し込みは特設Webページまたは専用フリーダイヤル 0120-153-020(受付 9:00〜18:00/土日祝含む)で受け付けています。
報道でも同番号・受付時間が案内されており、混雑時はWebからの申請がスムーズです。
型番・4桁番号・連絡先を手元に準備しておけば手続きが早く終わります。
事故・被害の把握としては、2024年4月以降に発煙・発火16件(軽いやけど1件)が公表されています。
製品自体は基準に適合とされていますが、コードを持って抜く/無理な曲げといった日常の扱いがリスクを高める点がポイントです。
交換品は構造の異なる電源プラグに置き換える対応で、2024年8月以降製造のモデルは対象外です。
今後も“プラグ本体を持って抜く”“タコ足や劣化コンセントを避ける”など、安全な使い方を徹底してください。
本件は2025年9月16日に公式告知・官公庁のリコール情報が出ており、内容は随時更新される可能性があります。
必ず公式PDF/官公庁のリコールページ/主要メディアの続報を確認し、情報に変化がないかチェックしてください。
迷ったら公式の特設ページと窓口に問い合わせるのが最短・最安全です。
今回は「設計不良そのもの」ではなく取り扱い実態に起因する事故が顕在化したケースで、メーカーが広範囲な無償交換を決めた点は、安全最優先の姿勢として評価できます。
一方で、キッチン家電は“毎日使う”がゆえに劣化や習慣の癖が見落とされがち。
対象確認→申請→交換までの動線は整っているので、該当の可能性が少しでもあれば今すぐ確認を。
正しい抜き差しや配線の見直しは、他の家電にも効く“今日からできる予防策”です。
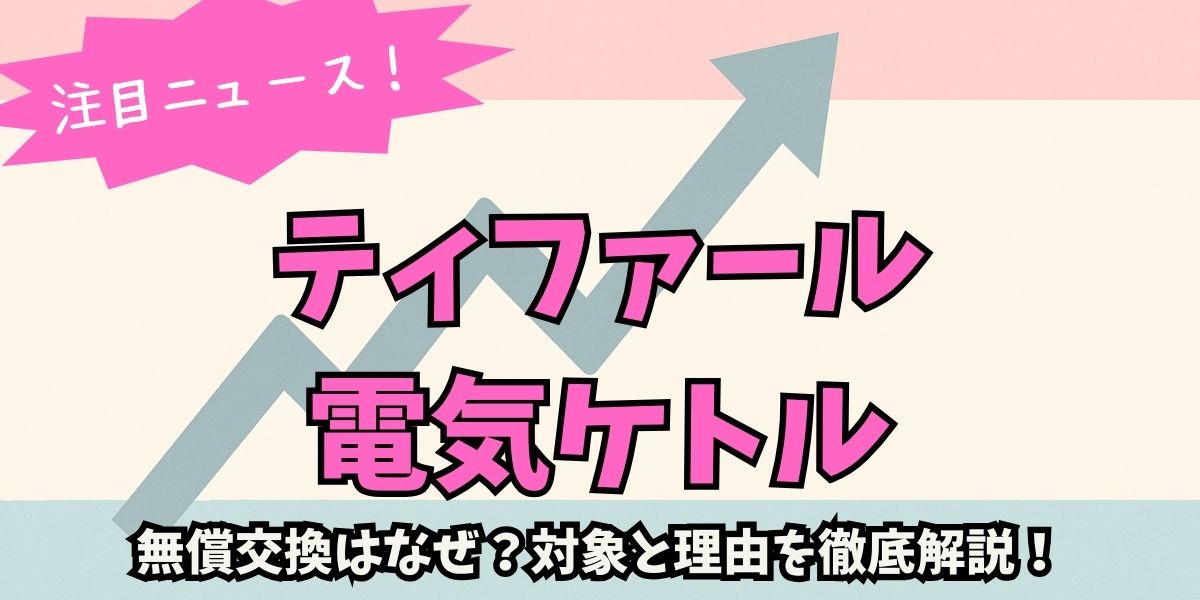
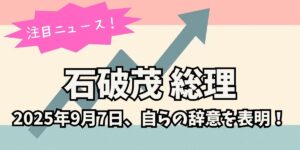
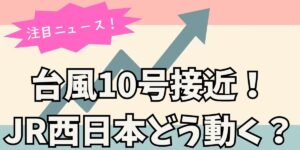



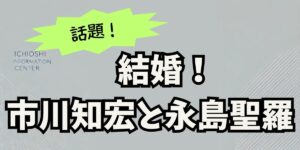
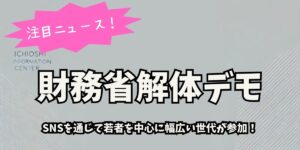
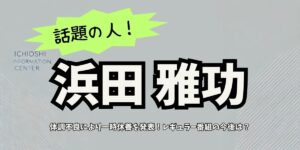
コメント