2025年9月6日(土)朝8時から、『朝だ!生です旅サラダ』のロコレココーナーにて、大友花恋さんが熊本県八代市を舞台にしたスペシャルな旅をお届けしました。
番組では、八代が誇る「冬トマト」、すなわち、10月から6月にかけて出荷され、その濃厚な甘さと豊かな風味で知られる“はちべえトマト”を使った郷土料理を中心に、名産「八代生姜」をきかせた絶品の生姜焼き、さらには“九州最後の秘境”とも呼ばれる幻の絶景スポットまでをじっくり巡ります。
この八代トマトは、ミネラルが豊富で干拓された肥沃な土壌に根ざし、日本一の冬春トマト生産量を誇る産地ならではの品質を持っており、県内外に高い評価を得ています。
加えて、番組ではトマトだけでなく、晩白柚やい草など、八代を象徴する名産品の魅力にも触れられており、地域文化の多様な豊かさを感じられる内容となっています。
本記事では、放送内容と八代の食文化・風景・アクセス・楽しみ方を一挙に整理しました。
「どんな料理が登場したのか」「実際に行くならどんなプランがいいか」「放送後にどう楽しみを続けるか」など、すべてを本記事でしっかりお伝えします。
放送をただ“見る”だけで終わらせず、「実際に行ってみたい」「味わってみたい」という気持ちに自然とつながるよう、最新情報とローカルの息吹を織り込みながらご案内しますので、どうぞご期待ください。
さあ、八代の“トマト旅”がどんな体験だったのか、一緒に見ていきましょう。
放送概要とロコレコ内容の詳細

9/6放送の時間・構成・出演者について
2025年9月6日(土)朝8時から9時30分に、テレビ朝日系で『朝だ!生です旅サラダ』が放送されました。
今回は「ゲストの旅」で佐々木蔵之介さんがルーマニアを旅する一方、「ロコレコ」コーナーには大友花恋さんが熊本県八代市の魅力を地元ロコの案内で巡る構成でした。
ロコレコでは、特産トマトを使った郷土料理や、生姜がきいた生姜焼き、そして“九州最後の秘境”とも称される絶景スポットなど、八代の見どころを多角的に紹介する内容だったことが記されています。
出演者は、大友花恋さんがロコレコを担当し、番組全体としては松下奈緒さん、藤木直人さん、勝俣州和さん、大仁田美咲さんらがレギュラー出演陣として登場しています。
大友花恋が熊本・八代市で紹介した「トマトと生姜焼き」
ロコレコの舞台は熊本県八代市。その中で特にフィーチャーされたのが、八代の地元で作られるトマトと、それを活かした料理。
番組では「特産のトマトを使った郷土料理」とともに、「名産の生姜が効いた絶品の生姜焼き」を大友花恋さんが現地ロコの案内で味わう様子が映されました。
さらに、ふるラボの記事では “八代の冬トマトは、トマト嫌いでも好きになるほど甘い”という表現で紹介されており、実際の収穫や加工工程、い草の田んぼからの流れの中でトマトを楽しむ描写もされています。
その甘さや地元ならではの調理法に焦点を当てた映像が印象的だったと推測されます。
「幻の秘境スポット」って何?ロケ地の特徴
番組内で語られた“幻の秘境スポット”は、ロコレコの案内により紹介された八代市内の自然豊かな景観です。
公式番組情報では“九州最後の秘境ともいわれる幻の絶景スポット”として言及されており、視聴者に八代の知られざる自然美を印象づける内容でした。
ただし、具体的な地名や名称についての言及は公式ページ等に見当たらず、映像やナレーションを通じてのみ紹介された可能性が高いです。
ナレーションやロコの語り口から、その場所が静寂と広がる自然の中にひっそりと存在する、映えるスポットであることが伝わってきた印象です。
八代市の「晩白柚」も登場?
ふるラボの記事には、八代市が誇るもう一つの特産品として「晩白柚(ばんぺいゆ)」も紹介されています。
直径25cmにもなる巨大柑橘で、ゼリーやお菓子にも使われるなど、インパクトあるビジュアルと使い方が魅力です。
記事文中では中丸さんが“八代自慢の『冬トマト』”とともに晩白柚を味わう場面があり、番組同様の特集で取り上げられた可能性が高いことが示唆されています。
この構成から、番組ではトマトだけでなく、晩白柚も並行して紹介されたと考えてよいでしょう。八代の食文化を複合的に伝える内容になっていた模様です。
八代のトマト情報を深掘り

八代の“冬トマト”文化と産地の特長
熊本県八代市は、市町村単位で見ても日本一のトマト生産量を誇る地域です。
これは八代平野というかつて干拓された肥沃な土地が広がっており、ミネラル豊富な土壌と球磨川の清らかな水、それに冬も比較的温暖な気候条件がそろっているためです。
特に“冬トマト”は、この地域の強みを活かして、10月から6月頃まで収穫。
ゆっくり時間をかけて熟すぶん、糖度が高くて濃厚な味わいを持つのが魅力です。
こうした八代トマトはブランド化され、「はちべえトマト」や「塩トマト」として知られ、地元飲食店でもパスタやパン、スイーツなど幅広いアレンジで商品化されています。
また、生でサラダにするのはもちろんのこと、加工品としても人気で、「トマトピューレ(リコプレン)」のように、カクテルや炭酸水にアクセントを加える用途にも使えるものが作られています。
このように八代のトマトは、味・用途・加工という複数の面で高い評価と活用の広がりを示しており、「冬トマト文化」という言葉がまさにぴったりな状況です。
番組で扱われた“トマトを使った郷土料理”の種類と提供店候補リスト
『朝だ!生です旅サラダ』のロコレコでは、八代特産トマトを使った郷土料理の紹介がありました。
具体的な店名は番組情報からは読み取れませんが、熊本の郷土食文化の文脈から、以下のようなメニューが考えられます。
- トマトのだご汁
小麦粉にすりおろしたトマトを練り込み、団子状にして野菜と肉の煮汁で加熱する郷土風のだご汁で、トマトの旨味が染み出す温かい一品です。 - トマトの炊き込みご飯
ざく切りにしたトマトを下火で煮てから米と合わせ、干しえび・昆布茶・オリーブオイルなどと炊き上げる、トマトの旨味がご飯に染み込む炊き込みご飯です。 - 青トマトのピクルス
青トマトを漬けたさっぱり系のピクルスメニュー。保存性があり、トマトの酸味が生きています。
こうした料理は、八代市内の地元飲食店、特産品扱いのお店、道の駅、物産館(例:「八代よかとこ物産館」)などで目にする可能性があります。
また、地元農家グループがレシピを広めている「はちべえグループ」のような取り組みもあり、食育やレシピ展開を通じて郷土料理の普及が進んでいます。
産直・ECで買える“旅サラダ紹介系”ミニトマト情報
八代のトマト産地からは、**直送やEC販売**でも特産トマトが入手可能です。
例えば、「野菜ソムリエ・岡田健志郎さん」が育てるミニトマトは、土づくり・農薬を極力抑える栽培で仕上げられており、トマト本来の自然な甘みと酸味のバランスが特徴です。
口に広がる後味が爽やかで、ついつい何個も食べたくなる味わいだと評価されています。
また、ふるさと納税の返礼品として「はちべえトマト」を使用した製品(例:冬トマト使用の加工品)も提供されており、遠隔地の方も手軽に八代の味を楽しむことができます。
さらに、「八代よかとこ物産館」や関連通販では、トマトピューレ“リコプレン”のような加工品も取り扱われており、料理や飲料に使いやすい形で提供されています。
こうしたEC・産直ルートは、2025年9月6日の番組を見た視聴者が「トマトを家で味わいたい」と思った際に、すぐに注文できる実用的な窓口として機能します。
ロケ地候補とアクセス・モデルコース

八代市中心部〜農園〜食スポット〜絶景スポットの半日コース案
八代市の中心部からスタートする半日コースは、都市の情緒と農村、自然の絶景をほどよく組み合わせた体験型モデルです。
まずは八代駅や新八代駅で下車し、市内のお菓子屋や地元カフェで軽くトマトスイーツやドリンクを楽しみつつ、八代の文化に触れます。
その後、市街地から車で約45分走れば、地元農家直営の農園に到着。
そこで、八代の「冬トマト」を実際に手に取り、味わい深い甘さや、土壌との関わりを感じながら収穫体験を楽しみます。
続いて、車でさらに30分ほど山間へ向かうと、「五家荘」の入口付近へと到達。
ここは山深く、平家の落人伝説が息づく地域で、吊り橋や渓谷沿いの散策路が整備されています。
最後に、山道をもう一歩進むと、迫力ある断崖にある「梅ノ木轟の滝」が待っており、昭和期までは“幻の滝”と呼ばれていた幽玄な水景が目の前に広がります。
都市・農・自然を巡りながら、八代のストーリーを五感で味わえる体験型ツアーです。
公共交通・車でのアクセス/駐車・営業時間の注意点
公共交通を利用する場合、まず目指すは「八代駅」または「新八代駅」。
新幹線を使えば、熊本方面からもアクセスしやすく、駅前からは産交バスや観光列車、乗合タクシーといった公共交通が使用可能です。
2025年8月29日以降は、令和7年7月豪雨の影響によって一部路線が減便されていた産交バスが、9月3日から全線で平常ダイヤに戻るとの発表がありました。
乗合タクシーや鉄道代替バスも通常通り利用でき、以前より安定したアクセスが確保されています。
車でのアクセスに関しては、「五家荘」へ向かう場合、九州自動車道の松橋インターチェンジから国道218・445号を通って約90分。
また、途中にある「梅ノ木轟の滝」には駐車場が整備されており、滝まで徒歩で10分ほどでアクセスできます。
ただし、紅葉シーズンなど観光ピーク時には、五家荘周辺で一方通行規制や混雑が発生しやすいため、出発前には最新の交通規制や道路情報の確認をおすすめします。
“九州最後の秘境”と呼ばれるスポットの安全・マナーガイド
「五家荘」は、山間部の標高1,300~1,700メートルの深い峡谷に広がる地域で、平家落人伝説を今に伝える、まさに森林と渓谷が織りなす“秘境”です。
ここへ訪れる際の安全対策としては、靴は滑りにくいトレッキングシューズを選び、急な雨に備えて軽いレインウエアを携帯するのが基本です。
また、吊り橋(たとえば「樅木の吊橋」に代表されるような橋)は構造上揺れがあり、高所恐怖症の方には体験が難しい可能性もあります。
上から橋を見下ろすような撮影アングルなど、慎重に行動することが求められます。
さらに、このような自然豊かな秘境を保全するため、登山道や周辺の草木を荒らさない、ゴミの持ち帰り、野生動物に餌を与えないなど、自然への配慮を忘れずに、訪問マナーを守るよう呼びかけられています。
地域の静けさと神秘があるからこそ、その価値を尊重した行動が必要です。
放送連動:再視聴・連載記事・SNS反響

再確認リンク:旅サラダPLUSと各回まとめ(ロコレコ未公開など)
『朝だ!生です旅サラダ』では、テレビで放送された内容を深く楽しみたい方向けに、『旅サラダPLUS』という公式WEBサービスを運営しています。
ここでは、番組内で紹介されたグルメのお取り寄せ情報に加え、ロコレココーナーの本放送では見られなかった未公開映像も公開されており、放送後に追加で視聴できる充実のオンラインコンテンツが揃っています。
また、『旅サラダPLUS』のSNS(特にX/旧Twitter)では、番組の裏話や次回予告、スタッフによるコメントなども定期的に配信されており、番組を通じて旅をさらに深掘りできる魅力的な補足情報が得られます。
当日・放送直後の番組表&地域局情報まとめ(KAB・OABなど)
2025年9月6日の放送について、地元熊本では「KAB(熊本朝日放送)」および「OAB(大分朝日放送)」などの地域系列局でも同時刻帯または直後に番組が展開されました。
特にOABの公式番組表には、8時からの放送内容として“佐々木蔵之介のルーマニア旅”と“大友花恋の八代ロコレコ”が明記されており、地域局でもプロモーションや内容紹介がしっかり行われていたことが確認できます。
こうした番組表の確認は、放送日時の再確認や見逃しチェック、視聴予約時の参考情報として視聴者に役立ちます。
X(旧Twitter)の反響・告知ポストまとめ(ゲスト旅/ロコレコ事前告知)
X(旧Twitter)などを通じた番組側の投稿では、事前に今回の放送内容についての告知が行われていました。
たとえば、「9月6日(土)朝8時から放送の…『ロコレコ』で八代市が特集されます!」という投稿には、特産トマトや生姜焼き、幻の絶景スポットに触れられており、地域の見どころを効果的にPRしていたことが伺えます。
さらに、視聴者からのリアルタイムの反応や投稿も、番組中から即時に集まり始めています。
番組ハッシュタグには「#旅サラダ」「#熊本トマト」などをつけて、視聴者が写真や感想、地元ネタなどを投稿しており、地域ファンから全国視聴者へと広がる双方向の盛り上がりが見て取れます。
まとめ:八代“トマト旅サラダ”放送回を最大限に味わうために

朝だ!生です旅サラダで紹介された熊本の特産トマトについて関心をお寄せいただいた読者の皆さま。
この記事では、八代市のトマトを中心に据えた放送内容、地域と共にある食の魅力、訪問モデルコース、そして放送後の楽しみ方まで網羅的に整理しました。
まず、八代の“トマト文化”は豊かな土壌と冬でも続く収穫期間によって、糖度が高く濃厚な味わいを誇る「冬トマト」が根幹にあります。
地元の特色として「はちべえトマト」や「塩トマト」としてブランド化され、幅広い料理や加工品にも使われている点は見逃せません。
これは、大友花恋さんが紹介したその「郷土料理」の背景として、地域の食文化を理解する上でも重要な要素です。
また、番組は八代の自然豊かな「幻の秘境スポット」にもフォーカス。都会では味わえない静かな峡谷や渓谷、棚田の中、滝の美などがVTRを通じて印象的に描かれました。
これを受けて、地元アクセス情報やモデルコースを組んだ体験は、視聴後のリアルな旅体験へとつながります。
さらに、放送後の楽しみとしては、以下のようなものがあります。
- 無料見逃し配信サービス
テレビで見逃してしまった方は、TVerでの無料見逃し配信をご活用いただけます。 - 「旅サラダPLUS」でのWEB追体験
番組公式サイト「旅サラダPLUS」では、放送では見られなかった未公開映像や、番組内で紹介されたグルメのお取り寄せ情報などを楽しむことができます。 - SNSや地元オンラインショップの余韻
Instagramでは、八代の地元食材を生かしたジェラート開発企画など、放送関連の投稿も出ています。
また、ふるさと納税や地元通販では、“冬トマト”や“晩白柚”などの特産品を購入して、家庭でその味を体験する楽しみもありました。
八代市のトマトはまさに「大地の甘み」が詰まった魅力のひと粒であり、放送を通してそれが五感で伝わる演出が心に響きました。
記事を書きながら改めて感じたのは、旅サラダという番組の持つ力——美味しさと風景、ローカルの温かさを同時に届ける力です。
これをきっかけに、番組を“見る”だけで終わらせず、「食べてみたい」「行ってみたい」「知りたい」という好奇心につなげていただけたらとても嬉しいです。
今後も、放送された魅力をしっかりと掘り下げ、記事として丁寧にお届けしますので、次回もぜひお楽しみに!

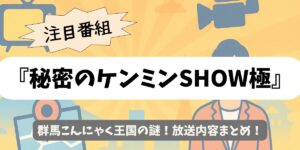
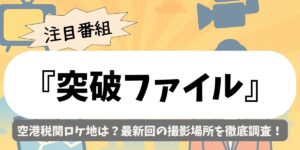
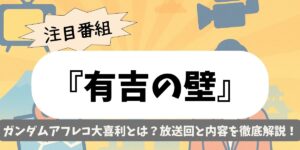
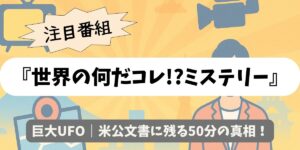
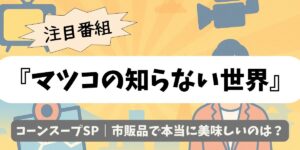
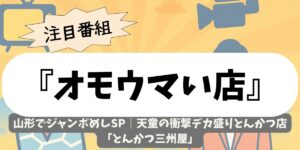
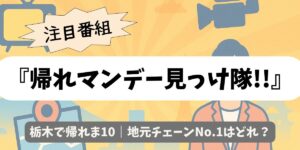

コメント