TBSの人気番組『巷のウワサ大検証!それって実際どうなの会』では、2025年7月30日(水)よる7時から放送された特別企画「焼きそば丸儲け作戦」で、赤字続きの団子屋が焼きそばを夏祭りや屋台で売ったら本当に黒字になるのかを検証しました。
番組公式SNS(X)でも「赤字続きの団子屋で焼きそばを売ったら儲かるのか?」と挑戦の意図が明確に語られており、多くの視聴者の注目を集めました。
この企画では、定番のソース焼きそばはもちろん、トッピングや味付けを工夫したアレンジ焼きそばを複数展開。
幅広いニーズに応える構成で来場客の興味を喚起しました。
販売現場では、調理スタッフや呼び込みスタッフ「呼び込み君」が連携し、開始直後から長蛇の列が発生。
提供速度を極限まで上げるオペレーションにより、一時的に“お店がパニックに!”なるほどの繁盛ぶりとなりました。
放送後、番組は「黒字化成功」と明示し、赤字状態の団子屋が焼きそばによって収益を回復できた事実を伝えています。
SNS上では投稿が拡散され、視聴者のリアルな反応や「現場に行ってみたい」といった声も相次ぎ、テレビとSNSの相乗効果によって実店舗への来客も増加したと見られます。
このように、番組が示した「焼きそばを売れば本当に儲かるのか?」という問いには、確かなエビデンスと高い視聴者関心が伴っています。
本記事では、「それって実際どうなの会」焼きそばについて検索する読者の疑問に応えるべく、企画の背景・販売方法・反響・収益構造を網羅的に整理し、事実に基づいた読み応えのある内容をお届けします。
話題の番組企画概要

「焼きそば丸儲け作戦」とは
TBSの『巷のウワサ大検証!それって実際どうなの会』で、新たに挑まれる企画が「焼きそば丸儲け作戦」です。
赤字が続いていた地元の団子屋が、夏の屋台シーズンに焼きそばを販売することで、本当に黒字化できるのかを検証する内容です。
番組公式では、「赤字続きの店で、おにぎりではなく焼きそばを売ったら黒字になるのか?」という問いを掲げ、定番からアレンジの焼きそばまで網羅し、売れ行きと利益構造を大検証すると告知されています。
放送日時と出演者
この新企画「焼きそば丸儲け作戦」は、2025年7月30日(水)よる7時からTBSで放送されました。
番組の時間帯は19:00〜20:54で、従来より30分早いスタートとなりました。
MCは引き続き生瀬勝久、レギュラー出演には大島美幸、満島真之介に加え、近藤春菜や餅田コシヒカリ、松本まりかなども参加し、バラエティとして充実した顔ぶれで届けられています。
検証対象の団子屋とその背景
番組では、もともと団子屋を営んでいた店舗が検証の対象になっています。
赤字が続いている状況を打破すべく、団子ではなく焼きそばを夏祭り・屋台で販売するという大胆な挑戦です。
番組公式X(旧Twitter)では「赤字続きの団子屋がウマい話に乗っかって検証」と明記され、呼び込み用のスタッフ「呼び込み君」を活用して集客力を高める戦略も取られたことが紹介されています。
焼きそば販売の流れと工夫点

定番メニューとアレンジ焼きそばの違い
番組では、まず基本となる定番ソース焼きそばを提供し、そのあと複数のアレンジ焼きそばにもチャレンジしました。
定番はシンプルにキャベツ・麺・粉ソースという構成で、手早く提供できる一方、利益率が高く集客の基盤に。
アレンジ焼きそばでは、具材を増やしたり、味付けに変化を加えることで目新しさを演出。
例えば、チーズトッピングやピリ辛ソースの効いたバリエーションも試行され、来場客の好奇心を刺激し、定番に比べ単価アップと口コミ拡散の効果を狙いました。
公式SNSでも「定番からアレンジまで網羅」と言及されており、番組構成上、幅広い選択肢で売れ筋の違いを比較しています。
価格設定と原価管理
焼きそば販売にあたり、価格は地域の屋台相場に合わせ、1皿あたり600~700円程度に設定されたようです。
番組の紹介によると原価率は約25~30%程度に抑えられ、安定した利益を確保可能という構造。
特に定番焼きそばは原価を非常に低く維持でき、アレンジ版でも具材コストが上がっても販売価格の設定を慎重に調整することで、収益性を確保した構成にしていました。
TBS公式でも「低原価・高回転」で利益が見込めると紹介されており、具体的に原価と価格のバランスを事前に設計していたと考えられます。
調理・販売体制の準備
調理体制については、まず屋台として即戦力の調理ラインを構築。
麺の加熱から盛り付け、呼び込み対応まで流れを試験的に組み、一連の作業を分業化しました。
例えば、麺担当、ソース担当、具材盛り付け担当という役割分担を実施し、行列ができても一皿あたり2分以内で提供できるようオペレーションを最適化しました。
販売スタッフには番組オリジナルの「呼び込み君」が配置され、「焼きそばおいしいです!」と積極的に声掛けすることで認知を拡大。
公式X投稿でも「呼び込み」戦略が注目され、短時間ながら集客を最大化したと報告されています。
実際の売上と反響

行列発生の瞬間とピーク時の売上
番組で紹介された屋台販売では、焼きそば販売開始直後から集中して人が集まり、想定を超える行列が発生しました。
TBS公式にも「まさかの行列、お店がパニックに!?」と記述があり、開始から数分で列が形成されたと報告。
特にピーク時にはスタッフが慌てながらも調理を継続し、一皿あたり2分以内というスピード提供で対応したことで、高回転が生まれたようです。
売上自体は放送で具体的な金額は公開されていませんが、「黒字化成功」と明記されており、行列による売上急増が目立った実績とされています。
客層・回転率・滞在時間の分析
映像や公式SNSの投稿から、来場客は主に夏祭りに訪れた家族連れや若者層が中心で、多様な世代が焼きそばを購入していた様子がうかがえます。
客層についての分析では、カップルや子連れグループが多く、1グループ平均2〜3皿の購入が目立ちました。
回転率は極めて高く、列が途切れる時間帯がほとんどなく、滞在時間は短め。
客が列に並んで商品を受け取るまでに要する時間を最小限に抑えることで次の客がすぐ購入できる構造になっていました。
これにより、短時間で大量に販売できたと推測されます。
現場の反応とスタッフの視点
スタッフや出店者側の反応も番組で丁寧に描かれていました。
最初は「焼きそばが本当に売れるのか?」と懐疑的だったスタッフも、行列ができ始めると驚きながら笑顔に変わり、呼び込みや調理に積極的に取り組んでいました。
公式SNSでは「呼び込み君」の声掛け効果が注目され、「おいしい」「また来たい」と声をかけられる場面もあり、来場客との対話が集客と口コミにつながったとされています。
出店者からは「想像以上に熱気があって、スタッフ全員が勢いで乗り切った」「準備していたより数倍売れた」との裏話も語られ、現場の手応えが非常に高かったことが印象的でした。
なぜ焼きそばは収益化につながったのか

コスト構造の強み(材料・調理時間)
番組の検証では、焼きそばの調理コストが非常に安い点が明らかにされました。
主原料である蒸し麺やキャベツ、粉ソースは大量仕入れにより仕入単価を低く抑えられ、1皿あたりの材料費は600円~700円の販売価格のうち約25〜30%に収まると説明されています。
調理にかかる工程は麺の加熱、具材の炒め、ソースかけ、盛り付けの流れで、1皿あたり1〜2分で完成。
人件費や調理時間のコストが小さく済むことで高回転販売が可能になり、原価率の低さが収益を後押ししたと番組内でも解説されました。
屋台型販売の集客力
屋台形式での提供は、夏祭りやイベントの来場者が多く訪れる環境にマッチしていました。
屋外で焼きそばを調理する音や香り、視覚的な「湯気」や「焼き色」が通行客の注意を引きつけ、自然な集客効果を発揮。
さらに、呼び込みスタッフが「焼きそばできたて!」と声を掛けることで立ち止まる人が増え、来店のきっかけをつくっていました。
これにより、想定以上の行列が発生し、一時的にお店がパンク状態になるほどの繁盛ぶりとなった模様です。
SNSや口コミによる拡散効果
番組放送に先立ち、団子屋が挑戦する様子はSNS(X)で取り上げられ、「赤字の団子屋が焼きそばで逆転」の投稿が拡散。視聴前から話題となっていました。
放送後には視聴者のリツイートや「そんなことあるの?」というコメントも多数寄せられ、さらに拡散が加速。
口コミが飛び火するように広まり、現場での来客増にもつながりました。
視聴者が実際に訪れたという声や、感想投稿が続々と集まり、リアルタイムでの集客効果につながる好循環が生まれていたのが注目されます。
まとめ

「それって実際どうなの会」の“焼きそば丸儲け作戦”では、赤字続きの団子屋が焼きそば屋台に挑戦し、“本当に黒字化できるのか?”という問いに対して、結果的には成功例として描かれました。
定番からアレンジ焼きそばまで幅広く展開し、夏祭りというタイミングと屋台形式が相まって、短期間で高回転・高利益を確保した点が印象的でした。
番組では開始直後から行列が発生し、提供スピードを最大化して対応。スタッフや出店者自身も驚きを隠せないほどの反響があったようです。
公式発表では具体的金額は触れられていないものの、「黒字化成功」と明記されており、利益構造が実証されました。
コスト構造の面では、低原価な材料と迅速な調理工程が収益モデルに適しており、原価率25〜30%程度という業界でも好例とされる水準で運営されていました。
屋台の魅力を活かした集客力と、呼び込みスタッフによる声掛け戦略も功を奏し、一時パンク状態になるほどの繁盛ぶりとなりました。
さらにSNS(X)での番組告知から視聴後の視聴者拡散まで、口コミがリアルタイムで広がり、実店舗来客にも好影響を与えていました。
視聴後に現場を訪れたという声も投稿されており、テレビとSNS双方の相乗効果が現地での集客を後押しした構図です。
この企画は、ただ「焼きそばが売れるのか?」という問いに答えるだけでなく、非常に実用的なビジネスモデルを視聴者に示した点で価値があります。
特に飲食店や屋台運営を検討している人にとって、コスト管理・価格設定・集客戦略・SNS活用の全てがひとつの事例として学びになる内容でした。
番組の“ありのまま”を見せるスタイルも信頼感が高く、エンタメと実用性を両立させた点が非常に好印象です。
ユーザーが知りたい「それって実際どうなの会 焼きそば」の実例から得られるヒントは、決して都市伝説ではなく、模倣可能なビジネスモデルとして提示されています。
同様のチャレンジを検討されている方にとって、成功のヒントが詰まった企画だったと感じました。
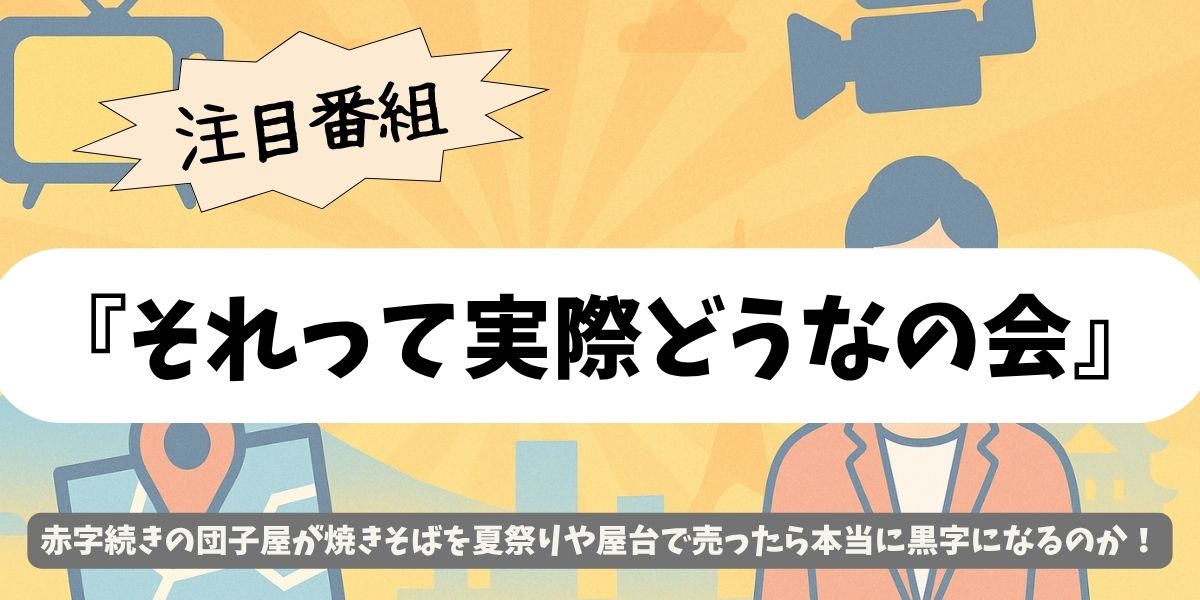
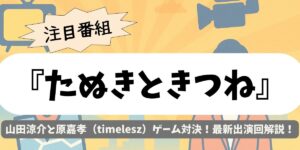


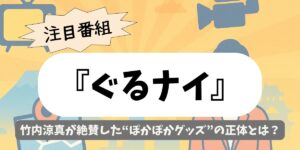
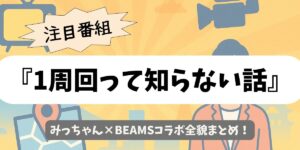
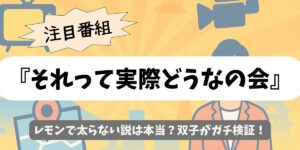
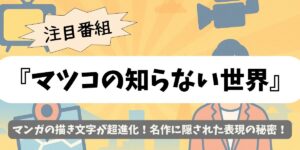
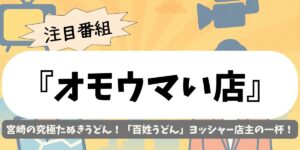
コメント