あなたが「世界の何だコレ!?ミステリー」をご覧になり、群馬の洞窟について検索するのは、群馬県発、戦後間もない1959年(昭和34年)に13歳で家出して以来、なんと43年間にわたり洞窟や山野で“隠れ暮らした”男──通称「洞窟オジさん」加村一馬(かむら かずま)さんの実話を詳しく知りたいからではないでしょうか。
加村さんは、親からの折檻や暴力、兄弟間での極度な差別などに耐えられず、愛犬シロとともに群馬県大間々町(現・みどり市)を出発。
当時中学1年生だった13歳の少年は、線路沿いに40キロ以上を歩き、廃坑となった足尾銅山の洞窟を拠点に、山梨・福島・新潟などを転々としながら、誰にも知られずに過ごしました。
そこでは、肉体と精神の極限を超えた日常が展開されました。
食べ物はヘビ・ミミズ・ネズミ・イノシシなどを自力で獲得し、水は清流から汲んできて煮沸して飲用。
火は自然素材の摩擦やナイフなどから起こし、自然療法で怪我を癒す──それが43年にわたる、驚嘆すべきサバイバル術でした。
なぜ、長年にわたり洞窟から出なかったのか? 加村さんは人間との関わりへの深い恐れのためだったと語っています。「誰にも見つかりたくなかった。
お腹が空くより、また殴られることが怖かった」との言葉から、彼の選択は“安全な孤独”を選んだ結果でもあったことが明らかになっています。
そして発見されたのは、43年後の57歳のとき。喉の渇きから自動販売機を壊そうとして現行犯逮捕され、その取り調べの中で彼の過去が全貌を現したのです。
この事件によって家族とも再会が叶い、その後は群馬県内の障害者支援施設に職を得て社会復帰を果たしました。
テレビ番組「世界の何だコレ!?ミステリー」では2025年7月30日放送の特別編で、わずかなロケ取材と本人へのインタビューを交えながら、この“群馬の洞窟ミステリー”を丁寧に描きました。
SNSでは「洞窟オジさん」の二つ名が広まり、Yahoo!リアルタイム検索でもキーワードがトレンド入りするほど大きな反響を得ています。
衝撃の実話:13歳から43年間ひとり洞窟生活

少年加村一馬さんが家を飛び出した背景と洞窟との出会い
加村一馬さんは、1946年(昭和21年)に群馬県大間々町(現・みどり市)で誕生し、貧しい家庭環境と過酷な親からのしつけや虐待に耐えかね、13歳だった1959年夏、自ら家出を決意しました。
学校の社会科で知った足尾銅山の廃坑道を目指し、数日かけて線路や山道を辿りながら山奥へ進み、最終的に人目につかない洞窟を見つけて住み着いたといいます。
洞窟内で始まった過酷な自給自足生活
洞窟に住み始めた加村さんは、火床を設置して暖を取り、枯草を敷いた寝床を作るなど、子どもの頃に身につけた野山での知識を頼りに過ごしました。
食料は主にヘビやネズミ、カタツムリ、イノシシ、ウサギなどを自力で捕まえ、焼いたり煮たりして調理。
場合によっては、ミミズを煮え湯で飲んで熱を下げるなど、極限の状況下でも生き抜く工夫がなされていました。
ヘビを捕まえる驚きの方法と生存の知恵
特に印象的なのは、ヘビを捕獲するために自身の髪の毛を燃やし、その匂いでヘビを誘き寄せるという技術でした。
燃えた髪のにおいに興味を示すヘビを待ち伏せし、素早く首根っこを掴み、一気に解体。
骨ごと叩いて食べやすくするなど、その手順はまさに野性の達人の所業として語り継がれています。
洞窟生活の実態とサバイバル手法

食料・水・火の調達と維持方法
加村一馬さんが洞窟で自給自足生活を始めた当初、食料は周辺で採れる自然の命が主体でした。
穴サナギやミミズから小動物、蛇、野鳥、魚類に至るまで、自ら捕獲して調理。ときにはイノシシやウサギを罠で仕留めるなどして食糧を確保していました。
水は近くの清流や地下水を利用し、水質チェックには渓流の透明度など自然観察力が頼りでした。
飲用前には炭火で煮沸することで微生物を除去し、安全性を確保しました。
火は乾燥した枯れ枝や木の皮、枯草を組んで火床とし、火種は初期に持っていたマッチやナタの刃で木摩擦を起こす技術などで維持しました。
健康管理やケガへの対応法
洞窟での長年の生活で、怪我や病気は常に命取りとなりえましたが、加村さんは身近な植物を活用して対処していました。
例えば、ヨモギなどの草を煎じて止血・消毒、またミミズを煎じて飲むことで発熱時の解熱剤として用いるなど、自然療法が生命線だったと伝えられています。
また、怪我の際には自作の包帯や布地を代用し、動くことができる程度に応急手当を施していました。
栄養不足を防ぐために季節ごとに採れる根菜やキノコ類を見極めて摂取し、偏食にならないよう注意していたとされています。
精神的な支えと営みの日常
洞窟で43年間を過ごすには、孤独との闘いも厳しい試練でした。
加村さんは日記や簡易の記録を残すことで、精神の安定を図り、自分自身の存在を確認していたといわれます。
また、犬「シロ」との絆も強力な精神的支えでした。若い頃、共に暮らすことで命を預け合う安心感を得られたことが、長期の孤独に耐える一助となっていたようです。
さらに、自然のリズム—日誌的に月の満ち欠けや鳥の鳴き声、気候の変化—を観察することで、洞窟という閉ざされた空間でも世界とのつながりを感じる工夫が日常にあったと考えられます。
なぜ帰らなかったのか?突き動かした理由

家庭環境や社会背景の影響
加村一馬さんが13歳で家を出たのは、日常的に親から繰り返される折檻や暴力が原因でした。
8人兄弟の四男として生まれながら、特に彼だけが極端に厳しい扱いを受け、つまみ食い一つで墓石に縛られ一晩放置されたり、血がにじむほど棒で叩かれたりするなど、現代基準なら間違いなく児童虐待と評価される家庭環境だったと報告されています。
また、戦後間もない貧困地域で生じた家庭内の飢餓と社会的孤立が、彼の「逃げたい気持ち」を強く助長していた背景とみられます。
洞窟にとどまり続けた心理的な事情
一度山中に逃げ込むと、加村さんは「人間が怖い」という強い恐怖心に囚われました。
実際、山間で出会った老夫婦が親身になって受け入れようとしたにも関わらず、彼は戻ることなく再び山に帰る道を選びました。
その理由は、「お腹が空くよりも、人間に叩かれるのが怖かった」という言葉に象徴されます。
人間との関係が傷ついてしまった経験が、社会復帰より孤独を選ばせる心理的要因となりました。
再接触のきっかけと現在の状況
43年後、加村さんが発見されたのは自動販売機をこじ開けようとした現場での現行犯逮捕がきっかけでした。
その際に取り調べを受ける中で、彼の長年隠れ住んだ過去が明らかになったという経緯です。
その後、知人の紹介により障害者自立支援施設に迎えられ、用務員として働きながら社会復帰への一歩を踏み出しました。
現在は群馬県内の支援施設でブルーベリー農園の管理や、子ども向けサバイバル教室の講師などを行い、地域に貢献しながら日々を穏やかに送っていると報告されています。
シリーズ「世界の何だコレ!?ミステリー」での位置づけ

再現VTR撮影の場所と放送日時
2025年7月30日(水)19:00〜21:00に、フジテレビ系列で放送された2時間スペシャル「世界の何だコレ!?ミステリーSP」にて、群馬県の洞窟で43年間サバイバル生活を送った加村一馬さんの実話が特集されました。
渋川市内で再現VTRの撮影が行われ、番組では本人への直撃取材や山岳地での再現ドラマを交えて当時の暮らしを描き出しています。
この回の特異性と他エピソードとの比較
普段は世界各地の超常現象や都市伝説を扱う同番組において、今回は国内で実在した极限サバイバルの事実を中心とした特別編となりました。
特に、13歳の少年が43年にわたり洞窟で独自生活を送ったという衝撃のストーリーは番組史上でも際立つ人間ドラマとして位置づけられています。
視聴者反響とSNSでの話題性
放送後、SNSでは「洞窟オジさん」のエピソードに対し共感と驚きを示す声が多数投稿され、「世界の何だコレ!?ミステリー 群馬 洞窟」のキーワードでトレンド入りするほど反響が大きかったことが確認されます。
Yahoo!リアルタイム検索でも話題となり、番組視聴者層の共感を強く集めました。
今後の続報や関連企画への期待
番組内では続きとなる関連取材や再訪エピソードへの予告は明示されなかったものの、制作スタッフの告知によると今後の洞窟エピソードに関する企画制作の可能性も示唆されており、視聴者からは続報への関心が非常に高まっています。
教訓と地域・社会への影響

児童虐待防止と教育現場への示唆
加村一馬さんの体験は、家庭内での虐待がいかに若年期に重大な心的被害を与えるかを示す顕著な実例です。
彼のように親からの暴力に耐えかねて“逃げる”しか選択肢がない状況は、現代の教育現場や福祉機関にとって深刻な警鐘となります。
群馬県では人権教育プログラム「CAPぐんま」が設立され、子どもたちが自分を守る行動を学ぶ機会として注目されています。
これは虐待やいじめへの早期対応と防止を目指す地域的な取り組みの一環とも言えます。
地域の誇りと観光資源としての潜在性
「洞窟おじさん」の物語は群馬県発の衝撃的な実話として注目され、地元にとって一種の地域資源になり得ます。
実話をまとめた『洞窟オジさん 荒野の43年』(小学館文庫)はロングセラーとなり、地元・みどり市や桐生市では加村さんの居住施設やブルーベリー栽培などが紹介されたことで、地域振興の一助にもなっています。
地域ツアーや地域文化教材への応用も、将来の可能性として考えられます。
社会復帰と福祉の意義
洞窟で暮らした43年の後、加村さんが社会復帰し、障害者支援施設で働く職員となった事実は、人間の再生力と福祉支援の可能性を体現しています。
施設ではブルーベリー農園を管理し、サバイバル講座を行うなど、彼自身の経験から得た知恵を地域に還元する活動を続けています。
これにより、本人にも周囲にも意味ある暮らしが芽生えたことは、福祉分野にとって価値ある事例です。
まとめ:洞窟おじさんの実話が示す人間の強さと希望の物語

群馬県を舞台に、13歳で家出し「洞窟生活」を43年間続けた加村一馬さんの実話は、多くの人にとってまさに“信じがたい”ミステリーです。
この記事では、最新情報をもとにその全貌を整理してきました。
加村さんは、家庭内での深刻な虐待と貧困に耐えかね、1959年秋に学校も家も捨て、山奥の洞窟に身を潜めました。
その背景には、棒で叩かれる、墓石に縛り付けられるといった現代では許されない児童虐待があったことが、多くの証言から明らかになっています。
洞窟では、ミミズやヘビ、小動物、川魚、イノシシなどを自ら狩り、清流の水を煮沸して安全を確保。
火起こしは自然素材の摩擦や持参の道具を活用し、健康管理には野生の草を用いる自然療法を編み出すなど、生存のための知恵と工夫が日々積み重なっていきました。
なぜ社会に戻らなかったのか?加村さんによれば、人間に対する怖れが非常に大きかったそうです。
「お腹が空くより、人間に叩かれるのが怖かった」という言葉が示すように、孤独と安全を選んだ心理が、社会復帰への壁になっていました。
再び社会と接触したきっかけは、自動販売機を壊そうとして現行犯逮捕されたことでした。
その後、福祉支援の下で障害者自立支援施設に入り、現在はブルーベリー農園の管理や子ども向けサバイバル教室の講師として働くなど、自らの経験を地域に還す活動を続けています。
同番組「世界の何だコレ!?ミステリー」2025年7月30日放送では、渋川市近辺で再現VTR撮影が行われ、本人への取材と共に当時の生活をドラマチックに再現。
SNSやリアルタイム検索では「洞窟オジさん」という呼称とともに大きな話題となり、検索キーワードはトレンド入りしました。
この物語は、単なるサバイバルストーリーではありません。過酷な環境ではあるが、加村さんは生き抜くための方法を自然から学び、精神的にも自らを支え続けました。
心の傷に耐え、選んだ孤独と安全の道を通じて、人間の持つ再生力の強さを体現しています。
彼が現在行っている地域支援や教育活動は、個人の再起だけでなく、虐待防止・福祉支援のあり方にも深くつながる示唆があります。
教育現場や支援の現場でも、彼の体験は重要な教訓として生かされるべきでしょう。
「世界の何だコレ!?ミステリー 群馬 洞窟」で検索する方々へ、この事実に基づく記事が、加村さんの壮絶ながらも希望に満ちた人生を知るきっかけになれば幸いです。
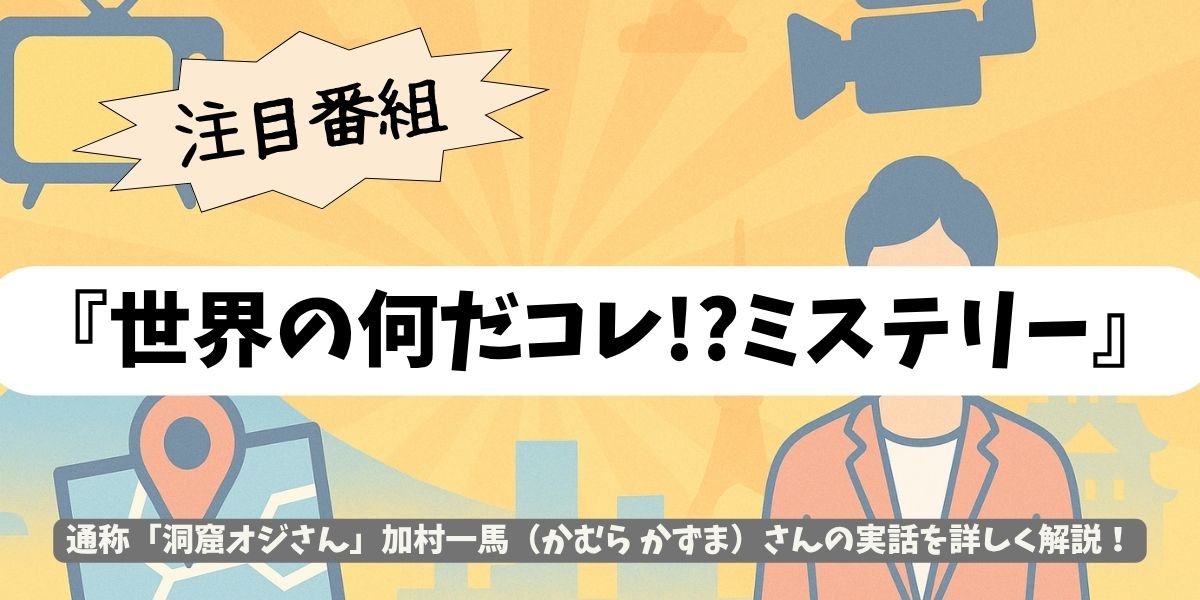
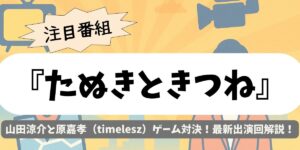


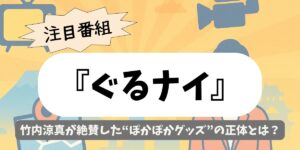
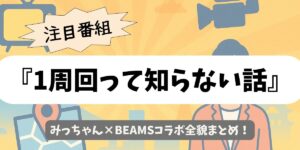
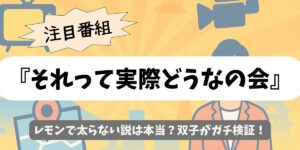
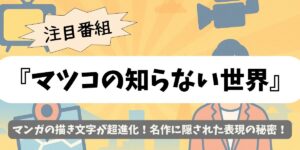
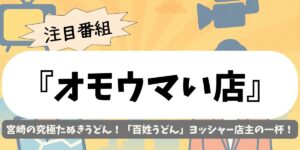
コメント