「相葉マナブ 〜地引き網で大調査!〜」の最新回は、千葉県旭市の地元名所 九十九里浜 を舞台に、季節の海の恵みを丸ごと追いかける一大ロケ企画です。
2025年10月26日(日)18:00~18:56に放送されるこの回では、なんと550 mもの長さの綱を人力で引く“本格地引き網漁”にチャレンジ。
公式サイトでも「この時期は“アジ”“イワシ”“クロダイ”、珍しい魚だと“エイ”も獲れることがあるのだとか!」と紹介されており、普通の漁体験を超えた壮大さとワクワク感が漂っています。
本記事では、「相葉マナブ 九十九里浜 地引き網」という検索キーワードを入力してこの放送をチェックしようとしている“あなた”のために、放送前に押さえておきたいポイントをわかりやすく整理します。
どんな魚が獲れるのか、どんな漁法なのか、そして実際に訪れるなら知っておきたいアクセス情報や体験のヒントまで――番組を「ただ観る」だけで終わらせず、「観て・知って・行ける」形で楽しめるように、最新の公式情報をもとに忠実にまとめました。
今夜の放送が、海の迫力と旬の魚の魅力、そして地域の伝統漁のドラマを体感できる特別な時間になることを、ぜひこの導入でイメージしてみてください。
放送の基本情報と見どころ総覧

「地引き網で大調査!〜九十九里浜〜」放送日時・局一覧
2025年10月26日(日)18:00〜18:56、テレビ朝日系列にて放送。
公式サイトの「次回予告」と各種番組表が同一内容で告知しており、放送時間・回タイトル・企画要旨(九十九里浜での地引き網と“獲れた魚で絶品調理”)が確認できます。
地上波本放送はテレビ朝日、番組表連携サービスでも10月26日(日)18時台の枠で掲載されています。
参加メンバーと役割(相葉/小峠/あばれる君/岡部大)
出演は相葉雅紀さん(MC)に、小峠英二さん(バイきんぐ)、あばれる君さん、岡部大さん(ハナコ)が参加。
ナレーターは神奈月さん・杉本るみさん。
今回のロケは「伝統を残すため有志で地引き網漁をしている」という視聴者投稿がきっかけで、千葉県旭市の九十九里浜で“完全人力”の地引き網に挑戦します。
“包丁王子”が地魚を捌いて握りに
当日引き上げた魚は番組名物“包丁王子”がその場でさばき、握り寿司に。
予告では、綱の全長は約550mで、アジ・イワシ・クロダイのほか、珍しい例としてエイが入ることもあると説明。
地引き網のスケール感と“とれたてを握る”ライブ感が、この回の最大の見どころとして強調されています。
九十九里浜の地引き網:場所・方法・当日の流れ

ロケ地は千葉県旭市の九十九里浜エリア/集合〜網入れ〜巻き上げの手順
今回の企画は、九十九里浜(千葉県旭市エリア)で行われます。
番組公式ページでは、「千葉県旭市の“九十九里浜の海”にやってきました!」と明記されており、地元有志が伝統を守るため実践している漁法を訪ねる、という形です。
海岸ではまず、参加者が浜に集まり、安全祈願や漁具の準備を整えた後、沖合へ船を出して網を仕掛ける流れが紹介されています。
例えば、番組告知の中には「全て人力で地引き網漁を行っており、550 mの綱を引っ張る必要があるのだそう!」との記述があり、綱の長さ・手作業の大変さが強調されています。
また地元の漁法資料によれば、九十九里浜では浅瀬を活かした「大地曳網漁」が行われており、沖合で大きな網を張り、砂浜まで引き寄せて一気に巻き上げる手法が古くから存在します。
このように、番組では集合→船出→網設置→綱引き→引き上げという一連の体験流れを、視聴者に“体験をともに”感覚で届ける構成になっています。
完全人力・約550 mの綱:必要人数と安全祈願の所作
番組内で明かされた「綱の長さ:550 m」という数字は、参加者だけでなく視聴者にもそのスケール感を伝えるために重要な要素です。
公式サイトでは「550 mの綱を引っ張る必要があるのだそう!」と書かれています。
このような長大な綱を人力で引くには、複数の参加者が綱に取り付いて浜と船の間を引き合う協力作業であることが想像されます。
実際、過去の地引き網漁の記録では浜では100人を超える作業者が網を引き上げていたという史実があります。
また、安全祈願や漁の成功を祈っての所作も番組内で軽く触れられており、伝統漁法の敬意を表す場面としての演出も確認できます。
例えば、ブログ投稿では「安全祈願と大漁を願って大漁旗を立て、日本酒を船にかけたら、船を沖に出し送り出します!」という記述があります。
このように、漁の始動だけでも“伝統”“連帯”“自然との共生”といったテーマが垣間見え、単なる体験では終わらない深みがあります。
旬魚ラインナップ(アジ・イワシ・クロダイ・エイなど)
番組予告では、地引き網によってこの時期に特に期待される魚種として「アジ」「イワシ」「クロダイ」、さらには「エイ」という珍しい魚も獲れる可能性がある、と紹介されています。
例えば、番組内容一覧では「アジ、イワシ、クロダイ、エイなども獲れると聞き、4人は期待を寄せる」と記載されています。
さらに、九十九里浜の伝統漁についての資料では、遠浅な砂浜と潮流の関係からイワシの群れが押し寄せることが多く、地引き網の対象として長く使われてきたことが紹介されています。
したがって、番組では“旬魚をその場で獲る”“とれたてを調理”という流れが視聴者の目線でも構成されており、魚種ラインナップが放送のキーになります。
さらに、エイのような意外な魚種が“何が入っているか分からない”というワクワク感を演出しているのもポイントです。
料理・レシピ・番組連動情報

番組内で作られた握りと“とれたて魚料理”一覧
今回の九十九里浜ロケは「地引き網で獲れた魚を包丁王子がその場で捌き、握る」ことが公式予告で明言されています。
握り寿司の実演は本回のコア見どころで、当日の漁獲に応じてネタが決まる構成です(予告段階で想定されている魚種はアジ/イワシ/クロダイ、珍例としてエイが入る可能性にも触れられています) 。
実際の放送枠(10月26日〔日〕18:00〜18:56、テレビ朝日系)も告知されています。
X(旧Twitter)の番組公式アカウントでも、同回の案内と「地引き網→包丁王子が握る」流れが周知されています。
放送までの時点で確定している“料理名”としては握り寿司の提供までが公式情報で、その他の一品は“絶品調理”として予告される段階です(放送後に公式レシピページへ追補されるのが通例)。
家で再現しやすいレシピとコツ(番組バックナンバーの活用)
当日のネタや一品が未確定でも、番組バックナンバーの“地引き網回(湘南編)”には、家庭向けの再現レシピが複数公開されています。
たとえば「シラスの二色丼」は、生シラスと釜揚げを半々に盛り付けるだけで“とれたて感”を丼で楽しめる入門メニュー。
作り方は塩湯でサッと釜揚げを作って盛るシンプル設計で、味付けは生姜・醤油・青ねぎの定番でまとめます。
もう少し手を動かしたい場合は「シラスのアヒージョ」。
弱火で香りを出したオイルに生シラスを入れて色が変わるまで加熱し、バゲットにのせるだけで“つまみ”にも“軽食”にも転ぶ万能皿です。
青魚が多く入った場合に重宝するのが「小イワシのから揚げ~スパイシーソースがけ~」。
下処理(えら・内臓を外す→水洗い→水気を拭く)をして片栗粉でカラッと揚げ、香味野菜とポン酢+ナンプラーのソースで後がけ。
揚げたてに酸味と香りが映え、家庭でも再現性が高い一皿です。
白身が入った時は「キスとハモの天ぷら」のように衣で素材を活かす調理が相性良し。
ハモの骨切りやキスの腹開きなど、公式手順が丁寧に示されているので、初挑戦でも手順を追いやすい構成になっています。
さらに“全部使い切る”観点では、魚のアラを活かす「あら汁」が鉄板。血合いやうろこをしっかり落としてから煮立て、味噌でまとめる基本形が公開されており、網に入った多彩な魚の旨味を一椀に集約できます。
余すところなく食べる:下処理・保存・アレンジ
地引き網の現場で映る下処理は、家庭でも応用可能です。
小魚は「えら・内臓を外す→流水で洗う→水気を拭く」の順で雑味を抜き、粉を薄くはたいて高温で短時間に揚げると臭みが出にくい――この基本は公式レシピでも具体手順として示されています。
骨や頭などの“アラ”は、丁寧に血合いを洗ってから酒を加えた湯で煮出し、味噌で調える「あら汁」に回すのが王道です。
保存は、生食(握り)にしない分を“加熱→冷蔵/冷凍”へ。から揚げや天ぷらは冷凍しても再加熱で戻しやすく、シラス系はオイル漬け(アヒージョの余り油を活用)にして冷蔵で数日楽しめます。
番組の地引き網シリーズでは“その場で握り、残りを加熱料理で活かす”流れが常で、公式バックナンバーの手順に沿えば、家庭でも“余さず使い切る”再現が可能です。
なお、本回(九十九里浜)の“握り以外の料理名”や“細かな手順”は放送後に公式レシピページへ掲載されるのが通例です。
視聴後は番組サイトのレシピ更新を確認すると、同一素材での家庭再現がさらに精緻になります(公式PRの案内にあるレシピページ・公式SNSが更新窓口)。
視聴者ガイド:アクセス・体験・関連回

九十九里浜へのアクセス(旭市方面)と周辺スポット
千葉県旭市の「矢指ヶ浦海水浴場」付近が、今回の体験地引き網の会場として特に案内されており、2025年の体験イベント案内でも「矢指ヶ浦海岸西500m付近」にて開催」と明記されています。
アクセス方法としては、都心から車で首都高速・東関東自動車道・千葉東金道路を経由し「旭 IC」または「匝瑳 IC」を降りて約20〜30分程度です。
公共交通利用の場合、JR「旭駅」または「八日市場駅」などを起点にバスやタクシー利用が現実的で、観光協会の案内にも「土日祝日の受付時間帯はあらかじめ電話確認を」と記載されています。
さらに、周辺には「道の駅 季楽里あさひ」があり、地元産品の直売所やレストラン、駐車場が整備されているため、体験前後の立ち寄りにも適しています。
2025年のイベント案内では集合場所として「道の駅季楽里あさひ」が目印として紹介されています。
このように、番組で紹介される「地引き網体験」は、アクセス面でも比較的整っており、テレビ番組を見て“行きたい”と思った視聴者が実際に訪れやすい構成となっています。
地引き網体験の可否・問い合わせ先の探し方
今回のロケ地である矢指ヶ浦での地引き網体験は、一般観光客向けにも開催されており、2025年7月13日(日)には「どなたでも参加OK!無料」の体験イベントが実施されました。
参加には申込・予約が必要なケースが多く、特に「矢指ヶ浦地曳き網漁保存会」が主催する体験プログラムでは、事前に電話(090-8816-0664)が案内されています。
また、体験実施の日時・集合場所・持ち物・雨天時の中止条件など、イベント告知ページに明記されており、参加を検討する際には当該ホームページまたは観光協会の最新情報を確認する必要があります。
例えば、2025年の例では「雨天決行・荒天中止」「持ち物:魚を入れる容器またはビニール袋」などが記載されています。
なお、番組で紹介される形式(550 mの綱を引く本格的な地引き網)は、一般体験プログラムすべてが同規模というわけではありません。
参加を希望する際には「実際の網の長さ」「参加人数」「魚の持ち帰り可否」など、条件を事前に確認することが重要です。
前回の地引き網“湘南編”との違いと見比べポイント
同番組の過去回では、例えば「湘南海岸」での地引き網回が放送されており、今回の千葉・九十九里浜編との最大の違いとしては「綱の長さ」「参加人数」「魚種」「地域文化の背景」が挙げられます。
今回、550 mという長大な綱が登場する点が公式予告で強調されています。
また、湘南編では観光体験としての色彩が強かったのに対し、九十九里浜編では「伝統を残すため有志で行われている漁」として地元漁師・保存会と協働しての漁がテーマになっており、地域への敬意・伝承の要素が構成に深さを与えています。
公式ブログでも「伝統を残すため有志で地引き網漁をしている」という投稿がベースになっています。
さらに、魚の種類も違いがあり、この時期の千葉・九十九里ではアジ・イワシ・クロダイなどが注目される一方、湘南ではメジナ・イサキ・キスなど海況・地形によって異なります。
この“魚種比べ”という観点から視聴後に番組を見返すと、地域差の面白さが理解しやすくなります。
以上から、今回の「九十九里浜 地引き網」回は、アクセス・体験可否・過去回との比較という観点からも“見ておきたい回”として位置づけられ、視聴者としてもただ放送を見るだけではなく“行動できるフィールド”としても活用可能です。
まとめ

今夜の『相葉マナブ』は、千葉県旭市・九十九里浜を舞台に“完全人力”の地引き網へ挑戦し、綱は前回の地引き網の2倍超となる約550mというスケール。
相葉雅紀さん、小峠英二さん、あばれる君さん、岡部大さんが参加し、獲れた魚は番組名物“包丁王子”がその場で握りに仕立てます(放送:2025年10月26日〈日〉18:00〜18:56・テレビ朝日系)。
公式予告で放送日時・出演者・企画内容・綱の長さ・その場で握る展開まで明示されているため、初見でも“どこで・誰が・何をする回か”を事前に押さえられます。
漁場は旭市側の九十九里浜で、この時期に見込める魚としてアジ、イワシ、クロダイ、そして稀にエイが入る可能性にも触れられています。
つまり“群れもの中心+サプライズ枠”という構図で、握りのネタや一品料理が当日の漁獲で決まる“ライブ感”が見どころです。
放送を見て「体験もしたい」と思った方には、同エリアで一般参加できる地引き網イベントが毎年行われている事実もチェックポイント。
2025年は矢指ヶ浦海岸(旭市)で予約不要の体験会(7/13)や、市主催イベント(7/19 サマーフェスタ in 矢指ヶ浦)で地引き網が実施されています。
次回以降に参加を検討する場合は、開催場所・集合時間・持ち物・荒天時対応などの最新案内を公式ページで確認するのが確実です。
アクセス面では、車なら東関道や千葉東金道路経由で旭IC・匝瑳IC方面から海岸へ、公共交通ならJR旭駅からの移動が現実的。
イベント告知でも目印として「道の駅 季楽里あさひ」が挙げられることがあり、体験前後の立ち寄りにも便利です。
総じて本回は、九十九里浜の“人が手で引く”伝統漁を通じて、地域の営みと旬の魚の魅力を体感できる内容。
まずは今夜の放送で、550mの綱を皆で引き上げる迫力と、包丁王子の“とれたてを握る”瞬間をチェックし、気に入ったら現地の体験情報を参照して“見る→行く→食べる”まで一気通貫で楽しむのがおすすめです。
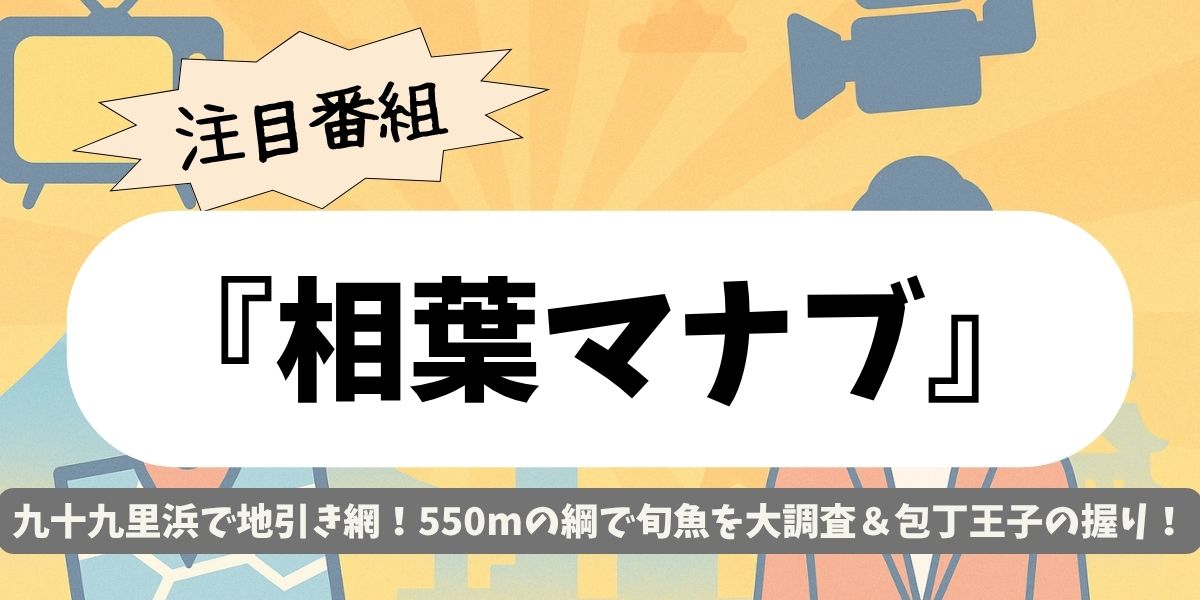
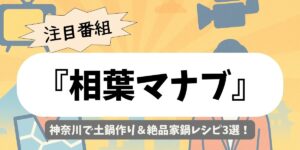
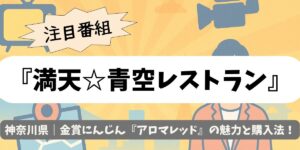
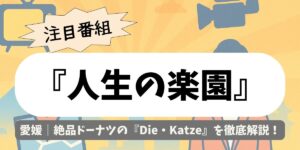
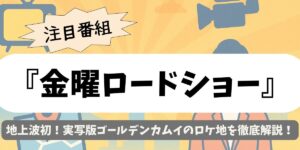
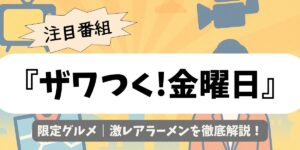



コメント